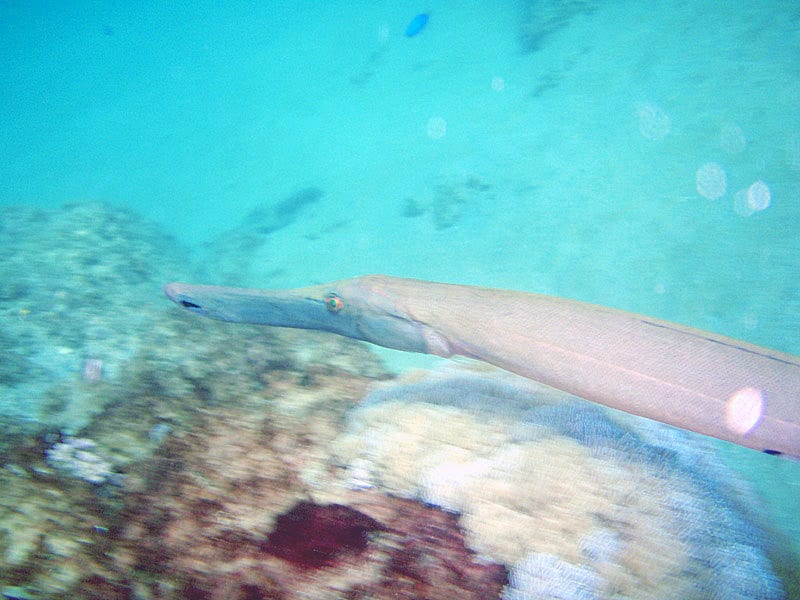アンドロメダ大星雲
50mmでは物足りなかったので、180mmで撮ってみると、銀河の構造も見えてきます。アンドロメダ大星雲の上にぼんやりした小さい天体が写っていますが、これもひとつの銀河。アンドロメダ大星雲にはいくつかの伴星雲があります。
この日は、レンズのピントリングを固定するセロテープを忘れて最悪。。。レンズは、Ai Nikkor ED 180mm f2.8Sという望遠レンズなのですが、天頂付近にレンズを向けると、ピントリングの座りが悪く、徐々に動きます。しかもEDレンズは温度変化に対する対応で、無限大より先まで余裕がみてあります。そっち方向に露光中に自然と動いていくので手で押さえながら撮りました。よって星が不自然な感じに写っています。。。グリス抜け出はないのですが、金属鏡筒のごついレンズ。ピントリングはグリスの制動力よりも重いようです。次はセロテープを忘れずに持っていきましょう。
ただし、いいレンズです。カメラのファインダーでこのような淡い天体も観察できるほど明るく、星のような点の光源でもフレアがほとんど出ません。
私が腫れ物のようにとても大事に扱う唯一のレンズ。
FUJIFILM FinePix S5 Pro + Nikon Ai Nikkor ED 180mm f2.8S