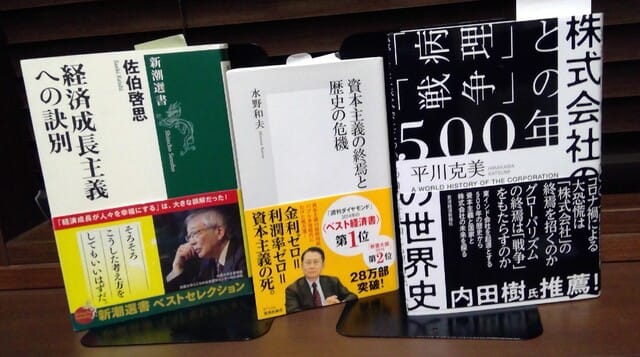
佐伯啓思氏は、経済学者、京都大学名誉教授。この本のカバーには、社会思想家とある。
佐伯氏の著作は、『自由と民主主義をもうやめる』(幻冬舎新書2008年)、『経済学の犯罪―希少性の経済から過剰性の経済へ』(講談社現代新書2012年)を読んでいる。他に、本吉図書館が蔵書していた新書を読んでいるはずだが、定かではない。アダム・スミスとケインズについての2分冊の新書版だったかとは思う。
【あたりまえのこと】
この本のまえがきで、佐伯氏は「あたりまえ」のことを述べるのだという。
「本書で私が述べていることは、実に「あたりまえ」のことである。「あたりまえ」過ぎて少々気恥しいほどである。…ただ、われわれの生きているこの社会が、表面上はにぎやかで楽し気に見えるものの、実は、一歩、一歩、破局へ向かっているのではないか、という思いに言葉を与えようとしただけである。」(3ページ)
現代社会に生きるわれわれは、楽しげに生きているだろうか?あるいは、楽しげには生きていないだろうか?破局へ向かっているのだろうか?
「「あたりまえ」とは、「ふつうの人」が「ふつうの生を送る」ということである。…政府も経済界もジャーナリズムや有識者も、「ふつう」ではだめだ、という。「もっとがんばって、もっと能力を発揮して、グローバル競争に勝つ」ということが至上命題になっている。われわれは、何か奇妙な思い込みにとらわれ、その結果として、たいへんに窮屈な社会に生きているのではなかろうか。」(3ページ)
私たちは、窮屈な社会に生きている。これは、教育の場、大学でも、高校、さらには、義務教育においても、同じことだろうし、ふつうの職場、グローバルな一流企業ではないふつうの会社でも、かなりのところそうなっている。先生も生徒も、経営者も勤め人も、管理職も部下も、毎日何かに急かされて、窮屈な生きづらさに支配されている、というべきかもしれない。
この奇妙な思い込みは、ほとんど強迫観念といっていいだろう。(補注1)
本書は、そんな、経済成長主義という強迫観念への決別をうたう書物である。
【脱成長主義とは】
「…本書のテーマも「脱成長主義」にあるのだが、そういった途端にたちどころに次のような反応が返ってくる。/「脱成長やゼロ成長社会とは、まったく変化のない停滞した社会ではないか。日本がどんどん貧しくなってもいいのか」という。あるいは、こういう反応もある。「今や、グローバル市場で新たな産業革命が起きており、世界は新たな豊かさのステージに変わろうとしている。それに乗り遅れたらたいへんだ。脱成長どころではない」。」(4ページ)
生きづらい社会からの脱却を目指して、無理な成長の追求はもう終わりにしようと言うと、そんなのはなんの解決にもならない、お花畑の議論にすぎないと批判される。
佐伯氏はそんな批判は「ほとんど意味のない情緒的な反応としか思われない」と一蹴し、「私の回答は本書を読んでいただくほかない」と述べつつ、次のように言う。
「…脱成長社会とは、決して「貧しくなる社会」ではない。さらに、それは変化のない停滞した社会でもない。」(5ページ)
なんの変化もない停滞した社会というと、たしかにつまらない、面白くもない社会となるところだが、脱成長社会は、決してそんな社会ではないのだと。
「ここで私が問いたいのは、経済成長、グローバル競争、技術革新などを推し進めることによって、人間は一層幸せになれる、という思い込みだ。もっと自由に、もっと便利に、もっと大きく、といった「成長主義」を問うことである。」(5ページ)
実際のところ、「豊かになればなるほど、われわれはさらに忙しく働かなければならなくなっている」、そして「それにもかかわらず、われわれは豊かさを実感できなくなっている」(23ページ)。現在を生きるわれわれは、豊かさを、幸せを、実感できなくなっているのだ。
そして実は、「経済成長を求めれば求めるほど、経済成長は達成できなくなる」(23ページ)というパラドクスがあるのだという。
たとえば、安倍元首相が推し進めたアベノミクスについて、こう語る。
「…経済思想的には全く敵対する新自由主義的なマネタリズムとケインズ主義を両方ともに組み合わせようというわけである。…まったく異なったふたつの経済観を強引に結びつけた、とんでもない異種混合のやり方に見える。」(28ページ)
その結果、うまくいったとは到底言えないわけである。
経済成長を追い求めても、経済成長は達成できない。その「問題の本質は、グローバル資本主義そのものにあるのだ」(29ページ)という。
これはどういうことか。
「…フランスの思想家、ジャン=ピエール・デュピュイは、今日の金融中心のグローバル資本主義はいずれ崩壊すると断言している。…資源も環境も土地も人口も食糧も有限の世界のなかで、無限に成長できるなどということはありえない。もし成長を続ければ、何らかの巨大な歪みが生み出されそれが世界を支えきれなくなるだろうことは、容易に想定できる。」(31ページ)
地球環境の有限性であり、地球上にもはや、開発可能なフロンティアは存在しないということである。
「私がいいたいのは、だからこそ、本当は、低成長へと緩やかに推移し、定常経済へ徐々に移行することが望ましいということなのである。脱成長こそが、ほとんど唯一、この資本主義を長期的に安定的に持続させる方法なのである。」(32ページ)
【人間中心主義はヒューマニズムではない】(補注2)
成長主義を脱却できないまま破局に至ることを避けるために、どうしなければならないか。
「そこで、私は「人間中心主義」に立ちたい、と思う。」(36ページ)
これは、いわゆるヒューマニズムとは違う、のだという。人道主義ではない。同情とか思いやりとか共感をもって、というのとは違う。個人個人が理性的に振る舞うだとかいうこととも違う。個人の考え方だとか、気の持ちようなどとは違う、もっと客観的なこと、だということかもしれない。
人間のサイズに合わせた経済ということだろうか。世界的に流通するモノを中心に考えるのでなく、あるいはお金を中心にするのでなく、人間一人ひとりの生活を中心に考える、ということだろうか。ふつうに生きている人間が暮らしを成り立たせることができるかどうか、良き生をおくることができるのかどうか、幸福になりうるのかどうか、という観点。
私としては、これは、広い意味では、いわゆるヒューマニズムとそんなに区別する必要もないような気もする。
いずれ、佐伯氏の論に異を唱えているわけではない。
あ、そうそう、そもそも経済とは、人間の生活に必要なモノやサービスをいかに届けるかということであって、お金儲けのことではない、と私は考えている。まさに、それと同じことを語られているのではないか?(補注3)
脱却しなければならないのは、「グローバル資本主義と科学技術のイノベーションを結合させて経済成長することこそが人間を幸福にする」という勘違いであり、その勘違いを生み出した「経済学という高度な「科学」を自任する学問的知識」(39ページ)、つまりは大雑把に言って現代の〈主流派経済学〉であり、その「効率万能主義、成長至上主義、科学技術絶対主義」(40ページ)という誤謬である、ということになるだろう。(補注4)
この書物もまた「経済学批判」の書であるということになる。
【カール・ポランニー、4つの人間の条件など】
さて、目次から、人名、書名などことばを拾っていくと、シューマッハ―の『スモール・イズ・ビューティフル』、「数学に席巻された理論経済学」、「レーガンの新自由主義」、「人間の条件」、シュンペーター「創造的破壊」、スミス、ケインズ、そしてカール・ポランニーなど。肯定的に言及されている言葉とそうではない言葉が混じっているわけだが。
カール・ポランニーといえば、栗本慎一郎の経済人類学を思い出す。自民党の国会議員も務めた栗本慎一郎は、当時、何を考えていたのだったろうか?二十代の頃に、ずいぶん読ませてもらった。ポランニーについて、佐伯氏は、経済史家、経済文明論者と述べているが、今でいえば主流派経済学の批判者である。『エコノミーとエコロジー』(みすず書房)によって「広義の経済学」を唱えた玉野井芳郎も、ポランニーを語っている。
そして「人間の条件」のこと。これは、ハンナ・アレントの書物とは、とりあえず別のもの。佐伯氏は、東日本大震災にも触れつつ、4つの条件を挙げている。
「2011年3月31日の東日本大震災は、特にこの地に住む人たちから何もかも奪い去った。…
このことはいいかえれば、われわれの「生」がいかに多くの、しかも一瞬で崩れかねないさまざまな条件の上に成り立っているかを示している。それを私はさしあたり、4つの次元で捉えておきたい。第一に「生命」、第二に「自然」、第三に「世界」、第四に「精神」である。」(208ページ)
「…経済成長は、こうした基盤を全く無視する。…それは金銭で測れないからである。」(216ページ)
ここで「基盤」とは、上記の4つの条件のことである。(4つの条件の内容については、この書物の中で明確に説明されている。)
「経済成長のロジックと「生命」、「自然」、「世界」、「精神」という「生の条件」が本質的に矛盾する…これらはすべて経済成長に対してはマイナスに作用するのである。」(218ページ)
経済成長にとらわれることは、人間の生の条件を突き崩すことにほかならない。人間が人間として生きていくことを否定するものである。経済成長が人々を幸福にするという考えは、思い込みであり、誤りだ、というのが佐伯氏の主張である。
(補注1)もちろん、全部が全部そうだというわけではなく、昔ながらの人間らしい職場もあるわけであろうし、そういう存在こそ、希望であるともいえるわけだろう。
(補注2)もちろん、サルトル『実存主義はヒューマニズム』のマネ。佐伯氏が、そんな言い方をしているわけではない。
(補注3)ある事業が、人間の生活に必要なモノやサービスを、よきマネージメントのもとに供給することができれば、その事業は持続する、つまり、結果としていくばくかの利潤が発生する、なんらかの疎外条件があれば失敗することもあるが、よろしき条件が揃えば、大儲けしてしまうこともある。企業とはそういうものであり、経済とはそういうものである、と思う。しかし、大儲けしてしまうこともある、というところに、根本的な問題がはらまれるのだ、と私は思う。柄谷行人が、マルクスを踏まえて語った「モノ→お金→モノ」が、「お金→モノ→お金」にすり替わってしまう図式である。
(補注4)われわれが「科学技術のイノベーション」に必死の思いで取り組んできたからこそ、経済が成長はせずとも縮小せず、なんとか現状維持に留めてきたのだ、と世の人は言うのだろう。現実、この二十年、日本はほとんどゼロ成長であったが、変化はあった。変化しすぎたくらいだ、と、本書で佐伯氏も言っている。
結果として経済成長はなかったかもしれないが、たとえば、スマホは普及し、昔は夢物語に過ぎなかったテレビ電話はふつうに実現し、最新流行のブランド品や希少な絶版本が、リビングに座ったままクリックひとつで翌日には配達される世となった。なんと便利になったことだろう。ずいぶんと変化した。進歩したといっていいのだろう。技術の成長はたしかにあったしずいぶんと便利になった。その結果、確かにわれわれは幾分かは幸福になった。
それは、必死に「科学技術のイノベーション」の取り組んできたからこそではないのか。成長成長とせかされて、なんとかグローバルな経済から取り残されまいと努力してきたからこそ、ではないのか。
そういう主張にはどう反論すべきか?
私自身は、そんな風に、他を蹴落とす競争にさらされ、汲々と窮屈な社会で生きていく、人生をおくる、というのは本末転倒としか思えないが、たとえば、そうだな。
「イノベーション」は、「効率万能主義、成長至上主義」からは生まれない、という反論はできそうだ。非効率で一見無駄な試行錯誤、成長には役立ちそうにない時間と費用の浪費からこそ、イノベーションは生まれると。理学なしの工学は存立しえないし、文学なしの理学は意味がない、などというと言葉遊びになるわけだが。あるいは、イノベーションは、義務からは生まれない、むしろ面白がる興味の広がり、深まりからこそ、とか。
人間をどんどん苦しみに追いやる「成長至上主義」を脱却して、地球環境の枠内で科学技術のイノベーションの恩恵にあずかることができるなら、それに越したことはないわけである。
いずれ、このあたりのことについては、然るべき書物が然るべき議論を展開してくれているだろう。


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます