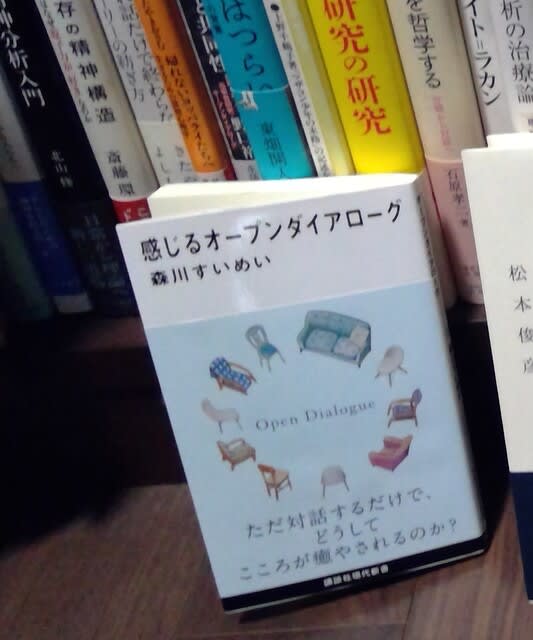
森川すいめい氏は、1973年生まれの精神科医。鍼灸師でもあるという。
ブック・カバーの裏に小さな顔写真がある。めがねをかけた細面の優男で、一般的な医師のイメージとはかけ離れているかもしれない。どこか弱さと優しさを感じさせる。威圧感がない。文章を読んでも、何だろう、権力的な感じがない。この威圧感のなさは、精神科の医師として、実は、他の誰もが求めることのできない優位点であるかもしれない。
経歴を読んでみると、精神科医であるというだけでなく、生活困窮者への支援に深く関わってきている方のようである。
「二つのクリニックで訪問診療等を行う。二〇〇三年にホームレス状態にある人を支援するNPO法人「TENOHASI(てのはし)」を立ち上げ、現在も理事として活動中。二〇一〇年、認定NPO法人「世界の医療団」ハウジングファースト東京プロジェクト代表医師、二〇一三年、同法人理事に就任。オープンダイアローグ国際トレーナー養成コース二期生で、二〇二〇年に日本の医師としては初めてオープンダイアローグのトレーナー資格を取得した二名のうちの一人。世界四九ヵ国を旅する。」
オープンダイアローグ発祥の地、フィンランドにも通って、そのトレーナー資格を取得した方である。
「はじめに」から読んでいく。
【著書自身のプロセス】
「本書は、私がオープンダイアローグ(開かれた対話/対話を開く)というものを理解していったプロセスを書いたものである。」(3ページ)
「オープンダイアローグの実践を通して感じるのは、既存の医療や支援の現場に、対話がもっとあったほうがいいということである。「対等の関係性の中で話す」「その人のいないところで、その人のことを話さない」「全員の声が大切にされる」「チームで対話する」など。
こうした考え方は、精神医療の分野だけでなく、学校、自治体、福祉、介護の現場や、もっと身近な家族の中でも応用可能だ」(5ページ)
オープンダイアローグ的な対話の実践は、医療の場だけではなく、教育、福祉、そして家族という場においても、たいせつなこととなる。
この書物は、そういう開かれた可能性を持つオープンダイアローグの実践のために、何が必要であるのか、著者の体験を語ることで明らかにしていくものである。
「本書の特徴といえるのは、第三章の、オープンダイアローグの実践者になるために筆者が受けた、対話のトレーニングの章だと思う。対話のトレーニングとは何かを簡単にまとめるとトレーニングを受ける一人ひとり(トレーニー)は、3年の期間、オープンダイアローグによる対話をつづけるということだ。
それはトレーニーにとって、対話の実践者になるためのトレーニングであると同時に、自分がクライアントになるのと同じだった。自分自身の抱える困難を話し、自分の家族を招いて会話し、それを仲間たちに聞いてもらう。」(7ページ)
トレーニーとは、トレーニングを受ける人という意味である。トレーニングを受けるとは、この場合、患者の立場に立つ、立たされるということであった。支援する立場に立つために、いったん支援される立場を経験しなければならない。
これは、精神分析において、分析家となるためには分析を受けなければならないと言われることと同じことに違いない。
人間だれしも、困難を抱えないものはないのであり、問題のない家族はない、のである。
オープンダイアローグの実践において、ここは重要なポイントになるのであろう。
「トレーニーたちは、それぞれ、自分の人生の中に困難を抱えていた。困難というのは誰のもとにもあるものだ。誰もが等しく何かに傷つき、大切なひととの別れがあり、ときには生きる意味に苦悩していた。…抱えている困難を、トレーニーたちはその場で仲間たちと話す。それはあたかも、一人の患者が対話によって回復するプロセスそのものだった。
この章で、私は、自分のトレーニングの様子を書いた。対話の場を開いてもらうことが私にとってどんな意味を持ち、私の抱えた傷がどうなって、私の中でどんな変化が起こったかを、ありのままに書いた。
それを書くことが、オープンダイアローグによって何が起きるのかを、今の私がいちばん具体的に示せるかたちだと思ったからだ。」(7ページ)
なるほど。
森川氏個人の生きてきたうえでの傷、その変化のありのままについては、ここでは詳細に紹介することはしない。書物に当たってほしい。森川氏自身が抱えた問題、過酷なともいうべき、親との関係性の物語である、とだけは言っておく。
【オープンダイアローグの7つの原則】
オープンダイアローグの7つの原則については、これまでもこのブログで紹介してきたものであるが、あらためて、この書物での森川氏による紹介を引いておく。何度も繰り返して読むべき大切な指針であることは言うまでもない。
「ケロプダス病院では、自分たちの実践を調査し、うまくいった事例を集めてなぜうまくいったのか、その要因を抽出し、7つに分類していた。それが以下に示す7つの原則で、ケロプダス病院では、困難に直面した人たちと接するときの指針として、ずっと大切にされている。
・IMMEDIATE HELP
・SOCIAL NETWORK PERSPECTIVE
・FLEXIBILITY AND MOBILITY
・RESPOMSIBILITY
・PSYCHOLOGICAL CONTINUITY
・TOLERANCE OF UNCERTAINTY
・DIALOGISM
それらは英訳するとこのようになる。これをさらに日本語訳すると、意味合いが少し変わってしまうようにも思うのだが、私なりに訳してみた。
・すぐに助ける
・本人に関わりのある人たちを招く
・柔軟かつ機動的に
・責務/責任
・心理的な連続性/積み重ね
・不確実な状況の中に留まる/寄り添う/すぐに答えに飛びつかない
・対話主義」(77ページ)
「7つの原則の意味は、固定されたものではない。時代やその場にいる人たちによって、柔軟に変化する。不確実な状況の中に留まるとはどういう意味なのか、どうしたらそうなるのか、責務とは何か、対話主義とは何か、そうした話し合いをスタッフ全員で対話的に行うのだという。」(79ページ)
教条主義的に一言一句そのまま記憶し、順守すべき規則といったものではない。対話を豊かに育てる手立てとなるものである。
【専門職の鎧を脱ぐこと】
以下のところは、「はじめに」の繰り返しともなるが、紹介しておく。心に傷を負ったセラピストは、心に分厚い鎧を装着していた。森川氏自身のことであり、森川氏以外の医師、専門職すべてに当てはまることでもある。
「オープンダイアローグのトレーニングは、自分自身がクライアントとなって、オープンダイアローグのセラピストたちと対話するという、オープンダイアローグによるトリートメントそのものだった。」(92ページ)
そして、自分の在り様に気づく。
「私はこの頃まだ、理論武装をして、病に闘いを挑む専門家の一人だったと思う。こころに分厚い鎧をまとっていた。
その鎧は、3年のトレーニングを経ていらなくなった。私のところに長く通ってくれているある人の言葉が、当時の状況をよく言い表している。
「先生は変わったね。昔はロボットみたいだった」
私はAIのように、正しい方法を見つけることで、人を助けようとしていたのかもしれない。医学を必死に学ぶほど、私の脳は「標準化」されて、私の言葉は技法のようになっていたと思う。」((93ページ)
「話を聞く専門職たちは、この仕事に就く前、そしてこの仕事を始めてから、こころが傷ついていた。苦しいときを経験したからこそ、セラピストという役割に辿り着いたのかもしれない。さらに、悩む患者さんを前に、何もできないという苦しみ。そうしたことを隠しながら、その傷を覆いながら、「専門職の鎧」を着て相談者の話を聞いていた。…
このトレーニングでは、自分が鎧を着けていることを知り、鎧を脱ぎ、その下の傷を顕わにして、自分が傷ついていえることを話す。傷はとても痛むものだ。そこに触れられたら、感情は大きく揺さぶられる。涙を流すかもしれないし、怒ってしまうかもしれない。
だから、その傷は癒やさなければならない。傷ついたまま鎧を脱いだら、話を聞くうちに感情が大きく揺さぶられて、自分がひどく傷つくか、反対に話した人を深く傷つけてしまうかもしれない。
価値や、大切な物を話す体験は、私にとって自分の傷を癒やす最初の作業になった。」(100ページ)
森川氏の具体的な心の傷については、上にも書いた通り、ここでは触れない。が、氏は、一般的な精神科医のイメージとは違う資質を持っているのかもしれない。
一方、オープンダイアローグが世に広まるにつれ、広く日本中の「精神科医の鎧」が溶けていく、という事態が生じるのかもしれない。
【オープンダイアローグによる変化】
氏は「おわりに」に、こんなことを記す。
「対話の場をたくさん持つようになってからは、新たにクスリを処方することがとても減った。…相談者たちは薬で症状を解決したいわけではなくて、苦悩を話し、それを軽減したいと思っている。どうしたらその助けになるのか、そのことを一緒に考える。
精神科の病院へ入院をお願いすることも少なくなった。入院を選択するときは、本人やご家族とよく対話したうえで、本人が入院して休みたいという場合がほとんどだ。…
職場では、よい変化もたくさんあった。私たちはとてもよく話すようになった。会議でも、クルマで移動するときも、ずっと喋っている。本当に良いチームになった、私は仲間のことがとても好きだ。…
これからは、医療以外の場で対話する場をもっと作ることができたらと仲間たちと話している。人生には対話が必要だから、あちこちで対話が発生するような仕掛けを作りたい。いろいろな人と話して、何か起きないかなと思っている。」
これは、まさに私も共有する夢である。
※カバー裏に、これまでの著書の紹介がある。『漂流老人ホームレス社会』(朝日文庫)、『その島のひとたちは、ひとの話をきかない―精神科医、「自殺稀少地域」を行く』(青土社)、『ハウジングファースト―住まいからはじまる支援の可能性』(共著/山吹書店)など、と。


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます