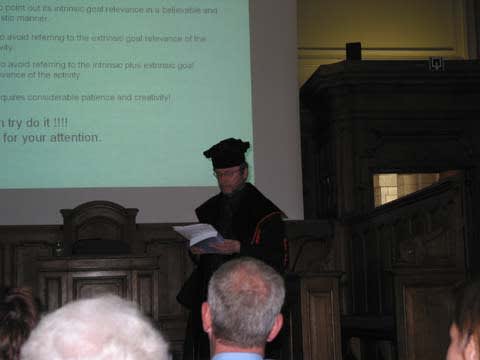日本では、どこに店に行ってもポイントカードを発行している。お客を自分の店に囲い込む戦略だ。
ルーヴァンに来て、一番近いスーパーマーケットのデレーズのポイントカードを作った。少なくとも週に3回はデレーズで買い物をする。何でもだいたい揃うので大変便利。
先日、ポイントが溜まって金券をもらった。買い物額2ユーロで1ポイント。500ポイント溜まると5ユーロの金券がもらえる。率にすると0.5%。日本のイトーヨーカドーは100円で1ポイントだから、それに較べると還元率は半分。それでも金券をもらうと嬉しい。記念に写真を撮った。申し込むと、カード一枚、来ホルダーに付けられるような小さなタグを2枚、セットでもらえる。
毎回レジに並んでいて、気づいたことが2点。
①レジスターのお金が入る部分は取り外しが可能で、レジ係はそれぞれ自分の箱をを持っている。休憩するときは、その箱をレジの下にしまう。仕事が終わると、お金の勘定。それぞれが自分の箱を管理している。
②レジでの支払いは、現金またはカード。カードで支払うときに、100ユーロとか200ユーロを受け取っている人がいる。極端な場合、キュウリ一本買って、100ユーロ受け取っている人もいる。ずっと疑問に思っていたので、レンズさんの奥さんに昨日聞いてみた。すると、スーパーのレジで、銀行のキャッシュ・ディスペンサーと同じように、お金を下ろすことができるというシステムなんだそうだ。一番最初に始めたのがデレーズで、それを他のスーパーも後追いし、今ではいろいろな店で可能になっているらしい。確かに、銀行まで行かなくてもお金をちょっと下ろせるのは便利だ。