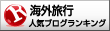以下、このホームページからの引用です。http://www.02.246.ne.jp/~kasahara/mariko.htm
書店で起こる反応
最近、“青木まりこ現象”として知られるようになった現象があります。2003年11月発行の『AERA』誌に掲載された記事(吉岡、2003年)によると、これは、青木まりこという女性が、1985年にある雑誌に投書したことから命名されたもので、書店に長時間いると便意を催すという現象を指すのだそうです。これは、私の言う反応(「「私の心理療法についての簡単な説明」」中の「反応」の説明参照)が日常生活の中で起こる実例として、比較的わかりやすいものです。このような現象が一般に知られるようになったことは、非常に大きな意味を持っていると思います。これらは、人間の心の本質を突き止めるための有力なヒントになるからです。
この症状は、書店ばかりでなく図書館でもごくふつうに見られるもので、現象としては少しも珍しくありません。しかし、長時間いなくても、書店や図書館に一歩足を踏み入れた瞬間に起こることもあります。また、その時に出現する症状は、排便に関係するものとは限りません。頭痛や脱力感をはじめとする自覚症状のこともあるし、あくびや眠気などのこともあるのです。そして、興味深いことに、書店や図書館を一歩出ると、その瞬間に便意が消えてしまうことが多いのです。たとえば、自宅にいると頭痛や便意が絶えずある人の場合、玄関を一歩出ると、その瞬間にそうした症状が消えてしまうことは珍しくありませんが、現象としてはそれと同じです。自宅にいる状況と自宅にいない状況で、対比的に症状が変化するという意味で、これを私は“状況的対比”と呼んでいます。
この種の症状は、書店や図書館に入っただけでは起こらず、特定のジャンルの棚に近づいた時点で、初めて出ることもあります。また、書店や図書館でしか起こらないわけではありません。変わった例ではゲームショップなどで起こることもあります。数は少ないですが、映画館や劇場やコンサート会場で必ず呼吸が苦しくなったり、眠ってしまったりする人たちもいます。このような場合、その症状を消すには、廊下に出るしかありません。廊下に出たとたんに、先ほどまでの症状はうそのように消えますが、再び会場に入ると、また、すぐに強い症状が襲ってきます。そうした症状が出るのは、自分が鑑賞したい演目や作品にほぼ限られるので、これは、酸欠のためや、椅子に座ってリラックスするためではないことがはっきりします。そのことは、体験者に聞けばすぐにわかるでしょう。拙著『懲りない・困らない症候群』(春秋社)には、さまざまな実例がたくさん掲載されているので、関心のある方はぜひご覧下さい。
どのように説明するか
では、この現象はどのような原因で起こるのでしょうか。何らかのストレスによるものなのでしょうか。『アエラ』所載の記事によれば、“青木まりこ現象”については、次のような解釈があるそうです。
●本の紙や印刷のインクのにおいが排泄欲を刺激するため
●トイレのない書店でトイレに入りたくなったら困るという精神的プレッシャーのため
●書店という非日常的空間で好きな本を探す行為が心身をリラックスさせるため
また、「本を手にとり読むという“まぶた”を伏せる姿勢が交感神経をOFFにし、胃腸の働きを支配する副交感神経がONになるため便意が生じる」というもっともらしい仮説を立てている医学部教授もいるそうです。これらは、それぞれ、刺激物質説、ストレス説、リラックス説、自律神経異常反応説となっており、ほとんどの可能性が網羅されているように見えます。最初のふたつは一般的な解釈のようですが、三番目は、ある精神科医による仮説、最後は、ある大学の医学部教授が唱えたもので、これまでのところでは、かなり有力視されている仮説だそうです。これらの仮説は、心理的原因説(ストレス説とリラックス説)と物理的原因説(刺激物質説と自律神経異常反応説)の二種類にまとめることができるでしょう。
しかしながら、それぞれの仮説を反証するのは簡単です。ひとつは、特定のジャンルの書棚に近づかない限り症状が出ない場合には、どの仮説も当てはまらないことになるからです。また、書店や図書館に入った瞬間に起こる場合にも、そうした考えかたでは説明できないでしょう。これまで知られている医学や生理学には、催眠暗示という概念を除けば、そのようなすみやかな反応を説明できる概念がないからです。では、催眠暗示が、現在の医学や生理学の知識で説明できるかというと、実際にはそれは不可能なのです。
医学部教授の仮説は、同じ姿勢で電車の中や自宅で、書店と同じく立った姿勢で読んだ場合にはどうなるのかを実際に実験してみれば、簡単に確認できます。そのような場合には、ほとんど便意は起こらないでしょう。それに、先述の通り、こうした状況で出る症状は便意ばかりではないのです。
科学的検証という問題
ところで、文学とは違って、科学では、実証ということが問題になります。心理的原因であっても物理的原因であっても、実験や観察によって、その仮説が正しいかどうかを検証しなければならないのです。そのような手続きを踏んで、その仮説の妥当性が確かめられると、それが、時の科学知識となり、必要とあらば、それに基づいた治療法なり対処法なりが取られることになるわけです。しかし、それが心理的原因であった場合、科学的方法を使って検証できるのか、という疑問が出されるかもしれません。
現在の心身医学や精神医学や心理療法では、それらしきものが見つかると、それが無批判に心理的原因と断定されてしまいます。たとえば、電車に乗ると尿意が起こり、ひと駅ごとに降りてトイレに入る、という訴えを聞いた心療内科医は、それは尿意が起こったらどうしようという予期不安がストレスになって起こる症状だと言うかもしれません。あるいは、会社に出勤することによるストレスが原因だと言う専門家もいるでしょう。そして、そのストレスを和らげるためと称して、向精神薬の投与やカウンセリングが行なわれることになるわけです。ここには、科学的方法が使われている形跡はありません。このように、勝手に原因を断定してしまってよいものなのでしょうか。
他の診療科では、さまざまな検査が行なわれ、それによって診断が決められ、治療に結びつけられます。もちろん、精神科や心療内科でも心理検査と呼ばれる検査はあります。しかし、それは、心理的原因の探究には全く役立ちません。脳波などの神経学的測定を除けば、精神科や心療内科には、他科の検査に相当するものがないのです。そのため、診断は、既往歴や、本人および家族の問診などから受ける印象に基づいて下されます。そのため、長い時間をかけて、さまざまな角度から検討しても、人によって診断が大幅に異なることも珍しくありません。
私は、これまで、心理的原因で起こるさまざまな病気(専門的な言葉では、心因性疾患)や問題を抱える人たちを対象にして、本格的な心理療法ばかりを30年以上続けてきました。心理相談やカウンセリングのようなものではなく、現実に症状や問題を解消するための心理療法を、自分なりに工夫、開発しながら続けてきたわけです。そのおかげで、さまざまな状況や条件の下で、多種多様な症状が出たり消えたりする場面を、自分の目で日常的に確認できるという、願ってもない経験を続けることができました。その中で、同じ症状であっても、さまざまな原因があること、逆に同じ原因であってもさまざまな症状が出る場合もあることなどが、経験的にわかってきました。
たとえば、心理的原因によって便意を催すという症状は、いろいろな状況で見られますが、その中に、“青木まりこ現象”の本質を考えるうえで参考になる、非常に興味深い例があります。海外旅行の添乗員をしている、30代の女性が、ある時、私的な観光旅行でハワイに出かけました。そして、現地で何度かバスに乗ったところ、そのたびごとに便意を催したのです。それらのルートは、仕事で何度も通っていました。しかし、仕事でバスに乗った時には、そのような症状が出たことは一度もなかったというのです。
また、私的な旅行では、ホテルのフロントで係と話していると気持が悪くなる、という症状も出ましたが、仕事の時には、同じホテルで同じ行動をしても、そのような症状が出たことは、やはり、後にも先にも一度もありません。同じ状況で同じ行動を取っても、本人の置かれた背景によって症状の出かたが変わってくることが、この実例からわかるでしょう。この種の事例はたくさんあります。
もちろん、厳密に言えば、この私的旅行で出た症状が“再現性”を持っているか――つまり、私的旅行の時にはいつも同じ症状が出るか――という問題も検討しなければなりません。とはいえ、現実には、行動や症状には“単発性”のものが多いため、その確認は難しいことが多いのです。私は、その代わりに、後述する反応を利用して、それを間接的に確認しています。 このような実例からすると、“青木まりこ現象”を持つ人が、もし書籍を扱う仕事に就いても便意が起こらないとすれば、この現象は心因性のものであることがかなりの確度で推測できます。この点は、“青木まりこ現象”を持つ人を対象にしたアンケート調査などを通じて、実際に調べることができるでしょう。ついでながらふれておくと、仕事中に、絶えず(あるいは頻繁に)便意や尿意を催す人もいないわけではありませんが、それは、書籍や読書とは無関係の原因によるものです。
もちろん、“青木まりこ現象”が心因性のものと、まだ決まったわけではありません。いずれにしても、厳密に検討したうえで原因を推定していかなければならないということです。
便意であれ脱力感であれ眠気であれ、書店や図書館でそうした症状が出る状況に共通して見られる条件は、《本がたくさん並んでいる中に入り、それらの中から、自分の読みたい本を探そうとする意志》が働いていることです。では、それが本人にとってストレスになるからなのかというと、そうではありません。他人から見るとわかりやすいでしょうが、本人にとってその場面は、本来、“至福”のはずの時間です。そもそも本当に本が嫌いなら、書店や図書館に入ることはないでしょう。しかし、本人の意識では、そうした症状のため、書店や図書館は苦痛を与える場所になります。場合によっては、その結果として、書店や図書館を避けるようになるでしょう。
では、その症状の原因は何なのでしょうか。まず、結果を見るとはっきりしますが、本を探したいのに、そうした症状が出てしまうと、それが容易には許されないことになります。自分が望んでいる行動を妨げる形で症状が出ているからです。これこそが、この症状の目的なのです。これを理解するには、人間観を根本から変えるしかありません。それはともかく、その症状が心理的原因で出ることは、ごく簡単な“思考実験”で確かめることができます。次に、どのようにするのかを説明しましょう。
これまで、心の専門家も一般の人たちも、人間の心については、思い込みに基づく推定を重ねるだけで、実証的に研究できるとは思っていないようです。実証的な研究といっても、心理学研究室のようなところで特別の装置を使うということではなく、誰でも簡単にできることです。ところが、これまで、この簡単な方法を誰も使ってきませんでした。
感情の演技という“思考実験”
たとえば、自分が書店や図書館にいるとして、そこで、自分の読みたい本を探している場面を頭に描きます。その場面を背景にして、「読みたい本を探したい」、あるいは「読みたい本が見つかってうれしい」、あるいは「本が好きだ」などの感情を作ります。その場合、一番作りにくい感情を選ぶのが“こつ”です。簡単なものを選んではいけません。最初は、雑念が入りやすいですが、それほど難しくないでしょう。2分間を一回分として、それを何度か繰り返すのです。これが、私が心理療法の中で唯一の治療法として使っている“感情の演技”という方法です。
人によっては、イメージを描こうとする段階で抵抗が起こりますが、ほとんどの人では、イメージ自体は描けます。しかし、繰り返すと、次第に難しくなり、感情もできなくなってきます。それでもむりに繰り返そうとすると、今度は反応と呼ぶ現象が起こります。反応は、2段構えになっています。最初の段階が雑念です。雑念というハードルを越えると、次のハードルとして、3種類の反応が待っています。眠気とあくびと身体的変化です。この場合のあくびは、いわゆる生あくびなので、眠気と一緒に出ることはありません。身体的変化には、あちこちの痛みやかゆみ、しびれ、熱感、脱力感などの自覚的反応と、鼻水や喘鳴や下痢などの他覚的反応とがあります。どのような反応が起こるかは、事前にはわかりませんが、わずか2分の間にそうした反応が起こるのです。しかも、感情を作るのをやめると、その瞬間に反応も止まります。実際に書店や図書館で便意を催す人では、感情の演技の時にも便意が起こるかもしれませんが、必ずしも便意とは限りません。
ほとんどの人は、そうした反応が出る前にやめてしまうでしょうが、数回から十数回ほど続けると、ほとんど例外なく反応が出るようになります。ただし、ふたつの“逃げ道”があるので、それをふさがなければ反応は出にくいかもしれません。ひとつは、空想的にしてしまうという逃げ道です。もちろん、感情の演技という方法はしょせん空想にすぎないのですが、その中でもなるべく現実的に作ろうとしなければ反応は出ません。ここでは、反応について説明しているので、このようなことを繰り返しても意味がないように聞こえるでしょうが、それ自体が治療になっているのです。
もうひとつの逃げ道は、物語を発展させるという方法です。つまり、感情の演技の場合、感情を作ることが目的であり、イメージはその手段にすぎないのですが、書店に入って、まずどのコーナーに行って、次に何をしてなどと物語を発展させると、イメージだけに終始してしまい、感情を作ることから遠ざかってしまうのです。そのため、たとえば、特定の棚の前で本を選んでいるという場面を選んだら、そこだけのイメージに固定して、感情を作るのです。
このふたつの逃げ道をふさぎ、感情を作る努力を何度か繰り返せば、次第に抵抗が強くなり、反応が出るようになるでしょう。さらにそれを続けると、反応はもっと強くなります。身動きができないほど脱力感が強くなったり、実際に下痢が始まったり、急速に眠り込んでしまったりすることもあります。しかし、その努力をやめれば、そうした症状はたちどころに消えます。この瞬間的変化は、ストレス仮説では説明できません。このような反応が出ることは、これまで全く知られていませんでした。私が心理療法の中で使っている感情の演技という方法は、実生活の中で起こる“青木まりこ現象”の一種のシミュレーションと言えるでしょう。その意味で、この現象は、私の治療理論の有力な裏づけになるわけです。
おわりに
たとえば、特に用事がない時に、何もせず、リラックスした姿勢で、眠らないようにしながら自分の好きなことを考えると、人間はどうなるでしょうか。楽しみ程度のことを考えるのなら、難しくはないでしょう。しかし、自分にとって前向きのことを考えようとすると、非常に難しいことがわかります。そこに、不安や悪い考えが入ってくるのを止めることはできません。自分のためになることでも、空想的になら考えられるでしょうが、現実的に考えるのは難しいのです。それをむりやり続けると、やはり反応が出てきます。しかし、不安なことや悪いことを考えている時には、原則として反応は出ません。この点も、ストレス仮説では説明できないでしょう。ストレス仮説が正しければ、不安なことを考えた時にこそ、症状が出なければならないからです。
このように、人間は、自分にとって前向きの方向に向かおうとすると、いわば、万難を排して体が抵抗するのです。こうした現象は、ほぼ例外なく起こりますが、これまでその存在は、一般にも専門家の間でも、全くと言ってよいほど知られていませんでした。“青木まりこ現象”は、そのひとつの例外的実例と言えるでしょう。その意味では、この現象は、人間の心の覗き窓と言ってもよいかもしれません。






書店で起こる反応
最近、“青木まりこ現象”として知られるようになった現象があります。2003年11月発行の『AERA』誌に掲載された記事(吉岡、2003年)によると、これは、青木まりこという女性が、1985年にある雑誌に投書したことから命名されたもので、書店に長時間いると便意を催すという現象を指すのだそうです。これは、私の言う反応(「「私の心理療法についての簡単な説明」」中の「反応」の説明参照)が日常生活の中で起こる実例として、比較的わかりやすいものです。このような現象が一般に知られるようになったことは、非常に大きな意味を持っていると思います。これらは、人間の心の本質を突き止めるための有力なヒントになるからです。
この症状は、書店ばかりでなく図書館でもごくふつうに見られるもので、現象としては少しも珍しくありません。しかし、長時間いなくても、書店や図書館に一歩足を踏み入れた瞬間に起こることもあります。また、その時に出現する症状は、排便に関係するものとは限りません。頭痛や脱力感をはじめとする自覚症状のこともあるし、あくびや眠気などのこともあるのです。そして、興味深いことに、書店や図書館を一歩出ると、その瞬間に便意が消えてしまうことが多いのです。たとえば、自宅にいると頭痛や便意が絶えずある人の場合、玄関を一歩出ると、その瞬間にそうした症状が消えてしまうことは珍しくありませんが、現象としてはそれと同じです。自宅にいる状況と自宅にいない状況で、対比的に症状が変化するという意味で、これを私は“状況的対比”と呼んでいます。
この種の症状は、書店や図書館に入っただけでは起こらず、特定のジャンルの棚に近づいた時点で、初めて出ることもあります。また、書店や図書館でしか起こらないわけではありません。変わった例ではゲームショップなどで起こることもあります。数は少ないですが、映画館や劇場やコンサート会場で必ず呼吸が苦しくなったり、眠ってしまったりする人たちもいます。このような場合、その症状を消すには、廊下に出るしかありません。廊下に出たとたんに、先ほどまでの症状はうそのように消えますが、再び会場に入ると、また、すぐに強い症状が襲ってきます。そうした症状が出るのは、自分が鑑賞したい演目や作品にほぼ限られるので、これは、酸欠のためや、椅子に座ってリラックスするためではないことがはっきりします。そのことは、体験者に聞けばすぐにわかるでしょう。拙著『懲りない・困らない症候群』(春秋社)には、さまざまな実例がたくさん掲載されているので、関心のある方はぜひご覧下さい。
どのように説明するか
では、この現象はどのような原因で起こるのでしょうか。何らかのストレスによるものなのでしょうか。『アエラ』所載の記事によれば、“青木まりこ現象”については、次のような解釈があるそうです。
●本の紙や印刷のインクのにおいが排泄欲を刺激するため
●トイレのない書店でトイレに入りたくなったら困るという精神的プレッシャーのため
●書店という非日常的空間で好きな本を探す行為が心身をリラックスさせるため
また、「本を手にとり読むという“まぶた”を伏せる姿勢が交感神経をOFFにし、胃腸の働きを支配する副交感神経がONになるため便意が生じる」というもっともらしい仮説を立てている医学部教授もいるそうです。これらは、それぞれ、刺激物質説、ストレス説、リラックス説、自律神経異常反応説となっており、ほとんどの可能性が網羅されているように見えます。最初のふたつは一般的な解釈のようですが、三番目は、ある精神科医による仮説、最後は、ある大学の医学部教授が唱えたもので、これまでのところでは、かなり有力視されている仮説だそうです。これらの仮説は、心理的原因説(ストレス説とリラックス説)と物理的原因説(刺激物質説と自律神経異常反応説)の二種類にまとめることができるでしょう。
しかしながら、それぞれの仮説を反証するのは簡単です。ひとつは、特定のジャンルの書棚に近づかない限り症状が出ない場合には、どの仮説も当てはまらないことになるからです。また、書店や図書館に入った瞬間に起こる場合にも、そうした考えかたでは説明できないでしょう。これまで知られている医学や生理学には、催眠暗示という概念を除けば、そのようなすみやかな反応を説明できる概念がないからです。では、催眠暗示が、現在の医学や生理学の知識で説明できるかというと、実際にはそれは不可能なのです。
医学部教授の仮説は、同じ姿勢で電車の中や自宅で、書店と同じく立った姿勢で読んだ場合にはどうなるのかを実際に実験してみれば、簡単に確認できます。そのような場合には、ほとんど便意は起こらないでしょう。それに、先述の通り、こうした状況で出る症状は便意ばかりではないのです。
科学的検証という問題
ところで、文学とは違って、科学では、実証ということが問題になります。心理的原因であっても物理的原因であっても、実験や観察によって、その仮説が正しいかどうかを検証しなければならないのです。そのような手続きを踏んで、その仮説の妥当性が確かめられると、それが、時の科学知識となり、必要とあらば、それに基づいた治療法なり対処法なりが取られることになるわけです。しかし、それが心理的原因であった場合、科学的方法を使って検証できるのか、という疑問が出されるかもしれません。
現在の心身医学や精神医学や心理療法では、それらしきものが見つかると、それが無批判に心理的原因と断定されてしまいます。たとえば、電車に乗ると尿意が起こり、ひと駅ごとに降りてトイレに入る、という訴えを聞いた心療内科医は、それは尿意が起こったらどうしようという予期不安がストレスになって起こる症状だと言うかもしれません。あるいは、会社に出勤することによるストレスが原因だと言う専門家もいるでしょう。そして、そのストレスを和らげるためと称して、向精神薬の投与やカウンセリングが行なわれることになるわけです。ここには、科学的方法が使われている形跡はありません。このように、勝手に原因を断定してしまってよいものなのでしょうか。
他の診療科では、さまざまな検査が行なわれ、それによって診断が決められ、治療に結びつけられます。もちろん、精神科や心療内科でも心理検査と呼ばれる検査はあります。しかし、それは、心理的原因の探究には全く役立ちません。脳波などの神経学的測定を除けば、精神科や心療内科には、他科の検査に相当するものがないのです。そのため、診断は、既往歴や、本人および家族の問診などから受ける印象に基づいて下されます。そのため、長い時間をかけて、さまざまな角度から検討しても、人によって診断が大幅に異なることも珍しくありません。
私は、これまで、心理的原因で起こるさまざまな病気(専門的な言葉では、心因性疾患)や問題を抱える人たちを対象にして、本格的な心理療法ばかりを30年以上続けてきました。心理相談やカウンセリングのようなものではなく、現実に症状や問題を解消するための心理療法を、自分なりに工夫、開発しながら続けてきたわけです。そのおかげで、さまざまな状況や条件の下で、多種多様な症状が出たり消えたりする場面を、自分の目で日常的に確認できるという、願ってもない経験を続けることができました。その中で、同じ症状であっても、さまざまな原因があること、逆に同じ原因であってもさまざまな症状が出る場合もあることなどが、経験的にわかってきました。
たとえば、心理的原因によって便意を催すという症状は、いろいろな状況で見られますが、その中に、“青木まりこ現象”の本質を考えるうえで参考になる、非常に興味深い例があります。海外旅行の添乗員をしている、30代の女性が、ある時、私的な観光旅行でハワイに出かけました。そして、現地で何度かバスに乗ったところ、そのたびごとに便意を催したのです。それらのルートは、仕事で何度も通っていました。しかし、仕事でバスに乗った時には、そのような症状が出たことは一度もなかったというのです。
また、私的な旅行では、ホテルのフロントで係と話していると気持が悪くなる、という症状も出ましたが、仕事の時には、同じホテルで同じ行動をしても、そのような症状が出たことは、やはり、後にも先にも一度もありません。同じ状況で同じ行動を取っても、本人の置かれた背景によって症状の出かたが変わってくることが、この実例からわかるでしょう。この種の事例はたくさんあります。
もちろん、厳密に言えば、この私的旅行で出た症状が“再現性”を持っているか――つまり、私的旅行の時にはいつも同じ症状が出るか――という問題も検討しなければなりません。とはいえ、現実には、行動や症状には“単発性”のものが多いため、その確認は難しいことが多いのです。私は、その代わりに、後述する反応を利用して、それを間接的に確認しています。 このような実例からすると、“青木まりこ現象”を持つ人が、もし書籍を扱う仕事に就いても便意が起こらないとすれば、この現象は心因性のものであることがかなりの確度で推測できます。この点は、“青木まりこ現象”を持つ人を対象にしたアンケート調査などを通じて、実際に調べることができるでしょう。ついでながらふれておくと、仕事中に、絶えず(あるいは頻繁に)便意や尿意を催す人もいないわけではありませんが、それは、書籍や読書とは無関係の原因によるものです。
もちろん、“青木まりこ現象”が心因性のものと、まだ決まったわけではありません。いずれにしても、厳密に検討したうえで原因を推定していかなければならないということです。
便意であれ脱力感であれ眠気であれ、書店や図書館でそうした症状が出る状況に共通して見られる条件は、《本がたくさん並んでいる中に入り、それらの中から、自分の読みたい本を探そうとする意志》が働いていることです。では、それが本人にとってストレスになるからなのかというと、そうではありません。他人から見るとわかりやすいでしょうが、本人にとってその場面は、本来、“至福”のはずの時間です。そもそも本当に本が嫌いなら、書店や図書館に入ることはないでしょう。しかし、本人の意識では、そうした症状のため、書店や図書館は苦痛を与える場所になります。場合によっては、その結果として、書店や図書館を避けるようになるでしょう。
では、その症状の原因は何なのでしょうか。まず、結果を見るとはっきりしますが、本を探したいのに、そうした症状が出てしまうと、それが容易には許されないことになります。自分が望んでいる行動を妨げる形で症状が出ているからです。これこそが、この症状の目的なのです。これを理解するには、人間観を根本から変えるしかありません。それはともかく、その症状が心理的原因で出ることは、ごく簡単な“思考実験”で確かめることができます。次に、どのようにするのかを説明しましょう。
これまで、心の専門家も一般の人たちも、人間の心については、思い込みに基づく推定を重ねるだけで、実証的に研究できるとは思っていないようです。実証的な研究といっても、心理学研究室のようなところで特別の装置を使うということではなく、誰でも簡単にできることです。ところが、これまで、この簡単な方法を誰も使ってきませんでした。
感情の演技という“思考実験”
たとえば、自分が書店や図書館にいるとして、そこで、自分の読みたい本を探している場面を頭に描きます。その場面を背景にして、「読みたい本を探したい」、あるいは「読みたい本が見つかってうれしい」、あるいは「本が好きだ」などの感情を作ります。その場合、一番作りにくい感情を選ぶのが“こつ”です。簡単なものを選んではいけません。最初は、雑念が入りやすいですが、それほど難しくないでしょう。2分間を一回分として、それを何度か繰り返すのです。これが、私が心理療法の中で唯一の治療法として使っている“感情の演技”という方法です。
人によっては、イメージを描こうとする段階で抵抗が起こりますが、ほとんどの人では、イメージ自体は描けます。しかし、繰り返すと、次第に難しくなり、感情もできなくなってきます。それでもむりに繰り返そうとすると、今度は反応と呼ぶ現象が起こります。反応は、2段構えになっています。最初の段階が雑念です。雑念というハードルを越えると、次のハードルとして、3種類の反応が待っています。眠気とあくびと身体的変化です。この場合のあくびは、いわゆる生あくびなので、眠気と一緒に出ることはありません。身体的変化には、あちこちの痛みやかゆみ、しびれ、熱感、脱力感などの自覚的反応と、鼻水や喘鳴や下痢などの他覚的反応とがあります。どのような反応が起こるかは、事前にはわかりませんが、わずか2分の間にそうした反応が起こるのです。しかも、感情を作るのをやめると、その瞬間に反応も止まります。実際に書店や図書館で便意を催す人では、感情の演技の時にも便意が起こるかもしれませんが、必ずしも便意とは限りません。
ほとんどの人は、そうした反応が出る前にやめてしまうでしょうが、数回から十数回ほど続けると、ほとんど例外なく反応が出るようになります。ただし、ふたつの“逃げ道”があるので、それをふさがなければ反応は出にくいかもしれません。ひとつは、空想的にしてしまうという逃げ道です。もちろん、感情の演技という方法はしょせん空想にすぎないのですが、その中でもなるべく現実的に作ろうとしなければ反応は出ません。ここでは、反応について説明しているので、このようなことを繰り返しても意味がないように聞こえるでしょうが、それ自体が治療になっているのです。
もうひとつの逃げ道は、物語を発展させるという方法です。つまり、感情の演技の場合、感情を作ることが目的であり、イメージはその手段にすぎないのですが、書店に入って、まずどのコーナーに行って、次に何をしてなどと物語を発展させると、イメージだけに終始してしまい、感情を作ることから遠ざかってしまうのです。そのため、たとえば、特定の棚の前で本を選んでいるという場面を選んだら、そこだけのイメージに固定して、感情を作るのです。
このふたつの逃げ道をふさぎ、感情を作る努力を何度か繰り返せば、次第に抵抗が強くなり、反応が出るようになるでしょう。さらにそれを続けると、反応はもっと強くなります。身動きができないほど脱力感が強くなったり、実際に下痢が始まったり、急速に眠り込んでしまったりすることもあります。しかし、その努力をやめれば、そうした症状はたちどころに消えます。この瞬間的変化は、ストレス仮説では説明できません。このような反応が出ることは、これまで全く知られていませんでした。私が心理療法の中で使っている感情の演技という方法は、実生活の中で起こる“青木まりこ現象”の一種のシミュレーションと言えるでしょう。その意味で、この現象は、私の治療理論の有力な裏づけになるわけです。
おわりに
たとえば、特に用事がない時に、何もせず、リラックスした姿勢で、眠らないようにしながら自分の好きなことを考えると、人間はどうなるでしょうか。楽しみ程度のことを考えるのなら、難しくはないでしょう。しかし、自分にとって前向きのことを考えようとすると、非常に難しいことがわかります。そこに、不安や悪い考えが入ってくるのを止めることはできません。自分のためになることでも、空想的になら考えられるでしょうが、現実的に考えるのは難しいのです。それをむりやり続けると、やはり反応が出てきます。しかし、不安なことや悪いことを考えている時には、原則として反応は出ません。この点も、ストレス仮説では説明できないでしょう。ストレス仮説が正しければ、不安なことを考えた時にこそ、症状が出なければならないからです。
このように、人間は、自分にとって前向きの方向に向かおうとすると、いわば、万難を排して体が抵抗するのです。こうした現象は、ほぼ例外なく起こりますが、これまでその存在は、一般にも専門家の間でも、全くと言ってよいほど知られていませんでした。“青木まりこ現象”は、そのひとつの例外的実例と言えるでしょう。その意味では、この現象は、人間の心の覗き窓と言ってもよいかもしれません。