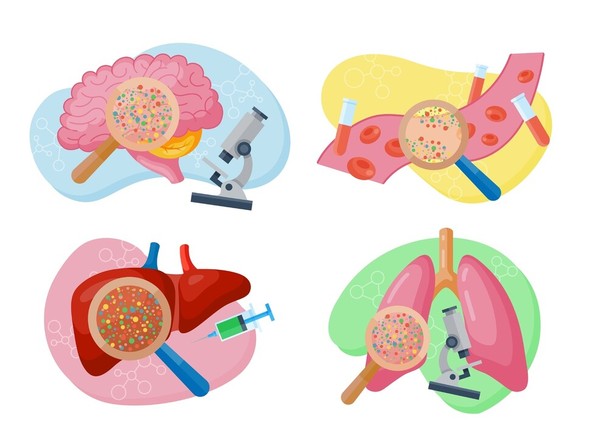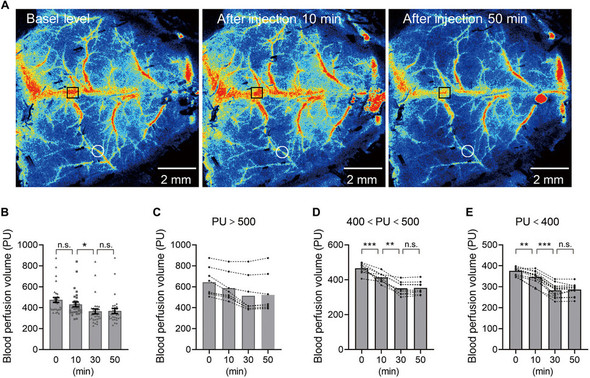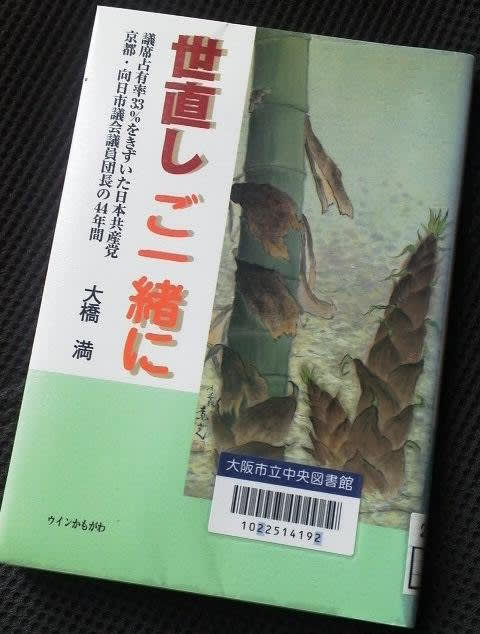トランプ大統領の2度目の任期開始後、私たちは今までの馴染みある世界とは違い過ぎる世界を経験するだろう。トランプの掲げる「米国第一主義(America First!)」というスローガンが、それ以前の馴染み深い「米国ナンバーワン」というスローガンとどれほど異なるかをみれば、その違いは推察できる。「米国ナンバーワン」が世界を共通の基準でまとめ、そこに例外なく従うことを強制するものだったとすれば、「米国第一主義」は、米国を偉大にする道なら例外が一般になるよう米国がいつでも変身し、それを世界に強制するという宣言だ。第2次トランプ政権の主導者たちは、米国の対外政策の失敗と悲劇は世界各地に介入した強硬な「ネオコン」に振り回されたせいで起きたと考え、彼らと断固として一線を引くことを主張する。今や米国は、世界に対する武力介入から脱し、「平和」の守護者へと変身しようとしているのだろうか。そうではない。第2次世界大戦後に米国が主導してきた世界秩序の共通の基準は、米国自身も制約されるせいで負担が重いため、これからは「米国第一主義」という独自の基準を掲げ、「無原則の世界」へと乗り出すという宣言に他ならない。その意味するところを米国の国内政治の視点と国際秩序の視点からみてみよう。
トランプ2期目の米国政治の変化をみる際のポイントは3つある。一つ目は、相次ぐトランプの「奇異な人選」だ。トランプが指名した長官たちの役割は、各自の省庁をきちんと守ることではなく、その省庁を「壊すこと」だ。二つ目のポイントは、トランプ-マスク連合だ。連合に参加したマスクにとって重要なのは脱規制だが、これは自動運転車、ツイッターの後身であるX、そしてスペースXのいずれも該当する。マスクなら、宇宙産業の非効率性を打破するためにNASAの機能を大幅に調整し、その機能の一部をスペースXが買収することを中身とする民営化も推進しうる。前の2つと関係する三つ目のポイントは「ディープステート」に対する攻撃だが、第1次トランプ政権はこの「ディープステート」のせいで自分たちの目標が挫折したと彼らは考える。国が企業であったなら、新たな主力産業を推進するためには、あえてそれまでの省庁をそのままにしておく必要もなく、流動的な市場の要求に合わせて、いかなる省庁であれ、改編を随時柔軟に行うべきなのではないか。
20世紀の米国自由主義の核心構図だった法人企業の経営に対する「公正な管理者」としての行政府、集団的権利の形成と管理の仲裁者としての行政府という枠組みは、こうして終わりを告げるだろう。
予想される国際秩序の再編を考えてみよう。トランプは北朝鮮の核問題、ウクライナ戦争、パレスチナ-イスラエル戦争を同時に解決するとともに、この3カ所から手を引いて負担を現地勢力に移転しようとするだろう。韓国にとって現実的な北朝鮮の核問題をまずみてみよう。トランプの再選を予想し、朝米首脳会談を再推進するという北朝鮮の立場は、ロシアを支援してウクライナ戦線に派兵したことではっきりした。北朝鮮の対米交渉と核戦略の重大な転換点は、2019年初めの「ハノイ・ノーディール」で、これを機として「韓国パッシング(韓国外し)」と韓国に対する戦術核による威嚇の拡大、および米国を標的とした戦略核による威嚇の増強という大きな変化があった。2025年に朝米首脳会談が再推進されれば、韓国を排除して合意の保証者としてプーチンを登場させるというやり方になる可能性がある。その会談は米国を標的とした戦略核の凍結・縮小が主な議題となり、韓国を標的とした戦術核は議論の対象から外される可能性がある。北朝鮮がウクライナ派兵の見返りとしてロシアからミサイル防衛システムの支援を受けたということも重要だ。朝米首脳会談の議題で扱われなかった北朝鮮の戦術核の脅威に対する対応コストは、その後、韓国に対する防衛費分担金協定の請求書に記載される可能性がある。
プーチンを朝米首脳会談に登場させることができれば、それはトランプがウクライナ終戦交渉を主導するうえでも有利な条件になる。米国は終戦後、ウクライナの長大な「非武装地帯」の維持から手を引いて、その軍事的責任を「欧州」に押し付けるだろうが、負担を抱え込む欧州は安保不安が高まるうえ、国内的には極右勢力の主張がよりいっそう激しくなるだろう。パレスチナ問題の解決は、2020年の「アブラハム合意」の道に沿うだろうが、これもまた紛争の終息ではなく紛争責任を現地に押し付ける方式の一時しのぎの対策であろう。
第2次世界大戦後の世界秩序を「ヤルタ体制」と呼ぶとすれば、ヤルタ体制解体後の世界は「米国第一主義」の新たな秩序へと再編されるだろうが、世界全体に適用される「多国間主義的秩序」が崩壊したこの世界においては、大国ではない国々、そして力なき民衆は、生存を支える共通規範の喪失で苦しむ可能性が高い。

ペク・スンウク|中央大学社会学科教授、『つながる危機』著者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
訳D.K