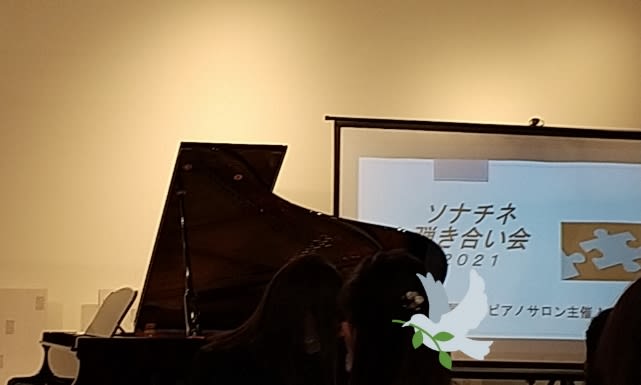
近くの楽器店の講座の一貫で、ソナチネの弾き合い会があり、アドバイザーとして参加しました

各教室から出場の生徒さんの演奏を聴き、講評を記入します📝
私は第2部の担当で、10人の生徒さんの講評をさせていただきました。
1番2番はバスティンの「四季のソナチネ」より、「冬のソナチネ」・「秋のソナチネ」。
発表会などで聴いたことがなかったので、YouTubeに上がってるもので講評の予習をしました

まずは、聴き取って楽譜に起こしてみました 📝
📝
 📝
📝「冬のソナチネ」は4分の4拍子にし、出だしを8分音符に取っていましたが、後で照合したら2分の2拍子で、出だしは4分音符でした

同様に「秋のソナチネ」は拍子こそ4分の4で同じでしたが、音価を半分に取っていました

結果は同じことかも知れないですが、私の表記だと細かくて1ページに収まってしまいます📃
それに、16分音符が出てくるので、小さなお子さんには難しく感じてしまいますね。
休符も8分休符より、4分休符の方が取りやすいです

今回それを踏まえて、小さな生徒さんたちの演奏を聴いて、バスティンは、学習段階に応じて無理なく、また表現しやすいように考慮されているのだ、と改めて気付きました

クレメンティ 7番

クーラウ 4番・6番

モーツァルト K545

ソナチネアルバムには、7・8・9とクレメンティの、きっぱりと歯切れのよい、古典派らしい曲が並んでいます。
4・6などのクーラウは、少しロマンチックで、のどかな雰囲気があります。
私的にはクレメンティは金管楽器🎺、クーラウは木管楽器📯のイメージです。
輝かしい感じと、少し牧歌的な感じでしょうか。
クーラウの6番は小学2年の時、発表会で先生が2台ピアノ🎹🎹の連弾パートを付けてくれました。
でも当日は興奮して、凄いスピードで弾いてしまい、先生を困らせた記憶があります

クーラウらしくない演奏だったな・・・と今になって思います。
(今度お会いしたら訊いてみよう。覚えておられるかな?)
モーツァルトになると、ソナタに近づいてきます

ソナチネは初心者向けソナタの意味がありますが、モーツァルトの音色の軽やかさ美しさを出すには、かなりのテクニック・熟練がいるかも知れないです

私もまだまだ追求中。
目指すはクラヴィコードのような、透明は澄んだ音色 ❄️
❄️
 ❄️
❄️今度のピアノステップでは、Y君がソナチネアルバム2の10番ベートーベンを弾く予定で練習に入りました

もう少し早ければ、こちらにも参加することができましたね

私も、母校(大阪音楽大学)での卒業生のための指導者研修の中でや、勉強会のコンクールで講評を書いた経験はありましたが

今回、講評のための観点を改めて勉強し、たくさんの色んな生徒さんの演奏を聴いて、とても刺激を受けました

また機会があったら参加していきたいと思います










