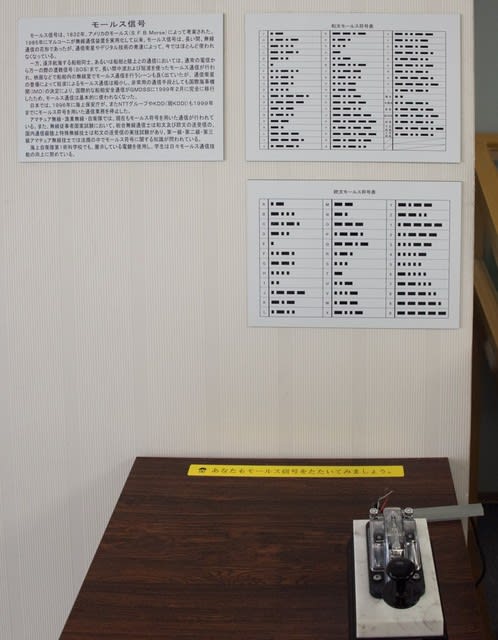観閲行進に先立ち、観閲官たる第一術科学校長、そして
幹部候補生学校長と江田島市長が観閲用の車に乗り込みました。

「先導いたします」
と指揮台前で宣言した観閲部隊指揮官は、先行の車両右側に着座して、
部隊の目の前を通過する際に部隊側を向くように座っています。
わたしが「お供いたします」といったように勘違いして覚えていたのは
同じ車に乗り込んで座る=お供と記憶が改変されたからに違いありません。
自衛隊法の細目によると、部隊指揮官は
執行者の目の前に進み、部隊指揮官の氏階級と人員等の報告後に
「ご案内します(どうぞ)」と右手を伸ばし誘導する
とされています。

音楽隊の演奏する「巡閲の譜」の調べがグラウンドに響く中、
全部隊を「閲兵」する観閲官。
練習艦隊などの場合は観閲官(防衛大臣か副大臣、政務官)が
儀仗隊の隊列を歩いて巡閲します。
巡閲を行う者を受礼者といい、このとき受礼者は隊員一人ひとりの
容儀、姿勢、眼光などに表れる気迫を通して、練度や士気を
確認するという意味があります。
これらの細目は全て自衛隊法の実施要項によって定められ、
指揮官は基本三尉から三佐まで、ということになっています。
幹部候補生はまだ任官しておらず海曹長という階級なので、
厳密にはこの基本から外れることになりますが、本式典は
あくまでも第一術科学校内での観閲行進なのでこれはありです。
海曹が指揮官になっていたことで前回unknownさんが
違和感を感じておられましたが、これが校内における行進で
さらに指揮官が海曹長であることを考えれば、
これもありなのではないか、と思われますがどうでしょうか。
いずれにしても旧海軍時代にはありえなかったリベラルさです。

巡閲終了。
「受礼者」に対し、この観閲部隊指揮官を「立会者」と称しますが、
立会者である部隊指揮官の
「巡閲終わります」
の報告で、巡閲は終了します。
ダビッドの前を普通に歩いている自衛官が気になる・・・。

部隊指揮官の
「観閲行進の態勢を取れ」
の号令により、各部隊が用意を行い、そののち
部隊指揮官が先頭となり観閲行進を指揮します。

しかし先頭を歩くのは実は行進曲「軍艦」を演奏する
音楽隊だったりします。

続いて幹部候補生隊(二大隊)、海曹部隊、海士部隊、
最後に喇叭隊が行進を開始します。

候補生部隊はもちろん全生徒が参加しているのでしょう。
隊列はグラウンドを右回りに行進し、芝生を取り囲む
観客の前を通過して術科学校の正面まで戻ってきます。

音楽隊が正面にさしかかりました。
部隊が通り過ぎるたびに盛大な拍手が観客席から起こります。

さすがはマーチングが本領の音楽隊、足の角度が皆ぴったり同じ。

音楽隊の先頭は全ての先頭ということになりますが、
このバトンを持った役目をドラムメジャーといいます。
ドラムメジャーは背の高い人しかなれませんが、それは
見栄えの問題というよりは背が高くないと、この
長いバトンを扱いにくいという実質的な理由があります。

海曹部隊の行進が始まりました。

そしてその頃観閲部隊指揮官を先頭とする指揮官部隊が通過。

続いてカラーガード部隊です。
「国旗が前方を通過するときにはご起立をお願いします」
というアナウンスがありました。
わたしの周りの来賓は当然皆立ち上がっていましたが、
昔防大の開校記念祭で、グラウンドを国旗が通過する際、
規律を促すアナウンスがあっても頑として立たない防大生の父兄らしい人や、
立ち上がったら後ろから
「(撮影の邪魔になるから)立つな!」
と怒鳴る連中がいて、茫然としたことがあります。
カメオタと呼ばれる中に得てしてとんでもない非常識さんがいるのは
あちこちのイベントで散見してよく知っていますが、
自分の子供が自衛官になるかもしれないのに国旗に敬意を払わない、
というのはいかがなものなんでしょうか。

候補生観閲部隊が観閲台前にさしかかりました。

こちらは候補生部隊の第二大隊。

部隊指揮官は、観閲台の手前(数十メーター)に隊列がさしかかると、
「頭(かしら)〜」
の号令を発すると同時に右手を伸ばします。

そして、その後、
「右!」
の号令で観閲台に向かって敬礼を行います。

旗を持って行進している旗手は「旗の敬礼」。
右手で旗ざおを垂直に上げ同時に左手で右脇で旗ざおを握り、
次に旗ざおを水平に前方に倒して行なう敬礼です。
このとき旗がちゃんと下に垂れるようにするのは難しそう。

銃を持って行進している部隊は、敬礼の代わりに、
「頭右」だけを行います。
ただし、一番観閲台寄りの列だけがまっすぐ向いたままです。
理由は知りませんが、多分全員で右を向いたら
列がまっすぐ進まないからじゃないでしょうか。

続いての海曹部隊旗手はすらりと背の高い女性隊員。

行進している海曹は、幹部候補生としてここ赤レンガで幹部を目指す、
「部内選抜一般幹部候補生」と言うことになろうかと思います。
このグループを「B幹部」といい、そのほかにも「C幹部」といって、
海曹長・准尉の中から試験で選抜された候補生もいますが、
履修期間は12週間だけですので行進に加わってはいない気がします。
防衛医大などの出身である医科歯科幹部候補生もいますが、
観閲行進にさんかしているかどうかについてはわかりませんでした。

最後に行進する海士の帽子には「第1術科学校」の金文字入り。
今見えている海士の全員が海士長(旧海軍の上等兵)です。

行進している海士のこちら側にも海士が立っていますが、
観閲行進が始まると同時に観閲台の両脇にたち、
いわば観閲官を「警護」しているという役割です。

この頃には音楽隊はグラウンドから建物の向こうに姿を消し、
音楽はまったくない状態がしばしあったわけですが、すぐに
最後尾の喇叭隊が「速足行進」の演奏を始めました。

このとき演奏されていたのは「速足行進その1」だと記憶します。

喇叭隊は二つに分かれ、メロディを交互に吹きます。
吹いていない時はこうやって右脇にラッパを抱え、
自分の吹く番になるとさっと構えるのです。

この行進&演奏を見ていて、わたしは最初に江田島にきた時を思い出しました。
毎日行われている第一術科学校の一般公開に参加したときです。
教育参考館の見学が終わり、ここにさしかかったとき、ちょうど
喇叭隊が行進していくところ(つまり行進部隊の最後)を目撃したのです。
そのときの見学グループを率いて説明してくれた
もと自衛官が、もうすぐ何々があるのでその練習です、といっていたのですが、
今にして思えばあれは自衛隊記念日の観閲行進の練習だったのですね。
同時に初めて見た自衛隊の行進に感激した気持ちまでもが蘇ってきました。
あれから幾星霜が流れました。
あの時行進していた自衛官のうち誰一人としておそらくここにおらず、
同じ制服を着ている自衛官もまずいないでしょう。
なによりも、いつの間にか同じ自分が、同じ場所で、その観閲行進を
観覧席に座って見ていることがなんだか不思議でした。
続く。