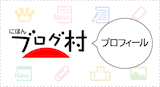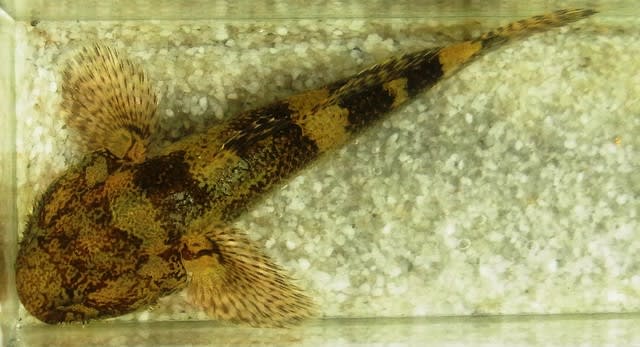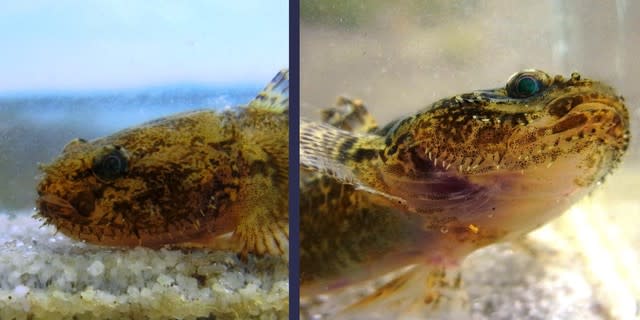2020年6月12日(金)
最近、魚釣り・魚採り・BC級グルメ・兄貴の刺繍・絵画にくわえ、サンショウウオだとか、俳句だとか、虫探しとか、うつつをぬかす他事が増えてしまった。
正直、書くネタがたまって困る。
今日も、雨が降らない間に園芸センターへ。
バラ園・果樹園・野菜畑・フジ棚・芝生・桜・ヤマモモ・竹林などなど、植物なら何でもござれの広大な所へ
私は虫探し、かみさんは俳句の吟行へ出かけてたのである。
これがおもしろいのなんの!
が、その話はまたいずれ。
本日は、5月末に小河川の干潟で魚採り(ガサ)の話。

2年前の西日本豪雨で、河床が砂で埋まり、かつてはワンサカいたミミズハゼもずいぶん減った。
それでも、なんとか1匹目のミミズハゼ

ま、いつも見るミミズハゼだね。
2匹目の黒っぽいミミズハゼ

コイツ、たぶんイソミミズハゼやなかろうか?

尾ビレ周縁の模様も、胸ビレ軟条の1本目も、それらしいわな。

ま、ここまでは順調だったのである。
3匹目を撮影しようじゃないか!
ん?顔つきはイソミミズハゼ?

でも、体中にはっきりした斑点がちらばっとるやん?

体色も少しずつ明るくなってくし、胸ビレも少しちゃうとちゃうか?

撮影ケースに、再び普段見てるミミズハゼを入れ比べてみる。

やっぱり顔つきといい、斑点といい、ミミズハゼちゃうやん!
黒いバットにそのまんま移してみる。

どうみても同じミミズハゼには見えない。
次に、イソミミズハゼだと思ったヤツを黒バットに移してパチリ!

比べてみる。

あか~ん!
イソミミズハゼのとき、ストロボしとらへんがな!
比べられんぞ、こりゃ?
こうなりゃ白バットぢゃ!
これで3匹の撮影条件はそろった!
あらためて
ミミズハゼとイソミミズハゼ

ほいでもって斑点ポツポツミミズハゼ

3匹そろえてパチリ!

左にミミズハゼとイソミミズハゼ
右に斑点ポツポツのミミズハゼ
さてさて、そろそろ結論の時間だ!
(TV観たり風呂入ったりしてくつろがんといけんけんな)
結論!
ミミズハゼ種群はわからんっ!
(最後までおつきあい下さり、誠に申し訳ござらぬ!)
最近、魚釣り・魚採り・BC級グルメ・兄貴の刺繍・絵画にくわえ、サンショウウオだとか、俳句だとか、虫探しとか、うつつをぬかす他事が増えてしまった。
正直、書くネタがたまって困る。
今日も、雨が降らない間に園芸センターへ。
バラ園・果樹園・野菜畑・フジ棚・芝生・桜・ヤマモモ・竹林などなど、植物なら何でもござれの広大な所へ
私は虫探し、かみさんは俳句の吟行へ出かけてたのである。
これがおもしろいのなんの!
が、その話はまたいずれ。
本日は、5月末に小河川の干潟で魚採り(ガサ)の話。

2年前の西日本豪雨で、河床が砂で埋まり、かつてはワンサカいたミミズハゼもずいぶん減った。
それでも、なんとか1匹目のミミズハゼ

ま、いつも見るミミズハゼだね。
2匹目の黒っぽいミミズハゼ

コイツ、たぶんイソミミズハゼやなかろうか?

尾ビレ周縁の模様も、胸ビレ軟条の1本目も、それらしいわな。

ま、ここまでは順調だったのである。
3匹目を撮影しようじゃないか!
ん?顔つきはイソミミズハゼ?

でも、体中にはっきりした斑点がちらばっとるやん?

体色も少しずつ明るくなってくし、胸ビレも少しちゃうとちゃうか?

撮影ケースに、再び普段見てるミミズハゼを入れ比べてみる。

やっぱり顔つきといい、斑点といい、ミミズハゼちゃうやん!
黒いバットにそのまんま移してみる。

どうみても同じミミズハゼには見えない。
次に、イソミミズハゼだと思ったヤツを黒バットに移してパチリ!

比べてみる。

あか~ん!
イソミミズハゼのとき、ストロボしとらへんがな!
比べられんぞ、こりゃ?
こうなりゃ白バットぢゃ!
これで3匹の撮影条件はそろった!
あらためて
ミミズハゼとイソミミズハゼ

ほいでもって斑点ポツポツミミズハゼ

3匹そろえてパチリ!

左にミミズハゼとイソミミズハゼ
右に斑点ポツポツのミミズハゼ
さてさて、そろそろ結論の時間だ!
(TV観たり風呂入ったりしてくつろがんといけんけんな)
結論!
ミミズハゼ種群はわからんっ!
(最後までおつきあい下さり、誠に申し訳ござらぬ!)