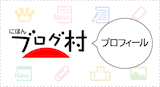2024年5月1日(水)
ホソミオツネントンボ Indolestes peregrinus オス

20240430 35mmほど
小雨が降っても散策は続けてる。
昨日はカワウとかキンクロハジロとかの潜水シーンを撮るために定点ため池めぐり。
そこで出会った青地に黒の美しいイトトンボ。

全国に普通にみられるトンボらしい。
が、私には一度会ってみたかった初見のイトトンボ。
なんせ成虫で越年するのだという。
冬の低温下では薄茶けた体色で生き延びるのだという。
最初、いつものアオモンイトトンボだろうと思いつつ近づき

斑紋の形の違いに気づき、「もしやホソミオツネントンボかも?」と撮影し

「間違いない」と確信したのだから、ここ数年で「昆虫図鑑」の読み込みのレベルも少し上がったのかもしれない。
よく似たオツネントンボは、郊外の少し高地のため池で見たことがある。
だから、まさかホソミオツネントンボが市内のため池にいるとは思いもしなかった。
近々、メスも見に行かねば・・・
それにしても、オツネンはなぜエツネン(越年)と呼ばないのだろう?
ホソミオツネントンボ Indolestes peregrinus オス

20240430 35mmほど
小雨が降っても散策は続けてる。
昨日はカワウとかキンクロハジロとかの潜水シーンを撮るために定点ため池めぐり。
そこで出会った青地に黒の美しいイトトンボ。

全国に普通にみられるトンボらしい。
が、私には一度会ってみたかった初見のイトトンボ。
なんせ成虫で越年するのだという。
冬の低温下では薄茶けた体色で生き延びるのだという。
最初、いつものアオモンイトトンボだろうと思いつつ近づき

斑紋の形の違いに気づき、「もしやホソミオツネントンボかも?」と撮影し

「間違いない」と確信したのだから、ここ数年で「昆虫図鑑」の読み込みのレベルも少し上がったのかもしれない。
よく似たオツネントンボは、郊外の少し高地のため池で見たことがある。
だから、まさかホソミオツネントンボが市内のため池にいるとは思いもしなかった。
近々、メスも見に行かねば・・・
それにしても、オツネンはなぜエツネン(越年)と呼ばないのだろう?