ウィーンで開かれていた核兵器禁止条約の締約国による初の会議が閉幕し、「核兵器と人類は共存できない」とするウィーン宣言を採択した。核兵器使用が現実味を帯びる中、核保有国との対話を進め、条約参加を呼びかける方針を確認した意義は大きい。「核なき世界」実現への第一歩としたい。
宣言は核兵器について「平和と安全の維持」との目的から離れ、攻撃を助長しているとして「核抑止論」を誤りと断じた。
また、一部の非核保有国が、核抑止や核兵器の保有継続を支持しているとも指摘した。米国のいわゆる「核の傘」の下にあり、現状を追認する発言の多い日本政府には耳の痛い話だろう。
核保有国は今回の会議に参加しなかったものの、北大西洋条約機構(NATO)加盟のドイツ、オランダやベルギーなどもオブザーバーとして参加した。
米国と核共有をしているドイツ政府代表は会議で、核軍縮の重要性に言及した上で、八月の核拡散防止条約(NPT)再検討会議で議論する考えを表明した。
日本政府が「核保有国と非保有国の橋渡し」を目指すならドイツのように条約締約国の声を、核保有国に伝えるのが役目のはずだ。
核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)のベアトリス・フィン事務局長が会議に先立ち、「(不参加の)日本には、橋渡し役の資格はない」と批判したことを重く受け止めるべきだ。
現地で開かれた市民フォーラムでは、広島や長崎をはじめとする世界の「ヒバクシャ」がオンラインで交流した。核被害の惨状を報告し、平和と核廃絶を願う声が相次いだという。日本の若者も現地を訪れて直接発信しており、政府とは違う立場から核軍縮を目指す活動には注目したい。
ウィーン宣言とともに採択された「行動計画」は、NPTなど多国間の軍縮体制と相互に補完し合うことを確認し、核保有国との対話の機会を設けることを明記した。核保有国と非保有国との対立を避けたいとの思いがにじむ。
世界を見渡せば、ロシアはウクライナ侵攻を巡って核使用をほのめかし、中国や北朝鮮も、核戦力を速いペースで増強している。核兵器が地球規模の差し迫った危機になっているとの認識を、多くの国が共有している。会議の成果を実際の核軍縮につなげたい。











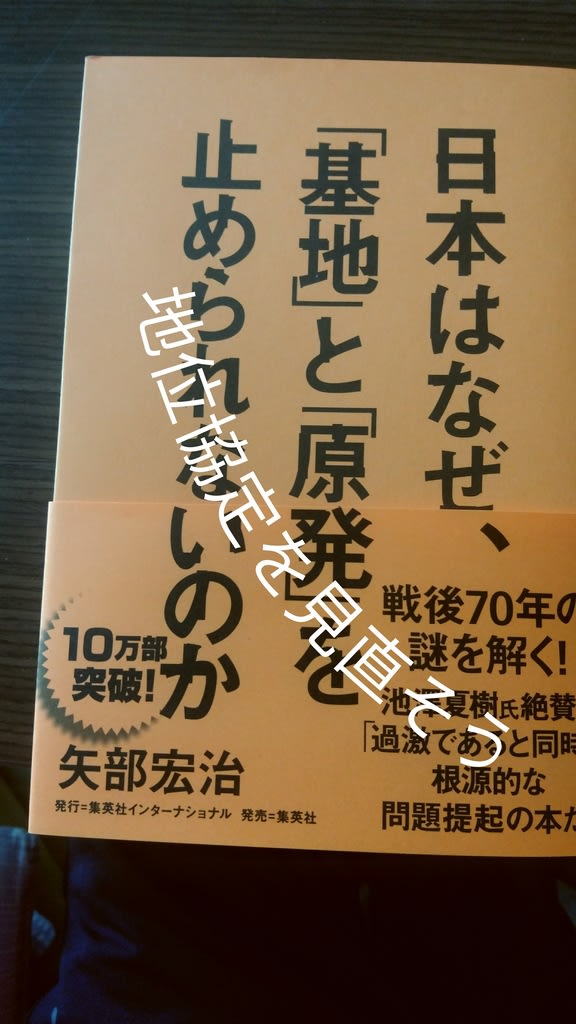


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます