光が丘ー春日町ー豊島園ー練馬ー新江古田駅、「江古田」は、中野区・練馬区で中野よりに哲学堂公園になる。
江古田の獅子舞は有名、氷川神社と練馬区側と云えば西武池袋線江古田駅になる。
中世の太田道灌ゆかりの古戦場「江古田ヶ原沼袋」がある。
西武線方面に向かう。
江古田銀座商店街に、西武線「江古田」駅南口に広がる商店街で、線路を隔てた「江古田ゆうゆうロード」とは踏切付近でつながっている。
飲食店をはじめ、300近い専門店などが並ぶ。
学生街らしく弦楽器の専門店もある。午後には多くの買い物客であふれる活気ある商店街。
大江戸線は環七通りに 商店街は西武線江古田駅



「中野区江古田の森公園」は、1919年東京市の療養所があり、後の国立療養所中野病院。 1971年 都市計画により、国立療養所中野病院に隣接してあった野方苗圃の部分を公園として整備し、都立北江古田公園として開園され、当事は、面積約16,000m²と小さかった。
1987年 北江古田公園の管理が中野区に変わり、中野区立の公園に、 1993年 国立療養所中野病院が、新宿区の国立国際医療センターへ組織統合され移転。 2007年 病院跡地が公園と福祉施設として整備され、北江古田公園の部分と併せて、全体で「江古田の森公園」として開園。
面積:58,911m²と広い。
江古田は、練馬・中野区の境に、 新宿区の西落合も近い



主な施設は、 芝生広場、球技場、遊歩道、 ビオトープ池、 ハナミズキの丘(かつて野方苗圃だった時に当地でアメリカハナミズキの栽培をしていたことにちなむという。保健福祉事業団による福祉施設など。
広大な園内



江古田獅子舞巡行絵巻 (江戸後期)区登録有形文化財
獅子や四神・お囃子などの一行が、舞を奉納する江古田の氷川神社へ行列をする様を、多少姿を変えてはいるが、現在も行われる巡行である。中野区内旧名主家の伝世品からと云う。
江古田獅子舞絵巻が
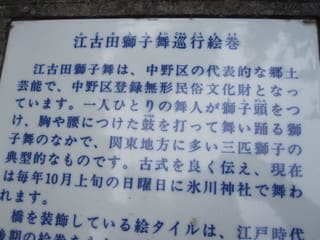

将軍吉宗は鷹狩が好きで度々中野にやってきますが、その時代にこのあたりに桃の木が植えられ、それ以前は、綱吉将軍のあのお犬様のお囲い跡です。
五代将軍綱吉と八代将軍吉宗は、間に二代の将軍をはさんでいるものの対照的。
桃園は庶民の行楽地にもなり、最初の国立公園だという人がいます。
「桃園」という地名があったという。
徳川家鷹狩ゆかりの地

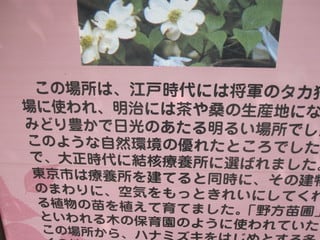
「練馬 東福寺」は、真言宗豊山派の寺院、金峯山世尊院と号す。
寺の創建年代は不詳、1573-1593年 江古田村の村民が開基となり、村内御嶽山に創建したと伝えられている。
江戸時代には3代将軍家光が鷹狩りの際に休息し、3代将軍吉宗は御膳所に指定している。
豊島八十八ヶ所霊場2番札所です。
東福寺 突き当りが本堂 お堂



新義真言宗にて中野村「宝仙寺」の末寺。
此寺元は村内御嶽山の邊にありしを、年月詳ならず此処へ移したりと云。本堂は8間半に7間。本尊不動の立像長1尺2寸。開山詳ならず。法流の祖を法運と云。享保7年示寂。開基は村民次郎右衛門が先祖にて、天正年中に起立といへど其詳なることを傳へず。
鐘楼。本堂の西にあり。鐘は宝永7年の銘を彫れり。(新編武蔵風土記稿より)
江古田森の公園に隣接 本堂 鐘楼



「落合南長崎」駅下車。ここは、新宿区北西部で、善福寺川、妙正寺川の合流点で落合に。駅は、他に営団東西線・西武新宿線で南部側に都
の水道処理場がある。地上は、中央公園。
「自性院」は、真言宗豊山派寺院、猫寺、豊島八十八ヶ所霊場24番札所前に出る。
西光山自性院無量寺は、弘法大師空海が日光山に参詣の途中で観音を供養したのが自性院の草創といわれている。
地蔵堂には秘仏の猫地蔵が祀られており、2月の節分会に開帳される。
江古田ヶ原の戦(1469~1486)で太田道灌が一匹の猫に救われたことから猫寺という愛称で親しまれ毎年2月には猫地蔵まつりが開催される。
江戸時代の明和4年(1767)に貞女として名高かった金坂八郎治の妻(覧操院孝室守心大姉)のために、牛込神楽坂の屋弥平が猫面の地蔵像を石に刻んで奉納しており、猫面地蔵と呼ばれている。二体とも秘仏となっており、毎年二月の節分の日だけ開帳されている。
毎年二月三日の午後に行われる節分会は、七福神の扮装姿の信徒らの長い行列が町内を練り歩く珍しいもので、秘仏開帳とあわせ、参詣客で賑わうという。区の文化財より
落合南長崎駅を出るとバス通り車の大渋滞 渡ると静かな自性院



「落合野鳥の森公園」は、 新目白通りから一歩入ったところにある 薬王院と隣接した静かな区立の森公園。
池のほとりにあるモミジを中心にケヤキ、コナラ等たくさん の落葉樹が植えられており、時期になると競い合うように真っ赤な姿を見せる。
雨が少ないのか池は枯れていた。
野鳥の森公園は住宅街に 緑一杯



真言宗豊山派 瑠璃山 「薬王院」 下落合4丁目 野鳥の森公園となり
公園隣が薬王院 楼門 高台に本堂



薬王院ー通称「東長谷寺」は、鎌倉時代の創建と伝えられ、その後江戸時代に中興され、本堂は昭和40年に、奈良-長谷寺と京都-清水寺とを模して建造で奈良の長谷寺の末寺になる。
本堂、参道、境内、山門など素晴らしい。
新目白通りを北へ渡ると、閑静な、落合の住宅街に入る。この家並みの中にひっそりと山門があり、ここからつづく細い参道の奥に、威風堂々とした"清水の舞台"が姿を現し、この周辺は、やや急勾配の斜面が続くところで、"清水の舞台"は、その斜面を利用するようにして造られていいる。この寺の舞台は南面しているので、天気が良い日には、その姿が一層引き立つと云う。
境内に数多いボタンが植えられ、「ぼたん寺」とも呼ばれている。
書院 長い階段途中に石仏 お堂



開山は鎌倉時代、相模国の大山寺を中興した「願行上人」、1673~81年に「実寿上人」が中興している。
1736~41年には火災によって焼失。明治11年 再興
江戸時代初期の墓石など境内には石造品が多い。
中世の板碑が8点保存されている。そのうち、徳治2年(1307年)、建武5年(1338年)、貞治6年(1367年)の3枚は、保存状態もよく大変貴重な資料と云う。
「ボタン寺」とも呼ばれ、見頃は、4月末から5月上旬。
本堂 総門彫刻


次回は、中井駅(西武線鷺ノ宮まで散歩)。









