成田駅も総武本線
成田街道は、江戸から下総成田に至る街道で、江戸から佐倉までを佐倉街道と重なっている。成田新勝寺参詣の旅人が多く通った街道。
江戸の人間は、千葉県市川行徳まで船を利用していたと云う。途中の船橋宿は、成田詣でで栄えた。
「市」は、北部で、熱田が転嫁(豊作の水田)説が有力。北部に、利根川に注ぐ「根木名川流域」の低地で、西部に「印旛沼」の低地が開けている。
台地上に先土器時代の石器が出土し「三里塚」で、又、多数の貝塚や遺構がある。
「鎌倉時代」は、千葉一族が支配、江戸時代は、佐倉藩や旗本の領地となった。中世以来「成田山新勝寺」の門前町で栄え、鉄道も1897年開通している。
現在は、昭和41年下総御料牧場から三里塚中心に新国際成田空港・空の玄関口として、外人観光客で賑わっている。
周辺は、成田ニュータウンや工業団地や駅前商店ビルなど人口も急増している。
JR成田駅中央改札・提灯

「三橋鷹女」
昭和期に活躍した代表的な女性俳人。中村汀女・星野立子・橋本多佳子とともに4Tと呼ばれたが、4人のなかでも表現の激しさと前衛性において
突出した存在と云う。
代表的な句
、
鞦韆(しゅうせん)は 漕ぐべし 愛は奪うべし 夏痩せて 嫌ひなものは 嫌ひなり
この樹 登らば鬼女と なるべし 夕紅葉 ひるがほに 電流かよひ ゐはせぬか
薄紅葉 恋人ならば 烏帽子で来など。
晩年は、孤独と幽玄の度合いを深め、
老いながら つばきとなつて 踊りけり 墜ちてゆく 燃ゆる 冬日を 股挟みー句も残している。
商店通りに老木 三橋鷹女の像

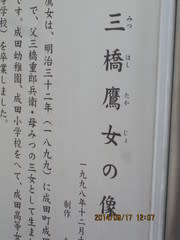

成田新勝寺の参道にある「長命泉」
県の酒蔵の歴史は江戸時代からとされており、この地域は、利根川などの水運に近い野で銘酒が多く、長い歴史をもつ酒蔵が数多く存在。
中でも、成田山に深い係わりを持つ長命延命霊力の酒「長命泉」の滝沢本店は、参道沿いにある。
成田市の手前に、酒々井町。
滝沢本店の長命泉と甲子正宗の飯沼本家のほか、水運で栄えた佐原の酒「東薫」の東薫酒造、糀善の馬場本店酒造が知られている。
滝沢本店「長命泉」蔵元


長命・延命霊力の酒,「長命泉」や、甘党の米屋總本店がある。
また、敷地内 には、成田羊羹資料館があり、羊羹の歴史に関する資料など展示。
成田は、利根川や印旛沼などの自然に恵まれ、漁業が発達、そこで獲れる魚介類を使った料理や加工品も、数多く生み出されてきた。
中でも栄養価の高いうなぎ料理は、この地域の食文化として広く定着し、全国でも珍しい「うなぎ」の街とも云える。
「成田うなぎ祭り」は、今年6回目を迎え、、毎年土用の丑の日を中心に、7月中旬から8月中旬にかけて開催される。
成田と云えば 鰻 店先でさばいている。 参道にいろいろなお店が並んでいる



「鰻丼とそばセット」¥1400・今日の昼食。
少々カロリーオバー

「成田山 新勝寺」
真言宗智山派大本山・939年「平将門の乱」の際し、東国鎮護の霊場として「朱雀天皇」が創建した。
1688~1704年元禄に江戸深川に、出開帳・歌舞伎の市川団十郎(成田屋)が演じる不動明王によって、江戸庶民の参詣が急増したと云う。
現在でも年間1千万人以上が参詣すると云う。
総門・(伽藍)

「朱雀天皇」在位期間・930年-946年。先代ー醍醐天皇・次代ー村上天皇。誕生ー923年・崩御ー952年。陵所ー醍醐陵
父親ー醍醐天皇・母親ー藤原穏子。皇居ー大内裏。
「平将門」~940 武将、東国桓武平氏の一人。武蔵国官人・土豪の争い国司追放し、一族の平貞盛らに討たれる。首は京都に送られたが江戸城大手門
飛んできて(大手町)に落ちた。首塚がある。
総面積約5万5000m2、本堂裏に成田山公園がある。
大提灯 手水舎 中楼門・光輪閣 仁王門



939年,朱雀天皇の密勅により寛朝大僧正を東国へ遣わしたことに起源を持つと云う。
寛朝は京の高雄山(神護寺)護摩堂の空海作の不動明王像を奉じて東国へ下り、翌940年、海路にて上総国尾垂浜に上陸。
平将門を調伏するため、下総国公津ヶ原で不動護摩の儀式を行い、新勝寺はこの天慶3年を開山の年としている。
乱平定の後の1566年頃と考えられるが未詳)に成田村一七軒党代表の名主が不動明王像を背負って遷座されて伽藍を建立された場所が、現在の成田市並木町にある「不動塚」周辺と伝えられ成田山発祥の地。
「また新たに勝つ」という語句に因み新勝寺と名づけられ、東国鎮護の寺院となった。
その後、新勝寺は戦国期の混乱の中で荒廃し、江戸時代までは寂れ寺となっていたとも云う。
仁王池の亀石


境内の石段

1858年本堂改築完成した時の様子を描いている。下総国成田山境内生写之図

明治維新以降、新勝寺はお札を通じて、戦時下の人々の精神的な助けとなったと云う。
「身代わり札」は「鉄砲玉から身を守る札」として日清戦争当時から軍人らに深く信仰され、満州事変から1945年の敗戦に至るまで、
「成田市史年表」から拾い出すだけでも、33年から41年までの間に、歩兵第57連隊の兵士や近衛兵たちが10回以上も参拝し武運長久を祈願、お札を身につけている。
18代住職荒木照定は1928年に新更会を設立、「成田町報」などを通じて、地域の民衆に対して、日本古来の伝統的思想の教化に積極的に努めた。
1938年には陸海軍に「新勝号」「成田山号」と名づけた戦闘機を献納、また真珠湾攻撃の翌日にはそれぞれに10万円を献納するなど、新勝寺は積極的に協力した記録が残る。
大本堂

三重の塔(重文)・ 正徳2年(1712)建立

一切経堂・(1722)建立 鐘楼は、1701年建立

江戸歌舞伎の第一人者、初代團十郎、舞台に暫や鳴神に代表される荒事を取り入れ、人気を博した。
しかし、跡継ぎに恵まれず、成田山の本堂・薬師堂で一心に子授けを祈願し、すると見事、待望の長男を授かったと云う。
不動さまの御利益りやくにむくいる父子で演じる「兵根元曽我」、中村座で親子共演した「兵根元曽我」は、お不動さまへの祈願が成就して長男を得たことに感謝をあらわした舞台であったと云う。
不動明王をテーマにした初めての歌舞伎で、舞台が大当たりしたことに感謝し、成田山に大神鏡を奉納した。
また、この共演を機に、市川家は、「成田屋」の屋号を使うようになったと云う。
薬師堂 釈迦堂


「出世稲荷」は、釈迦堂前の小高い丘の上に位置し、 総門を通り大本堂を正面に左手に進み、正面の長い階段を登ると、左手に出世稲荷が。
そのまま抜けると詣り道が、この道は、車道からも離れますので、静か、しばらく進むと、緑の木立が広がる。 成田山三学院が見えてきた。
成田山三学院とは、成田山の将来を担う法資(仏弟子)を育成する「発心院」、真言宗智山派並びに成田山の教師を育成する「勧学院」、成田山が招いた外国人留学生の勉学する施設「修智院」に。
中に入ることはできませんが外観は。
光明堂・額堂・多宝塔・仏塔など。 出世稲荷はこの奥に 新勝寺の前楼門



寺 大本堂の奥にある165,000㎡の広大な広さを誇る成田山公園の秋の紅葉を。
もみじまつりは、平成12年より始められ、15回目を迎ると云う。
旧齊藤家夏の別荘や渋澤榮一邸などを手がけた庭師、2代目松本幾次郎により昭和3年に完成、自然が織り成す四季を通じて変化に富んだ、日本庭園。
完成から80有余年を経て、立派に成長を遂げた公園内の樹木は見事である。
モミジ、クヌギ、ナラ、イチョウといった約250本の樹木の葉は、11月半ばから12月上旬に赤や黄色に色づく。
総武本線の旅は終了します。
成田街道は、江戸から下総成田に至る街道で、江戸から佐倉までを佐倉街道と重なっている。成田新勝寺参詣の旅人が多く通った街道。
江戸の人間は、千葉県市川行徳まで船を利用していたと云う。途中の船橋宿は、成田詣でで栄えた。
「市」は、北部で、熱田が転嫁(豊作の水田)説が有力。北部に、利根川に注ぐ「根木名川流域」の低地で、西部に「印旛沼」の低地が開けている。
台地上に先土器時代の石器が出土し「三里塚」で、又、多数の貝塚や遺構がある。
「鎌倉時代」は、千葉一族が支配、江戸時代は、佐倉藩や旗本の領地となった。中世以来「成田山新勝寺」の門前町で栄え、鉄道も1897年開通している。
現在は、昭和41年下総御料牧場から三里塚中心に新国際成田空港・空の玄関口として、外人観光客で賑わっている。
周辺は、成田ニュータウンや工業団地や駅前商店ビルなど人口も急増している。
JR成田駅中央改札・提灯

「三橋鷹女」
昭和期に活躍した代表的な女性俳人。中村汀女・星野立子・橋本多佳子とともに4Tと呼ばれたが、4人のなかでも表現の激しさと前衛性において
突出した存在と云う。
代表的な句
、
鞦韆(しゅうせん)は 漕ぐべし 愛は奪うべし 夏痩せて 嫌ひなものは 嫌ひなり
この樹 登らば鬼女と なるべし 夕紅葉 ひるがほに 電流かよひ ゐはせぬか
薄紅葉 恋人ならば 烏帽子で来など。
晩年は、孤独と幽玄の度合いを深め、
老いながら つばきとなつて 踊りけり 墜ちてゆく 燃ゆる 冬日を 股挟みー句も残している。
商店通りに老木 三橋鷹女の像

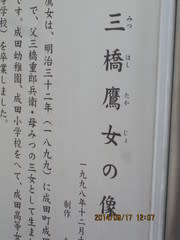

成田新勝寺の参道にある「長命泉」
県の酒蔵の歴史は江戸時代からとされており、この地域は、利根川などの水運に近い野で銘酒が多く、長い歴史をもつ酒蔵が数多く存在。
中でも、成田山に深い係わりを持つ長命延命霊力の酒「長命泉」の滝沢本店は、参道沿いにある。
成田市の手前に、酒々井町。
滝沢本店の長命泉と甲子正宗の飯沼本家のほか、水運で栄えた佐原の酒「東薫」の東薫酒造、糀善の馬場本店酒造が知られている。
滝沢本店「長命泉」蔵元


長命・延命霊力の酒,「長命泉」や、甘党の米屋總本店がある。
また、敷地内 には、成田羊羹資料館があり、羊羹の歴史に関する資料など展示。
成田は、利根川や印旛沼などの自然に恵まれ、漁業が発達、そこで獲れる魚介類を使った料理や加工品も、数多く生み出されてきた。
中でも栄養価の高いうなぎ料理は、この地域の食文化として広く定着し、全国でも珍しい「うなぎ」の街とも云える。
「成田うなぎ祭り」は、今年6回目を迎え、、毎年土用の丑の日を中心に、7月中旬から8月中旬にかけて開催される。
成田と云えば 鰻 店先でさばいている。 参道にいろいろなお店が並んでいる



「鰻丼とそばセット」¥1400・今日の昼食。
少々カロリーオバー

「成田山 新勝寺」
真言宗智山派大本山・939年「平将門の乱」の際し、東国鎮護の霊場として「朱雀天皇」が創建した。
1688~1704年元禄に江戸深川に、出開帳・歌舞伎の市川団十郎(成田屋)が演じる不動明王によって、江戸庶民の参詣が急増したと云う。
現在でも年間1千万人以上が参詣すると云う。
総門・(伽藍)

「朱雀天皇」在位期間・930年-946年。先代ー醍醐天皇・次代ー村上天皇。誕生ー923年・崩御ー952年。陵所ー醍醐陵
父親ー醍醐天皇・母親ー藤原穏子。皇居ー大内裏。
「平将門」~940 武将、東国桓武平氏の一人。武蔵国官人・土豪の争い国司追放し、一族の平貞盛らに討たれる。首は京都に送られたが江戸城大手門
飛んできて(大手町)に落ちた。首塚がある。
総面積約5万5000m2、本堂裏に成田山公園がある。
大提灯 手水舎 中楼門・光輪閣 仁王門



939年,朱雀天皇の密勅により寛朝大僧正を東国へ遣わしたことに起源を持つと云う。
寛朝は京の高雄山(神護寺)護摩堂の空海作の不動明王像を奉じて東国へ下り、翌940年、海路にて上総国尾垂浜に上陸。
平将門を調伏するため、下総国公津ヶ原で不動護摩の儀式を行い、新勝寺はこの天慶3年を開山の年としている。
乱平定の後の1566年頃と考えられるが未詳)に成田村一七軒党代表の名主が不動明王像を背負って遷座されて伽藍を建立された場所が、現在の成田市並木町にある「不動塚」周辺と伝えられ成田山発祥の地。
「また新たに勝つ」という語句に因み新勝寺と名づけられ、東国鎮護の寺院となった。
その後、新勝寺は戦国期の混乱の中で荒廃し、江戸時代までは寂れ寺となっていたとも云う。
仁王池の亀石


境内の石段

1858年本堂改築完成した時の様子を描いている。下総国成田山境内生写之図

明治維新以降、新勝寺はお札を通じて、戦時下の人々の精神的な助けとなったと云う。
「身代わり札」は「鉄砲玉から身を守る札」として日清戦争当時から軍人らに深く信仰され、満州事変から1945年の敗戦に至るまで、
「成田市史年表」から拾い出すだけでも、33年から41年までの間に、歩兵第57連隊の兵士や近衛兵たちが10回以上も参拝し武運長久を祈願、お札を身につけている。
18代住職荒木照定は1928年に新更会を設立、「成田町報」などを通じて、地域の民衆に対して、日本古来の伝統的思想の教化に積極的に努めた。
1938年には陸海軍に「新勝号」「成田山号」と名づけた戦闘機を献納、また真珠湾攻撃の翌日にはそれぞれに10万円を献納するなど、新勝寺は積極的に協力した記録が残る。
大本堂

三重の塔(重文)・ 正徳2年(1712)建立

一切経堂・(1722)建立 鐘楼は、1701年建立

江戸歌舞伎の第一人者、初代團十郎、舞台に暫や鳴神に代表される荒事を取り入れ、人気を博した。
しかし、跡継ぎに恵まれず、成田山の本堂・薬師堂で一心に子授けを祈願し、すると見事、待望の長男を授かったと云う。
不動さまの御利益りやくにむくいる父子で演じる「兵根元曽我」、中村座で親子共演した「兵根元曽我」は、お不動さまへの祈願が成就して長男を得たことに感謝をあらわした舞台であったと云う。
不動明王をテーマにした初めての歌舞伎で、舞台が大当たりしたことに感謝し、成田山に大神鏡を奉納した。
また、この共演を機に、市川家は、「成田屋」の屋号を使うようになったと云う。
薬師堂 釈迦堂


「出世稲荷」は、釈迦堂前の小高い丘の上に位置し、 総門を通り大本堂を正面に左手に進み、正面の長い階段を登ると、左手に出世稲荷が。
そのまま抜けると詣り道が、この道は、車道からも離れますので、静か、しばらく進むと、緑の木立が広がる。 成田山三学院が見えてきた。
成田山三学院とは、成田山の将来を担う法資(仏弟子)を育成する「発心院」、真言宗智山派並びに成田山の教師を育成する「勧学院」、成田山が招いた外国人留学生の勉学する施設「修智院」に。
中に入ることはできませんが外観は。
光明堂・額堂・多宝塔・仏塔など。 出世稲荷はこの奥に 新勝寺の前楼門



寺 大本堂の奥にある165,000㎡の広大な広さを誇る成田山公園の秋の紅葉を。
もみじまつりは、平成12年より始められ、15回目を迎ると云う。
旧齊藤家夏の別荘や渋澤榮一邸などを手がけた庭師、2代目松本幾次郎により昭和3年に完成、自然が織り成す四季を通じて変化に富んだ、日本庭園。
完成から80有余年を経て、立派に成長を遂げた公園内の樹木は見事である。
モミジ、クヌギ、ナラ、イチョウといった約250本の樹木の葉は、11月半ばから12月上旬に赤や黄色に色づく。
総武本線の旅は終了します。









