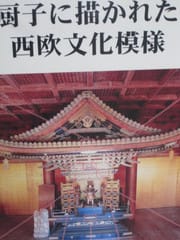JR仙石線は、仙台市内青葉通りから多賀城・本塩釜・松島海岸・矢本・石巻間を云う。石巻からは、女川・石巻・前谷地・小牛田で東北本線
と連絡・古川で東北新幹線と連絡している。
JR石巻線は、3月11日の「東北地方太平洋沖地震」の発生により全線で不通。4月17日に小牛田駅 - 前谷地駅間が運転再開。
5月、前谷地駅 - 石巻駅間が運転再開。12月ー平日朝に石巻駅から仙台行直通快速が運行開始。2012年1月、平日夜に仙台駅から石巻行直通快速が運行開始。3月、石巻駅 - 渡波駅間が運転再開。代行バス区間を渡波 - 女川間に変更。仙台駅 - 石巻駅間の直通快速が毎日運行開始。
10月、貨物列車が運行再開。2013年3月、渡波駅 - 浦宿駅間が運転再開。代行バス区間を浦宿 - 女川間に変更。
2014年の平成26年4月全線が新設の仙台近郊区間となる。
平成27年 3月21日:浦宿駅 - 女川駅間が運転再開。5月仙台駅 - 石巻駅間の直通快速。
石巻駅 - 女川駅間には、1915年から1926年にかけて軽便鉄道の金華山軌道が開通していたが、石巻線の開業に伴って廃線補償を受け、1939年に休止、
翌年廃止となった。
「牡鹿半島」宮城県東部・石巻湾東太平洋に突き出ている半島・遠島とも云った。石巻・女川・牡鹿町が、リアス海岸形成されている。
暖流と寒流の交わる金華山沖漁場を控え、女川・鮎川の漁港がある。
南三陸金華山国定公園・硯上山万石浦県立自然公園・月浦は、仙台藩遣欧使節「支倉常長」が出航した地。
鮎川は、鯨の町として知られている。
成瀬川 田園地帯が続く



「石巻市」
1189年「葛西清重」奥州総奉行任ぜられてから約400年間城下町として発達。
江戸時代には、伊達正宗の命により「北上川大改修」が行われた。その結果、田園開発が進み、江戸を結ぶ「東廻航路」の拠点として繁栄している。
仙台城・利府・小野・矢本・石巻ー石巻街道。「牡鹿半島沖・金華山参詣道」「国道45号線」



「坂上田村麻呂と奥州伝説の寺・神社」
田村麻呂が同時に建立したと伝えられる6カ寺・成敗された賊や鬼神が埋められたと伝えられている。
牧山観音(石巻市)・ 箟嶽観音(涌谷町)・ 大武観音(登米市)・ 長谷観音(登米市)・ 鱒淵観音(登米市)・ 小迫観音(栗原市)
奥州三観音は、牧山観音 ・ 箟嶽観音 ・ 富山観音 (松島町)。



「石巻城」-鎌倉時代、葛西氏が日和山に築いた城で、南北朝時代には、奥州最大の軍事拠点と云う。現在公園。
日和山公園説明板より
日和山は標高60・4m。 山上に延喜式内社である鹿島御児神社が鎮座、
中世には葛西氏が城館を構えていたと伝えられ、平成9・10年の発掘調査では、拝殿の北側から空堀の跡などが見つる。
眼下に見える北上川の河口は、江戸時代には仙台藩の買米制度によって集められた米の積出し港として、千石船の出入でにぎわい、日和山は
出港に都合のよい風向きや潮の流れなど、「日和」を見る場所であることから、その名が付いたと考えられる。
元禄2年(1689)、松尾芭蕉と曽良ー石巻を訪れた時の「曽良旅日記」には
「日和山と云へ上ル 石ノ巻中不残見ゆル奥ノ海 今ワタノハト云 遠嶋尾駮としまおぶちノ牧山 眼前也 真野萱原かやはらも少見ゆル」と
日和山からの眺望が記されている。
「奥の細道」には「・・・石の巻といふ湊に出ス こかね花咲とよみて奉たてまつりたる金花山きんかさん海上に見渡シ 数百の廻船入江につとひ 人家地をあらそひて竈かまどのけふり立つゝけたり」と表現されています。
「こかね花咲」とは、「万葉集巻第18にある大伴家持おおとものやかもちの「天皇すめろきの御代栄えむと東あづまなる 陸奥山みちのくやまに金花くがね咲く」の歌。
天平産金地は、涌谷町の式内社黄金山神社の御神体として崇あがめられた、黄金山を中心とした地域であったのですが、芭蕉の頃には金華山が産金地であると考えられていました。
鹿島御児神社の鳥居をくぐり、拝殿に向かう階段を登った右側に、延享5年(1748年)に雲裡房門人である棠雨を中心として建立された
「雲折ゝ人を休める月見かな」という芭蕉の句碑がある。
石川啄木、宮沢賢治、志賀直哉、斎藤茂吉、種田山頭火、釈超空(折口信夫)などの文人が訪れており、日和山公園には多くの歌碑や句碑などが建立。
悪天候で下界から (白いドームの奥の山が日和山)

「葛西清重」 1161頃ー1238 別名は三郎、壱岐入道定蓮 墓所は、東京都葛飾区四ツ木1丁目「西光寺」
官位ー従五位下、右兵衛尉、左衛門尉、壱岐守 。主君 源頼朝、頼家、実朝 。氏族ー桓武平氏良文流、秩父氏、豊島氏、葛西氏
父母 豊島清元、秩父重弘の娘 妻ー正室:畠山重能の娘 子ー清親、朝清、時清(孫とも)、清宗?。
「石ノ森萬画館」-仮面ライダー・サイボーグ009等の石ノ森章太郎漫画ミュージアムー
入館料800円ー石巻駅から徒歩で約10分



「支倉常長」 1571-1622 世界を一周した仙台藩士伊達侍 伊達家中の山口常成の子 叔父支倉へ養子
43歳で欧州へ旅立つ・ローマ教皇に謁見したがスペイン通商交渉は不調に終わっている。
宮城県出身彫刻家ー佐藤忠良作の常長が

太平洋を横断メキシコへ、それから大西洋でスペインについている。帰途はインド洋・マニラ、船は破損と資金不足で一年以上足止めしている。
出発から7年後、2年後病没、支倉家は、キリシタン匿った罪で断絶している。
「宮城県慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館)」石巻市渡波、渡波駅徒歩約21分。入園料 700円
日本における20世紀最後で最大のガレオン船である「サン・ファン・バウティスタ復元船」を展示する博物館。
約400年前に仙台藩主伊達政宗の命を受けて石巻市月浦から出帆した慶長使節の偉業や大航海が。
南三陸金華山国定公園・硯上山万石浦県立自然公園公園等の牡鹿半島から



「釣石神社」
市の北東部、新北上川の河口付近の北側にある。
「釣石神社」の名の由来は、御神体の巨石をしめ縄で釣りあげていて、今にも落ちそうに見えるところにある。
祭神の天児屋根命は、知恵の神様、学業の神様で、ご神体は、断崖に釣り上げられたように見える「釣石」が
男の神様で周囲14m、下の巨石が女の神様およそ8m×4mある。
巨石は、昭和53年、の宮城県沖地震でビクともしなかったことから、「落ちそうで落ちない受験の神様」として有名に、更に2011年の平成23年
「東日本大震災」で、北上川河口に近い周辺の集落は津波にさらわれ、神社も社務所や鳥居、飾ってあった絵馬などが流されたものの巨石は落ちることはなかったと云う。
東日本大震災でも動かなかった。

「女川駅から・石巻駅・小牛田駅ーJR石巻線が全線開通」
東日本大震災で被害を受けたJR石巻線(44・7キロ)が、4年ぶりに全線開通。
不通だった女川―浦宿(2・3k)が繋がる。
石巻ー曾波神ー鹿又ー佳景山ー前谷地、、、、、、。
気仙沼線で旧北上川・北上川からBRTで南三陸ー気仙沼へ移動する。



次回は、気仙沼方面へ。