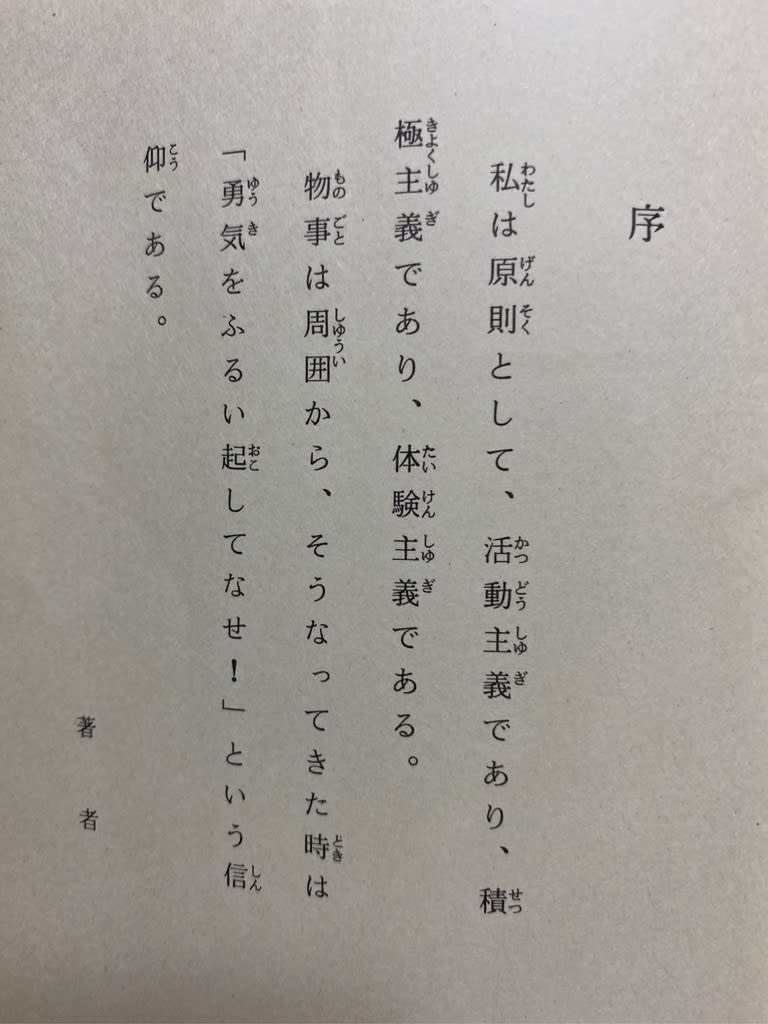例の紋付の人が導くままに、私はたんたんたる大道を飛ぶように通って(飛ぶようにというのは、足は地の上に直接ついているのではなく、三尺ばかり上をスーッとすべるように過ぎている。時によると、直接地上を普通に歩む事もあり、また、場合によっては、空地や自体が飛ぶ事もあり、またある鳥に乗ってゆくこともあり、何か大きな手に抱かれて一散にある地点に達していることもある。そのそれぞれの理由はいろいろあるが、概して言えば、高い霊界ほど。自由自在であり、低い世界ほど、一歩一歩、直接にあえぎあえぎ歩まねばならぬのである。)ある山麓に達した。
日出麿「ここはどこです。」
天使「ひらおか」
鬼雷述べる。枚岡神社である。
「どこの国です。」
「河内。」
私は何心なく坂道を登った。すると中腹にあまり大きくない、どちらかと、言えば古ぼけた一つのお社があった。
二人は問答をはじめた。
日出麿「いったい、人間は何しに生まれたんですか。」
天使「神様の御用しに……」
「神様はどこにいるんです。」
「お前のまえに」
「あなたは神様ですか?」
「いや、わしはお使いだ。わしがおるとおらぬとに関わらず、神様はお前のまえにおられるのだ。しかし、わしがお前のまえにおる時は、よりはっきり、神様はお前のまえにおられるのだ。」
「神様の御用というのは何ですか。」
「一口にいうなら、各自に、本当の自分の心の声に従って、一歩一歩、精進したら、それで善いのだ。」
「では、だれでも神様の御用を知らず知らずしているんですな。」
「まあ、そうじゃ。がしかし、今の世の人は、本当の、自分の心の声と(内鳴る神の響き)、それとは違った声とを、混線してしまって、どちらがどちらやら、分からなくなってしまっているのが多い。」
「本当の自分の心の声というのは、どんなのです?。私には、本当の自分がわかりません。始終、ぐらついておるようにしか思えません。」
「そうむずかしく考えないでもよい。その時、その折のベストをつくし、最善さえしたらよい。
誰でもみんな、途中であるんだから、行き着いた後から、考えると、過去は恥ずかしい事ばかりだ。
あの時、もう少しうまくやったら良かったとか、いまの知恵があったら、あんな失敗はしなかったとか、いろいろ悔やむかもしれぬが、それは致し方ないことである。
一つずつ、体験を重ねていって、次第に真に賢くなり、大きく広くなることが出来るのであって、最初からチットも間違わぬよう、狂わぬようやろうと思ってもダメのことだ。
それはちょうど、相手から一度も叩かれずに、撃剣の達人になろう、生まれてから一度も砂の味を知らずに、横綱になろうと企むようなものだ。
お前は、疑いもなく、造られたものである。
造られた者は、造った者の意のままに、なるより外はない。
(鬼雷述べる。人は神からの造られた存在であり、故に神の意、天命を汲まねばならない。)
最初から完全を期することは誰だって出来ない。
その時の最善と信ずる道を行ったらよいのだ。
たとえ、後になって、それが間違っていてもかまわない。
そのために、外では得られないよい教訓をあがない得たのであるから。
ところが、この場合、多くの人は、その唯一の教訓をつかまずに、ただ、失望と後悔ばかりを得ているのだから、たまらない。」
「でも、今の世の多くの人は物質主義者であって、霊魂の存続などということは、まるで
迷信かなんぞのように思っているんですもの。」
「それが前に言った混線だ。こんな人達に対しては、いくら理屈をいってもダメだ。」
「なぜです。」
「こちらの理屈と、向こうの理屈が違うからだ。赤ん坊の理屈と、大人の理屈とは違い、小作人の理屈と地主の理屈は違い、インド人の理屈と英国人の理屈とは、おうおうにして、非常に、違っているのだ。」
「神様は全知全能なんですから、ひとつ、今の世の学者たちに、霊界を見聞させてやったらいいでしょう。」
「見聞させてやっても、却って現界を混乱させてしまうまでだ。それに、大抵は浮浪霊のとりこになって彼らのおもちゃになるのがおちだ。というのは、彼らに信仰がなく、いまだ利己執着の念がつよく、ややすれば、嫉妬、怨恨などの悪念が兆しがちであるからである。だいたい、霊界は現界人に見聞さすことは、非常に危険がともないがちだ。
現界人は現界人として、ただ、今の最善を、尽くしたらそれでよいのだ。
もっとも正しい霊覚は、神格の内流である。
霊眼霊耳に、とらわれると迷信におちいりがちだ。
全て、理屈をこねまわしている間は、断じて分かっているのではない。
このことは、よくよく心得ておくがよい。」
「では、神を信ぜず、霊界を認めぬ人達を導くには、どうしたらよろしいのでしょうか。」
「みちびく?、そんなことが、クチバシの黄色い、尻っぺたの青いお前に出来てたまるか。」
語気が急に荒くなったので、心中いささか不快に感じながら、私は神使の顔を凝視した。
と同時に、恐ろしく、強い眼光に射返えされて、私の身はちぢまってしまった。
今まで慣れ慣れしく話していた私は、もう、一言も発する事ができなかった。
私は心中「悪うございました。」とお詫びした。
すると、神使は、晴れ晴れとした、いつもの調子で後をつがれた。
「いつもいう通り、自分が、自分がという気が先になっては、真に何ひとつも出来るものではない。
神様のお陰で生かして頂いている。神様のお陰でさして頂くという気持ちを、どんな場合にでも失わぬようにせねばいけない。
今から、人を導くというようなことがらお前達に出来てたまるものか。
限りなく、上には上があるのだ。
進んでも進んでも、進みきれない我々だ。
天国から直接現界へ降りての仕組みであるから、何事も惟神(かんながら)にまかして、その時その折の時局に最善をつくしたら、それで充分なのだ。
大事なことは、必ず、神が肉体に懸かってさすのだ。
現界は霊界の胞衣であり、卵であり、苗代であり、設計図であり、鋳型であり、土台であって、霊界の一切はことごとく、その基礎を現界においているのだ。
だから、宇宙的大神業も、かならずや、その基礎をまず、現界から固めてかからねばならぬのだ。
人間一個についていうも同様であって、現界において、早く神第一の霊的生活にはいり得た人は、死後ただちに、ひかりの国に安住する事が出来るが、いつまでも自己第一の物的生活を営んでいる人は、死後は実につまらない境涯にはいらなければならぬ。こっちへ来い。」
私はだまってついていった。
ある穴の入り口に立った。
仲を覗いて見ると、巡礼のような風体をした、人達が、いずれも淋しそうな顔つきをして、何かブツブツ言いながら往来していた。
非常に汚くて臭かったが、しいて中に降りてゆくと、その時、神使の姿は見えなかった。
小さい祠みたいなような建物のまえに、みんなうずくまって礼拝していた。
立てられたローソクの灯が気味わるく、トロトロと燃えて、流れた蝋が黒ずんで、そこら一面、蛇の子が重なり合っているように這うていた。
私は大急ぎでそこを過ぎて前方を進むと、また登り坂になって、一方の出口へ出た。
このトンネルのちょうど上方に普通のお宮があって、立派にお祀りしてあったが、ここへは、誰もお参りしていなかった。
この時、天使が見えた。
「あの人達はなんですか。」
「利欲一方の信仰は、ああいう状態にあるのだ。
あの人達は、まだ神第一ということがわからないのだ。
全ては上から来るということが、悟れぬのだ。
そして遮二無二あせっているつもりで、実は同じ穴の中でお百度を踏んでいるのだ。」
「どうしたら、外へ脱け出ることができるんでしょう?。」
「こんな事をしていても詰まらない。こんな所はいやだ。という気持さえ充分にわいたら、自然に上方に足が向くのだ。
いやな所にいつまでも頑張っており、あくまでも義理立てをしたり、つまらないことに、得意がっているなどは、まったくの偽善だ。」
「しかし、現界では境遇上、いたし方なくいなや所におり、つまらないことをしておらねば、ならぬ場合も多うございますが……。」
「周囲の事情がそうなっている間は、その人にめぐり(悪因縁)が、あるからだ。覚悟と努力が足らぬために、脱け出られる境遇をも、脱け出ずに、あがいている人達の方がずいぶんに多い。」