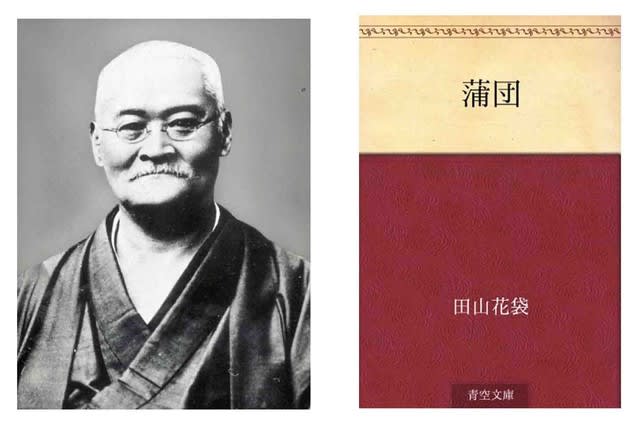主宰五句 村中のぶを
奥津城や提燈花の一ところ
独活の花山はろけさにあるばかり
夏帽子背にすべらしし髪愛し
撰一日明窓机邊花あふひ
「川辺川」とふ球磨焼酎の宜しさよ
松の実集
秋近見み 福島公夫
夕風や思考の先の蝉の声
蝉涼しひもろぎの森鳴きつつみ
三弦の音の嫋やかに夕立あと
人もまた雨に和みて花菖蒲
ビルの間の雲のしろさよ秋近み
秋 月 荒牧多美子
菩提樹の花に佛の匂ひとも
生命あるものに生命の水を打つ
開け放つだけで涼しき山家かな
葛餅や秋月はすき水音も
囲に獲物残して蜘蛛の影見えず
夏を遣る 那須久子
梅干すや三日三晩をつつがなく
ともかくも土用鰻を五人前
欠かさずや一日たりとも胡瓜もみ
総生りを日々持て余すミニトマト
居ながらに閉ざすカーテン酷暑かな
夕野火一回忌 西村泰三
梅雨しとど訃報届きし朝のごと
膝くずす梅雨の灯の下経長く
梅雨座敷曾孫おとなし一回忌
筆塚の石らしきもの木下闇
梅雨を溜め遺る小鳥の水飲み場
雑詠選後に 村中のぶを
立礼の薄茶手前よ花槐 園田 篤子
掲句は「立礼」による茶会の一景を手際よく描出してゐます。それも席の花がアカシアに似た「花槐」の浅黄白色の花とあれば、その「薄茶手前」の所作が新鮮に浮かんで来ます。
立礼とは辞書にもありますが、椅子と卓とを用ゐて茶をたてる点前で、茶室でも行はれます。私は近くの水戸の偕楽園で、女子高生も混へた此の茶会を見開した事がありますが つまり昨今の一般の生活様式も椅子式になり、外国の人達も増え、立礼は最も身近な茶の湯になってゐるやうです。
薄茶手前といふ言葉も辞書に見えますが、一人に一碗づつ、飲みまはすこともなく、それに幾口飲んでもよいことになってゐますので、この手前もまた一般に受けがよいやうです。
絽の裾の捌き美し炭手前 同
一句はまた「絽」のきものの、女人の亭主の、炭をつぐ際立った容姿を詠みとつてゐます。やはり作者の美意識が生かされた、平明にして情感豊かな詠句と言ってよいでせう。
青田風あすのわたしにどんな風 松尾 敦子
前に「方丈記」を読むといふ一句がありますが、方丈記といへばつひ口に出る (ゆく河の流れは絶えずして)と冒頭の一節が浮かびますが、掲句の 「あすのわたしにどんな風」とは、ひいては方丈記を「声に出し読む」心情と相通じた詠情ではと思ったりしました。 してまた、口語調の措辞も然る事ながら、その自問自答する、自在な句境に感じ入りました。
青空の久し振りやなとんぼ生る 竹下ミスエ
「青空の久し振りやな」は、青空が覗くのは久し振りだなあといふこと。このやうな口誦性の措辞に「とんぼ生る」とは、読者には初初しいとんぼの四枚の薄羽が見えて来る筈です。それに一句もまた自在な詠出です。
ところでこのとんぼの句、先の青田風の詠にも共通することですが、蛇笏賞の女流岡本眸さんが(俳句は日記)と強く提唱してゐたのを思ひ出しました。事実、実作の私共にとって最もな事で、銘すべき言葉だと深く共鳴する所です。
青桐や思ひ出多き師の屋敷 村田 徹
なんとなく心魅かれる句です。作者にとって師とは宗像夕野火さんの事で、本誌発行の抑抑の方です。その「師の屋敷」を訪れての詠ですが、本当に竹林、池水も据ゑた広い家屋敷です。この全望の中心である「青桐」 の措辞ですが、青桐の樹がまた実に印象的です。一体に実景を点描した、観念的でない表出に師への思ひが伝はつて来ます。
生きてゐる証しの汗の有難く 安永 静子
前号にも採択させて貰ってゐますが、その予後の一句です。一般に健常者は汗を厭ふものですが、作者は生還した「証しの汗の有難く」と、その喜びを生生しく叙してゐます。普通に「生きてゐる」私共にとって、この汗への賞賛は思ひも寄らないことです。翻って大手術の後複帰した作者の、俳句に対する心根に自然と頭が下ります。更に作者の、いのちへの観照を思ひ知らされました。
沖ノ島遠く峙つ卯浪かな 塩川 久代
「沖ノ島」とは、いはゆる 八神の島 沖ノ島です。土地の漁師の人は(沖ノ島は、お神様の海やけん)と言ってゐる事が文献にあります。先年、都心の出光美術館で(宗像大社国宝展)を拝観しましたが、ビデオでも沖ノ島は、玄界灘の絶海の孤島であることがよく分りました。掲句は正にその通りの詠情です。
蛇足ながら沖縄の久高島も神の島、神宿る島と謂れてゐます。
炎天や我が影さへも短かくて 川上 恵子
「我が影さへも短かくて」、つまり「炎天」 の真っ只中、日ざしの直下に在ることを直叙してゐるのです。女性の方に拘はらず、勇ましい、割目すべき一句だと思ひます。
浜木綿や白きフエリーと青き空 多比良美ちこ
作者は島原の方。浜木綿の彼方、青空の下、有明海を渡るフェリーを詠じた南国の風光です。なんとも一幅の風景画を観るやうです。
峰雲や運河しづかに水湛へ 山岸 博子
札幌市在住の作者、掲句の「運河」とあれば直ぐに小樽の倉庫街の運河を思ひ出します。その「峰雲」の湧き立つ影を映した疎水を「しづかに水湛へ」と叙して、盛夏の午下らしい風景を詠じてゐます。季語の扱ひ方、描写の確かさ、それに旅愁を誘ふ一句です。