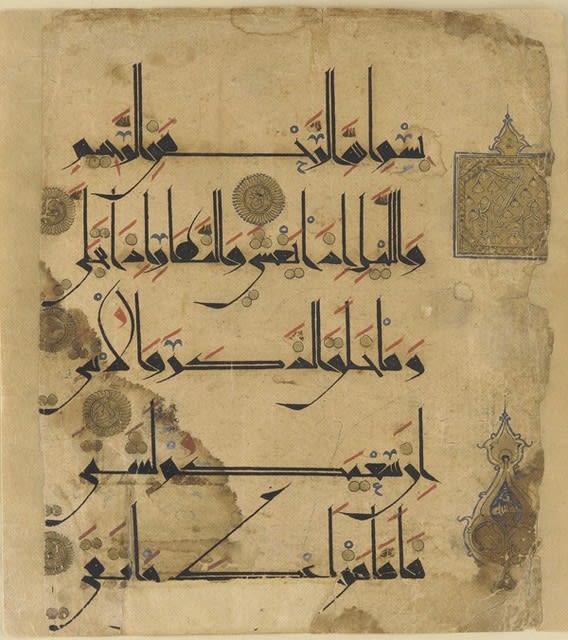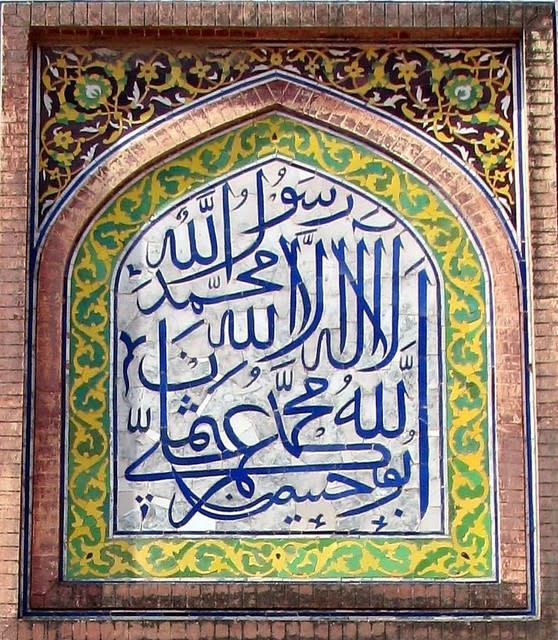函館郊外の武井の島(むいのしま)と同じ字を書く古武井(こぶい)の地域には
縄文早期から縄文後期、続縄文、擦紋時代と長きにわたり人が暮らした遺跡があります
昨年、武井の島がある戸井町の貝塚が12月函館市文化財に指定され
函館博物館において23日から6月14日まで戸井貝塚展が行われています
骨格器、貝製品による採取で現代と同じような食生活をしている

津軽海峡の向かいは大澗、戸井のマグロも高級品として扱われるようになってきたようです
戸井町と函館市街の間には志海苔館跡
和人の不合理な要求にアイヌが蜂起しコシャマインの乱の起った場所
志海苔館跡の近くからは日本で最多の古銭
唐、南宋、北宋、明の時代の古銭が大量に見つかり
古くより中国までの広域と交易していたようです
アイヌの不満を募らせる売り買いがあったことを示すものなのか
現在でも道南の干しナマコは中国で高額で取引されるそうです
戸井の漁師に信仰される丸山龍神様が、5キロほど山の中に有ります
豊魚を祈願し、海での見立てとされた丸山
十年ほど前はじめて丸山龍神様を訪ねた時
青年が白装束で太古を鳴らし祠の前で祝詞をあげていました
母親が熱心に信仰していたと
そんな祝詞の中、誰もいないはずの山に家族の遊ぶ声
色々不思議な体験を何度かしました
その丸山の龍穴に入り武井の島から龍神様が飛ぶと
丸山龍神を祀る方から聞いたことがあります
戸井貝塚の発掘される青龍刀
現代の漁師の生活と縄文の漁師の違いは
海山川に神の息吹を観じることではないだろうか
武井の島の夕陽にそんな想いが浮かびます