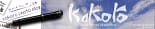酒田市日吉町 下日枝神社にて□□
先々週の15日に、酒田市内の日和山にある山王の森に紅葉を求めて出かけたときのこと、この森の中にある日枝神社で、5歳の男の子が袴姿で両親とお祖母ちゃんに付き添われ七五三のお参りをしていました。
我が家の子供達もここで七五三参りをしたので、何だかとても懐かしく眺めました。
現代は、七五三というと何となく形式的な行事、というような雰囲気で捉えられ、そんな形式的な堅苦しいものをやるよりも気楽に外食なんかで美味しいもの食べて、なんていうのが多いようです。
まあ、子供の成長を祝うと言うことでそれも良しとは思いますが、七五三の由来を知って、自分たちだけの満足ではなく、日本の伝統文化に添ってお祝いして、子どもを育ててくれたいろいろなものに感謝する日にした方がより心が豊かになると思うのです。
昔は子どもが3歳まで生き延びるということはとても大変だったそうです。さらに5歳、7歳までとなるともっと大変だったそうで、そんなこともあり子供は生まれてから7歳までは「神様からの預かりもの」という意識を持っていたのだそうです。
七五三というお祝いの文化は、この考えをもとに生まれたのです。
無事に7歳まで成長出来た子どもはお祝いをし、神社で氏神様(自分が住んでいるところを守ってくれている神様)にお参りして、氏子札を貰いました。氏子札を貰って初めて神様からの預かりものから人格として認められ、地域社会の仲間入りを果たすことができたのです。
日本では奇数を陽数、偶数を陰数といって奇数は縁起のいい数という考え方があります。
神様から子どもを預かっている間の縁起の良い奇数歳3歳、5歳、7歳を「よくぞここまで生きて成長してくれた」という喜びをもってお祝いするようになったのが七五三の文化なのです。
化学や医療技術の向上で生存率が高い現代と、低い生存率の中を無事に育てなければならなかった昔とでは喜びの度合いはやはり違うのでしょうが、子どもを思う親の心は昔も今も変わらないものです。
神様から預かった大切な子どもが無事に成長できた喜びを祝い、氏神様に報告して子どもを育ててくれた様々なものに感謝する気持ちを忘れない。
子どもが育つのが当たり前になった現代だからこそ、そんな七五三の文化が大切なようにも思うのです。


ちなみに、奥に見える古ぼけたビルは、
映画 『おくりびと』でNKエージェントとして使われた建物です
→ ここ
 |
赤ちゃん・子どものお祝いごと―出産から小学校入学までの行事 成美堂出版 このアイテムの詳細を見る |