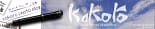山形県遊佐町丸子□□
前回のエントリーで私は、「春が来た」の歌詞の、春が来る順序が逆なのでは?と書いたのですが、 「もんぜんひつじ」さんから以下のようなコメントをいただきました。
-----------------------------
春は何処から来るのでしょうか?
当然下界の里や野の方が先なんですが、「昔の信仰」(今も残っている所もありますが)は
山の神が里に下りてきて田の神になり豊富な雪解け水で田や畑を潤し、収穫後は山の神
へと戻ってゆきます。
こういう山ノ神への崇拝から春は山から~となったと考えましたがどうでしょうか?
-----------------------------
このコメントを読んだ瞬間、はっとしました。
そうなのです。その通りだと思いました。
庄内地方の田んぼには「祠(ほこら)」や小さな「社(やしろ)」をよく見かけます。
(前回のエントリー写真に見えます。今回の写真は暗くて見えませんが、松木の中にあるのです。)
これは、春に山から下りてくる山の神を田んぼにお迎えし、田の神となって水を絶やさずに稲を見守って欲しい、という願いのためのものなのです。
春は、野や里に先に訪れ、そして山に上がって行く、というのは自然の現象を目で捉えたもの(つまりは雪解けや植物の芽生えの順番)ですが、農耕の民がその生活で春を感じるのは、山の神を田畑にお迎えし、そこから年が始まると感じるわけですので、山の神が降りてくる=春がやってくる、春は山から降りてくるものなのですね。
例えば、春の代表的な花と言えば、我々日本人にとってはなんと言っても「桜」ですが、その語源は(諸説あるようですが)、サクラの「サ」は田の神を意味し、「クラ」は「依代(よりしろ)」や「座」を意味するのだそうです。
つまりは「サクラ」とは田の神が降りてくる木という意味なのです。
「桜」が咲いて「春」がやってくる、と考えた場合、「桜」は「田の神・山の神」が降りてきて咲くのですから、春は山から里へ、野へ、となったのでしょう。
私が浅はかでした。単純な歌詞だと勘違いしていましたが、日本の信仰や風習、生活、人々の感情などが密かに息づいている素晴らしい詩なのでした。
高野辰之さんはやはり偉大な作詞家です。
「もんぜんひつじ」さん、ご指摘ありがとうございました。目が覚めました。(^^;)
浅学を恥じ入るばかりです。これからも色々と教えて下さ~い。(^^)/
「もんぜんひつじ」さんのブログは ここ ←です。