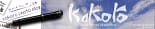|
|
|
|
たとえば、
|
|

撮影DATA
Nikon D750
TAMRON SP 90mm F/2.8 Di MACRO VC![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 |
明日はきっといい日になる |
| クリエーター情報なし | |
| Della Ink. |
「あっ・・、良いなぁ♪」
そんな ささやかな嬉しさの瞬間
心に懐かしく そよ風が吹く瞬間
そんな瞬間を 大切に思う今日この頃です

撮影DATA
Nikon D300s
TAMRON SP 90mm MACRO F2.8
 |
松任谷由実40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。 (通常盤) |
| クリエーター情報なし | |
| EMIミュージックジャパン |
久しぶりの、本当に久しぶりのエントリーです。
気がつくと季節は秋。
私事ですが、7月に母を亡くしてしまいました。
親の死はいずれはやってくるもの とそれなりに覚悟はあったのですが、それはあまりにも突然やってきてしまいました。
悲しさは一瞬ですが、その後の喪失感といおうか寂寥感はその覚悟を超えて如何ともしがたいものがありました。いまでもその寂しさは続いています。
親の死は覚悟していたとしても、その存在が現実として今はもう無いとあらためて突きつけられたときの寂しさがこれほどのものとは思いもしませんでした。
それは日に日に薄らいではいくのでしょうが、無くなることはきっとないのでしょう。
人は皆、親を亡くします。
親よりも先に逝ってしまう、という最大の親不孝をおかさない限り、親の方が先に旅立ちます。その覚悟は誰しもしなければならないと思います。でもできるなら、それは穏やかに自然にやってきてもらいたかった。私たち子どもや孫たちが見守る中で、ありがとうという言葉に包まれながら旅立ってほしかった。
7月、今年もまた暑い夏が始まろうとしているさなかに、母は突然、誰にもさよならを言わずに旅立ってしまいました。
“ おかあちゃん、でんぶ ちゃっちゃど逝てしまたなだの。おかーの口癖「じゃぁね~♪」ぐらい言て欲しがったのぅ。 へばの、まだの、ありがどの。 ”
季節はもう秋。
庭には母が植えた秋咲きの花たちがきれいに咲いています。
母の味


撮影DATA
Nikon D300s
TAMRON SP 180mm F3.5 MACRO
たとえどんなに離れても、会えない時が続いても
つないだ手を離さないこと
この空に誓うから
Rake – 「誓い」より
あの日 3.11
東北被災地へ日本中の人々が心を寄せた
世界中の人々からエールを受けた
そして「絆」が生まれた
あの心は今でも変わりありませんか?
被災地では今もなお、行方不明者の捜索が続いています
今もなお、見つかった行方不明者の通夜や葬儀が毎日行われています
もはや自力では処分できない膨大な瓦礫が、前進することを阻んでいます
つないだ手を離さないこと
撮影DATA
Nikon D300s
Nikkor ED 70-300mm F4.5-5.6G VR
Nikkor DX 35mm F1.8G
 |
河北新報特別縮刷版 3.11東日本大震災1ヵ月の記録 |
| クリエーター情報なし | |
| 竹書房 |
 |
河北新報のいちばん長い日 震災下の地元紙 |
| クリエーター情報なし | |
| 文藝春秋 |
 |
ともしび |
| クリエーター情報なし | |
| 小学館 |
ただ、風を感じただけで
何か懐かしい気持ちになったことはありませんか
ただ、風に吹かれただけなのに
何故か満ち足りた気分になったことはないでしょうか
今、自分がここにこうして存在し 生きている
そんなあたりまえのことが 何か嬉しくて 何処か懐かしくて
そんな気持ちになったことはありませんか
稲穂を渡る風に豊かな秋を感じ
身を刺す冷たい風に冬の存在を知り
雪を融かす暖かな風に春の訪れをよろこび
そして、風鈴の音色に夏を感じる
現代人はそんな風の言葉を感じる余裕もなく生きています
でも、そんな私たちでも
ある日 風に吹かれた瞬間
何か心を揺り動かされるようなことがあります
からだを吹き抜ける風の感覚
風の記憶
私たちは 風の中を生きているのだから・・・
blowin'in the wind

酒田市最上川河口より
 |
|
|
クリエーター情報なし |
|
|
ミュージック・シーン |
小学生の頃、剣道を習っていました。昭和45年頃のことです。
田舎の小さな小学校でしたので部員は多くはありませんでしたが、それでも10人くらいはいました。
酒田は剣道の盛んな地域でしたのでどの学校でも剣道の練習があり、大会ともなると会場に入りきれないほど選手がいたものです。
今は子どもの数も少なくなり、剣道を習う子もほとんどいなくなってしまいました。
久しぶりに小学校の体育館を訪れたら、小さな女の子が先生に稽古をつけてもらっていました。
夏、古い体育館で少女は汗をいっぱいかきながら、元気な声で打ち込みをしています。
少女のかけ声と乾いた竹刀の音、外からはうるさいほどの蝉の鳴き声がしています。
遠い夏の記憶。
なんだか無性に懐かしくなって、携帯電話のカメラで写真を撮りました。
ふと、あの頃に戻りたくなる季節、夏。
けたたましい蝉時雨は、人の魂を現実の世界から遠いあの日に連れて行ってくれる水先案内人のようです。
 |
あの夏の日 葉 祥明 自由国民社 このアイテムの詳細を見る |
つくし
忙しさにかまけてブログの更新が滞ってしまいました。
気がつけば季節はもうすっかり春。
野道には土筆がたくさん顔を出しています。
すでに桜は散った地方もあるようですが、庄内地方ではこれから桜の季節の始まりです。
 |
「いのち」と「こころ」の教科書 手塚 治虫,谷川 彰英 イーストプレス このアイテムの詳細を見る |
酒田市日吉町 下日枝神社にて□□
先々週の15日に、酒田市内の日和山にある山王の森に紅葉を求めて出かけたときのこと、この森の中にある日枝神社で、5歳の男の子が袴姿で両親とお祖母ちゃんに付き添われ七五三のお参りをしていました。
我が家の子供達もここで七五三参りをしたので、何だかとても懐かしく眺めました。
現代は、七五三というと何となく形式的な行事、というような雰囲気で捉えられ、そんな形式的な堅苦しいものをやるよりも気楽に外食なんかで美味しいもの食べて、なんていうのが多いようです。
まあ、子供の成長を祝うと言うことでそれも良しとは思いますが、七五三の由来を知って、自分たちだけの満足ではなく、日本の伝統文化に添ってお祝いして、子どもを育ててくれたいろいろなものに感謝する日にした方がより心が豊かになると思うのです。
昔は子どもが3歳まで生き延びるということはとても大変だったそうです。さらに5歳、7歳までとなるともっと大変だったそうで、そんなこともあり子供は生まれてから7歳までは「神様からの預かりもの」という意識を持っていたのだそうです。
七五三というお祝いの文化は、この考えをもとに生まれたのです。
無事に7歳まで成長出来た子どもはお祝いをし、神社で氏神様(自分が住んでいるところを守ってくれている神様)にお参りして、氏子札を貰いました。氏子札を貰って初めて神様からの預かりものから人格として認められ、地域社会の仲間入りを果たすことができたのです。
日本では奇数を陽数、偶数を陰数といって奇数は縁起のいい数という考え方があります。
神様から子どもを預かっている間の縁起の良い奇数歳3歳、5歳、7歳を「よくぞここまで生きて成長してくれた」という喜びをもってお祝いするようになったのが七五三の文化なのです。
化学や医療技術の向上で生存率が高い現代と、低い生存率の中を無事に育てなければならなかった昔とでは喜びの度合いはやはり違うのでしょうが、子どもを思う親の心は昔も今も変わらないものです。
神様から預かった大切な子どもが無事に成長できた喜びを祝い、氏神様に報告して子どもを育ててくれた様々なものに感謝する気持ちを忘れない。
子どもが育つのが当たり前になった現代だからこそ、そんな七五三の文化が大切なようにも思うのです。


ちなみに、奥に見える古ぼけたビルは、
映画 『おくりびと』でNKエージェントとして使われた建物です
→ ここ
 |
赤ちゃん・子どものお祝いごと―出産から小学校入学までの行事 成美堂出版 このアイテムの詳細を見る |
すずらん
先日、知り合いの若いお母さんから聞いた話です。
小学2年生と1年生の息子たちが、初めての母の日のプレゼントということでスズランの鉢植えをプレゼントしてくれたそうです。
母の日と言えば赤いカーネーションが定番、なのに何故スズランだったかというと、昨年の5月にそのお母さんが息子たちを連れて近くにある実家に帰ったときに、そこに咲いているスズランを好きだと言ったことがあって、お兄ちゃんがそれをしっかり憶えていたのだそうです。(おじいちゃんおばあちゃんの家に咲いている小さな白い花。)
お母さんが大好きなあの白い小さな花を、おじいちゃんおばあちゃんの家に子どもたち二人はもらいに行きました。ところが、スズランはまだ咲いていなかったのです。庄内地方ではスズランは5月中旬頃からチラホラ咲き始めるのです。
ガッカリして半べそをかいているお兄ちゃんを見兼ねたおじいちゃんが、花屋さんを一緒に探し回ってくれて無事スズランを手に入れることができました。
思いもよらない子どもたちからのプレゼント、お母さんは嬉しくて嬉しくて嬉しくて・・・、感激のあまり泣きだしてしまったそうですが、泣いたお母さんを見て子ども達はビックリ、何か悪いことをしてしまったのかと勘違いして、二人ともごめんなさいと泣きだしてしまったのだそうです。
お母さんは、悲しくて泣いたんじゃないのよ、とありがとうを何度も言いながら息子たちと三人で泣きあいっこをしたそうです。
きっと、子どもたちもお母さんも一生忘れられない母の日になるのでしょうね。
スズランの花言葉は、『純粋』『純愛』『幸福の再訪』、そしてヨーロッパでは『聖母の涙』と言われているそうです。



1000の星のむこうに (大型絵本)
アネッテ ブライ
岩波書店
このアイテムの詳細を見る
月うさぎ さんのブログに、とても素敵なエントリーを見つけました。 写真も詩も、やさしい潮風のように心地よい雰囲気がお気に入りです。
なんとなく 幸せ
浜辺を のんびり
あなたと歩く
なんとなく 幸せ
陽だまりで ボーっと過ごす
なんとなく 幸せ
ふっと、時折感じる
この なんとなく幸せが
一番 心地よい
↓
(小さな旅 by 月うさぎさん)
大きな幸せなんて、滅多に訪れてはくれません
何となく、幸せ
何となく、心地良い
それだったら、何となく訪れてくれそうです
気持ちの持ちようで、いくらでも見つけられそうな気がします
なんとなく、しあわせ
幸せな人生って、実は
何となく幸せなことを
たくさん知っているかどうか
のような気がします
我が家の庭にも、梅が咲き始めました♪
 |
スヌーピーたちの心の相談室――(1) 楽天家になる法 (講談社 α文庫) チャールズ M.シュルツ,谷川 俊太郎 講談社 このアイテムの詳細を見る |
生きる
Nikon D200 Nikkor ED70-300□□
山形県酒田市 最上川河口にて□□
先日、本屋さんで 『「生きる」~私たちの思い~ 』 という本を買いました。
泣きたくなるほど優しい本です

生きる わたしたちの思い
谷川 俊太郎 with friends
角川SSコミュニケーションズ
このアイテムの詳細を見る
これが実に素晴らしいのです。
この本は、詩人である谷川俊太郎さんの詩「生きる」という作品に、詩を読んだ方達それぞれが考える「生きる」をつなげよう、とインターネットの交流サイト「ミクシィ」でトピックが立ち、あっという間に何千という投稿があったものを本にしたものだそうです。
谷川俊太郎さんの「生きる」という詩は、私もだいぶ以前に知り 大好きな詩でした。
生きる ~谷川俊太郎~
生きているということ
いま生きているということ
それはのどがかわくということ
木もれ陽がまぶしいということ
・・・・・・
と始まる谷川さんの詩は、私たちの身近な風景や心象、毎日湧きあがってくる感情や些細な心の動き、身の回りにある美しさや危うさ、それらを短い一言にして重ね、人が生きている、とはどんなことなのか?という風景を、さりげなく、やさしく、そして力強く切り取ってみせる素敵な詩です。
一人の詩人が言葉を磨きに磨いて削り出した「詩」
その詩に続けて、詩人でも何でもない一般の人々が、自分の言葉を詩にしてつなげていくのですが、その人々の生な言葉が実に生き生きとそこに在り、心に響くのです。
例えば、SUSANさんの「生きる」ということ、
メールの返信を 待つということ
そして自分の気持ちに気づくということ
あっこさんの場合、
流れる涙が あなたのためだということ
有さんは、
多くの人の死を見送るということ
いつか見送られるその日まで
あおによしさん、
初恋の人から借りた本を
再び読み返すということ
さんぼさん、
「もう私はダメだ」と考え
「未来は何も見えない」などと考えながら
きちんとお腹が空いて お酒も飲みたくなって
今日の夕焼けをみて感動していること
それぞれの言葉には、その言葉を紡ぎ出した経緯みたいなものが書いてあり、これもまた読んでいて面白いのです。人間が100人いれば100の「生きる」があるのだ、とあらためて納得させられます。
そして、「生きるって良いなぁ。」「人間って可愛いなぁ」と、何だか勇気が湧いてくるのです。
この本、超オススメです。(^o^)v
では、私も一句・・・・・、じゃなくて、一言
素晴らしい瞬間に出会い、
ああっっ♪と急いでカメラを取り出し、
パシャッとシャッターを切ること。
そして、
家でその写真を見て、ガッカリすること。
それでもカメラを持って歩くということ・・・。
素晴らしい瞬間はいつも突然やってきます。心を躍らせながら、焦り急いでカメラバッグからカメラを取り出し、レンズを交換し、フィルタを確認して、構図を決め、シャッターを切るのです。その素晴らしい瞬間を確かにカメラに納めたと思ったときの感激・・・。
そして、ワクワクしながらコンパクトフラッシュから画像をパソコンに取り出し確認した瞬間、まず間違いなくガッカリするのです。(-_-;
もう半段アンダーにすべきだった、ピントが甘かった、PLをかけすぎた・・・、後悔が津波のようにやって来ます。被写体に感動しすぎて冷静さを失う。何度となく経験してもやはりやってしまう失敗です。
それでもまた撮り続けるのは何故???
そしてもうひとつ、
子は 切ないものだと 知ること
そして、切なく温かいものを抱きながら
子のしあわせを願い続ける日々を送ること
親になってはじめて知ることがあります
それは
子は可愛いものではなく、切ないものだということ
しあわせになって欲しい、と
ただ ただ 一心に 願い続ける日々を送ること
そして
その願い続けた歳月のことを「しあわせ」と呼ぶのかもしれません
→ 「祈り」 ということ
・・・・・・
人は愛するということ
あなたの手のぬくみ
いのちということ
~谷川俊太郎
 |
生きる わたしたちの思い 谷川 俊太郎 with friends 角川SSコミュニケーションズ このアイテムの詳細を見る |
映画『山桜』を見ました。
封切りは昨年の5月だったのですが見に行けず、12月24日のDVD発売を予約して買ったのですが、年末は忙しくてお正月休みでやっと見ることが出来ました。
私にとっては、巷の評判以上に、とても素晴らしい映画でした。
この映画『山桜』は同名の原作が『時雨みち 』(1981年青樹社、1984年新潮文庫)に収録されており、私は未だ読んだことがありませんでした。
昨年、映画化になると聞きつけてさっそく購入してじっくり読んだのですが、これがとても素晴らしい。(^^)
端正で品高い文章、美しい風景描写、温かい視線の人物描写、そんな藤沢小説のエッセンスが約20頁あまりの短編に見事に咲いていました。
そんな原作の映画化ですので、とても楽しみにしていたのですが、期待を裏切らない素晴らしい出来だと思いました。
藤沢さんのご長女である遠藤展子さんが「まるで父の小説を読んでいるような錯覚を覚える映画でした。本のページをめくるように父の原作の映画を観たのは初めての経験でした。」と感想を述べておられるとおり、まさに藤沢作品を読んでいるような詩情豊かな映画です。
決して声高にならず静かで淡々とした流れの中に、凛と真っ直ぐに立つ人間の気高さ、美しい北国の風景描写と人々の心情、そして少ない台詞の行間に溢れてくる美しい日本人の心。
東山紀之さん演ずる手塚弥一郎はほとんど台詞がありません。しかし、その無言で在ることの存在感、立ち居振る舞いの美しさ、そして殺陣の潔さが実に見事です。
藤沢さんの小説には必ず魅力的な女性が登場しますが、この映画でも女性がとても魅力的です。
野江を演ずる田中麗奈さんはもとより、野江の母親役の壇ふみさんの微笑みの温かさ、「あなたはほんの少し回り道をしているだけなのです」と言う台詞に、娘の気持ちを思いやる優しさが溢れています。
それと、ラストシーンの手塚弥一郎の母親役の富司純子さんが実に素晴らしい。
全てを肯定して包み込んでくれるような優しい微笑み。小説では野江のこのときの心情を「取り返しのつかない回り道をしたことが、はっきりとわかっていた。ここが私の来る家だったのだ。なぜもっと早く気づかなかったのだろう」と表現していますが、映画での富司純子さんにはこの野江の今までの思いや苦労、後悔、そういった全ての時間を肯定して迎え入れてくれている温かさが感じられました。
自分の全てを肯定してくれるような温かさに、野江は泣くのです。 その涙の美しいこと・・・。
そして映画はここで終わります。物語は最後、はっきりとした結末は示しません。
しかしこの先にどのような結末が待ち受けていようとも、彼らは自ら選び取った人生を決して後悔はしないだろう、という確信を残して映画は終わります。
この終わり方も実に見事な幕切れだと思います。
慎ましく控え目で、それでいてまっすぐな恋の物語、そして、この静寂の中に凛として佇むような感覚、久しぶりに日本の心の美しさと繊細さを感じさせてくれる素晴らしい映画に出会った、と感じています。
「山桜」の花言葉は、「あなたにほほえむ」そして「気高さ」です。
 |
山桜 [DVD] バンダイビジュアル このアイテムの詳細を見る |
Nikon D200 TAMRON 17-50□□
山形県遊佐町落伏□□
男たちの黒い姿は、鳥海山、月山と連なる山脈の麓の方角を目ざして小さく消えて行こうとしていた
と辰之助は思った。
白木の箱に納めた嘆願書は、佐助の曲がった背に背負われているはずだった。
『 義民が駆ける 』 ~ 藤沢周平
天保11年(1840年)、江戸幕府は、庄内(酒井)藩を長岡に、長岡(牧野)藩を川越に、川越(松平)藩を荘内に移す幕命を下しました。いわゆる 三方国替え です。
当時の庄内藩は14万石でしたが実収20万石以上の裕福な藩でした。庄内藩の十代目藩主、酒井忠器公は名君の声が高く領民に慕われていました。それが何故か7万石の長岡藩に移封させられるのです。これは財政難に苦しむ川越藩主松平斉典が、将軍家とのコネをつくり賄賂をばら撒き、川越よりもはるかに経済の内容がいい庄内への国替えを画策したことから起きた国替えだったのです。
「何も悪いことをしていない、おらだの殿様が、なして余所さ移されでしまうなだ?」
酒井公に対する思慕や、替わりにやってくる新藩主の過酷な年貢の取り立ての噂に恐れをなした農民、権益を失うことを恐れた商人、石高が減る移封先で放免になる武士に至るまで、領民が一丸となって庄内酒井家に対する命令撤回の嘆願運動を展開したのです。
嘆願運動の方法は「直訴(かご訴)」。当時は打ち首覚悟の犯罪でしたが、庄内の農民たちは怖れることなく合計7回にわたる命をかけた直訴を次々と幕府や諸大名に続け、ついには幕命を撤回させたのです。(この運動のリーダーの中心となったのが玉龍寺(遊佐郷江地)の文隣和尚で、遊佐町稲川地区では今でも幕命取消しが庄内に知れた7月16日に『 載邦碑祭 』が行われています。)
徳川時代の大名家は250ほどあったと言われますが、国替えが一度もなかったのは庄内藩の他数藩だけだそうです。藩主と領民の絆が幕府を動かし、ましてや幕府が命令を取り消すというのは、徳川幕府の絶対的な体制にあった当時としては、異例中の異例で始めての大事件です。
この快挙をモデルに書かれたのが藤沢周平さんの「義民が駆ける」。上記の一節は、まさに志願した農民が嘆願書を持って庄内を出発し400㎞の江戸迄の苦難の旅路に出ようとする場面なのです。(犯罪行為ですので真っ当な道は通れず、人が通らない道を選んでの400㎞です。スゴイ!)
緊迫感のある展開と農民たちの心情を庄内弁を交えリアルに描き、幕府の沙汰を覆した痛快な傑作です。
ちなみに、幕末最後の戦い「戊辰戦争」の時、東北と越後の諸藩は幕府方となり「奥羽越列藩同盟」を結び新政府軍と戦いましたが、特に庄内藩は酒井家と領民が一致団結し、酒田の本間家の莫大な献金もあり最新鋭の武器を装備して連戦連勝だったそうです。
しかし、東北諸藩が続々と新政府に降伏、盟友の会津藩が降伏したのを見て、庄内藩はほぼ無敗であったにもかかわらず恭順、撤兵し、この庄内藩の降伏をもって日本の全藩が新政府軍の支配下に入ったのだそうです。
戊辰戦争に敗れ、いったんは公地没収された酒井家ですが、会津藩は事実上取り潰されたのに対し、庄内藩は新政府の西郷隆盛公が藩主と領民のあまりにも強い絆に感心して寛大な処分となり、いまも酒井家と庄内の人々の絆は続いているのです。

Nikon D200 TAMRON 17-50
山形県遊佐町落伏


 |
義民が駆ける (講談社文庫) 藤沢 周平 講談社 このアイテムの詳細を見る |
里の風景
Nikon D200 Nikkor ED70-300□□
山形県真室川町□□
地球温暖化、オゾン層破壊、大気汚染、酸性雨、水質汚染、土壌汚染、砂漠化などなど、地球は今、深刻な問題を抱えています。
最近は特に急激な環境悪化による影響が顕著に出て、ニュースは連日そのことを伝えています。そして、残念ながらこの地球環境の悪化はすべからく人間の所業が原因であることは明らかです。
テレビのコメンテーターは叫びます。『地球を救え。』、『地球を守ろう。』
そのことの主旨についてはまったく異論がありません。今、何とかしないと取り返しのつかない事態が地球に起こるのだと思います。
ただ、最近のこの表現、私にはどうもしっくりこない部分もあるのです。
『救え』、『守れ』・・・・・。
言葉尻を非難するつもりはありませんが、何か人間の傲慢な部分が垣間見えるような気がする、と言ったら考えすぎでしょうか?。今風の表現を借りれば『上から目線』と感じてしまうのです。
そもそも、こうなった原因は私たち人間なのに・・・。
日本人は古来から自然と共生してきました。
自然の恵みへの感謝、自然を畏敬する謙虚さ、八百万の神というあらゆるものへの信仰、そして四季の移り変わりを愛で豊かな叙情性や情緒性を育んできたはずです。
私が子供の頃は、ゴミなんてほとんど出ませんでした。食べ物を粗末にしたら親からひどく怒られ、わずかに出た残飯は家畜の餌になり、その家畜の糞尿は畑の肥料になったのです。無駄なく資源を生かす精神、などと言う格好の良いものではありません。ただ、無駄なことは罪悪で、神様(自然)から罰(バチ)をあてられるのではないか、といった感覚、自然を畏敬していたのです。
人間は自然の中で生かされている、という感覚が最近の日本人には無くなってきたのでしょうか。
『救え』『守れ』と言った言葉は、自然を征服の対象物と捉えた欧米人の感覚に近いものの考え方のように感じてしまうのです。
地球環境の悪化は、人間の驕りやエゴがまねいたものです。
自然と共に生きるという意識が大切なのではないか、と感じています。
わたしたちが 大地に属しているのだ
あらゆるものが つながっている
わたしたちが この命の織り物を織ったのではない
わたしたちは そのなかの 一本の糸にすぎないのだ
インディアンの首長シアトルの言葉
全文はこちらをご覧下さい。→ ここ
 |
父は空 母は大地―インディアンからの手紙 寮美千子・編訳 篠崎正喜・画 パロル舎 このアイテムの詳細を見る |

Nikon D200 Nikkor ED70-300□□
山形県鶴岡市羽黒町□□