身近な植物図鑑 ショカッサイ(おおあらせいとう、ムラサキハナナ)一部変更
今年の「しょっかさい」おおあらせいとう、むらさきはななは、こんなに貧弱でした
これでは、なんの花かわかりせんよね、
いままで、この花を「花ダイコン」とよんでいましたが、間違いでした
外見が似ているのでそう読んでいたようで
ウィキペディアによると
オオアラセイトウ (Orychophragmus violaceus) は、アブラナ科オオアラセイトウ属の越年草。別名にショカツサイ(諸葛菜:諸葛孔明が広めたとの伝説から)、ムラサキハナナ(紫花菜)。このため Orychophragmus属はショカツサイ属、ムラサキハナナ属とも呼ばれる。
ハナダイコン(花大根)(カブ)とも呼ばれることがあるが、この名前は花の外観が類似した同科ハナダイコン属の Hesperis matronalis にも与えられているため混乱が見られる(ダイコンが野生化したハマダイコンとも別種)。
基部は耳状で茎を抱き、縁には不揃いの鋸歯がある。花は茎先につく総状花序で、薄紫色の花弁には細い紋様がある。花期の後期では徐々に花弁の色が薄くなり、最終的には白色に近くなる。稀に白花もある。花弁は4枚が十字状に・・・
むむっつ!! この花の形の説明によると、家のはオオアラセイトウとも、ムラサキハナナとも違うようです。。。。
のこぎり歯のような、葉にきれこみがありませんし、花が咲き終わる頃に、花びらの色が薄くなることは、ありません
これまた、違うようですね
一輪しか着いた写真しかのせられませんでした。以前は、あんなにどこでも咲いていたのですが、見かけなくなりました
写真をよくみてくださいね

花ダイコン、オオアラセイトウ、ムラサキハナナとも、違うようだいし・・・雑種が広まってしまったのでしょうか
今回は、花が一輪しか着きませんでした、本来は、アブラナ科の他の花と同じようにつきます
またまた、難問にひっかかってしまいました。・
・
・
待って!!
もしや、以前コメントを書いたような気がして、林の子さんのところに覗きに行って来ました
やはり書いていました。
この花は「ムラサキハナナ」と紹介されていました。
諸葛菜(しょかっさい)(おおあらせいとう)等々いろいろ 呼び名があるようです
毎年聞いていたのでした。物覚えの悪い自分にがっかりです(恥)
・・・そう、だから 「身近な植物図鑑」が必要なんです。
フォトアルバムに追加しました
身近に見かける花で簡単に、わかると思ったのですが・・奥が深い!
6月14日、林の子さんから、コメントがありました。
画像は、幼苗なので花付きも少なく、葉に鋸歯も無いわけです
大きくそだってないので、鋸歯になってなかったのですね
コメントに書かれていて、初めて知ったのですが「標準和名」というのが、あるとのこと、
ウィキペディアによると(標準和名)とは
学名同様に使えるような日本語の名前があった方が便利である。そのような目的で学界やその周辺で慣習的に用いられているものが標準和名である
種の学名と一対一となるように調整した和名を、標準和名と呼ぶ。標準和名は日本国内の範囲では、学名に準じて扱われている。ただし、命名規約等はなく、それぞれの分野で研究者同士のやりとりの中で決まっている。
この、ムラサキハナナの、標準和名は、「ショカッサイ」とのことでしたので、
おおあらせいとう(牧野富太郎博士の命名)
↓
ムラサキハナナ
↓
ショカッサイに変更です(三国志で有名な諸葛孔明に由来する諸葛菜のことです)
でも、紫花菜でも、OKですよね















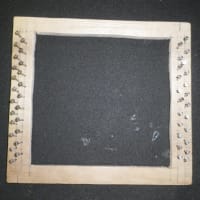




うちの一番上の姉は「しょかっさい」で通しています。
私は初めしょかっさいってなんのこと?と聞いていました。
今ではムラサキハナナがいいなと思ってます。
自分のためのものだから忘れないようにということで入れておくのは大切ですね。
この写真の中にはシダも入ってる~
カタバミもタチイヌノフグリらしきものも!
この所、紫花菜(ムササキハナナ)の方が分かり易い!・・・紫色の菜の花の仲間・・・ですものね
タチイヌノフグリが、映り込んでいるの?
ちょっと調べてみました。写真だと、どうも花がアップになっているので、実物のは、比べにくくて・・・
左側のやや上の方の、四方にとがった葉を広げているの。かしら?
ひょろりと一本で立っていて、極極小さな青い花がついているのが、あちこちに生えているのですが・・・それのことでしょうか
オオイヌノフグリは、知っていますが・・・
タチイヌノフグリは・・・これだと良いな。
個人の備忘録的図鑑、他人がとやかく言っても無視…が良いようです。
そうじゃなければ、売っている図鑑を買う方が気楽です。
私も大学ノートに幾つも走り書きをしていますが、自分自身の判断で書きます。
時にはそれを検証したり、確認したりして大半は訂正・加筆されていますが。
オオアラセイトウは明治期に牧野博士がつけた名前、
たぶん今使う人はいないでしょうね。
権威を重んじる人たちは使うようですが。
Orychophragmus violaceusについては、ショカツサイが標準和名になっているので、
正式にはそれを使う方が良いかも知れません。
それでも、「ムラサキハナナ」の通称が一番しっくりと来ますね。
ハナダイコンは書かれている通り、別のものにつけられた別名、その植物はハナスズシロが標準和名です。
画像は、幼苗なので花付きも少なく、葉に鋸歯も無いわけです。
とんちゃんが指摘されているタチイヌノフグリは、ショカツサイの左真横に花殻が白く写っている植物でしょうね。
コメントありがとうございます
林の子さんの画像を見て、「あっつ、これ見たことがある。名前はXXXと、いうのね、」
で、写真を撮ってみるのですが、写真にして比べてよく見てみると、「あれっ、なんな違う」って、ことがあります。
今回も確信して、「ムラサキハナナ」としたのに、葉の形から、ゆらいでしまって・・・
幼苗だからなんですね。
「標準和名」について、初めて知りました。
そういうものがあった方が、いいですよね。ただ、地域によって馴染みのない名前がついているとさみしくなるかな・・・出来るだけ、その標準和名を使いたいです。