身近な植物図鑑 (目白の森編)ムクロジの実
やっと、拾ってきたムクロジの実が見つかりました
遅くなりましたが、五月の連休中の頃に行った続きです
公園で、子供さんがお父さんを黒い実をたくさん持っていたのできいてみました。
「ムクロジの実だよ。」
「たくさん、落ちているんだ」
目白の森の、ちょうどムクロジの花が咲いていたようです
というのも、木が丈が高くて。咲いていたか、よくわかりませんでした・・・残念です
調べると6月頃、小さな花がさいて終わると雨のように降ってくるそうです。・・・・五月の初めてしたので?です。
しかし、木の根元には、秋に緑色だった実が茶色になって落ちてきていました
まるで、ランタンのような形に黒い種子が透けて見えています。
これがその子供さんが話していたムクロジの実の写真です。

左上の持ち手のついたランタンのような形のケースに透けるようにみえるのは黒い種子です。(実物は、もっと、薄い色をしていました)
中に入っていた黒い実(右上)が、正月の羽子板遊びの時に使う羽の黒い玉(オモリ)の所になるだそうです
この外側の皮の、ムクロジエキスには、サポニンが含まれており、その界面活性作用で泡立ち、洗浄効果があり、抗炎症、抗菌作用がある
石けん代わりになるのだそうですが、試して見ると確かに泡がたつようです。戦争中は、石けんの代用としてつかわれたそうです。
ムクロジの実・・黒い堅い実・・どこかで似たようなのを見たことがあるような
そうなんです「フウセンカズラ」
秋になって、薄茶色のぷっくりと膨らんだ中が3つの部屋に分かれていてそれぞれに種がついています。その種が黒と白の実なんです
今年の夏は、節電の影響で緑のカーテンとして「フウセンカズラ」を植えている庭が多く見かけられます
でも、
ムクロジ科(むくろじか、Sapindaceae)は双子葉植物に属する科で、約140属2000種からなる。高木から草本まであり、つる性のものもある。葉は互生し、羽状複葉のものが多い。亜熱帯、熱帯に多く分布する
となっているので、そうなんでしょうね。
木の「ムクロジ」と一年草の「フウセンカズラ」が、同じ仲間だとは信じられません!!
紹介したかったムクロジの実が見つからなくて、梅雨も終わって真夏になってしましましたが、ぜひ見て欲しかったのです。
これで、時間がかかってしましましたが春編は、今回でおわりです。















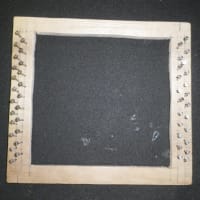




昔のはねつきの羽は全部このムクロジが使われていました。
なつかしいです。安っぽい羽子板しかもてなかったので羽根を突くと羽子板に丸く跡がついて・・・
フウセンカズラはムクロジの仲間だなんて全然気にしていなかったです。
教えていただいてありがとう!
フウセンカズラの種の形も可愛いですよね。
ムクロジの実は、半透明の丸い中に収まっていました。しかも、少し開いたふたと、持ち手がついてたくさん落ちていました。
子供さんが、ムクロジの実の落ちていたところを教えてくれたんですが、上から小さな薄緑のものがパラパラと落ち続けていました。どうも、それがムクロジの花のようでした。
写真に撮れば良かったんですが、、ほかの植物に目移りしてしまって。。。今となっては、残念です。
林の子さんのおっしゃるとおり、「咲いている場所を覚えておけばまた、出会える。」とおもっています。
フウセンカズラは、日よけに以前植えていたのですが。。今年こそ必要だったのには、時期がずれてしまいました。
細い柄に大きな緑の風船がユラユラ揺れているのは、かわいらしいし、涼しげですよね。
ムクロジの仲間には、楊貴妃が好んだという「ライチ」も、加わっているそうです。
ムクロジ科は、草も木もあると言いますが・・・信じられませんよね