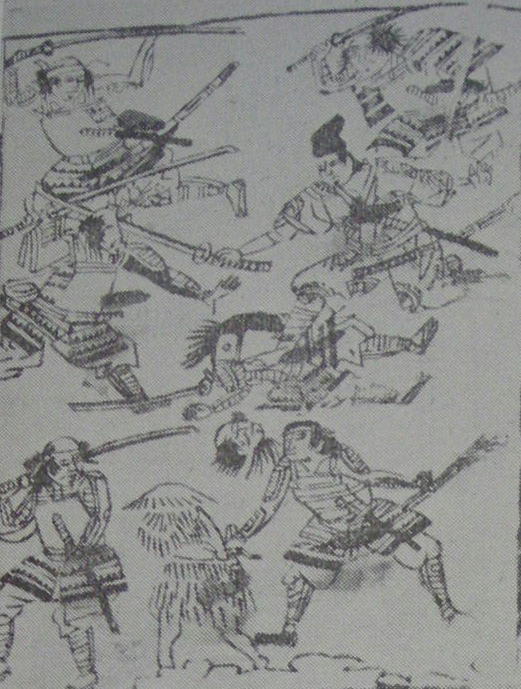はらだ ③
都に残された御台様は、種直が捕らえられたことも知らずに過ごしておりましたが、やがて、玉の様な男の子を産んだのでした。御台様は、大変お喜びになって、御乳や乳母を付けて、大切にお育てになりました。そうして、3年の月日が流れたのでした。しかし、種直からは便りも無いので、御台様は、
「恨めしい種直様。鎌倉で美しい花と戯れて、私たちのことを忘れてしまったのでしょうか。」
と、恨み事を言うのでした。御台様は、通りに出て、鎌倉から来る人に、種直の事を聞いてみようと思い立ちました。道端に立っていますと、山伏が三人、通りかかりました。御台様が、
「申し、客僧達。あなた方は、どちらからお出でですか。」
と訪ねますと、客僧達は、
「おお、我等は、鎌倉より来ました。何かご用ですか。」
と答えます。そこで御台様は、
「鎌倉では、何か大きな事件はありませんでしたか。」
と尋ねたのでした。客僧は、
「おお、ありましたよ。ちょうど三年前の事になりますが、原田の二郎種直という者が、由比ヶ浜で、討ち死になされました。」
と、言い捨てて通り過ぎたのでした。これを聞いた御台様は、夢か現かと、泣き崩れました。
「私は、なんと馬鹿なのでしょう。種直殿は、都の事を忘れてしまったと思い込んで恨み、都の事を思い出す様にと、賀茂神社に祈誓を掛けておりました。ああ、恨めしい憂き世です。」
と口説く様子は、哀れな有様です。やがて、涙を押しぬぐった、御台様は、
「三歳になる若君を、出家させて、後世を弔ってもらう外はありません。」
と考えて、若君を山寺に登らせたのでした。
若君は、大変優秀でした。他の子供達は及びもしません。一字を十字に覚ったので、十三歳になる頃には、山一番の稚児学者と呼ばれる様になりました。御台様は、大変お喜びになり、若君を呼び戻しました。御台様は、立派になった若君に、父の事を話すことにしたのです。
「良く聞きなさい。お前の父親の種直は、十三年前に、由比ヶ浜で討たれたと聞きました。」
と、泣きながら、父の話しをしました。若君は、これを聞くと、
「それでは、私は、鎌倉へ行って、事の子細を確かめて来ます。」
と言いました。御台様は、
「七月半で捨てられた父を恋しく思って、鎌倉まで行くというのですか。しかし、十三年も前のことです。恨めしいことですが、鎌倉へ行ったとしても、白骨すらもみつからないでしょう。」
と、歎くばかりです。しかし、若君は、
「いえ、それでも私は参ります。許して頂けないのなら、如何なる淵へでも身を投げて、死ぬ覚悟です。」
と、がんとして譲りませんでした。とうとう、御台様は、
「それ程までに、思うのであれば、尋ねて行ってごらんなさい。」
と、折れるのでした。若君は、
「このままの姿では、人売りに、売られてしまう。」
と考えて、修行者の姿に身をやつすと、鉦鼓を首に掛けました。御台様はこの姿をご覧になると、
「もし、父と巡り逢った時に、何を証拠とするつもりですか。」
と、守り袋と黄金作りの御佩刀を取り出しました。
「これこそ、父、種直の形見の品ですよ。」
と、若君に手渡すと、
「夫に別れてよりこの方、袖を絞らない日は無いというのに、今日から、子にも別れて、明日からの恋しさを、誰に話して慰めればいいのですか。」
と、重ねて歎き悲しむばかりです。しかし、若君は、名残の袖を振り切って、鎌倉へと旅立ったのでした。
馴れない旅でしたから、若君の足からは、血が噴き出し、道端の砂や草を朱に染めるのでした。それでも、日数は重なり、いよいよ相模の国に着きました。由比ヶ浜まで、あと三里という辺りです。日が暮れて来ましたので、とある人家に一夜の宿を乞いました。その家の夫婦は、若君を見ると、奥の座敷へと招き入れました。
しかし、その亭主は人売りだったのです。亭主は、しめしめと、早速に、人買いを呼びに行きます。それとも知らずに若君は、旅の疲れから、前後不覚に寝入ってしまいました。しばらくして、亭主は人買いを連れて戻って来ました。寝入っている若君を見定めた人買いは、
「年寄りでは、鮫の餌にもならぬが、このように若い者であれば、買いましょう。」
と言うと、二人は又連れだって浜の方へと、下りて行きました。若君の心の内は何に例え様もありません。
つづく

都に残された御台様は、種直が捕らえられたことも知らずに過ごしておりましたが、やがて、玉の様な男の子を産んだのでした。御台様は、大変お喜びになって、御乳や乳母を付けて、大切にお育てになりました。そうして、3年の月日が流れたのでした。しかし、種直からは便りも無いので、御台様は、
「恨めしい種直様。鎌倉で美しい花と戯れて、私たちのことを忘れてしまったのでしょうか。」
と、恨み事を言うのでした。御台様は、通りに出て、鎌倉から来る人に、種直の事を聞いてみようと思い立ちました。道端に立っていますと、山伏が三人、通りかかりました。御台様が、
「申し、客僧達。あなた方は、どちらからお出でですか。」
と訪ねますと、客僧達は、
「おお、我等は、鎌倉より来ました。何かご用ですか。」
と答えます。そこで御台様は、
「鎌倉では、何か大きな事件はありませんでしたか。」
と尋ねたのでした。客僧は、
「おお、ありましたよ。ちょうど三年前の事になりますが、原田の二郎種直という者が、由比ヶ浜で、討ち死になされました。」
と、言い捨てて通り過ぎたのでした。これを聞いた御台様は、夢か現かと、泣き崩れました。
「私は、なんと馬鹿なのでしょう。種直殿は、都の事を忘れてしまったと思い込んで恨み、都の事を思い出す様にと、賀茂神社に祈誓を掛けておりました。ああ、恨めしい憂き世です。」
と口説く様子は、哀れな有様です。やがて、涙を押しぬぐった、御台様は、
「三歳になる若君を、出家させて、後世を弔ってもらう外はありません。」
と考えて、若君を山寺に登らせたのでした。
若君は、大変優秀でした。他の子供達は及びもしません。一字を十字に覚ったので、十三歳になる頃には、山一番の稚児学者と呼ばれる様になりました。御台様は、大変お喜びになり、若君を呼び戻しました。御台様は、立派になった若君に、父の事を話すことにしたのです。
「良く聞きなさい。お前の父親の種直は、十三年前に、由比ヶ浜で討たれたと聞きました。」
と、泣きながら、父の話しをしました。若君は、これを聞くと、
「それでは、私は、鎌倉へ行って、事の子細を確かめて来ます。」
と言いました。御台様は、
「七月半で捨てられた父を恋しく思って、鎌倉まで行くというのですか。しかし、十三年も前のことです。恨めしいことですが、鎌倉へ行ったとしても、白骨すらもみつからないでしょう。」
と、歎くばかりです。しかし、若君は、
「いえ、それでも私は参ります。許して頂けないのなら、如何なる淵へでも身を投げて、死ぬ覚悟です。」
と、がんとして譲りませんでした。とうとう、御台様は、
「それ程までに、思うのであれば、尋ねて行ってごらんなさい。」
と、折れるのでした。若君は、
「このままの姿では、人売りに、売られてしまう。」
と考えて、修行者の姿に身をやつすと、鉦鼓を首に掛けました。御台様はこの姿をご覧になると、
「もし、父と巡り逢った時に、何を証拠とするつもりですか。」
と、守り袋と黄金作りの御佩刀を取り出しました。
「これこそ、父、種直の形見の品ですよ。」
と、若君に手渡すと、
「夫に別れてよりこの方、袖を絞らない日は無いというのに、今日から、子にも別れて、明日からの恋しさを、誰に話して慰めればいいのですか。」
と、重ねて歎き悲しむばかりです。しかし、若君は、名残の袖を振り切って、鎌倉へと旅立ったのでした。
馴れない旅でしたから、若君の足からは、血が噴き出し、道端の砂や草を朱に染めるのでした。それでも、日数は重なり、いよいよ相模の国に着きました。由比ヶ浜まで、あと三里という辺りです。日が暮れて来ましたので、とある人家に一夜の宿を乞いました。その家の夫婦は、若君を見ると、奥の座敷へと招き入れました。
しかし、その亭主は人売りだったのです。亭主は、しめしめと、早速に、人買いを呼びに行きます。それとも知らずに若君は、旅の疲れから、前後不覚に寝入ってしまいました。しばらくして、亭主は人買いを連れて戻って来ました。寝入っている若君を見定めた人買いは、
「年寄りでは、鮫の餌にもならぬが、このように若い者であれば、買いましょう。」
と言うと、二人は又連れだって浜の方へと、下りて行きました。若君の心の内は何に例え様もありません。
つづく