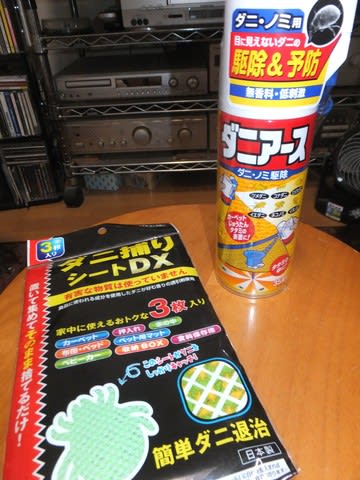久々に“超早起き(3時起床)”のブログ更新

ZUYAさんは毎週金曜日はシフトの都合で通常よりも30分程早くZUYA邸を出発する

そうすると時々駅に向かう途中で視覚障害のある初老の男性に遭遇する。何度か“お手伝い(補助)”させて頂いたことがあるのですが、ここのところ男性の勤め先が若干移動したようで片側1車線の道路の信号機を横断しないとい行けなくなった

設置されてある信号機は押しボタン式で音が鳴らないタイプ。その男性はZUYAさんに 『 信号機の所までで大丈夫です。信号が変わったら教えてください 』 と言うので、信号が変わったら、それを伝えて双方別々の道を行くわけです

ZUYAさんに会わない他の日はどうしているのだろうか。他にも誰かが助けてくれているのだろうか。そんなことを考える。だって信号が変わったことは匂いではわかるものでもない

今の世の中、“バリアフリー”と騒がれるがZUYAさんに言わせれば“ブーム”に過ぎない。だいたい他の先進国からずいぶん遅れを取っているしね。興味がない人には興味がないのだ

今の世の中“性善説”など通じない。それは電車内や駅のホーム上の 『 マナー啓発広告 』 が一向に減るどころか増えていることからも伺える。だいたいその前でヘッドフォンから音が漏れていたり、顔に絵の具を塗りたくっていたり、歩きスマホしたりしている輩がいるのだから

話を戻そう


さて、ZUYAさんは単純にその信号機を音響式の物に変えられないのかと考えてみた。調べてみると信号機の相談・苦情は各管轄の警察署に言うそうだ。ちなみにその信号機は豊島区と北区の“区境”に設置されている。これは“たらい回し”の予感が...

上の写真のように信号機の管理番号らしきものはわかるので大元の警視庁にでも問い合わせてみるか、などといろいろ考えたらある問題が脳裏に浮かんだ...昨今よく耳にする 『 保育園等の建設反対問題 』 だ

その反対理由の一つに“子供の声がうるさい”と言うものがある。ZUYAさんなどは“ぢゃあ子供はどこで育てば良いんだよ?文句言ってるあんただって、周囲に迷惑(と言うならば...)かけて学校に通ったのだろうよ”と思うわけだ

確かに多くの学校のように何十年と長くある施設ならまだしも、高いお金を出して購入したマイホームの裏に、学校に限らず急に賑やかな施設が出来たらたまったものではないのかもしれない

確かに渡る時だけ信号が変わる押しボタン式とは言え、今まで静かだった所に“とおりゃんせ”が鳴りだしたら...この手の問題は全国に少なくないようだ。でも最近は“ピヨピヨ”と言った周辺に優しい音色もありますからね

やはり信号機の場合は“社会的弱者”に歩み寄るべきではないかとZUYAさんは思う。もしそれを“騒音”と感じる人達は、その人達が24時間信号機に立って子供や障害のある人達を補助すべきであると思う。それともその人達はそこの信号機は通らないでくれと言うのであろうか




自分にとっては良い物でもそれに興味を持たない、依存していない人にとってただの“ガラクタ”である。例えばZUYAさんが良質の音楽だと思っても、興味のない人からすればただの騒音にすぎないのだ

ZUYAさんは以前、隣室の騒音に耐えかねて6ヶ月で賃貸マンションを退去したことがある。隣の部屋の女性は頻繁に友人達を呼び“どんちゃん騒ぎ”をしていた。音楽を聴いていてもその合間に漏れ聞こえる女性達のカン高い笑い声は苦痛以外の何物でもなかった。挙句の果てには大家さんを通じて注意してもらったら、それに対する罵りまで聞こえ出した

退去の日に大家さんからその部屋の住人は学校の先生だと知り愕然としたことを覚えている

その次に住んだ物件(先日写真を後悔した所)では最上階、隣の部屋とくっついていない、狭い部屋だったので床にはしっかり遮音カーペットを敷き防音には可能な限り徹底した

しかし結婚後住んでいる今のZUYA邸は典型的な昭和の住宅。2階建ての一軒家なのだが、1階部分は大家さんの身内、2階部分はZUYA夫婦が住んでいるわけで、床(下から見れば天井)はかなり薄い

そう言う特殊な賃貸物件だからその部分はちゃんと作ってあるのだろうと入居したのだがとんでもない。それでもZUYAさんは普通に音楽を聴いているし、下の方がいらっしゃらないと思われる時間にはアンプにまでつないでギターを弾く。時々何を顔を会せるが一度もクレームはない。実に寛大な大家さんだ

話を戻そう

信号機の件だ。とにかく行動してみようと思う。ZUYAさんはその場所を毎日通るだけで直接音の問題をこうむるわけではないが、“社会共存”と言う面から判断するのであれば第一に考えることは“障害者の方にとって不便である”と言う点。ZUYAさんが動けば警察も調査・検討してくれるだろう。ZUYAさんはその“着火剤”となれば良いのだ

どう料理しどんな器に盛り付けるかは現時点ではZUYAさんの考えることではないのであろう