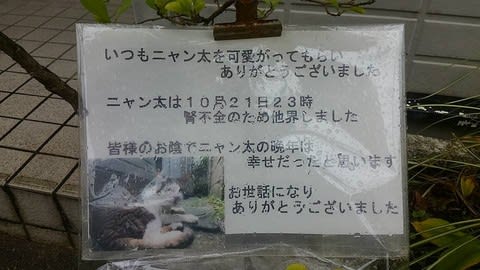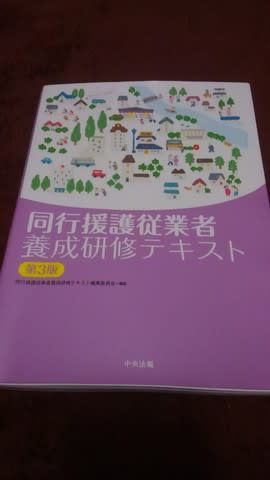<はじめに>
当ブログはZUYAさんの経験したこと、感じたことを率直に書き連ねることを第一の目的としており、一個人、一企業等、他者を誹謗中傷することを目的とはしておりません。ご理解の上、お楽しみくださいませ。
さて無事に最後まで受講し終えた 『 同行援護従業者養成研修 』 についてまとめておこうと思う

まず 『 同行援護 』 とは視覚障害者の外出の援護をすることです。研修中も講師が“介護ではなく援護”であり、“やれることはやってもらうのです”と繰り返し仰っておられた。昔は公的なサービスは病院等の医療機関への同行ぐらいしかなかったらしいが、昨今は障害のある方もどんどん社会参加することが増え、その生活も我々(健常者)と大差なく積極的に行う方も多くなってきている。だからこの同行援護従業者と言うものが重要になっている

とは言え、障害者に対する間違った知識や偏見は現在でも変わらず残っていることは否めない。研修でも“周りの人が全て協力してくれると思ったら大間違いですよ!”と講師が声を大にして仰っていた。罵声やら暴力を受けることもあるのだ。これに関してはZUYAさんは経験済みで嫁の仕事に付いて知的障害のある方と出掛けた時に交通機関の乗降時に世間の冷たさを肌で感じた

最近何度も書いているが、ZUYAさんが今回 『 同行援護 』 に興味を持ったのは、通勤時に度々視覚障害のあるおじさん(以後“Nさん”とする)に遭遇し、その都度些細だがお手伝いをさせて頂いたことに始まる。その時に“素人の優しさ”だけでなく、もっと知識を持って接することが出来ないものかと考えたわけです

ちなみに記憶にある限りでは一番最初に視覚障害者の存在を知ったのは 『 アルプスの少女ハイジ 』 に出てくる“ペーターのおばあさん”だと思います

さてさて、ZUYAさんのモットーである“ピピッと来たら動く”に従って探してみると 『 同行援護従業者養成研修 』 なるものが開催されていることを知った

地域自治体等で開催されているものは講習費が安いのだが日程が合わない。毎週有休を取れるほどZUYAさんの職場は寛容ではない。費用は高くなるが福祉関連の学校を見つけて申し込んでみた。しかも池袋なので通学にも問題はない

受講者の多くは埼玉やら栃木やらと遠方からの人だった。やはり研修会の開催自体が少ない上に日程の問題があるようで。ZUYAさんのようにそれを生業にしようと思わない方は二の足を踏んでしまうかもしれない、実際ほとんどの受講者は介護関連の仕事に携わっている人でした

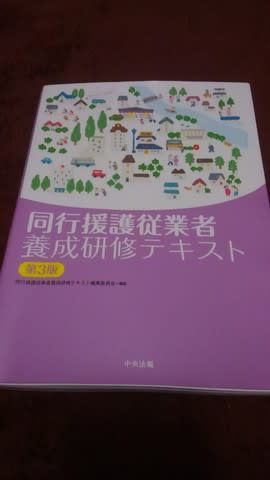
1日目は同行援護だけでなく、日本の福祉の法律や歴史を学んだ。意義深い内容の講義であったが意気込みを持って挑んだZUYAさんにしても後半戦には流石に眠気を催したことは隠さず正直に書いておきます

講師が執拗に“わかる、わからないを声に出して明確にしなさい!”と促す。実際に援護を行うときは利用者はこちらの“表情から判断できない”のだから当然だ

2日目も座学だが、メインである同行援護に深く入る。“これをしてはいけない”、“あれはダメです”の連発で少々面喰らった。(研修を終えた)今となっては当たり前だが、“目の前”と言う表現は確かに良くない

同行援護における基本的なルールは“主観的に物を考えず客観的に考える”とのこと。これが2回の座学を通して最も重要なことの一つであると思う。
とかく障害者に接したことのない方は勝手に思い込みで判断してしまう。例えば見えない方に“空の色や風景の話はタブーである”とか“見えないからこれは出来ないだろう”と言った具合にだ。これは間違いで我々の目から得られるあらゆる情報を与えてあげるのが同行援護従業者の役目なのである

思い込みと言えば、視覚障害者の伝達方法の一つに点字があるが、点字をマスターしている人は視覚障害者全体の僅か5%であることに驚かされた。皆が皆、点字を使えるわけではないのだ。こういうことである

3日目は実技である。アイマスクを装着して利用者の立場になってみたり、基本的な援護方法を色々なシチュエーションで練習する。アイマスクを使うのは一般的には就寝時のみですよね、でも初めてそれを付けての歩行、食事に挑んだが、これは...正直恐ろしい

でもまさにそういう状況に置かれている人達を手助けしないといけないのだと実感する。ドアの通過や階段の昇降訓練と言うのもやった

大雑把に書いてしまったがこれが 『 一般課程(3日) 』 と呼ばれるもの。これだけでも実際の事業所でもう働くことは出来るのだが、サービス管理者と言うものを目指す場合には 『 応用課程(2日) 』 を受講しなければならない。実はこの応用課程が実に重要で実際に街中へ出て交通機関の乗り降りの援護なども訓練するのだ

ZUYAさんは恥ずかしながら薄給のため、今回は受講出来ないがその内折りをみて受講したいと思う。確かに一般課程だけでも知りたかった情報や知識は想像以上に得られたのだが、まだ“序の口も序の口”である

さて、ここからはさらに正直思うことを書いてみる

実際、自分の時間をどれだけ他者に使うことが出来るのだろうか。福祉業務を“生業”にされている方はそれでお金を得ているわけだから問題ないだろうが、本業以外に携わる場合はどれだけの時間を使えるかは人それぞれだと思う。無茶をして体調を崩してしまって他人に迷惑をかけてしまっては本末転倒である

ZUYAさんもNさんが同行援護の事務所で働いていることを知り、ZUYAさんが研修を受けていることを話した時、“お休みの日にぜひ来てください”と言われたが、ZUYAさんにも休みの日は必要なのだ

もちろんZUYAさんはボランティア活動が好きだから、時間を見つけて参加をしたこともあるが、どれだけ自分の時間を割けるのか、割けるべきなのかは自分の中で葛藤したことのある人は決して少なくないと思う。そう言う時は“自分のやれる範囲”で良いのだろう。中途半端な気持ちで他者に接するものではないとZUYAさんは思う

ZUYAさんが子供の頃は学校で道徳の時間やら障害者のことをを学ぶ時間はあったが、今ではあまりないように聞く。英語やら算数やらの方が重要なのだろう。だから福祉施設であるにもかかわらず中途半端な人間性のまま働いている一部の人達が問題を起こしたりする原因の一つなのではないかと

ZUYAさんは幸いにも嫁が障害のある子供たちのデイケアを生業としており、ZUYAさん自身の祖母が介護施設に入っていることもあり、ここ8年ほどでずいぶん福祉に接する機会を持つことが出来た(以前は皆無でしたからね)

2020年には賛否両論の中、オリンピックとパラリンピックがやって来る。特にパラリンピックでは障害がある中で苛酷に挑む多くの人達を観る機会がある。それがこれからの社会、特に福祉の発展につながれば意義のあることになればと心から願います

今回、ZUYAさんの選んだ研修は良い講師(厳しさと優しさの変化球が巧い)に恵まれ充実していて十分に望んでいた情報を入れることが出来ました。施設も清潔感があり、駅からも近く 実に快適でした。興味のある方にはお勧めしますが、あえて名前を書くと“いやらしい”ので、学校名はZUYAさんの最近の写真から覗き見してくださいね