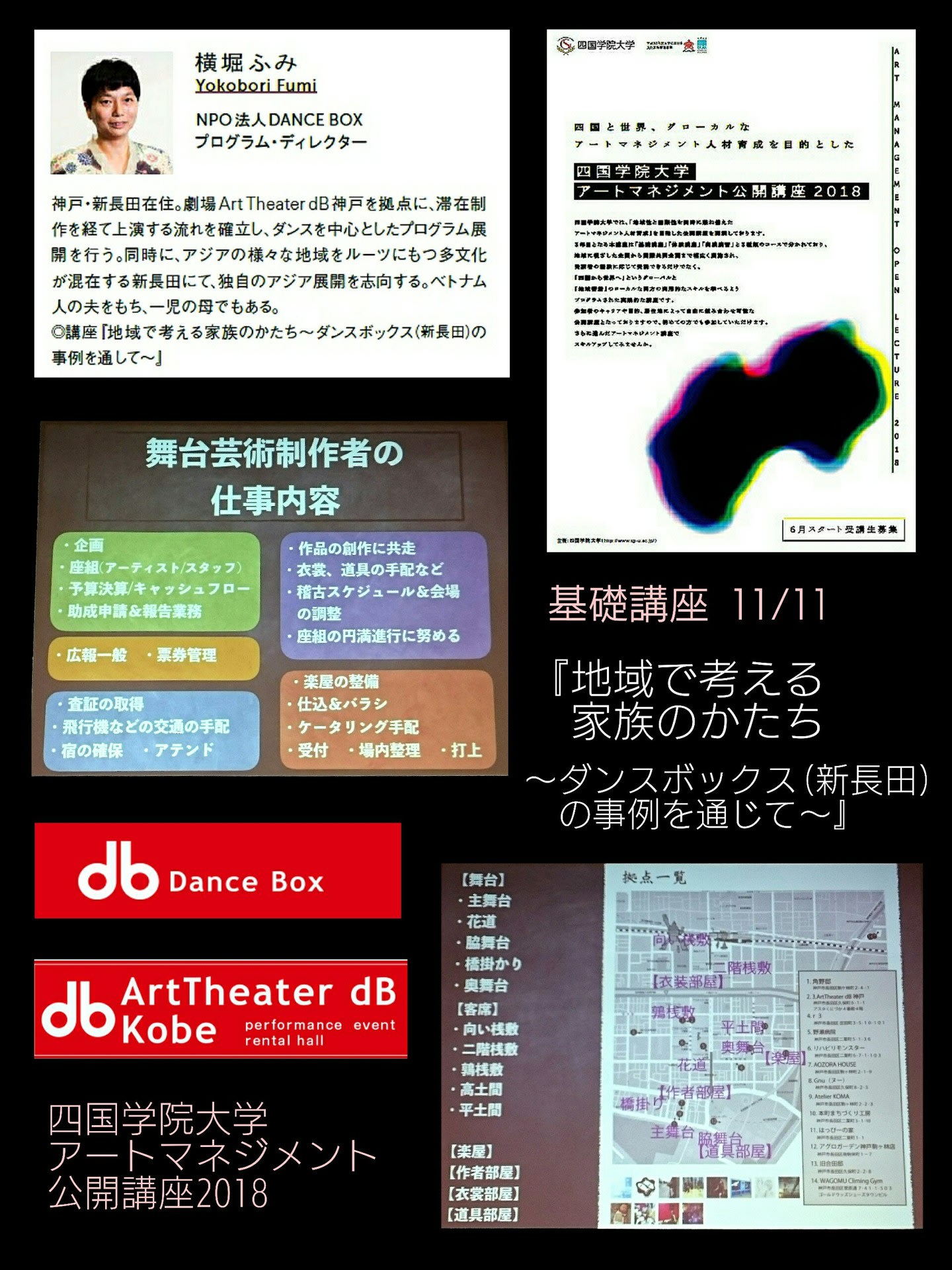
アートマネジメント公開講座2018
基礎講座 11/11(日)
『地域で考える家族のかたち
~ダンスボックス(新長田)の事例を通じて~』
講師:横堀ふみ
http://www.notos-studio.com/contents/event/event/3198.html
神戸、新長田にある
NPO法人 ダンスボックス
https://db-dancebox.org/
プログラムディレクター
ダンスボックスが
神戸市と協同して運営する
「ArtTheater dB 神戸」という小劇場
https://db-dancebox.org/project/
横堀さんはベトナム人の夫をもち
一児の母でもある。
新長田にはベトナム人のコミュニティがある。
そんな土地柄をふまえた活動が紹介された。
新長田の事例を見ながら、
何か取り入れることがないかと考えた。
…………………………
抜けている部分もあるが、講座のメモ。
↓ ↓ ↓
■舞台芸術制作者の仕事内容
多岐にわたる。
それぞれの得意分野を分担できたら。
〈写真〉
■各企画についての紹介
★企画内での共通言語〔共通言語〕
★どのように育てたのか〔 育て方〕
★ここから次へ生まれたこと〔次への展開〕
★協同アーティストの言葉〔アーティスト〕
これらをキーワードに各事例を紹介
振り返り記録するのにも良いと思った。
他の地域でも実践可能な試みではないか。
■topic1:企画の構造
■topic2:地域の中の様々な公共空間①
銭湯( 地元で活動している人との出会いがあった )
地元のフェスティバル、イベント、子ども会等
→会合に参加することによって
どんなコミュニティで成り立っているか
見えてくる
▼みんなのフェスティバル(2013-2015)
色々な切り口からプログラムに関わってもらう
■topic3:形態を遊ぶ
▼映画、ダンス、唄や音楽、トーク、その他
色々な切り口から色々な人が関われる形
入り口をつくる
地域と繋ぐ人がいないと難しかったそうだ。
ベトナム人の夫がいたからできたと。
■topic4:地域の中の様々な公共空間②
宗教空間(結婚式、葬式、正月)
食材店やレストラン
▼花道ジャンクション( 2015 )
地域とのかかわり
■topic5:家族とのかかわり
その人の背後にある家族の理解を得ること。
家族ぐるみで動きやすい方法を考える。
託児の必要性。参加者もスタッフも同様に。
確かに必要。これが整うと、
参加できる人の幅が広がりそう。
▼滲むライフ( 2017 )
新長田周辺は関西の中の
“第2のコリアンタウン”
在日コリアンの人たちの今
■topic6:地域の中の様々な公共空間③
学校空間 多様なルーツを持つ子ども
福祉空間 お年寄りを通して文化を知る
▼新長田アートマフィア
場や拠点をリソースした
民間の極小アーツカウンシル
地域で活動する人たちそれぞれが所属する
自分たちのいる場所を
アーティストの活動場所として提供
■topic7:地域の中の様々な公共空間④
どういうふうにしたら生きやすい場にできるか
劇場空間の公共
個人の歴史も 大きな歴史の一部
共存
劇場は個人で対等である場
色々な背景や繋がり等関係なく
公共
=共に生きる場について考える、
試行する、つくる
……………………
【グループワーク】
本の紹介
『天井桟敷から江戸を観る』渡辺豊和
建築家の観点からみる劇場都市の成立条件8つ
舞台(主舞台/花道/脇舞台/橋掛かり/奥舞台)
客席(向い桟敷/二階桟敷/鶉桟敷/平土間/高土間)
楽屋、作家部屋、衣装部屋、道具部屋
新長田なら、どこがそれに当たるのか。
(地図上で)〈写真〉
自分たちの住む地域なら
どこが何に見立てられるか、話し合い。
…………………………
新長田の地域性からの課題など、
何を必要としているかリサーチして
活動されている事例の数々、参考になった。
それでもまだ十分に分からないこともあり、
それを無理に結論づけないところが良いなと。
劇場は個人で対等である場、というのが
腑に落ちる感じがした。
どんな人にも開かれている場所、
特に孤立している人にとっての
居場所のひとつとなれば…と思った。















