この9月1日は防災記念日でした。これは、100年前の1923年に起こった関東大震災の災禍を後世に伝え防災意識を喚起する役目があったことから設けられたものでしょうが、新聞やテレビでも関東大震災やそれに関連する報道が行われました。例えば9月2日付けの山形新聞の土曜コラム「マルチアングル」では、「佐野利器(白鷹出身)と関東大震災」と題し、「復興小学校に込めた思い」という記事を掲載しています。これは、論説委員長の鈴木雅史氏のもので、関東大震災後に後藤新平のもとで街作りや復興建築を進めた東京帝国大学の佐野利器(としかた)教授が、若い時代に東京帝国大学で辰野金吾教授に学び、歐米の建築学では未開の分野であった耐震構造の研究を志したこと、廃墟と化した首都の復興に耐震耐火性の高い鉄筋コンクリート造の建築による街作りを推進したこと、白鷹町出身の山口少年が米沢中学に学んでいた時に、恩師が教え子を養子とし佐野姓として帝国大学に送り出したように、出自や財産ではなく才能と成績とを惜しんでくれた恩師たちのことなどを紹介するものです。

そして9月4日付けの「ふるさとの文化財」シリーズでは国登録有形文化財として「山形市立第一小学校旧校舎、門柱および柵」が取り上げられ、「県内の防災建築の先駆け」として東北初の鉄筋コンクリート造の小学校となった改築工事の設計を担当した秦・伊藤建築設計事務所(やはり東北初)の秦鷲雄と佐野利器が親戚であり、佐野は山形一小の改築にあたって耐震耐火構造を重視して鉄筋コンクリート造を助言したらしいことを伝えています。(堀川貴志記者)
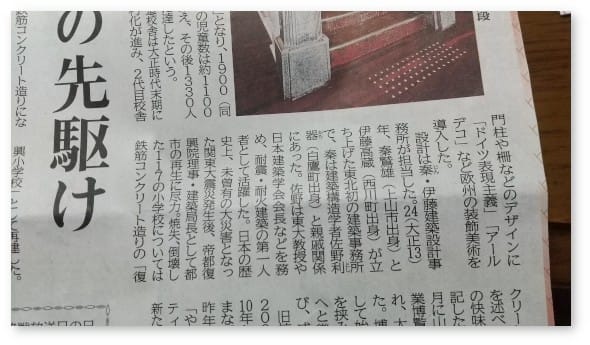
長州ファイブの一人・山尾庸三が設立した工部大学校の卒業生・辰野金吾から教え子の佐野利器へというこの流れもまた、幕末のサムライの息子たちが歐米の科学技術を学び、明治期のお雇い外国人教師の後を受けて後進を育てる中で、大正期には日本独自の視点による世界レベルの業績が出始めた化学等の分野の大きな流れ(*1)と軌を一にするものです。そしてその流れは、大都市部から財政力のある地方都市部へと移行しつつあるのでした。残念ながら、貧しい農山村漁村部まで普及するには、戦後、高度成長期を過ぎて子供の数が急激に減っていったバブル期前後まで待たなければいけなかったようですが。
いずれにしろ、同じ新聞社の中で短い数日間の間に関連する記事が複数登場するのは興味深いことです。これが意図したものであれば編集部の慧眼を表すものでしょうし、偶然であっても地元の歴史を大切にする報道姿勢があってこそのものでしょう。興味深いことです。
(*1): 「電網郊外散歩道」〜歴史技術科学カテゴリーの一連の記事、特に前半部あたり

そして9月4日付けの「ふるさとの文化財」シリーズでは国登録有形文化財として「山形市立第一小学校旧校舎、門柱および柵」が取り上げられ、「県内の防災建築の先駆け」として東北初の鉄筋コンクリート造の小学校となった改築工事の設計を担当した秦・伊藤建築設計事務所(やはり東北初)の秦鷲雄と佐野利器が親戚であり、佐野は山形一小の改築にあたって耐震耐火構造を重視して鉄筋コンクリート造を助言したらしいことを伝えています。(堀川貴志記者)
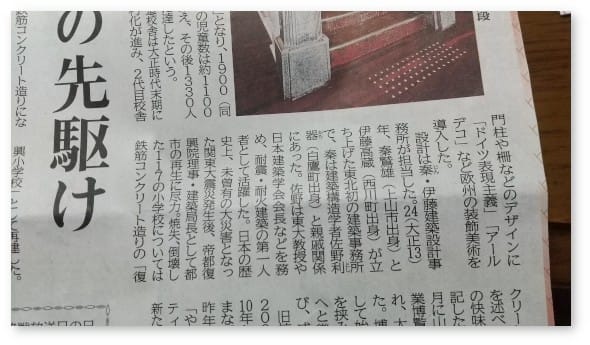
長州ファイブの一人・山尾庸三が設立した工部大学校の卒業生・辰野金吾から教え子の佐野利器へというこの流れもまた、幕末のサムライの息子たちが歐米の科学技術を学び、明治期のお雇い外国人教師の後を受けて後進を育てる中で、大正期には日本独自の視点による世界レベルの業績が出始めた化学等の分野の大きな流れ(*1)と軌を一にするものです。そしてその流れは、大都市部から財政力のある地方都市部へと移行しつつあるのでした。残念ながら、貧しい農山村漁村部まで普及するには、戦後、高度成長期を過ぎて子供の数が急激に減っていったバブル期前後まで待たなければいけなかったようですが。
いずれにしろ、同じ新聞社の中で短い数日間の間に関連する記事が複数登場するのは興味深いことです。これが意図したものであれば編集部の慧眼を表すものでしょうし、偶然であっても地元の歴史を大切にする報道姿勢があってこそのものでしょう。興味深いことです。
(*1): 「電網郊外散歩道」〜歴史技術科学カテゴリーの一連の記事、特に前半部あたり
















