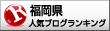(つづき)
西鉄バスの行先番号についてまとめた記事に意外に反響があったので、今回は、行先番号とともに、このブログでこれまでとりあげてきた中で比較的大きなテーマである「バス路線のネットワーク化」に関する記事を、いくつかの切り口から拾ってみる。
まとめが続いていますが、ブログを春で終わらせるつもり…というわけではありません、とりあえず今のところ(笑)。
以下では、6つの過去記事を紹介します。
なお、基本的に記事をそのまま転載しているため、情報は当時のままです。
1.鳥栖駅で考える広域ネットワークの価値(2009年1月17日の記事)

佐賀県鳥栖市の「鳥栖駅前」のうち、「10番」の久留米行きと「8番」の小郡行きが停車するバス停。
「甘木」と「端間」の文字を隠したテープが剥がれかけている。
考えてみれば、かつては「鳥栖~小郡~甘木」「甘木~田主丸」「鳥栖~基山~筑紫野」「久留米~北野~小郡~鳥栖」「鳥栖~小郡~大刀洗」「大刀洗~三輪」「久留米~鳥栖~筑紫野~飯塚」…などの、各自治体間を結ぶ西鉄のバス路線があったわけで、現在と比較すればかなり高度なネットワークが形成されていたといえる。
現在でも西鉄バスの営業地域は広範囲に及んでいるが、路線廃止やコミュニティバス等への移管により、エリアをダイナミックにまたぐような路線は衰退しており、特に中小都市間では、バス路線のネットワークはほぼ壊滅している。
「路線を廃止する」というのは、その沿線への影響だけにとどまらず、広域的にみた場合の「損失」も大きいのかもしれない。
もちろん、ネットワークが形成されていたからといって、それをうまく乗り継いで移動するという人もそこまで多くはなかっただろうし、そもそも採算が合わないのだから、ネットワークがなくなったって別に「損失」ではないという意見もあるだろう。
ただ、個人的には、路線が「つながっている」ということに、つい価値を見出してしまうのである…。
2.「97番」にみる福岡市内バス路線のネットワークの形成過程(2013年3月15日の記事)

3月15日までの運行となった「97番」。
現在のルートは「姪浜駅南口~内浜西区役所前~都橋~下山門~中村~拾六町団地~野方」であり、「都橋」までの区間に行きたい人は「1-4番」「507番」、「中村」までの区間に行きたい人は「507番」、「中村」から先に行きたい人は「1-5番」に乗ればよいので、「97番」がなくなったからといって、ここ「姪浜駅南口」から行けなくなる場所がなくなる訳ではない。
ただ、他の路線の本数が増える訳でもないため、明らかに利便性は低下する。
このように“削れるところは削ってしまおう”というのが、今回のダイヤ改正の特徴のひとつ。

こちらは「97番」が運行を開始した昭和57年当時の時刻表。

そしてこちらはそれから5年後、昭和62年当時の時刻表。
西山行き、四箇田団地行き、姪浜(折り返し場)行き、藤崎行き、一本だけの新道経由、拾六町団地への乗り入れ、旧道から新道への乗せ換え、能古渡船場行き、都心まで足を延ばす「1-1番」、橋本駅行き…などなど、今日までいろんな変化を遂げてきた「97番」。
「90番台」の位置づけが、“「1番」「2番」「3番」の補完的役割”から“区役所連絡路線”に変化する中で登場した路線であり、西鉄バスの営業エリア(当時)の西端にへばりつくように走るのも特徴的で、私の好きな路線の一つだった。
また、「97番」の登場により、それまでは「狭義の終点」であった「羽根戸」「藤ケ丘団地」「下山門」の3つのバス停が一気に「狭義の終点」ではなくなったという意味においては、西鉄バス路線のネットワーク化、そして、福岡市の都市化の進展を象徴する路線でもあった。
その「97番」が、“削れるところは削ってしまおう”というポリシーで廃止というのは、これもまた、時代の流れを象徴する出来事といえるのかもしれない。
復活の可能性もない訳ではないと思うのだが、とりあえず31年間お疲れさまでした。
3.蛭池で考えるバス路線が自治体境界を跨ぐことの意義(2010年4月16日の記事)

「鵜の池」と同じく国道442号上に位置する「動物+池」だが、ここには堀川バスではなく、「JR羽犬塚駅~蛭池~八丁牟田~大川市役所~一ツ木~大野島農協前」を結ぶ西鉄バスの「無番」が停車する。
八女市街地~羽犬塚~大川の間はひたすら一直線であるが、広すぎない道幅がバス旅には心地よい(ただし、トラックも多いので、歩くと怖い箇所もあります)。
バス停には、「国、福岡県、大川市、大木町、筑後市の補助金により運行されています」という掲示があった。
もし仮に、各自治体が独自でコミュニティバスなどを走らせるようになると、このような自治体の境を跨いで運行されるローカル線は、存在が危うくなりそうだ。
柳川市~大川市~佐賀市を結ぶ「西鉄柳川~市役所前~御花前~北間~大野島農協前~早津江」の「6番」も同様といえるかもしれない。
各自治体の中をきめ細かいルートで結んで住民のニーズに応えること自体は決して間違いではなく、それが功を奏している例も多いと思う。
ただ、それによって、自治体を跨ぐ移動が困難になっていくことに対しては、もう少し目を向けてほしい気がする。
「となり町の大型商業施設や病院に行きたいけど、バスがない」ということはよくあることであり、「住民サービス」という観点からも、広域的な移動手段という視点も忘れないでいてほしい。
春日市の徳洲会病院への「45-1番」の福岡市側からの乗り入れなどは、そのようなニーズに応えるものであるといえ、今後、西鉄バスが生きていくための選択肢のひとつとして、もっと積極的に検討していく余地があるのではないだろうか。
例えば、「72番」の古賀橋トリアス行きを、新宮町の「佐屋」まで延長して、「マリンクス」や「高速立花山」との乗り継ぎを可能にするとか…(「需要」という点では、まず実現は困難そうだけど…。あくまで「例えば」です)。
Kassyさんが、「Mほろば」「Mどか」「Yよい」「Kわせみ」の「渡り」をされていたが(ここだけ伏せ字にしても仕方ないですかね?笑)、これらのコミバスを横断的に繋ぐ「幹線」的なものが一本あれば、各「支線」の利用ももっと増えるのではないだろうか。
「国境は人間が勝手にひいたものであって、実際の地球の上には線なんてない」というような内容は、メッセージソングなどにありがちなテーマだが、バスについても同じようなことが言えそうである。
4.自治体の意向がバス路線ネットワーク衰退に強く作用する時代(2011年4月24日の記事)

「大板井」と「小板井」の間なので「中板井」かと思いきや、「小郡市役所」バス停。
小郡市内には、かつては「鳥栖~小郡~松崎~北野~久留米」「鳥栖~小郡~松崎~甘木」「鳥栖~小郡~松崎~乙隈」「鳥栖~端間~本郷」「基山駅~東野~小郡」「三国が丘駅~ニュータウン第一~原田駅~筑紫駅」…など、市町村、そして県の枠を超えて、様々な西鉄バスのバス路線が走っていて、バス路線のネットワークの「要衝」という感さえあった。
しかし、時代とともに次々に廃止となり、現在は、「西鉄小郡駅」のバス停一つだけが、鳥栖プレミアムアウトレット行きの起点として残るだけである(大分自動車道上の「高速大板井」は除く。また、「新津古橋」バス停は、小郡市内にはないものとして扱われている)。
西鉄バスに代わり、コミュニティバス6路線がそれぞれ数便ずつ、市内各所と市中心部(市役所、あすてらす〔福祉センター〕、文化会館など)を結んでいるが、西鉄の時代とは異なり、いずれも市内のみの運行であり、「バスで行くことのできる場所」は大きく様変わりしてしまっている(「西鉄白木原駅」でも似たようなことを書いた)。
一昨年9月の「17番」の三国が丘系統の廃止により、市内の「美鈴が丘」「希みが丘」などの住宅地から、隣りの筑紫野市にある商業施設ベレッサ(旧筑紫野とうきゅうショッピングセンター)やJR原田駅に行くことができなくなり、住民から改善を求める声があがっていた。
そして、今月1日から、自治会が独自で運行する住民用のミニバン「ベレッサ号」がスタートしている。
「ベレッサ号」は、「美鈴が丘」「希みが丘」それぞれ週2日ずつ、一日4便が運行されているとのこと(運転手さんはボランティアだそうです)。
西鉄が開発した住宅団地が多く含まれる地区であるにもかかわらず、住民の方(かた)がバスのことでここまで苦労しないといけないというのは、なんだかやりきれない感じもする。
ゆくゆくは、「隣接する筑紫野市と共同でコミュニティバスを運行」…みたいになって、この苦労が報われればいいなと思うのだが、先行きやいかに。
5.大型商業施設がバス路線ネットワーク再形成に与える影響(2010年6月1日の記事)

筑紫野市の「イオンモール筑紫野」バス停。
オープンと同時(オープンの何日か前でしたっけ?)に、「西鉄二日市~JR二日市~むさしケ丘団地」を運行していた「2-2番」の大部分が、ここ「イオンモール筑紫野」を複乗(一部はイオンモール筑紫野で終点)する「2-3番」に振り替えられた。
バス停には、土日祝日には車両混雑による遅延の発生が予想される旨の告知があった。
イオンモールに用がなく、団地と駅の間を利用したい人にとっては気の毒に見えてしまう。
ちなみに、告知には「約30~50分の遅れ」と書いてあり、ゾーンを指定してかなり具体的に「予想」しているのが、なんだか面白かった(1~29分の間の遅れは基本的にないということだろうか??)。
周辺の「イオンモール」としては、福岡都市圏東部に「イオンモール福岡ルクル」、北九州都市圏南西部には「イオンモール直方」がある。
「イオンモール福岡ルクル」(開業当初は「ダイヤモンドシティ福岡ルクル」)には、西側から「32番」(現在は「30番」)「空港~ルクルの無番」が、東側から「36番」が乗り入れることにより、バス路線がつながった。
「イオンモール直方」には、北九州市側から「53番」、直方市側から「直方バスセンター~イオンモールのシャトルバス」などが乗り入れることにより、ここでもバス路線がつながった(ルクルのほうは、のりばがかなり離れてますけど)。
「野芥交差点~田隈小学校前交差点」「干隈交差点~東七隈交差点」「東比恵交差点~瑞穂交差点」「中津口交差点~三萩野交差点」…など、路線の廃止や大幅な減便により、路線やバス停単体ではなく、それらを総合体としてみた場合の「使い勝手」が悪くなるという事態(このブログではしばしば「ネットワークの崩壊」という言葉で説明している)が進む中、「イオンモール」のような大型商業施設は、逆に、ネットワークを構築する作用をもたらすといえ、バスが今後生き残っていくための頼みの綱(ネットなので“頼みの網”でしょうか)といえるのかもしれない。
ここ「イオンモール筑紫野」には、「2-3番」と反対側(東側)からはバスの乗り入れはないものの、東側にはJR天拝山駅、そしてそこから少し行くと西鉄朝倉街道駅があり、交通機関のネットワークの構築という観点からは、それが達成されている。
ちなみに、粕屋町の「イオンモール福岡ルクル」行きのバスは、行先表示が「イオンモール福岡」となっているのだが、福岡都市圏にもうひとつの「イオンモール」である「筑紫野」ができたことから、「イオンモール福岡」という表現は、今となってはやや曖昧に見える(バス停の時刻表には単に「イオンモール」とだけ書いてあり、もっと曖昧である)。
字数も多いことだし、そろそろ単に「ルクル」とかでも伝わるのでは?…と考えるのだが、いかがでしょう。
6.今も孤軍奮闘する「75番」(2009年5月1日の記事)

平成8年11月10日時点の、赤間~直方を結ぶ「75番」及びその支線「10番」の時刻表の一部。
当時はネオポリス~高六は「10番」として運行されていた。
「75」という番号は、宗像地区の番号としては異質なので、もともとは、黒崎~香月~直方の「70番」や、黒崎~畑観音の「72番」など、八幡西~直方エリアの「70番台」のひとつという位置づけだったのかもしれない(このエリアの変遷にはあまり詳しくないので、間違っていたら指摘してください)。
当時、赤間~直方間は平日23往復運行されていた。
現在は12往復とほぼ半減しているが、なんとか生き延びている。
中小都市間における西鉄バス路線のネットワーク崩壊については、これまで何度か取り上げたことがある。
この路線は、宗像市と直方市を結んでおり、ネットワークの崩壊を必死で阻止しているようなルートになっている。
赤間から直方までを乗り通す人はおそらく少ないと思われるが、途中で切れてしまうことがないよう願うばかりである。
(つづく)
西鉄バスの行先番号についてまとめた記事に意外に反響があったので、今回は、行先番号とともに、このブログでこれまでとりあげてきた中で比較的大きなテーマである「バス路線のネットワーク化」に関する記事を、いくつかの切り口から拾ってみる。
まとめが続いていますが、ブログを春で終わらせるつもり…というわけではありません、とりあえず今のところ(笑)。
以下では、6つの過去記事を紹介します。
なお、基本的に記事をそのまま転載しているため、情報は当時のままです。
1.鳥栖駅で考える広域ネットワークの価値(2009年1月17日の記事)

佐賀県鳥栖市の「鳥栖駅前」のうち、「10番」の久留米行きと「8番」の小郡行きが停車するバス停。
「甘木」と「端間」の文字を隠したテープが剥がれかけている。
考えてみれば、かつては「鳥栖~小郡~甘木」「甘木~田主丸」「鳥栖~基山~筑紫野」「久留米~北野~小郡~鳥栖」「鳥栖~小郡~大刀洗」「大刀洗~三輪」「久留米~鳥栖~筑紫野~飯塚」…などの、各自治体間を結ぶ西鉄のバス路線があったわけで、現在と比較すればかなり高度なネットワークが形成されていたといえる。
現在でも西鉄バスの営業地域は広範囲に及んでいるが、路線廃止やコミュニティバス等への移管により、エリアをダイナミックにまたぐような路線は衰退しており、特に中小都市間では、バス路線のネットワークはほぼ壊滅している。
「路線を廃止する」というのは、その沿線への影響だけにとどまらず、広域的にみた場合の「損失」も大きいのかもしれない。
もちろん、ネットワークが形成されていたからといって、それをうまく乗り継いで移動するという人もそこまで多くはなかっただろうし、そもそも採算が合わないのだから、ネットワークがなくなったって別に「損失」ではないという意見もあるだろう。
ただ、個人的には、路線が「つながっている」ということに、つい価値を見出してしまうのである…。
2.「97番」にみる福岡市内バス路線のネットワークの形成過程(2013年3月15日の記事)

3月15日までの運行となった「97番」。
現在のルートは「姪浜駅南口~内浜西区役所前~都橋~下山門~中村~拾六町団地~野方」であり、「都橋」までの区間に行きたい人は「1-4番」「507番」、「中村」までの区間に行きたい人は「507番」、「中村」から先に行きたい人は「1-5番」に乗ればよいので、「97番」がなくなったからといって、ここ「姪浜駅南口」から行けなくなる場所がなくなる訳ではない。
ただ、他の路線の本数が増える訳でもないため、明らかに利便性は低下する。
このように“削れるところは削ってしまおう”というのが、今回のダイヤ改正の特徴のひとつ。

こちらは「97番」が運行を開始した昭和57年当時の時刻表。

そしてこちらはそれから5年後、昭和62年当時の時刻表。
西山行き、四箇田団地行き、姪浜(折り返し場)行き、藤崎行き、一本だけの新道経由、拾六町団地への乗り入れ、旧道から新道への乗せ換え、能古渡船場行き、都心まで足を延ばす「1-1番」、橋本駅行き…などなど、今日までいろんな変化を遂げてきた「97番」。
「90番台」の位置づけが、“「1番」「2番」「3番」の補完的役割”から“区役所連絡路線”に変化する中で登場した路線であり、西鉄バスの営業エリア(当時)の西端にへばりつくように走るのも特徴的で、私の好きな路線の一つだった。
また、「97番」の登場により、それまでは「狭義の終点」であった「羽根戸」「藤ケ丘団地」「下山門」の3つのバス停が一気に「狭義の終点」ではなくなったという意味においては、西鉄バス路線のネットワーク化、そして、福岡市の都市化の進展を象徴する路線でもあった。
その「97番」が、“削れるところは削ってしまおう”というポリシーで廃止というのは、これもまた、時代の流れを象徴する出来事といえるのかもしれない。
復活の可能性もない訳ではないと思うのだが、とりあえず31年間お疲れさまでした。
3.蛭池で考えるバス路線が自治体境界を跨ぐことの意義(2010年4月16日の記事)

「鵜の池」と同じく国道442号上に位置する「動物+池」だが、ここには堀川バスではなく、「JR羽犬塚駅~蛭池~八丁牟田~大川市役所~一ツ木~大野島農協前」を結ぶ西鉄バスの「無番」が停車する。
八女市街地~羽犬塚~大川の間はひたすら一直線であるが、広すぎない道幅がバス旅には心地よい(ただし、トラックも多いので、歩くと怖い箇所もあります)。
バス停には、「国、福岡県、大川市、大木町、筑後市の補助金により運行されています」という掲示があった。
もし仮に、各自治体が独自でコミュニティバスなどを走らせるようになると、このような自治体の境を跨いで運行されるローカル線は、存在が危うくなりそうだ。
柳川市~大川市~佐賀市を結ぶ「西鉄柳川~市役所前~御花前~北間~大野島農協前~早津江」の「6番」も同様といえるかもしれない。
各自治体の中をきめ細かいルートで結んで住民のニーズに応えること自体は決して間違いではなく、それが功を奏している例も多いと思う。
ただ、それによって、自治体を跨ぐ移動が困難になっていくことに対しては、もう少し目を向けてほしい気がする。
「となり町の大型商業施設や病院に行きたいけど、バスがない」ということはよくあることであり、「住民サービス」という観点からも、広域的な移動手段という視点も忘れないでいてほしい。
春日市の徳洲会病院への「45-1番」の福岡市側からの乗り入れなどは、そのようなニーズに応えるものであるといえ、今後、西鉄バスが生きていくための選択肢のひとつとして、もっと積極的に検討していく余地があるのではないだろうか。
例えば、「72番」の古賀橋トリアス行きを、新宮町の「佐屋」まで延長して、「マリンクス」や「高速立花山」との乗り継ぎを可能にするとか…(「需要」という点では、まず実現は困難そうだけど…。あくまで「例えば」です)。
Kassyさんが、「Mほろば」「Mどか」「Yよい」「Kわせみ」の「渡り」をされていたが(ここだけ伏せ字にしても仕方ないですかね?笑)、これらのコミバスを横断的に繋ぐ「幹線」的なものが一本あれば、各「支線」の利用ももっと増えるのではないだろうか。
「国境は人間が勝手にひいたものであって、実際の地球の上には線なんてない」というような内容は、メッセージソングなどにありがちなテーマだが、バスについても同じようなことが言えそうである。
4.自治体の意向がバス路線ネットワーク衰退に強く作用する時代(2011年4月24日の記事)

「大板井」と「小板井」の間なので「中板井」かと思いきや、「小郡市役所」バス停。
小郡市内には、かつては「鳥栖~小郡~松崎~北野~久留米」「鳥栖~小郡~松崎~甘木」「鳥栖~小郡~松崎~乙隈」「鳥栖~端間~本郷」「基山駅~東野~小郡」「三国が丘駅~ニュータウン第一~原田駅~筑紫駅」…など、市町村、そして県の枠を超えて、様々な西鉄バスのバス路線が走っていて、バス路線のネットワークの「要衝」という感さえあった。
しかし、時代とともに次々に廃止となり、現在は、「西鉄小郡駅」のバス停一つだけが、鳥栖プレミアムアウトレット行きの起点として残るだけである(大分自動車道上の「高速大板井」は除く。また、「新津古橋」バス停は、小郡市内にはないものとして扱われている)。
西鉄バスに代わり、コミュニティバス6路線がそれぞれ数便ずつ、市内各所と市中心部(市役所、あすてらす〔福祉センター〕、文化会館など)を結んでいるが、西鉄の時代とは異なり、いずれも市内のみの運行であり、「バスで行くことのできる場所」は大きく様変わりしてしまっている(「西鉄白木原駅」でも似たようなことを書いた)。
一昨年9月の「17番」の三国が丘系統の廃止により、市内の「美鈴が丘」「希みが丘」などの住宅地から、隣りの筑紫野市にある商業施設ベレッサ(旧筑紫野とうきゅうショッピングセンター)やJR原田駅に行くことができなくなり、住民から改善を求める声があがっていた。
そして、今月1日から、自治会が独自で運行する住民用のミニバン「ベレッサ号」がスタートしている。
「ベレッサ号」は、「美鈴が丘」「希みが丘」それぞれ週2日ずつ、一日4便が運行されているとのこと(運転手さんはボランティアだそうです)。
西鉄が開発した住宅団地が多く含まれる地区であるにもかかわらず、住民の方(かた)がバスのことでここまで苦労しないといけないというのは、なんだかやりきれない感じもする。
ゆくゆくは、「隣接する筑紫野市と共同でコミュニティバスを運行」…みたいになって、この苦労が報われればいいなと思うのだが、先行きやいかに。
5.大型商業施設がバス路線ネットワーク再形成に与える影響(2010年6月1日の記事)

筑紫野市の「イオンモール筑紫野」バス停。
オープンと同時(オープンの何日か前でしたっけ?)に、「西鉄二日市~JR二日市~むさしケ丘団地」を運行していた「2-2番」の大部分が、ここ「イオンモール筑紫野」を複乗(一部はイオンモール筑紫野で終点)する「2-3番」に振り替えられた。
バス停には、土日祝日には車両混雑による遅延の発生が予想される旨の告知があった。
イオンモールに用がなく、団地と駅の間を利用したい人にとっては気の毒に見えてしまう。
ちなみに、告知には「約30~50分の遅れ」と書いてあり、ゾーンを指定してかなり具体的に「予想」しているのが、なんだか面白かった(1~29分の間の遅れは基本的にないということだろうか??)。
周辺の「イオンモール」としては、福岡都市圏東部に「イオンモール福岡ルクル」、北九州都市圏南西部には「イオンモール直方」がある。
「イオンモール福岡ルクル」(開業当初は「ダイヤモンドシティ福岡ルクル」)には、西側から「32番」(現在は「30番」)「空港~ルクルの無番」が、東側から「36番」が乗り入れることにより、バス路線がつながった。
「イオンモール直方」には、北九州市側から「53番」、直方市側から「直方バスセンター~イオンモールのシャトルバス」などが乗り入れることにより、ここでもバス路線がつながった(ルクルのほうは、のりばがかなり離れてますけど)。
「野芥交差点~田隈小学校前交差点」「干隈交差点~東七隈交差点」「東比恵交差点~瑞穂交差点」「中津口交差点~三萩野交差点」…など、路線の廃止や大幅な減便により、路線やバス停単体ではなく、それらを総合体としてみた場合の「使い勝手」が悪くなるという事態(このブログではしばしば「ネットワークの崩壊」という言葉で説明している)が進む中、「イオンモール」のような大型商業施設は、逆に、ネットワークを構築する作用をもたらすといえ、バスが今後生き残っていくための頼みの綱(ネットなので“頼みの網”でしょうか)といえるのかもしれない。
ここ「イオンモール筑紫野」には、「2-3番」と反対側(東側)からはバスの乗り入れはないものの、東側にはJR天拝山駅、そしてそこから少し行くと西鉄朝倉街道駅があり、交通機関のネットワークの構築という観点からは、それが達成されている。
ちなみに、粕屋町の「イオンモール福岡ルクル」行きのバスは、行先表示が「イオンモール福岡」となっているのだが、福岡都市圏にもうひとつの「イオンモール」である「筑紫野」ができたことから、「イオンモール福岡」という表現は、今となってはやや曖昧に見える(バス停の時刻表には単に「イオンモール」とだけ書いてあり、もっと曖昧である)。
字数も多いことだし、そろそろ単に「ルクル」とかでも伝わるのでは?…と考えるのだが、いかがでしょう。
6.今も孤軍奮闘する「75番」(2009年5月1日の記事)

平成8年11月10日時点の、赤間~直方を結ぶ「75番」及びその支線「10番」の時刻表の一部。
当時はネオポリス~高六は「10番」として運行されていた。
「75」という番号は、宗像地区の番号としては異質なので、もともとは、黒崎~香月~直方の「70番」や、黒崎~畑観音の「72番」など、八幡西~直方エリアの「70番台」のひとつという位置づけだったのかもしれない(このエリアの変遷にはあまり詳しくないので、間違っていたら指摘してください)。
当時、赤間~直方間は平日23往復運行されていた。
現在は12往復とほぼ半減しているが、なんとか生き延びている。
中小都市間における西鉄バス路線のネットワーク崩壊については、これまで何度か取り上げたことがある。
この路線は、宗像市と直方市を結んでおり、ネットワークの崩壊を必死で阻止しているようなルートになっている。
赤間から直方までを乗り通す人はおそらく少ないと思われるが、途中で切れてしまうことがないよう願うばかりである。
(つづく)