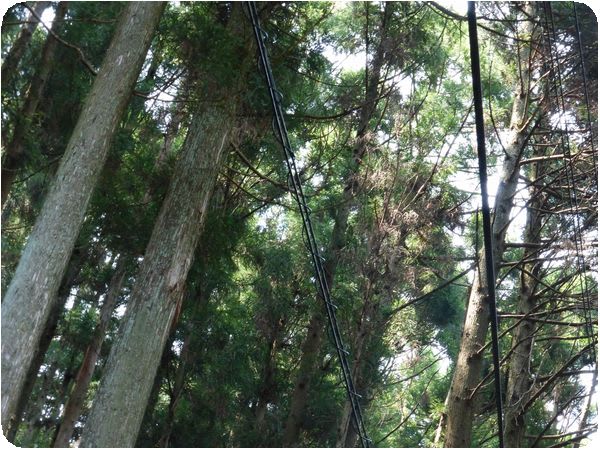実は神水瀑を観に行った時から、潜水橋や三山冠、十万岳とかも気になっていました。うまく峯の薬師堂に行けていれば、きっと帰りに潤野の方にも行けていた筈でしたが、あまりにも無駄な歩きをしたので、翌日出直すことにしたのです。前日の帰るころにはデジカメのバッテリーが切れかけており、帰ったら充電しようと思っていたのですが、忘れてしまっていました。

翌朝も一瞬デジカメを充電せなアカンと思ったのですが、それも忘れてしまって昼食をとってから車を走らせました。もうデジカメのバッテリーが切れかけていることなど頭の隅にもありません。『みんなの店』に車を停めて潤野橋を渡るときに上流・下流の写真を撮りました。最初の写真が下流側で潜水橋も写っています。上流側にはアユ釣りの人が一人写っていますが、『みんなの店』に車を停めて川へ降りようとするアユ釣りの集団を見かけました。水曜日だったのにアユ釣りの人とかカヌーに乗っている人を多く見かけました。

この潤野の集落の入り口でデジカメのバッテリー切れのサインが出始めてしまい、「しまった」とこんな所で思い出したのでしたが、後の祭りです。もう多くても十数枚しか撮れないでしょう。この写真に写っている山が三山冠です。三山冠を見る眺めは潜水橋からのものが最高だとか、きっとそこまでバッテリーは持たないでしょう。



時間的にも家に戻って充電して再来することは出来ないでしょうから、このままバッテリーが切れるまで撮り続けるしかありません。供養塔とか地図には無い神社とか、古座では見かけたことがない竃も有りました。

潤野は古座川流域では最も広い平野部で、その名の通り潤った野であり、田んぼや畑が一面に広がっています。

潤野の集落を抜ける道を南へ向かって歩いています。この古座川右岸の道は高瀬に繋がっていて、高瀬からは古座川沿いに道は無く、重畳山方面に道が付いています。この時は思わなかったのですが、この道を走って高瀬へ抜け、重畳山の山頂手前で姫川方面へ走れば、案外早く姫の家に着いたのかも知れません。



ここはもう十万岳の麓道、崖に石仏が置かれています。集落の中では神倉神社のゴトビキ岩のような岩がドカッと有って、私は目を奪われました。カエルが座っているように見えますでしょう。

向こうに見える橋が明神橋、ここが小川と古座川の合流点です。カヌーは現在ここからしか出発できない筈です。これより上流はこの期間アユ釣り師が多く、カヌー客とのトラブルが多いのが原因でしょう。明神橋のこの出発現場、小川から古座川に合流する地点は以前は大きな樹が出張っていたり、水流が早かったので危なかったのですが、対岸から見る限り改善されたように思えます。

明神橋が見える地点からは高瀬へ行っても仕方がないので、引き返しました。探検マップには集落の山側に下地の滝という滝が記されており、その滝も見つけたかったのです。



残念ながら古座川風土記には、その下地の滝の記事はありません。どうやらマップで見る限りこの川というか水路を辿ると左岸に滝がある筈ですが、水が流れていません。でも水の音はどこかから聞こえるので、左岸を辿ってみようとしたら、柵が張られていて上へは行けないようになっていました。最後の写真の道を登ると三山冠の上に行けるような気がしますが、低山なのに亜高山植物のシャクナゲが咲くと書かれていた三山冠、今はシャクナゲの季節ではないので、春にチャレンジしようと思い直したのでした。