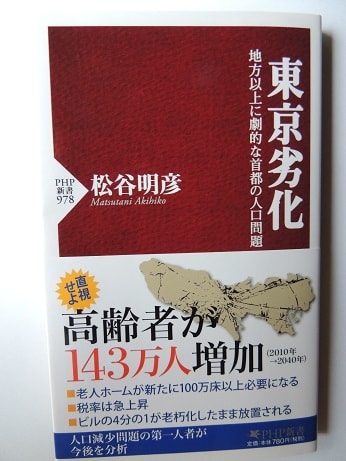私は東京の調布市に住む年金生活の老ボーイの71歳の身であるが、
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭である。
そして雑木の多い小庭に古ぼけた一軒屋に住み、お互いの趣味を互いに尊重して、日常を過ごしている。
家内は私より5歳若く、お互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。
ここ5年、少子高齢化が加速する中、年金、医療、介護などの社会保障費は毎年一兆円が増加し、
昨今は日本の借金は1100兆円を超えている、と新聞、テレビのニュースなどで報じられ、
無力な年金生活の私は、憂いたりしている。
こうした心情を秘めている私は、愛読している【Business Journal】を読んでいる中で、
【 「消費増税しないと財政危機」のまやかし…日本人だけが知らない本当の日本財政の実情 】と見出しを見て、
どのようなことですか、と思いながら精読してしまった・・。

この記事は、ファイナンシャルリサーチ代表、ファイナンシャルプランナーの深野康彦さんが、
「あなたと家族と日本のための、お金の話」の連載している記事のひとつで、
本日の7月15日配信され、無断ながら転載させて頂く。
《・・前回、日本の財政は言われているほど、悪くないと述べたので、その根拠を述べることにしましょう。
日本の借金(負債)は、1100兆円を超えている、破綻したギリシャよりも悪い、GDPの2.5倍ある等々、
日本の財政が悪いという話は、尽きません。
しかも大学教授、エコノミストなど名だたる人たちが、財政悪について述べることから、
大多数の人が「日本は大丈夫なのか?」「消費税引き上げを行わなくて大丈夫か?」となるわけです。
実は筆者も、数年前まで日本は「大丈夫か?」派だったのですが、
調べてみると、日本はそんなに悪くないということがわかるのです。

日本の財政悪を述べる人の大多数は、貸借対照表(バランスシート)の向かって右側、
「負債の部」の数字だけを述べていることがわかります。
貸借対照表は、負債の部と共に資産の部を見て、通算した結果を見ることが大切であることは、いうまでもありません。
負債の部しか見ないことは、偏りがあるので、資産の部も見てみましょう。
それとも日本は、資産を持っていないのでしょうか。
いえいえ、財務省は毎年きちんと「国の財務書類」というかたちで貸借対照表を作成しているのですが、
残念ながら国の貸借対照表が、詳しく報じられたことはありません。

☆なぜもっと円も国債も、売られていないのか?
下図は2014年度の「国の財務書類」の概要、「国の貸借対照表」です。
http://biz-journal.jp/2016/07/post_15892.html
資産の部の1番下、資産合計を見ると、国は679.8兆円もの資産を保有していることがわかります。
一方、負債の部の負債合計を見ると1171.8兆円の負債があります。
この負債合計を取り出して、財政悪が声高に報じられているのですが、
財政を見るときの基本は、資産合計から負債合計を差し引いた「純資産額」または「純負債額」を計算して判断するのです。
日本の財政状況は、「資産・負債差額の部」の「資産・負債差額」の数字である-492兆円になります。
負債が資産を上回る「純負債」という状況ですから、とても偉そうなことはいえませんが、
それでも純負債額は492兆円と、GDPの額とほぼイコール(1倍)の額にすぎないのです。

もちろん、国が保有する資産をすべて売却できるのか? と問われれば、
皇居や国会議事堂などを売ることは、できないでしょう。
あくまでも貸借対照表上の判断による見方だと考えてください。
日本の財政状況が本当に悪いのであれば、円が売られ、国債も売られるはずですが、
売られないのは、貸借対照表の内容を海外投資家などが、理解しているからといわれているのです。
1100兆円を超える負債額が、いまだ増えているため、楽観的になることはできませんが、
信号にたとえれば、少なくとも赤信号とはいえず、黄色信号が点滅している程度にすぎないと思われてなりません。・・》
注)原文にあえて改行を多くした。

私は大手メディアの新聞、テレビなどは日本の借金は1100兆円を超えている、と報じられているのは、
財務省が国の財政が悪化し、これからも支出の多くを占める社会保障費に危惧して、
資産合計を抜きにして、負債合計だけの1171.8兆円を声高に公表されている、と感じたりした。
そして悪しき表現で明記すれば、財務省は社会保障費は殆ど使用する高齢者を人質に、
消費税など増税しないと財政危機になりますょ、そして年金は激少したり、医療、介護も低下しますょ、
と私は思い馳せて、苦笑させられた。
私は苦笑した根拠には、昨年の2015年の12月下旬に、1980年、大蔵省(現財務省)入省、理財局資金企画室長、内閣参事官など歴任され、
小泉内閣、安倍内閣では 「改革の司令塔」として活躍され、2007年には財務省が隠す「埋蔵金」を公表し、
政策シンクタンク「政策工房」会長、嘉悦大学教授の高橋洋一さんのひとつの寄稿文を学んだりしたからであった。
この氏の寄稿文は、【「日本の借金1000兆円」はやっぱりウソでした
~それどころか…なんと2016年、財政再建は実質完了してしまう! この国のバランスシートを徹底分析 】で、
私が愛読している講談社の基幹サイトのひとつの【現代ビジネス 】で、多々教示されたからである。
そして「日本の借金1000兆円」以上と思っている方に、読んで頂きたく、無断ながら記事を転載させて頂く。

《・・
☆鳥越俊太郎氏もダマされていた
先週26日(土曜日)、大阪朝日放送の番組「正義のミカタ」に出た。
大阪のニュース情報番組だが、東京とは違って、自由な面白さがある。
そこで、「日本経済の諸悪の根源はZ」というコーナーをやった。Zとは財務省である。
その中で筆者が強調したのは「借金1000兆円のウソ」である。
借金が1000兆円もあるので、増税しないと、財政破綻になるという、
ほとんどのマスコミが信じている財務省の言い分が、正しくないと指摘したのだ。
借金1000兆円、国民一人当たりに直すと800万円になる。
みなさん、こんな借金を自分の子や孫に背負わせていいのか。
借金を返すためには増税が必要だ。
こんなセリフは、誰でも聞いたことがあるだろう。
財務省が1980年代の頃から、繰り返してきたものだ。
テレビ番組は時間も少ないので、簡単に話した。
「借金1000兆円というが、政府内にある資産を考慮すれば500兆円。
政府の関係会社も考慮して連結してみると200兆円になる。
これは先進国と比較してもたいした数字ではない」
これに対して、番組内で、ゲストの鳥越俊太郎さんから、
「資産といっても、処分できないものばかりでしょう」と反論があった。
それに対して、多くの資産は金融資産なので換金できる、といった。

筆者がこう言うのを財務省も知っているので、財務省は多くのテレビ関係者に対して、
「資産は売れないものばかり」というレクをしている。
鳥越さんも直接レクされたかが、どうかは定かでないが、財務省の反論を言ってきたのには、笑ってしまった。
番組が昼にかかり15分くらいの休憩があった。
そのとき、鳥越さんから、「金融資産とは何ですか」と筆者に聞いてきた。
「政策投資銀行(旧日本開発銀行)やUR都市機構(旧住都公団)などの特殊法人、
独立行政法人に対する貸付金、出資金です」と答えた。
それに対して「それらを回収したらどうなるの」とさらに聞かれたので、
「民営化か廃止すれば、回収ということになるが、それらへの天下りができなくなる」と答えた。
このやりとりを聞いていた他の出演者は、CM中のほうが、ためになる話が多いといっていた。
実際に、番組中で言うつもりだったが、時間の都合でカットせざるを得なくなった部分だ。
借金1000兆円。これは二つの観点から間違っている。

☆巨額な政府資産に驚くなかれ
バランスシートの左側を見てみれば・・・
第一に、バランスシートの右側の負債しか、言っていない。
今から20年近く前に、財政投融資のALM(資産負債管理)を行うために、国のバランスシートを作る必要があった。
当時、主計局から余計なことをするなと言われながらも、私は財政投融資が抱えていた巨額の金利リスクを解消するために、
国のバランスシートを初めて作った。
財政が危ういという、当時の大蔵省の主張は、ウソだったことはすぐにわかった。
ただし、現役の大蔵官僚であったので、対外的に言うことはなかった。
筆者の作った国のバランスシートは、大蔵省だからか「お蔵入り」になったが、
世界の趨勢から、その5年くらい後から試案として、10年くらい後から正式版として、財務省も公表せざるを得なくなった。
今年3月に、2013年度版国の財務書類が公表されている。
その2013年度末の国のバランスシートを見ると、資産は総計653兆円。
そのうち、現預金19兆円、有価証券129兆円、貸付金138兆円、出資66兆円、
計352兆円が比較的換金可能な金融資産である。
そのほかに、有形固定資産178兆円、運用寄託金105兆円、その他18兆円。

負債は1143兆円。
その内訳は、公債856兆円、政府短期証券102兆円、借入金28兆円、これらがいわゆる国の借金で計976兆円。
運用寄託金の見合い負債である公的年金預り金112兆円、その他45兆円。
ネット国債(負債の総額から資産を引いた額。つまり、1143兆円-653兆円)は490兆円を占める。
先進国と比較して、日本政府のバランスシートの特徴を言えば、政府資産が巨額なことだ。
政府資産額としては、世界一である。
政府資産の中身についても、比較的換金可能な金融資産の割合が、きわめて大きいのが特徴的だ。
なお、貸付金や出資金の明細は、国の財務書類に詳しく記されているが、そこが各省の天下り先になっている。
実は、財務省所管の貸付先は、他省庁に比べて突出して多い。
このため、財務省は各省庁の所管法人にも天下れるので、天下りの範囲は他省庁より広い。
要するに、「カネを付けるから、天下りもよろしく」ということだ。

☆財政再建は、実は完了している?
第二の問題点は、政府内の子会社を連結していないことだ。
筆者がバランスシートを作成した当時から、単体ベースと連結ベースのものを作っていた。
現在も、2013年度版連結財務書類として公表されている。
それを見ると、ネット国債は451兆円となっている。
単体ベースの490兆円よりは少なくなっている。
ただし、この連結ベースには、大きな欠陥がある。
日銀が含まれていないのだ。
日銀への出資比率は5割を超え、様々な監督権限もあるので、まぎれもなく、日銀は政府の子会社である。
経済学でも、日銀と政府は「広い意味の政府」とまとめて、一体のものとして分析している。
これを統合政府というが、会計的な観点から言えば、日銀を連結対象としない理由はない。
筆者は、日銀を連結対象から除いた理由は知らないが、連結対象として含めた場合のバランスシート作ることはできる。

2013年度末の日銀のバランスシートを見ると、資産は総計241兆円、そのうち国債が198兆円である。
負債も241兆円で、そのうち発行銀行券87兆円、当座預金129兆円である。
そこで、日銀も含めた連結ベースでは、ネット国債は253兆円である(2014.3.31末)。
直近ではどうなるだろうか。
直近の日銀の営業毎旬報告を見ると、資産として国債328兆円、負債として日銀券96兆円、当座預金248兆円となっている。
直近の政府のバランスシートがわからないので、正確にはいえないが、
あえて概数でいえば、日銀も含めた連結ベースのネット国債は、150~200兆円程度であろう。
そのまま行くと、近い将来には、ネット国債はゼロに近くなるだろう。
それに加えて、市中の国債は少なく、
資産の裏付けのあるものばかりになるので、ある意味で財政再建が完了したともいえるのだ。
ここで、「日銀券や当座預金も債務だ」という反論が出てくる。
これはもちろん債務であるが、国債と違って無利子である。
しかも償還期限もない。
この点は国債と違って、広い意味の政府の負担を考える際に重要である。

☆滑稽すぎる 「日本の財政は破綻する」論
このようにバランスシートで見ると、日銀の量的緩和の意味が、はっきりする。
政府と日銀の連結バランスシートを見ると、資産側は変化なし、負債側は国債減、日銀券(政府当座預金を含む)増となる。
つまり、量的緩和は、政府と日銀を統合政府で見たとき、負債構成の変化であり、
有利子の国債から、無利子の日銀券への転換ということだ。
このため、毎年転換分の利子相当の差益が発生する(これをシニョレッジ〔通貨発行益〕という。
毎年の差益を現在価値で合算すると、量的緩和額になる)。
また、政府からの日銀への利払いは、ただちに納付金となるので、
政府にとって日銀保有分の国債は、債務でないのも同然になる。
これで、連結ベースの国債額は、減少するわけだ。
量的緩和が、政府と日銀の連結バランスシートにおける負債構成の変化で、
シニョレッジ〔通貨発行益〕を稼げるメリットがある。
と同時にデメリットもある。
それはシニョレッジ〔通貨発行益〕を大きくすればするほど、インフレになるということだ。
だから、デフレの時にはシニョレッジ〔通貨発行益〕を増やせるが、インフレの時には限界がある。
その限界を決めるのが、インフレ目標である。
インフレ目標の範囲内であればデメリットはないが、超えるとデメリットになる。
幸いなことに、今のところ、デメリットはなく、実質的な国債が減少している状態だ。

こう考えてみると、財務省が借金1000兆円と言い、「だから消費増税が必要」と国民に迫るのは、
前提が間違っているので、暴力的な脅しでしかない。
実質的に借金は150~200兆円程度、GDP比で30~40%程度だろう。
ちなみに、アメリカ、イギリスで、中央銀行と連結したネット国債をGDP比でみよう。
アメリカで80%、65%、イギリスは80%、60%程度である。
これを見ると、日本の財政問題が大変で、すぐにでも破綻するという意見の滑稽さがわかるだろう。
以上は、バランスシートというストックから見た財政状況であるが、
フローから見ても、日本の財政状況はそれほど心配することはない、というデータもある。

本コラムの読者であれば、筆者が名目経済成長で、プライマリー収支を改善でき、
名目経済成長を高めるのは、それほど難しくない、
財政再建には、増税ではなく経済成長が必要、と書いてきたことを覚えているだろう。
その実践として、小泉・第一安倍政権で、増税はしなかったが、プライマリー収支が、ほぼゼロとなって財政再建できた。
これは、増税を主張する財務省にとって触れられたくない事実である。
実際、マスコミは財務省の言いなりなので、この事実を指摘する人はまずいない。
さらに、来2016年度の国債発行計画を見ると、新規に市中に出回る国債は、ほぼなくなることがわかる。
これは、財政再建ができた状況と、ほぼ同じ状況だ。
こうした状態で、少しでも国債が市中に出たらどうなるのか。
金融機関も一定量の国債投資が必要なので、出回った国債は、瞬間蒸発する。
つまり、とても国債暴落という状況にならないということだ。
何しろ市中に出回る国債がほとんどないので、
「日本の財政が大変なので財政破綻、国債暴落」と言い続けてきた、
デタラメな元ディーラー評論家には、厳しい年になるだろう。

☆今の国債市場は「品不足」状態
2016年度の国債発行計画を見ると、総発行額162.2兆円、
その内訳は市中消化分152.2兆円、個人向け販売分2兆円、日銀乗換8兆円である。
余談だが、最後の日銀乗換は、多くの識者が禁じ手としている「日銀引受」である。
筆者が役人時代、この国債発行計画を担当していたときにもあったし、今でもある。
これは、日銀の保有国債の償還分40兆円程度まで引受可能であるが、市中枠が減少するため、
民間金融機関が国債を欲しいとして、日銀乗換分を少なめにしているはずだ。
要するに、今の国債市場は、国債の品不足なのだ。
カレンダーベース市中発行額は147兆円であるが、短国25兆円を除くと、122兆円しかない。
ここで、日銀の買いオペは新規80兆円、償還分40兆円なので、合計で120兆円。
となると、市中消化分は、最終的には、ほぼ日銀が買い尽くすことになる。
民間金融機関は、国債投資から、貸付に向かわざるを得ない。
これは日本経済にとっては望ましいことだ。
と同時に、市中には実質的に国債が出回らないので、これは財政再建ができたのと同じ効果になる。
日銀が国債を保有した場合、その利払いは直ちに政府の納付金となって財政負担なしになる。
償還も乗換をすればいいので、償還負担もない。
それが、政府と日銀を連結してみれば、国債はないに等しいというわけだ。

こういう状態で、国債金利はどうなるだろうか。
市中に出回れば瞬間蒸発状態で、国債暴落なんてあり得ない。なにしろ必ず、日銀が買うのだから。
こうした見方から見れば、2016年度予算の国債費23.6兆円の計上には、笑えてしまう。
23.6兆円は、債務償還費13.7兆円、利払費9.9兆円に分けられる。
諸外国では、減債基金は存在しない。
借金するのに、その償還のために、基金を設けて、さらに借金するのは不合理だからだ。
なので、先進国では債務償還費は計上しない。
この分は、国債発行額を膨らせるだけで無意味となり、償還分は借換債を発行すればいいからだ。
利払費9.9兆円で、その積算金利は1.6%という。
市中分がほぼなく国債は品不足なのに、そんなに高い金利になるはずない。
実は、この高い積算金利は、予算の空積(架空計上)であり、
年度の後半になると、そんなに金利が高くならないので、不用が出る。
それを補正予算の財源にするのだ。・・》
注)原文にあえて改行を多くした。

この寄稿文を読み終わった後、「日本の借金1000兆円」は誤りで、
《・・実質的に借金は150~200兆円程度、GDP比で30~40%程度だろう。
ちなみに、アメリカ、イギリスで、中央銀行と連結したネット国債をGDP比でみよう。
アメリカで80%、65%、イギリスは80%、60%程度である。・・》
と学び、私は安堵したりした。
そして財務省は省内の権益の拡大、天下り先の確保なども含めて、どうして無知な国民を翻弄させるのょ、
と小心者の私は微苦笑したりした。

このような高橋洋一さんのひとつの寄稿文を学んだりし、今回のファイナンシャルプランナーの深野康彦さんの寄稿文を読み重ね、
大手メディアの新聞、テレビなどは、財務省に恐れ、日本の借金は昨今は1100兆円を超えている、と報じられいる、
と無力な私でも、微苦笑を重ねたりしている。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪
 にほんブログ村
にほんブログ村

私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭である。
そして雑木の多い小庭に古ぼけた一軒屋に住み、お互いの趣味を互いに尊重して、日常を過ごしている。
家内は私より5歳若く、お互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。
ここ5年、少子高齢化が加速する中、年金、医療、介護などの社会保障費は毎年一兆円が増加し、
昨今は日本の借金は1100兆円を超えている、と新聞、テレビのニュースなどで報じられ、
無力な年金生活の私は、憂いたりしている。
こうした心情を秘めている私は、愛読している【Business Journal】を読んでいる中で、
【 「消費増税しないと財政危機」のまやかし…日本人だけが知らない本当の日本財政の実情 】と見出しを見て、
どのようなことですか、と思いながら精読してしまった・・。

この記事は、ファイナンシャルリサーチ代表、ファイナンシャルプランナーの深野康彦さんが、
「あなたと家族と日本のための、お金の話」の連載している記事のひとつで、
本日の7月15日配信され、無断ながら転載させて頂く。
《・・前回、日本の財政は言われているほど、悪くないと述べたので、その根拠を述べることにしましょう。
日本の借金(負債)は、1100兆円を超えている、破綻したギリシャよりも悪い、GDPの2.5倍ある等々、
日本の財政が悪いという話は、尽きません。
しかも大学教授、エコノミストなど名だたる人たちが、財政悪について述べることから、
大多数の人が「日本は大丈夫なのか?」「消費税引き上げを行わなくて大丈夫か?」となるわけです。
実は筆者も、数年前まで日本は「大丈夫か?」派だったのですが、
調べてみると、日本はそんなに悪くないということがわかるのです。

日本の財政悪を述べる人の大多数は、貸借対照表(バランスシート)の向かって右側、
「負債の部」の数字だけを述べていることがわかります。
貸借対照表は、負債の部と共に資産の部を見て、通算した結果を見ることが大切であることは、いうまでもありません。
負債の部しか見ないことは、偏りがあるので、資産の部も見てみましょう。
それとも日本は、資産を持っていないのでしょうか。
いえいえ、財務省は毎年きちんと「国の財務書類」というかたちで貸借対照表を作成しているのですが、
残念ながら国の貸借対照表が、詳しく報じられたことはありません。

☆なぜもっと円も国債も、売られていないのか?
下図は2014年度の「国の財務書類」の概要、「国の貸借対照表」です。
http://biz-journal.jp/2016/07/post_15892.html
資産の部の1番下、資産合計を見ると、国は679.8兆円もの資産を保有していることがわかります。
一方、負債の部の負債合計を見ると1171.8兆円の負債があります。
この負債合計を取り出して、財政悪が声高に報じられているのですが、
財政を見るときの基本は、資産合計から負債合計を差し引いた「純資産額」または「純負債額」を計算して判断するのです。
日本の財政状況は、「資産・負債差額の部」の「資産・負債差額」の数字である-492兆円になります。
負債が資産を上回る「純負債」という状況ですから、とても偉そうなことはいえませんが、
それでも純負債額は492兆円と、GDPの額とほぼイコール(1倍)の額にすぎないのです。

もちろん、国が保有する資産をすべて売却できるのか? と問われれば、
皇居や国会議事堂などを売ることは、できないでしょう。
あくまでも貸借対照表上の判断による見方だと考えてください。
日本の財政状況が本当に悪いのであれば、円が売られ、国債も売られるはずですが、
売られないのは、貸借対照表の内容を海外投資家などが、理解しているからといわれているのです。
1100兆円を超える負債額が、いまだ増えているため、楽観的になることはできませんが、
信号にたとえれば、少なくとも赤信号とはいえず、黄色信号が点滅している程度にすぎないと思われてなりません。・・》
注)原文にあえて改行を多くした。

私は大手メディアの新聞、テレビなどは日本の借金は1100兆円を超えている、と報じられているのは、
財務省が国の財政が悪化し、これからも支出の多くを占める社会保障費に危惧して、
資産合計を抜きにして、負債合計だけの1171.8兆円を声高に公表されている、と感じたりした。
そして悪しき表現で明記すれば、財務省は社会保障費は殆ど使用する高齢者を人質に、
消費税など増税しないと財政危機になりますょ、そして年金は激少したり、医療、介護も低下しますょ、
と私は思い馳せて、苦笑させられた。
私は苦笑した根拠には、昨年の2015年の12月下旬に、1980年、大蔵省(現財務省)入省、理財局資金企画室長、内閣参事官など歴任され、
小泉内閣、安倍内閣では 「改革の司令塔」として活躍され、2007年には財務省が隠す「埋蔵金」を公表し、
政策シンクタンク「政策工房」会長、嘉悦大学教授の高橋洋一さんのひとつの寄稿文を学んだりしたからであった。
この氏の寄稿文は、【「日本の借金1000兆円」はやっぱりウソでした
~それどころか…なんと2016年、財政再建は実質完了してしまう! この国のバランスシートを徹底分析 】で、
私が愛読している講談社の基幹サイトのひとつの【現代ビジネス 】で、多々教示されたからである。
そして「日本の借金1000兆円」以上と思っている方に、読んで頂きたく、無断ながら記事を転載させて頂く。

《・・
☆鳥越俊太郎氏もダマされていた
先週26日(土曜日)、大阪朝日放送の番組「正義のミカタ」に出た。
大阪のニュース情報番組だが、東京とは違って、自由な面白さがある。
そこで、「日本経済の諸悪の根源はZ」というコーナーをやった。Zとは財務省である。
その中で筆者が強調したのは「借金1000兆円のウソ」である。
借金が1000兆円もあるので、増税しないと、財政破綻になるという、
ほとんどのマスコミが信じている財務省の言い分が、正しくないと指摘したのだ。
借金1000兆円、国民一人当たりに直すと800万円になる。
みなさん、こんな借金を自分の子や孫に背負わせていいのか。
借金を返すためには増税が必要だ。
こんなセリフは、誰でも聞いたことがあるだろう。
財務省が1980年代の頃から、繰り返してきたものだ。
テレビ番組は時間も少ないので、簡単に話した。
「借金1000兆円というが、政府内にある資産を考慮すれば500兆円。
政府の関係会社も考慮して連結してみると200兆円になる。
これは先進国と比較してもたいした数字ではない」
これに対して、番組内で、ゲストの鳥越俊太郎さんから、
「資産といっても、処分できないものばかりでしょう」と反論があった。
それに対して、多くの資産は金融資産なので換金できる、といった。

筆者がこう言うのを財務省も知っているので、財務省は多くのテレビ関係者に対して、
「資産は売れないものばかり」というレクをしている。
鳥越さんも直接レクされたかが、どうかは定かでないが、財務省の反論を言ってきたのには、笑ってしまった。
番組が昼にかかり15分くらいの休憩があった。
そのとき、鳥越さんから、「金融資産とは何ですか」と筆者に聞いてきた。
「政策投資銀行(旧日本開発銀行)やUR都市機構(旧住都公団)などの特殊法人、
独立行政法人に対する貸付金、出資金です」と答えた。
それに対して「それらを回収したらどうなるの」とさらに聞かれたので、
「民営化か廃止すれば、回収ということになるが、それらへの天下りができなくなる」と答えた。
このやりとりを聞いていた他の出演者は、CM中のほうが、ためになる話が多いといっていた。
実際に、番組中で言うつもりだったが、時間の都合でカットせざるを得なくなった部分だ。
借金1000兆円。これは二つの観点から間違っている。

☆巨額な政府資産に驚くなかれ
バランスシートの左側を見てみれば・・・
第一に、バランスシートの右側の負債しか、言っていない。
今から20年近く前に、財政投融資のALM(資産負債管理)を行うために、国のバランスシートを作る必要があった。
当時、主計局から余計なことをするなと言われながらも、私は財政投融資が抱えていた巨額の金利リスクを解消するために、
国のバランスシートを初めて作った。
財政が危ういという、当時の大蔵省の主張は、ウソだったことはすぐにわかった。
ただし、現役の大蔵官僚であったので、対外的に言うことはなかった。
筆者の作った国のバランスシートは、大蔵省だからか「お蔵入り」になったが、
世界の趨勢から、その5年くらい後から試案として、10年くらい後から正式版として、財務省も公表せざるを得なくなった。
今年3月に、2013年度版国の財務書類が公表されている。
その2013年度末の国のバランスシートを見ると、資産は総計653兆円。
そのうち、現預金19兆円、有価証券129兆円、貸付金138兆円、出資66兆円、
計352兆円が比較的換金可能な金融資産である。
そのほかに、有形固定資産178兆円、運用寄託金105兆円、その他18兆円。

負債は1143兆円。
その内訳は、公債856兆円、政府短期証券102兆円、借入金28兆円、これらがいわゆる国の借金で計976兆円。
運用寄託金の見合い負債である公的年金預り金112兆円、その他45兆円。
ネット国債(負債の総額から資産を引いた額。つまり、1143兆円-653兆円)は490兆円を占める。
先進国と比較して、日本政府のバランスシートの特徴を言えば、政府資産が巨額なことだ。
政府資産額としては、世界一である。
政府資産の中身についても、比較的換金可能な金融資産の割合が、きわめて大きいのが特徴的だ。
なお、貸付金や出資金の明細は、国の財務書類に詳しく記されているが、そこが各省の天下り先になっている。
実は、財務省所管の貸付先は、他省庁に比べて突出して多い。
このため、財務省は各省庁の所管法人にも天下れるので、天下りの範囲は他省庁より広い。
要するに、「カネを付けるから、天下りもよろしく」ということだ。

☆財政再建は、実は完了している?
第二の問題点は、政府内の子会社を連結していないことだ。
筆者がバランスシートを作成した当時から、単体ベースと連結ベースのものを作っていた。
現在も、2013年度版連結財務書類として公表されている。
それを見ると、ネット国債は451兆円となっている。
単体ベースの490兆円よりは少なくなっている。
ただし、この連結ベースには、大きな欠陥がある。
日銀が含まれていないのだ。
日銀への出資比率は5割を超え、様々な監督権限もあるので、まぎれもなく、日銀は政府の子会社である。
経済学でも、日銀と政府は「広い意味の政府」とまとめて、一体のものとして分析している。
これを統合政府というが、会計的な観点から言えば、日銀を連結対象としない理由はない。
筆者は、日銀を連結対象から除いた理由は知らないが、連結対象として含めた場合のバランスシート作ることはできる。

2013年度末の日銀のバランスシートを見ると、資産は総計241兆円、そのうち国債が198兆円である。
負債も241兆円で、そのうち発行銀行券87兆円、当座預金129兆円である。
そこで、日銀も含めた連結ベースでは、ネット国債は253兆円である(2014.3.31末)。
直近ではどうなるだろうか。
直近の日銀の営業毎旬報告を見ると、資産として国債328兆円、負債として日銀券96兆円、当座預金248兆円となっている。
直近の政府のバランスシートがわからないので、正確にはいえないが、
あえて概数でいえば、日銀も含めた連結ベースのネット国債は、150~200兆円程度であろう。
そのまま行くと、近い将来には、ネット国債はゼロに近くなるだろう。
それに加えて、市中の国債は少なく、
資産の裏付けのあるものばかりになるので、ある意味で財政再建が完了したともいえるのだ。
ここで、「日銀券や当座預金も債務だ」という反論が出てくる。
これはもちろん債務であるが、国債と違って無利子である。
しかも償還期限もない。
この点は国債と違って、広い意味の政府の負担を考える際に重要である。

☆滑稽すぎる 「日本の財政は破綻する」論
このようにバランスシートで見ると、日銀の量的緩和の意味が、はっきりする。
政府と日銀の連結バランスシートを見ると、資産側は変化なし、負債側は国債減、日銀券(政府当座預金を含む)増となる。
つまり、量的緩和は、政府と日銀を統合政府で見たとき、負債構成の変化であり、
有利子の国債から、無利子の日銀券への転換ということだ。
このため、毎年転換分の利子相当の差益が発生する(これをシニョレッジ〔通貨発行益〕という。
毎年の差益を現在価値で合算すると、量的緩和額になる)。
また、政府からの日銀への利払いは、ただちに納付金となるので、
政府にとって日銀保有分の国債は、債務でないのも同然になる。
これで、連結ベースの国債額は、減少するわけだ。
量的緩和が、政府と日銀の連結バランスシートにおける負債構成の変化で、
シニョレッジ〔通貨発行益〕を稼げるメリットがある。
と同時にデメリットもある。
それはシニョレッジ〔通貨発行益〕を大きくすればするほど、インフレになるということだ。
だから、デフレの時にはシニョレッジ〔通貨発行益〕を増やせるが、インフレの時には限界がある。
その限界を決めるのが、インフレ目標である。
インフレ目標の範囲内であればデメリットはないが、超えるとデメリットになる。
幸いなことに、今のところ、デメリットはなく、実質的な国債が減少している状態だ。

こう考えてみると、財務省が借金1000兆円と言い、「だから消費増税が必要」と国民に迫るのは、
前提が間違っているので、暴力的な脅しでしかない。
実質的に借金は150~200兆円程度、GDP比で30~40%程度だろう。
ちなみに、アメリカ、イギリスで、中央銀行と連結したネット国債をGDP比でみよう。
アメリカで80%、65%、イギリスは80%、60%程度である。
これを見ると、日本の財政問題が大変で、すぐにでも破綻するという意見の滑稽さがわかるだろう。
以上は、バランスシートというストックから見た財政状況であるが、
フローから見ても、日本の財政状況はそれほど心配することはない、というデータもある。

本コラムの読者であれば、筆者が名目経済成長で、プライマリー収支を改善でき、
名目経済成長を高めるのは、それほど難しくない、
財政再建には、増税ではなく経済成長が必要、と書いてきたことを覚えているだろう。
その実践として、小泉・第一安倍政権で、増税はしなかったが、プライマリー収支が、ほぼゼロとなって財政再建できた。
これは、増税を主張する財務省にとって触れられたくない事実である。
実際、マスコミは財務省の言いなりなので、この事実を指摘する人はまずいない。
さらに、来2016年度の国債発行計画を見ると、新規に市中に出回る国債は、ほぼなくなることがわかる。
これは、財政再建ができた状況と、ほぼ同じ状況だ。
こうした状態で、少しでも国債が市中に出たらどうなるのか。
金融機関も一定量の国債投資が必要なので、出回った国債は、瞬間蒸発する。
つまり、とても国債暴落という状況にならないということだ。
何しろ市中に出回る国債がほとんどないので、
「日本の財政が大変なので財政破綻、国債暴落」と言い続けてきた、
デタラメな元ディーラー評論家には、厳しい年になるだろう。

☆今の国債市場は「品不足」状態
2016年度の国債発行計画を見ると、総発行額162.2兆円、
その内訳は市中消化分152.2兆円、個人向け販売分2兆円、日銀乗換8兆円である。
余談だが、最後の日銀乗換は、多くの識者が禁じ手としている「日銀引受」である。
筆者が役人時代、この国債発行計画を担当していたときにもあったし、今でもある。
これは、日銀の保有国債の償還分40兆円程度まで引受可能であるが、市中枠が減少するため、
民間金融機関が国債を欲しいとして、日銀乗換分を少なめにしているはずだ。
要するに、今の国債市場は、国債の品不足なのだ。
カレンダーベース市中発行額は147兆円であるが、短国25兆円を除くと、122兆円しかない。
ここで、日銀の買いオペは新規80兆円、償還分40兆円なので、合計で120兆円。
となると、市中消化分は、最終的には、ほぼ日銀が買い尽くすことになる。
民間金融機関は、国債投資から、貸付に向かわざるを得ない。
これは日本経済にとっては望ましいことだ。
と同時に、市中には実質的に国債が出回らないので、これは財政再建ができたのと同じ効果になる。
日銀が国債を保有した場合、その利払いは直ちに政府の納付金となって財政負担なしになる。
償還も乗換をすればいいので、償還負担もない。
それが、政府と日銀を連結してみれば、国債はないに等しいというわけだ。

こういう状態で、国債金利はどうなるだろうか。
市中に出回れば瞬間蒸発状態で、国債暴落なんてあり得ない。なにしろ必ず、日銀が買うのだから。
こうした見方から見れば、2016年度予算の国債費23.6兆円の計上には、笑えてしまう。
23.6兆円は、債務償還費13.7兆円、利払費9.9兆円に分けられる。
諸外国では、減債基金は存在しない。
借金するのに、その償還のために、基金を設けて、さらに借金するのは不合理だからだ。
なので、先進国では債務償還費は計上しない。
この分は、国債発行額を膨らせるだけで無意味となり、償還分は借換債を発行すればいいからだ。
利払費9.9兆円で、その積算金利は1.6%という。
市中分がほぼなく国債は品不足なのに、そんなに高い金利になるはずない。
実は、この高い積算金利は、予算の空積(架空計上)であり、
年度の後半になると、そんなに金利が高くならないので、不用が出る。
それを補正予算の財源にするのだ。・・》
注)原文にあえて改行を多くした。

この寄稿文を読み終わった後、「日本の借金1000兆円」は誤りで、
《・・実質的に借金は150~200兆円程度、GDP比で30~40%程度だろう。
ちなみに、アメリカ、イギリスで、中央銀行と連結したネット国債をGDP比でみよう。
アメリカで80%、65%、イギリスは80%、60%程度である。・・》
と学び、私は安堵したりした。
そして財務省は省内の権益の拡大、天下り先の確保なども含めて、どうして無知な国民を翻弄させるのょ、
と小心者の私は微苦笑したりした。

このような高橋洋一さんのひとつの寄稿文を学んだりし、今回のファイナンシャルプランナーの深野康彦さんの寄稿文を読み重ね、
大手メディアの新聞、テレビなどは、財務省に恐れ、日本の借金は昨今は1100兆円を超えている、と報じられいる、
と無力な私でも、微苦笑を重ねたりしている。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪