天狗がはじめて文献にあらわれるのは『日本書紀』(720年)です。舒明天皇9年2月23日(637年)に天狗が出現しました。現代語にあらため引用します。
大きな星が東から西に流れた。大音が響いたが雷に似ている。人々が言うに、流星(ながれぼし)の音だと。また別の人が言うのに、土雷(つちのいかづち)であろうと。しかし僧旻(そうみん)法師は「流星ではない。あれは[ 天狗 ]である。その吠え声が雷に似ているだけだ」
「書紀」より後に記された『聖徳太子伝歴』(917年)でも、この天変について「大星東ヨリ西ニ流ル。声有リ雷ノ如シ、時ニ僧旻法師曰ク、是レ[ 天狐 ]ト謂フ也」
天狗の読みは、書紀でも天狐「アマツキツネ」であろうというのが定説になっているようです。しかしわたしは、「キツネ」には無理があるように思います。狐は音<コ>です。天鼓<コ>ではないかしら?
しかしなぜ天の「狗」が「狐」キツネなのか? 狗<ク・コウ>は犬であり、子犬や小さな犬をふつう言います。鳶と糞鴟、そして狐…。天狗の正体はわかりにくい。
ところで僧旻ですが、もとの名は日文(にちもん)です。渡来人の子で、在日2世か3世だったと言われています。推古16年(608年)の第2次遣隋使、国書「日出処の天使…」を持参した使節の小野妹子とともに、留学生の高向玄理や南淵請安などと隋に向かいました。日文は2字を上下にくっつけ「旻」とし、「僧旻」と名乗る。隋そしてあたらしく建国なった唐に24年間留まり、学業に励んだ。そして舒明4年632年に帰国。その5年後に彼が語った「天狗」あるいは「天狐」は、隋や唐の時代に、大陸の人たちが信じていた「天狗」観からの解釈だったはずです。
僧旻法師は、大陸帰りの文人僧として、朝廷で重きをなします。蘇我入鹿や藤原鎌足たちにも講義をしています。中大兄皇子も話しを聞いたことでしょう。もしかしたら皇子は、天狗の正体を聞きただしたかもしれませんね。そのように考えると、実に楽しい。僧旻と皇子の天狗談義を喜んでいるのは、おそらくわたしだけでしょうが…。
大化元年645年には、国博士に任じられています。653年没ですが、享年は不詳です。
僧旻法師が隋唐で学んだであろう『史記』『漢書』、そして『山海経』などに天狗が登場します。ミイラからは離れてしまいましたが、天狗連載の次回は「世界最古の天狗」、すなわち「古代中国の天狗」の予定です。
<2011年2月1日>










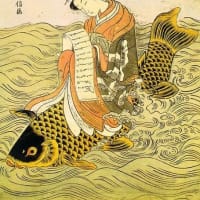



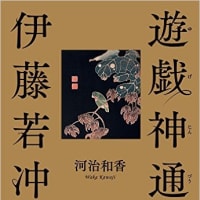





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます