京都・岡崎の細見美術館で、注目の抱一展が開かれています。2月まで開催なので、のんびり構えていました。ところが、気づいたら来月といっても2月2日まで! 日があまりありません。早く行かなければ。あわててお知らせします。
展覧会名「抱一に捧ぐ 花ひらく雨華庵(うげあん)の絵師たち」。江戸琳派は抱一にはじまりますが、弟子一門は延々と続き、雨華庵5世の酒井抱祝に至るまで、昭和の戦後まで続きます。雨華庵とは、抱一の住まいかつ、江戸琳派たちの画塾かつサロン。
日経新聞の記事では「酒井抱一は、姫路藩主酒井家の次男として江戸でうまれている。あの姫路城の主となる可能性も、僅かにだがあったわけである。」1月24日夕刊
年譜で抱一の仮養子と、世継ぎの甥の誕生をみてみましょう。
1773年、兄の忠以は第2代姫路藩主として初の国入り。抱一は仮養子として、江戸に留守居。もしもことあれば、抱一が第3代藩主をつとめることもある。仮養子の制度は、跡継ぎのいない大名が長旅をするときの決まりだそうだ。
1774年、兄忠以が高松藩主の娘と婚姻。
1777年、6月22日、忠以の国入りに際し、抱一は再び仮養子となる。兄が幕府に差し出した願いは「未男子無御座候付、私弟酒井栄八(抱一)儀、当酉二十歳相成申候、右之者当分養子仕度奉願候」
9月10日、兄忠以の長男、酒井忠道が生まれる。9月18日、忠以は抱一の仮養子願いを取り下げ申請。翌日了承される。
1790年、7月17日、抱一が30歳のとき、兄の姫路藩主・第2代酒井忠以が36歳で急逝。11月27日、抱一の甥の忠道が家督・第3代姫路城藩主を相続。
抱一は江戸琳派を大成させた。彼がもし姫路城主についていたら、どうだったでしょう。文化全般に精通した抱一です。画だけでなく、たくさんの成果を残したことでしょう。しかし時間の経つのを忘れて、度々作画に没頭することは、城主兼幕府要人では、困難ではないでしょうか。
ところで、彼の名「抱一」は『老子』からとっています。
「載営魄抱一、能無離乎。」10章
「是以聖人抱一為天下式」22章
「一」は道の同義語だそうです。「道」は万物の根源。「式」は模範、おきて。
魂魄(精神と肉体)を安らかにして唯一の「道」をしっかりと守り、それから離れないでいることができるか。
聖人は、道の本質をしっかりと身につけて天下の模範となるのだ。
抱一の俳号に「白鳧」「白鳧子」(はくふし)があります。杜甫の詩「白鳧行」からとっています。白鳧は、白い鴨ですが、鳧は日本では「けり」。鳧には「アヒル」の意味もあります。抱一は、表は杜甫のふりをして、実は名に白い「アヒル」をひそめているのではないか。兄の忠以の俳号は「銀鵝」、銀のガチョウです。ふたりは互いの命名に当たり、談笑しながら決めたのかもしれません。
同様に、「抱一」の名は『老子』からとっていますが、実は「放逸」を裏に隠しているのではないか? そのような説もあるようです。
また脱線してしまいました。アヒルや放逸はさて置いて、細見美術館に行きましょう。
<2025年1月27日/ほぼ毎回そうですが、年月日について。年は西暦ですが、月日は原則旧暦。正確には新旧で何日かのずれが生じます。ご了解ください。以降まず同様>










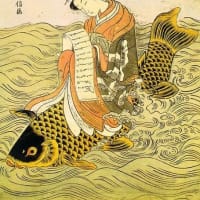



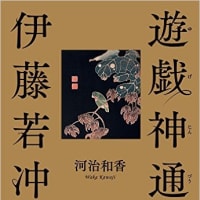





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます