◎大晦日と正月のハレの食事のことを前回、書きました。そのなかで「新年は大晦日の日暮れ直後、すでにはじまっている!」としました。「ウッソー」「信じられん」、「元旦夜明けからなら納得できますが…」。そのような反論を聞きました。一日のはじまりは一体、いつからなのか? この問題は次々回あたりにゆずるとして、興味と妙味の深い文章に出会いましたので、今日はダイジェストでお届けします。平山敏治郎先生の「七草粥に白砂糖」。『民俗学の窓』(昭和56年・学生社刊)所収です。
<お正月にいただくお雑煮は、実はいわゆる大年・大歳の夜、つまり大晦日の夕方から年神・歳神を迎えて祭った供え物を、朝になって祭りが終わったとき、お下がりを直会(なおらい)して食べたのだということは、すでに柳田国男先生が説き明かし、解釈しておられるので、もはや充分に知られていることと思う。
ところで雑煮だが、調理の仕方は地方によってさまざまである。おおきく分けると、京都・大阪など上方風は味噌汁に丸餅を入れて煮る。東京はすまし汁に焼いた切り餅を入れる。山陰から北陸では、小豆汁の餅である。ほぼ三通りがある。しかし例外も多い。鳥取には、善哉雑煮がある。能登にもこの食べ方はある。
江戸っ子のわたしが生まれ育った本所両国の家では、すましの雑煮であったが、京都に移り住んで(昭和12年京都帝国大学卒)、京都育ちの家内を迎えた翌年はじめての正月に、雑煮の調理法についてまず話し合うことになった。わたしは生家のなれた味を固執し、家内は京都の正月は白味噌雑煮、これを食べないと正月らしい気分になれないと主張する。ようやく妥協して、元旦は旦那さまの顔を立てて江戸前に、二日は奥さま手馴れた京風のものということに決まった。
元旦は切り餅を早朝から火鉢であぶって無事に祝い膳についたまではよかったが、二日の朝には、味噌は味噌でも甘い白味噌は避けて、日常の赤味噌で花嫁がつくった雑煮は、一口して舌上に異和感があり、思わずマズイと叫んで、半日胸やけして閉口した。その奇襲によって、以来今日まで数十回の正月を迎えて、東京流の雑煮を祝うことになった。家内には言い分もあり、味噌雑煮への郷愁もあるらしいが、まずはのどかな新年がつづいている。>
◎筆者追記:雑煮ですが、四国の讃岐・阿波あたりでは、白味噌汁に餅が入っているだけだそうです。また何と、餅には餡(あん)が込められている。大福餅雑煮のようなものでしょうか。わたしはまだ食したことはありませんが。なぜこのように甘い雑煮が好まれるか? おそらく江戸時代後半期から盛んになった白糖「和三盆」の生産地だからではないかと思います。ご存じの方がありましたら、ぜひご教示ください。砂糖は江戸期、とてつもなく高価な貴重品でした。
また滋賀県湖北・高島市の方に聞きました。「雑煮は、白味噌に餅が入っているだけ。餡なんてとんでもない。シンプルなモチです。せいぜいカツオの削り節をかけるくらいです」
この稿続く。<2010年1月31日 大晦日からもう一カ月… 南浦邦仁記> [208]
最新の画像[もっと見る]










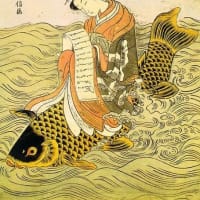



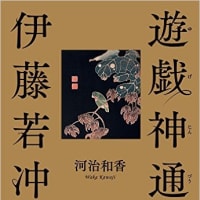





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます