平山敏治郎「七草粥に白砂糖」(『民俗学の窓』昭和56年・学生社刊)からのダイジェスト掲載の後篇です。文が輻輳していますので<平山文><河鰭文>、わたしのコメントは◎以下で区分けしました。
<友人の篠田統さんがかつて、島根県の五月五日、端午の節供(せっく)の粽と柏餅の分布調査を行った。柏餅をつくる村で育った女性が、粽の村へ嫁入った場合、その家ではやがて柏餅をつくるようになる。つまり主婦の嗜好習慣が家風に大きく作用を及ぼす、ひとつの例である。>
◎筆者の個人的意見:粽より柏餅の方が、甘いからではないか? 子どもは柏餅を好みます。おとなももちろん。いずれにしろ大家族制のもと、嫁が婚家の食習慣をかえた珍しい例です。
<家族のだれの好物でも、主婦が嫌う食物は決して食膳にのらない。そのような個人的好物は、外食でおぎなわなければならない。
ところで今年もわが家では、正月七日の朝に七草粥、十五日の朝には小豆粥を祝った。わたしの恒例の粥祝いは、白砂糖を鉢に盛り上げ、これを適宜に粥に振りかけて食べることになっている。ものごころついて以来、家族揃ってこのようにしてきた。わが家の仕来たりであったから、別に珍しいことをしているとも思わず、しごくあたりまえの食作法としか考えなかった。
ところが大学生になってはじめて京都に来て、この家風が実はかなり異風であることを、いやというほど思い知らされた。
米の粥に砂糖をかけて食べるなど、聞いただけでも見ただけでも、いやらしいという人に、たびたび出会った。しかしわたしの古いかすかな記憶をたどると、妹が産まれたとき、母が産後の養生食いに、粥に白砂糖をかけているのを見て、ねだって食べたこともある。それほど、粥と砂糖は切って離せない。
ところがあるとき、日本橋の旧家出身者に会って正月粥のことを話したら、彼も近所の知り合いも、みな粥に白砂糖をかけるという答えが、即座に返ってきた。そのときのわたしの感動、うれしさは何にたとえようも知らない。
池田弥三郎さんも『私の食物誌』の「一月七日のななくさの話題」に書いている。「わたしのうちなどでは、別に植物類のたきこみもしなかった。ただ、さとうで味をつけた『おかゆ』であった。あまりおいしくもないので、大抵いっぱいでごめんをこうむった」…>
◎ 参考:池田先生の生家は、東京銀座のテンプラ屋「天金」
◎平山先生はこの異風の食習慣に思いをめぐらす。これらを思いあわすと江戸時代、国産の白砂糖、四国は阿波・讃岐地方でようやく産出された三盆白(和三盆)は高価であり、豪奢品でもあった。身分制にあぐらをかいていた侍も多くが貧乏で、貴重な白砂糖など口にすることができなかった。そこで経済力豊かな富商たちは、ひそかに家族だけで魅力的な甘味に舌鼓を打った。威張るばかりで無力な侍たちを馬鹿にしながら。また砂糖は薬でもあった。新年の甘粥は、江戸の富商にとって、一家繁栄の象徴の祝いであったようだ。
<よくよく考えてみると、粥それも小豆粥ならばともかくも、七草の青みを加えた粥に白砂糖をふりかけたところで、天下の美味になるわけではない。いわば痩せ我慢にも似た態度であった。わたし自身も家風の惰性で、家族が口を尖らせ、白い眼を見せるからこそ肩肘張ってみせるだけのことである。急に止めようとは考えないが、江戸末期以来の町人層のひそかな工夫もわが家では、わたし一代で廃れるであろう。それも惜しいとは思わない。>
◎コメント:平山敏治郎先生の家では、もうこの砂糖粥はすたれているのでしょうね。ところが最近、驚くべき文章に出会いました。河鰭実英「近世に於ける公家食生活の研究」(雄山閣出版『全集日本の食生活』第2巻・1999年)
◎公家の倉橋家史料(1818~1830)によると、正月の七種粥にはナズナと餅を入れた。河鰭先生によると、
<もちろんこの粥のなかには、白砂糖をかけたこと疑いをいれない。三条家史料(1819)では、小正月15日は餅の入った小豆粥であるが、もちろんこの粥のときも、白砂糖をかけて食したのである>
◎いずれも京都の公家たちの史料である。19世紀のはじめ、貧乏であった公家であるが、和三盆普及の初期に白砂糖を粥にかけた! 当然、維新ののちに江戸・東京に移り住み、この風習を持ち込んだに違いない。
しかし江戸商人の砂糖粥も、江戸時代からの食習慣であるという。いったい、粥に砂糖をかけるという異習は、どのように広まったのか?
◎淡白な味をたっとぶ京都である。雑煮をみても公家たちは、意外なことに「すまし雑煮」を好んでいた。
<それは大正時代まで宮廷で保存されたおくゆかしき料理法であるが、公家家庭においても同様に料理した。すなわち雑煮のなかに入れるものは鉄板で焼いた「焼餅」と青味、すなわち季節の青菜だけで、それに昆布のダシ、およびカツブシのダシを用いた「すまし汁」をかけて、食の直前にカツブシを削ったもの、いわゆる「花カカ」(かか)をかけて食するのである。枯淡な公家風の味は、ここに味わう事ができよう>
◎何と、すまし汁に焼餅入りである。現代の京都庶民の雑煮とはおおいに異なり、濃い口にすれば関東風になってしまう。
◎読めば読むほど、知れば知るほど、年中行事の食事のバラエティ豊かさには感心してしまいます。なお著者の河鰭実英先生(1891~1983)は、日本服飾史・有職故実の専門家で、大正天皇の侍従をつとめられた方です。ご存命であればお会いして、あれこれお話を聞きたいのですが。
しかし幸いなことに、今週の水曜日、あるお公家さんと晩ご飯をご一緒することになりました。現代公家の食を聞き取りします。収穫が楽しみです。お楽しみに。
◎追記:白砂糖粥についてその後、あれこれ考えてみました。河鰭先生が江戸期の史料に記載がないのに「もちろん粥のとき白砂糖をかけて食したのである」と断定されるのはなぜか? おそらく公家たちは、明治大正期にも正月に砂糖粥を食していたのだろう。当時なら江戸時代に生まれた御隠居さんも多数、健在である。東京遷都後の新風習ではないはずだ。
また氏は、大正天皇の侍従をつとめた方である。明治・大正、両天皇も同様であったからではなかろうか。さらには、昭和も平成も、天皇は砂糖粥を踏襲しておられるのではなかろうか。雅子さんは結婚後の初正月、甘い粥に辟易したのでは。わたしなりの結論です。
<2010年2月7日> [209]
<友人の篠田統さんがかつて、島根県の五月五日、端午の節供(せっく)の粽と柏餅の分布調査を行った。柏餅をつくる村で育った女性が、粽の村へ嫁入った場合、その家ではやがて柏餅をつくるようになる。つまり主婦の嗜好習慣が家風に大きく作用を及ぼす、ひとつの例である。>
◎筆者の個人的意見:粽より柏餅の方が、甘いからではないか? 子どもは柏餅を好みます。おとなももちろん。いずれにしろ大家族制のもと、嫁が婚家の食習慣をかえた珍しい例です。
<家族のだれの好物でも、主婦が嫌う食物は決して食膳にのらない。そのような個人的好物は、外食でおぎなわなければならない。
ところで今年もわが家では、正月七日の朝に七草粥、十五日の朝には小豆粥を祝った。わたしの恒例の粥祝いは、白砂糖を鉢に盛り上げ、これを適宜に粥に振りかけて食べることになっている。ものごころついて以来、家族揃ってこのようにしてきた。わが家の仕来たりであったから、別に珍しいことをしているとも思わず、しごくあたりまえの食作法としか考えなかった。
ところが大学生になってはじめて京都に来て、この家風が実はかなり異風であることを、いやというほど思い知らされた。
米の粥に砂糖をかけて食べるなど、聞いただけでも見ただけでも、いやらしいという人に、たびたび出会った。しかしわたしの古いかすかな記憶をたどると、妹が産まれたとき、母が産後の養生食いに、粥に白砂糖をかけているのを見て、ねだって食べたこともある。それほど、粥と砂糖は切って離せない。
ところがあるとき、日本橋の旧家出身者に会って正月粥のことを話したら、彼も近所の知り合いも、みな粥に白砂糖をかけるという答えが、即座に返ってきた。そのときのわたしの感動、うれしさは何にたとえようも知らない。
池田弥三郎さんも『私の食物誌』の「一月七日のななくさの話題」に書いている。「わたしのうちなどでは、別に植物類のたきこみもしなかった。ただ、さとうで味をつけた『おかゆ』であった。あまりおいしくもないので、大抵いっぱいでごめんをこうむった」…>
◎ 参考:池田先生の生家は、東京銀座のテンプラ屋「天金」
◎平山先生はこの異風の食習慣に思いをめぐらす。これらを思いあわすと江戸時代、国産の白砂糖、四国は阿波・讃岐地方でようやく産出された三盆白(和三盆)は高価であり、豪奢品でもあった。身分制にあぐらをかいていた侍も多くが貧乏で、貴重な白砂糖など口にすることができなかった。そこで経済力豊かな富商たちは、ひそかに家族だけで魅力的な甘味に舌鼓を打った。威張るばかりで無力な侍たちを馬鹿にしながら。また砂糖は薬でもあった。新年の甘粥は、江戸の富商にとって、一家繁栄の象徴の祝いであったようだ。
<よくよく考えてみると、粥それも小豆粥ならばともかくも、七草の青みを加えた粥に白砂糖をふりかけたところで、天下の美味になるわけではない。いわば痩せ我慢にも似た態度であった。わたし自身も家風の惰性で、家族が口を尖らせ、白い眼を見せるからこそ肩肘張ってみせるだけのことである。急に止めようとは考えないが、江戸末期以来の町人層のひそかな工夫もわが家では、わたし一代で廃れるであろう。それも惜しいとは思わない。>
◎コメント:平山敏治郎先生の家では、もうこの砂糖粥はすたれているのでしょうね。ところが最近、驚くべき文章に出会いました。河鰭実英「近世に於ける公家食生活の研究」(雄山閣出版『全集日本の食生活』第2巻・1999年)
◎公家の倉橋家史料(1818~1830)によると、正月の七種粥にはナズナと餅を入れた。河鰭先生によると、
<もちろんこの粥のなかには、白砂糖をかけたこと疑いをいれない。三条家史料(1819)では、小正月15日は餅の入った小豆粥であるが、もちろんこの粥のときも、白砂糖をかけて食したのである>
◎いずれも京都の公家たちの史料である。19世紀のはじめ、貧乏であった公家であるが、和三盆普及の初期に白砂糖を粥にかけた! 当然、維新ののちに江戸・東京に移り住み、この風習を持ち込んだに違いない。
しかし江戸商人の砂糖粥も、江戸時代からの食習慣であるという。いったい、粥に砂糖をかけるという異習は、どのように広まったのか?
◎淡白な味をたっとぶ京都である。雑煮をみても公家たちは、意外なことに「すまし雑煮」を好んでいた。
<それは大正時代まで宮廷で保存されたおくゆかしき料理法であるが、公家家庭においても同様に料理した。すなわち雑煮のなかに入れるものは鉄板で焼いた「焼餅」と青味、すなわち季節の青菜だけで、それに昆布のダシ、およびカツブシのダシを用いた「すまし汁」をかけて、食の直前にカツブシを削ったもの、いわゆる「花カカ」(かか)をかけて食するのである。枯淡な公家風の味は、ここに味わう事ができよう>
◎何と、すまし汁に焼餅入りである。現代の京都庶民の雑煮とはおおいに異なり、濃い口にすれば関東風になってしまう。
◎読めば読むほど、知れば知るほど、年中行事の食事のバラエティ豊かさには感心してしまいます。なお著者の河鰭実英先生(1891~1983)は、日本服飾史・有職故実の専門家で、大正天皇の侍従をつとめられた方です。ご存命であればお会いして、あれこれお話を聞きたいのですが。
しかし幸いなことに、今週の水曜日、あるお公家さんと晩ご飯をご一緒することになりました。現代公家の食を聞き取りします。収穫が楽しみです。お楽しみに。
◎追記:白砂糖粥についてその後、あれこれ考えてみました。河鰭先生が江戸期の史料に記載がないのに「もちろん粥のとき白砂糖をかけて食したのである」と断定されるのはなぜか? おそらく公家たちは、明治大正期にも正月に砂糖粥を食していたのだろう。当時なら江戸時代に生まれた御隠居さんも多数、健在である。東京遷都後の新風習ではないはずだ。
また氏は、大正天皇の侍従をつとめた方である。明治・大正、両天皇も同様であったからではなかろうか。さらには、昭和も平成も、天皇は砂糖粥を踏襲しておられるのではなかろうか。雅子さんは結婚後の初正月、甘い粥に辟易したのでは。わたしなりの結論です。
<2010年2月7日> [209]










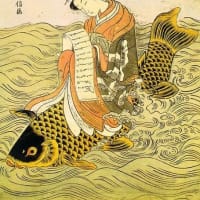



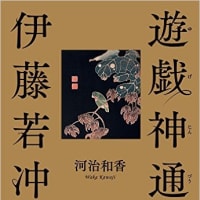





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます