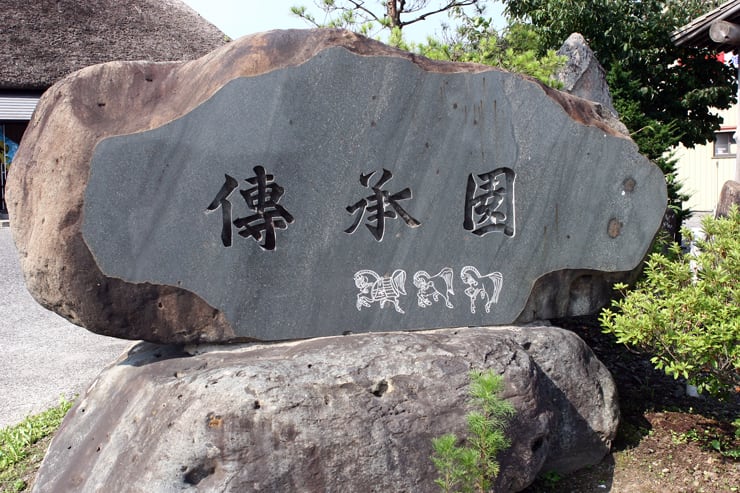名所旧跡を訪ねる旅
兵庫県のご夫婦に感謝の意を込めて
最近老化現象が進行し足腰が弱ってきている。歩けるうちにもう一度「三仏寺 投入堂」に参拝したいと以前から考えていた。
2・3日前にこれからどこに放浪しようかと考えていた時に、三仏寺のことが頭に浮かんできた。
餘部鉄橋から鳥取砂丘と意図を持って三仏寺の方に向かってきている。

三仏寺で一番困ることは単独では入山できないことだ。
今回、車から降りたときにご夫婦が歩いてきたので「ご一緒できないか」と声をかけてみた。
ご快諾いただいたので入山できることになり感謝している。
ご夫婦にブログのことを伝えているので、投入堂まで順を追って紹介していく。旅の思い出になってくれると大変嬉しい。
宿入橋

十一面観音堂

役行者

かづら坂

くさり坂
目の前に文殊堂が見えるがここにたどり着くには、鎖の力を借りることになる。

文殊堂(重要文化財)



地蔵堂(重要文化財)


地蔵堂から見える景色。
美しさより回廊から転落するのではないかとの恐怖が。文殊堂の屋根が見える。


鐘撞堂

鐘は自由に撞いて良いのだが、体が自由に動かず撞くのに苦労する。

馬の背、牛の背


納経堂(重要文化財)



観音堂

裏側は暗く胎内くぐりを体験できる。


元結掛堂


投入堂(国宝)
以前来たときは「ああっ」と大きな声が出たほど感動したが、今回は冷静でいられた。

ここまで来るにはかなりの苦労があるが、やはり一見の価値は十分ある。


足場も悪く移動できないため同じような写真しか撮れないのが残念である。


今回が最後と決めて入山している。

本堂


地蔵堂と七福神

馬を掲載するとその週の競馬の馬券が的中するのでこれは私のために。

宝物蔵
展示物の見せ方としては最悪である、蛍光灯の光がガラスに反射して重要文化財である仏像もまともに観ることができない。本当に残念である。

小さな石仏たち

最後の一枚は遙か遠くから見える投入堂

撮影 平成25年10月31日
兵庫県のご夫婦に感謝の意を込めて
最近老化現象が進行し足腰が弱ってきている。歩けるうちにもう一度「三仏寺 投入堂」に参拝したいと以前から考えていた。
2・3日前にこれからどこに放浪しようかと考えていた時に、三仏寺のことが頭に浮かんできた。
餘部鉄橋から鳥取砂丘と意図を持って三仏寺の方に向かってきている。

三仏寺で一番困ることは単独では入山できないことだ。
今回、車から降りたときにご夫婦が歩いてきたので「ご一緒できないか」と声をかけてみた。
ご快諾いただいたので入山できることになり感謝している。
ご夫婦にブログのことを伝えているので、投入堂まで順を追って紹介していく。旅の思い出になってくれると大変嬉しい。
宿入橋

十一面観音堂

役行者

かづら坂

くさり坂
目の前に文殊堂が見えるがここにたどり着くには、鎖の力を借りることになる。

文殊堂(重要文化財)



地蔵堂(重要文化財)


地蔵堂から見える景色。
美しさより回廊から転落するのではないかとの恐怖が。文殊堂の屋根が見える。


鐘撞堂

鐘は自由に撞いて良いのだが、体が自由に動かず撞くのに苦労する。

馬の背、牛の背


納経堂(重要文化財)



観音堂

裏側は暗く胎内くぐりを体験できる。


元結掛堂


投入堂(国宝)
以前来たときは「ああっ」と大きな声が出たほど感動したが、今回は冷静でいられた。

ここまで来るにはかなりの苦労があるが、やはり一見の価値は十分ある。


足場も悪く移動できないため同じような写真しか撮れないのが残念である。


今回が最後と決めて入山している。

本堂


地蔵堂と七福神

馬を掲載するとその週の競馬の馬券が的中するのでこれは私のために。

宝物蔵
展示物の見せ方としては最悪である、蛍光灯の光がガラスに反射して重要文化財である仏像もまともに観ることができない。本当に残念である。

小さな石仏たち

最後の一枚は遙か遠くから見える投入堂

撮影 平成25年10月31日