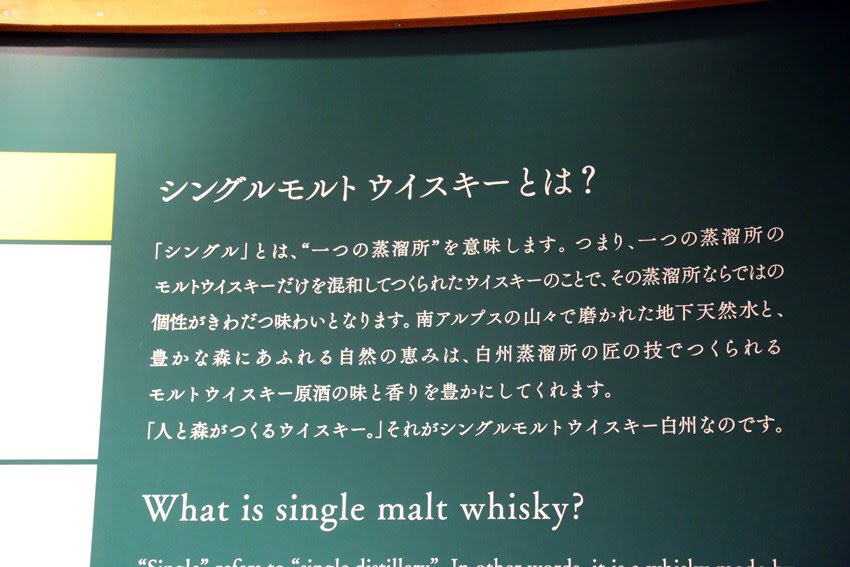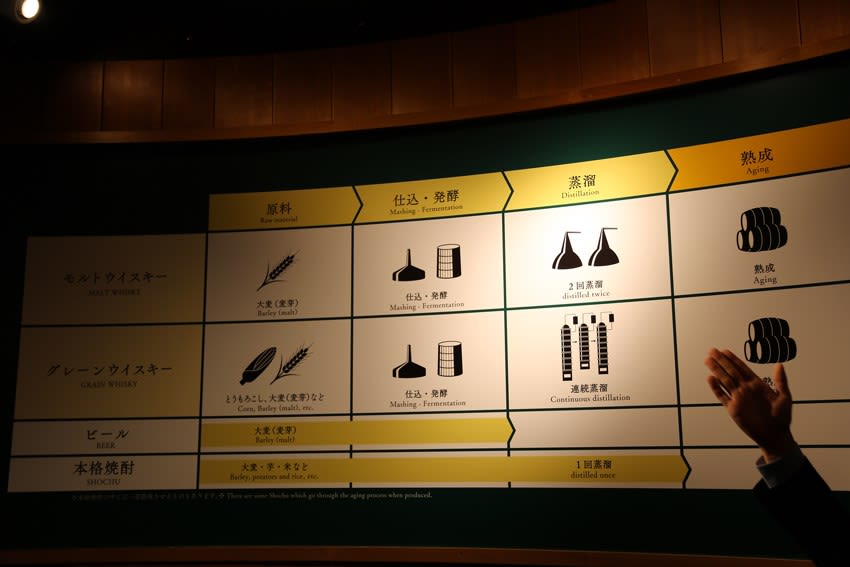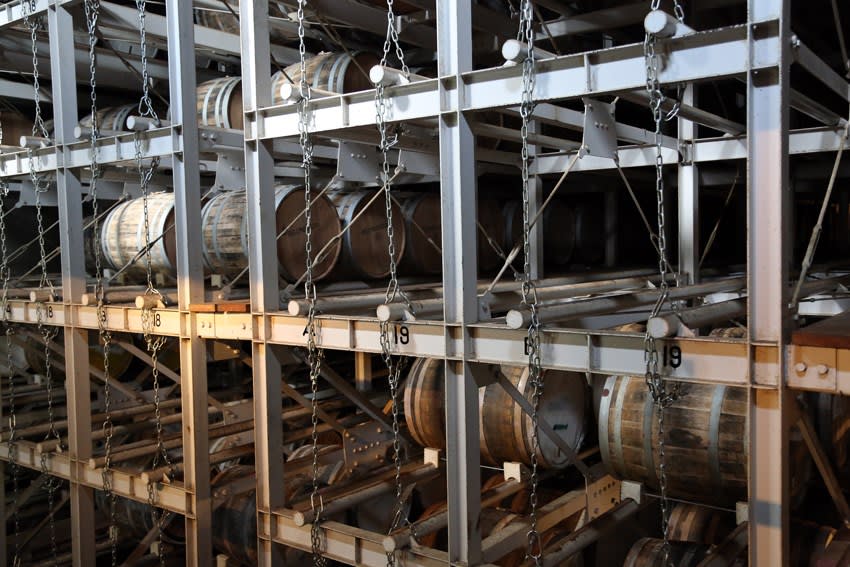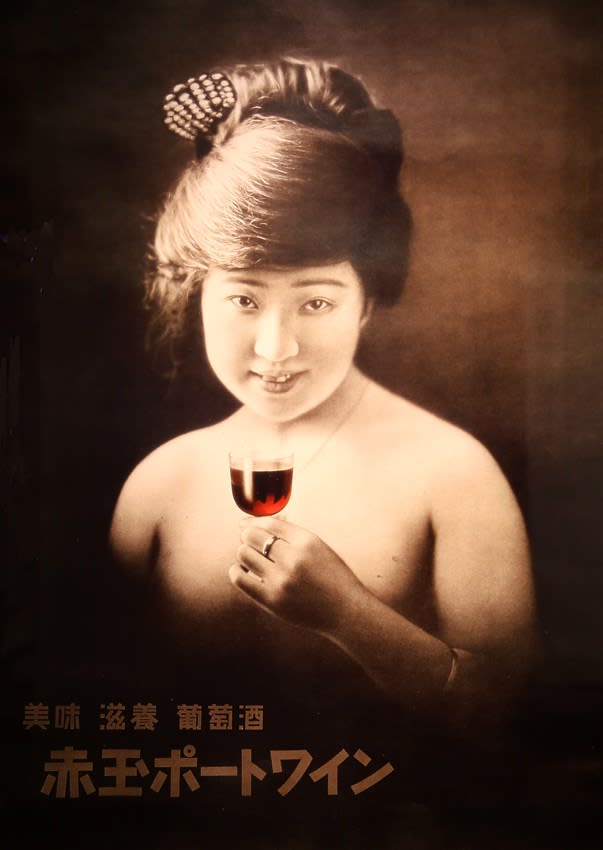諏訪大社 本宮
諏訪大社には以前から訪れてみたいと思っていた
朝、パンとコーヒーを飲みながら調べてみると4箇所に分かれていることを知った
最初に中心となる本宮からと思いナビに行き先をセットした
駐車場の近くにある東参道から境内に入る
手水舎

鳥居

出早社

大欅(樹齢約千年)
境内最古の樹木

神馬舎(重要文化財)
駒形屋とも呼ばれている

背に御幣を立てた銅製の神馬と木製の神馬が安置されている
重文とは知らずいつものように隙間にレンズを突っ込み撮った

本宮二の御柱
社殿の周囲四隅には、御柱(おんばしら)と呼ぶ以下4本の樅の柱が建てられている
御柱は一から四の順に短く細くなり、上空から見た場合に時計回りに配置される

入口御門(重要文化財)

文政12年(1829)建立

しばし立ち止まり彫刻を観ていた


布橋(重要文化財)
古くは大祝(おおほうり):諏訪氏(神氏)のみが渡り、布が敷かれた

布橋の左右にも興味を惹く建物がある。進行方向の左から拝観する
額堂(重要文化財)

絵馬堂とも呼ばれている


摂末社遙拝所(重要文化財)

大国主社

東御宝殿


勅使門(重要文化財)
元禄3年(1690年)造営。数々の神事が行われた


五間廊(重要文化財)
安永2年(1773年)造営

あまりにも由緒ある建物が多くて、その全てを紹介できなかった
撮影 平成29年5月19日
諏訪大社には以前から訪れてみたいと思っていた
朝、パンとコーヒーを飲みながら調べてみると4箇所に分かれていることを知った
最初に中心となる本宮からと思いナビに行き先をセットした
駐車場の近くにある東参道から境内に入る
手水舎

鳥居

出早社

大欅(樹齢約千年)
境内最古の樹木

神馬舎(重要文化財)
駒形屋とも呼ばれている

背に御幣を立てた銅製の神馬と木製の神馬が安置されている
重文とは知らずいつものように隙間にレンズを突っ込み撮った

本宮二の御柱
社殿の周囲四隅には、御柱(おんばしら)と呼ぶ以下4本の樅の柱が建てられている
御柱は一から四の順に短く細くなり、上空から見た場合に時計回りに配置される

入口御門(重要文化財)

文政12年(1829)建立

しばし立ち止まり彫刻を観ていた


布橋(重要文化財)
古くは大祝(おおほうり):諏訪氏(神氏)のみが渡り、布が敷かれた

布橋の左右にも興味を惹く建物がある。進行方向の左から拝観する
額堂(重要文化財)

絵馬堂とも呼ばれている


摂末社遙拝所(重要文化財)

大国主社

東御宝殿


勅使門(重要文化財)
元禄3年(1690年)造営。数々の神事が行われた


五間廊(重要文化財)
安永2年(1773年)造営

あまりにも由緒ある建物が多くて、その全てを紹介できなかった
撮影 平成29年5月19日