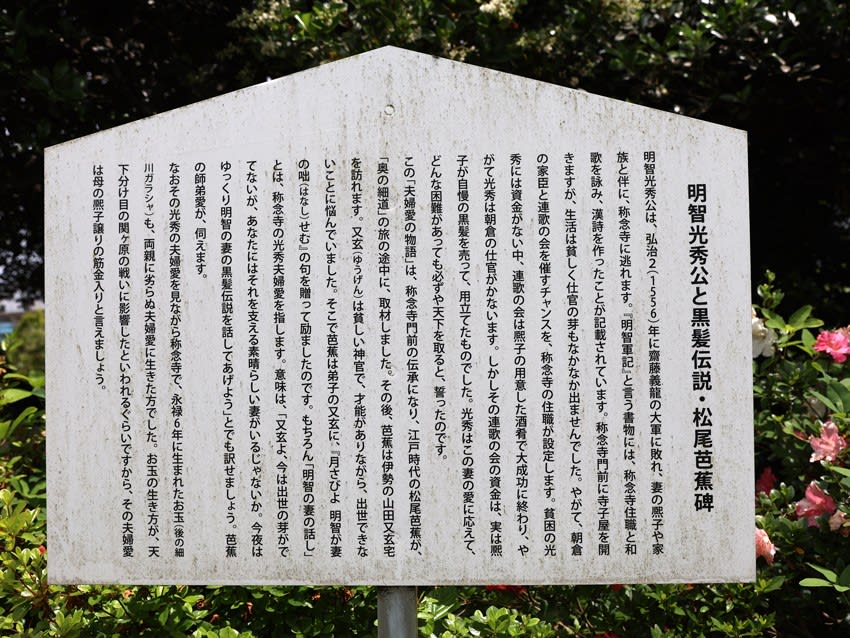訪問日 令和6年5月31日
2024年春 放浪の旅(18日目)福井県・石川県
道の駅「さかい」(福井県坂井市坂井町蔵垣内34 -14-1)
前日は暑さで予定していた神社をキャンセルしたため、近くにあった道の駅を選んだ
初めての場所かと思っていたが数年前訪れたことがあった

道の駅の中央部分に置かれているのだが、今回は大谷選手の姿があった

初めて訪れたときに宮城県から来たという男性に声を掛けられた
車内を見せてもらったところ男の一人旅とは思えないほど整理整頓されていた
輪ゴムを使ってゴミを圧縮していることを教わり、私も実践しているが効果がない

1 三国神社(福井県坂井市三国町山王6丁目2-80)
この周辺を走ったときには、いつも訪問地の候補にあがるのだが、今回が初めてとなる
実は昨日最後の訪れる予定だった場所でもある
鳥居

随身門(福井県指定文化財)

随身像

拝殿


本殿
祭神:大山咋命(山王権現)継体天皇

2 雄島(福井県坂井市三国町安島)
東尋坊から雄島の赤い橋がずっと気になっていた
橋の前は無料駐車場があり、小学生が雄島のスケッチをしていた

橋の前で40年前は20歳代と思われる3名の女性の記念写真を撮ってあげた
この世代に限らず女性は活動的だ

島全体が流紋岩でできており、東尋坊同様に「柱状節理」が発達している

大湊神社鳥居
鳥居の奥からやって来た、二人の若い女性に「どうでしたか」と声を掛けた
「階段は急だけど雰囲気がとてもいいですよ」と勧められた

美人さんの言うとおり、確かに雰囲気はいい

この石段は歩きやすく疲れない感じがする

社殿(福井県指定文化財)

この鳥居の奥に見えるのが「東尋坊」

拝殿前で気持ちのよい挨拶をされたのがこの女性
隙間時間を見つけ日帰りで観光地を巡っているそうだ
数分間話をしたが聡明で美人(爺元気になる)

3 道の駅「蓮如の里あわら」(福井県あわら市吉崎1丁目801)
道の駅が開業したことを知り立ち寄ってみた
道の駅ができる前に一度訪れたことがあるが、最近では通過することが多かった
史跡 吉崎御坊址

蓮如像(「高村光雲作)
蓮如は、開祖親鸞と並び、浄土真宗の指導者として、広く民衆の中に生き続けてきた

作家 五木寛之氏の小説を読んで、蓮如の存在を知り興味を持った


蓮如上人「お腰掛けの石」

そして、見たであろう景色がここ


4 安宅住吉神社(石川県小松市安宅町タ17)
小松市には何度か訪れているが、この神社は初めてとなる
安宅といえば「安宅関」が有名であるが、ここにあるとは知らなかった

鳥居
駐車場に入った時から、神社の雰囲気の良さには驚いた

拝殿

拝殿内部

安宅関址(源義経公奥州落ち経由地)
兄の源頼朝に謀反を疑われて追われる義経が奥州平泉へと落ちのびる途中の文治3年(1187 年)、山伏姿で安宅の新関にさしかかる
関を越えようとしたその時に、関守富樫泰家に見とがめられ、詮議の問答が始まる

勧進帳とは寺院建立などの資金集めにその趣意をしたためたもの
弁慶は白紙の勧進帳を読み上げて、強力に身をやつした義経をかばう

しかし顔が似ているという関守の前で義経に似た貴様が憎しと主人を打ちすえる
その忠義の心に感じた富樫は義経と知りながらも一行を解放し、関を通してしまう

2024年春 放浪の旅(18日目)福井県・石川県
道の駅「さかい」(福井県坂井市坂井町蔵垣内34 -14-1)
前日は暑さで予定していた神社をキャンセルしたため、近くにあった道の駅を選んだ
初めての場所かと思っていたが数年前訪れたことがあった

道の駅の中央部分に置かれているのだが、今回は大谷選手の姿があった

初めて訪れたときに宮城県から来たという男性に声を掛けられた
車内を見せてもらったところ男の一人旅とは思えないほど整理整頓されていた
輪ゴムを使ってゴミを圧縮していることを教わり、私も実践しているが効果がない

1 三国神社(福井県坂井市三国町山王6丁目2-80)
この周辺を走ったときには、いつも訪問地の候補にあがるのだが、今回が初めてとなる
実は昨日最後の訪れる予定だった場所でもある
鳥居

随身門(福井県指定文化財)

随身像

拝殿


本殿
祭神:大山咋命(山王権現)継体天皇

2 雄島(福井県坂井市三国町安島)
東尋坊から雄島の赤い橋がずっと気になっていた
橋の前は無料駐車場があり、小学生が雄島のスケッチをしていた

橋の前で40年前は20歳代と思われる3名の女性の記念写真を撮ってあげた
この世代に限らず女性は活動的だ

島全体が流紋岩でできており、東尋坊同様に「柱状節理」が発達している

大湊神社鳥居
鳥居の奥からやって来た、二人の若い女性に「どうでしたか」と声を掛けた
「階段は急だけど雰囲気がとてもいいですよ」と勧められた

美人さんの言うとおり、確かに雰囲気はいい

この石段は歩きやすく疲れない感じがする

社殿(福井県指定文化財)

この鳥居の奥に見えるのが「東尋坊」

拝殿前で気持ちのよい挨拶をされたのがこの女性
隙間時間を見つけ日帰りで観光地を巡っているそうだ
数分間話をしたが聡明で美人(爺元気になる)

3 道の駅「蓮如の里あわら」(福井県あわら市吉崎1丁目801)
道の駅が開業したことを知り立ち寄ってみた
道の駅ができる前に一度訪れたことがあるが、最近では通過することが多かった
史跡 吉崎御坊址

蓮如像(「高村光雲作)
蓮如は、開祖親鸞と並び、浄土真宗の指導者として、広く民衆の中に生き続けてきた

作家 五木寛之氏の小説を読んで、蓮如の存在を知り興味を持った


蓮如上人「お腰掛けの石」

そして、見たであろう景色がここ


4 安宅住吉神社(石川県小松市安宅町タ17)
小松市には何度か訪れているが、この神社は初めてとなる
安宅といえば「安宅関」が有名であるが、ここにあるとは知らなかった

鳥居
駐車場に入った時から、神社の雰囲気の良さには驚いた

拝殿

拝殿内部

安宅関址(源義経公奥州落ち経由地)
兄の源頼朝に謀反を疑われて追われる義経が奥州平泉へと落ちのびる途中の文治3年(1187 年)、山伏姿で安宅の新関にさしかかる
関を越えようとしたその時に、関守富樫泰家に見とがめられ、詮議の問答が始まる

勧進帳とは寺院建立などの資金集めにその趣意をしたためたもの
弁慶は白紙の勧進帳を読み上げて、強力に身をやつした義経をかばう

しかし顔が似ているという関守の前で義経に似た貴様が憎しと主人を打ちすえる
その忠義の心に感じた富樫は義経と知りながらも一行を解放し、関を通してしまう