「誰の山 どんな山」 「2017 四方山話 その壱」 「2017 四方山話 その弐」 「2017 四方山話 その参」 「2017 四方山話 その肆」 「2017 四方山話 食事編」
「2017 四方山話 食事編」を、「いつものお宿''上高地温泉ホテル''で体重計に乗ったなら」で終えているが...
一年に一度は上高地で過すことにしている我が家が毎年お世話になるホテルのお決まりの部屋。
ここで、ワンコと寛いで体重が増えないはずがない。

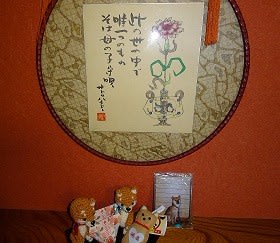
体重増加に大いに寄与している食事の写真を掲載できれば良いのだが、一品ひとしなずつ供される食事を撮ることは憚られたので、食事の写真はない。
他にも、本当は撮りたかったにも拘らず(やはり憚られて)撮れなかったものに、ロビーに併設されているギャラリーに展示される、秩父宮様がお使いになられた茶器と、青蓮院門跡門主 東伏見慈晃様(今上陛下の従弟)の書が ある。
書を撮るのは憚られたが、揮毫された「山川草木悉皆成仏」「一隅を照らす」の言葉は胸にしみるので、ここに記しておきたい。
というわけで、最後のお宿の食事の写真はないが、「日常ではありえない荷物を担ぎ、日常ではありえない距離を歩き攀じ登り、なぜに体重が減らないのか、どうかすると増えるのか」と嘆いたままでは情けないので、何か科学的根拠はないかと検索していると、あったんだな、コレが。
「Little Medical~ちょっとメディカ~あなたの毎日を充実させるために」というサイトの「登山後に大樹が増加するのは【むくみ】が原因?予防法や対処法は?」によると、登山時に生じる筋肉痛が体重増加の原因だという。
筋肉痛は、筋肉繊維が破壊され炎症を起こすことにより生じるそうだが、人間の身体は良くできており、破壊された繊維はすぐさま、より太く強い筋肉繊維をつくることで回復しようとするのだという。その時に、多くの糖分を溜め込もうとするため水分の代謝が一時的に悪くなり【むくみ】となり体重増加の原因となるのだそうだ。
『(記事より引用)この体重増加は一時的なもので、筋繊維が完全に修復されたら、水分の代謝ももとに戻り、体重も元通りになります。
登山経験が浅い人だと登山後に体重増加が起こりやすいです。
これは、登山に必要な筋肉の筋繊維が破壊されるためです。
登山経験の長い人は、登山による筋肉痛が起こりにくくなるため、登山後の体重増加もほとんど見られなくなります。』
https://currentjp.com/archives/12938.html
確かに、下山直後に増加した体重は、帰宅して2~3日もすれば元通りになり、その後しばらくは減少傾向が続いてくれる。
これを私は、登山により基礎代謝量がupしたおかげだと思っていたが、記事によると、どうやら勘違いのようだ。
山に魅せられて20年ちかくになるが、実際には年に一二度登ることができれば上等という状態なので、これからも下山直後の体重増加は続くと思うが、安全で楽しい登山を最大の目標にし、これからも山を歩きたいと思っている。
お山の話は、あと一つ つづく
「2017 四方山話 食事編」を、「いつものお宿''上高地温泉ホテル''で体重計に乗ったなら」で終えているが...
一年に一度は上高地で過すことにしている我が家が毎年お世話になるホテルのお決まりの部屋。
ここで、ワンコと寛いで体重が増えないはずがない。

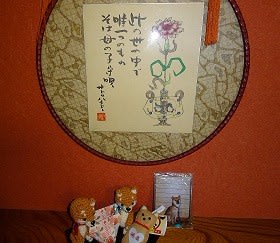
体重増加に大いに寄与している食事の写真を掲載できれば良いのだが、一品ひとしなずつ供される食事を撮ることは憚られたので、食事の写真はない。
他にも、本当は撮りたかったにも拘らず(やはり憚られて)撮れなかったものに、ロビーに併設されているギャラリーに展示される、秩父宮様がお使いになられた茶器と、青蓮院門跡門主 東伏見慈晃様(今上陛下の従弟)の書が ある。
書を撮るのは憚られたが、揮毫された「山川草木悉皆成仏」「一隅を照らす」の言葉は胸にしみるので、ここに記しておきたい。
というわけで、最後のお宿の食事の写真はないが、「日常ではありえない荷物を担ぎ、日常ではありえない距離を歩き攀じ登り、なぜに体重が減らないのか、どうかすると増えるのか」と嘆いたままでは情けないので、何か科学的根拠はないかと検索していると、あったんだな、コレが。
「Little Medical~ちょっとメディカ~あなたの毎日を充実させるために」というサイトの「登山後に大樹が増加するのは【むくみ】が原因?予防法や対処法は?」によると、登山時に生じる筋肉痛が体重増加の原因だという。
筋肉痛は、筋肉繊維が破壊され炎症を起こすことにより生じるそうだが、人間の身体は良くできており、破壊された繊維はすぐさま、より太く強い筋肉繊維をつくることで回復しようとするのだという。その時に、多くの糖分を溜め込もうとするため水分の代謝が一時的に悪くなり【むくみ】となり体重増加の原因となるのだそうだ。
『(記事より引用)この体重増加は一時的なもので、筋繊維が完全に修復されたら、水分の代謝ももとに戻り、体重も元通りになります。
登山経験が浅い人だと登山後に体重増加が起こりやすいです。
これは、登山に必要な筋肉の筋繊維が破壊されるためです。
登山経験の長い人は、登山による筋肉痛が起こりにくくなるため、登山後の体重増加もほとんど見られなくなります。』
https://currentjp.com/archives/12938.html
確かに、下山直後に増加した体重は、帰宅して2~3日もすれば元通りになり、その後しばらくは減少傾向が続いてくれる。
これを私は、登山により基礎代謝量がupしたおかげだと思っていたが、記事によると、どうやら勘違いのようだ。
山に魅せられて20年ちかくになるが、実際には年に一二度登ることができれば上等という状態なので、これからも下山直後の体重増加は続くと思うが、安全で楽しい登山を最大の目標にし、これからも山を歩きたいと思っている。
お山の話は、あと一つ つづく










































