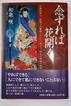[ポチッとお願いします]
 人気ブログランキング
人気ブログランキング年末年始の4日間の喧騒も通り過ぎてしまった。
あっという間のことだった。
昔の人はよく云ったもの・・・。
『孫は来て良し、帰って良し』。
遠方にいる孫たち、年数回会えるかどうか。
元気な声を聞き、元気に走り回る姿を見るとやはり家内共々気分も高揚する。
で、あるが、普段静かな2人の生活、家内も喧騒にはやや疲れるらしい。
ところで、NHK総合テレビ(21時00分から22時15分)の正月時代劇。
『家康、江戸を建てる』を堪能。
これは、かなり勉強になると共に徳川300年の礎を作った家康公の将来が見通せた頭脳、偉大なる人心掌握術を垣間見ることができた。
前編は、秀吉から未開の地・武蔵の国へ入封された家康(市村正親)が、この地を大坂に劣らぬ日本一江戸の町にすると決意し、まずは水を制するという話だった。
人が住めるようにするには、豊富な飲み水が必要であること。
湿地帯となっている地を人が住めるようにするには、河川(利根川)の流れを変える大工事が必要となっていた。
上水道を引く責任者には、家臣の大久保藤五郎(佐々木蔵之介)が抜擢された。
藤五郎は、戦場で家康を守って被弾し馬にも乗れない身となって、家康のための菓子職人となっていた。
一方、河川工事には、伊奈忠次(松重豊)が任命されていた。
それぞれの家臣の苦労話、このようなことがあったのかと、思わず知らないことばかりで・・・大いに感銘を受けることとなった。
遠大なる計画であり、関ヶ原、大坂の役を経た後、徳川政権となった大江戸の礎の見知らぬ物語。
いかに人と人の関わりが必要であるか垣間見られる。
徳川政権確立のバックヤード的な物語だった。
今夜の後編「金貨の町」も楽しみである。
[追 記]~前編あらすじ~
徳川家康(市村正親)は、低湿で水浸しの大地(今の東京)に、人が住めるようにするには、どうすれば良いか?と考えた。海水が流れ込んでくる関東の低地では井戸から水を得難く、人が生きるための清水の確保が急務であった。いわゆる上水の整備を命じられたのは、家臣・大久保藤五郎(佐々木蔵之介)。若き日、戦場で傷を負い、馬にもまたがれぬ身となり、家康のための菓子作りを長年してきた大久保は、現在の井の頭池から江戸の町に上水を通すという一世一代の大仕事に取り組む。が、右腕となるのは、武蔵野農民の人望厚いだけの名主・内田六次郎(生瀬勝久)と、変人テクノクラート・春日清兵衛(千葉雄大)。
二人の扱いに手を焼く藤五郎に比べ、利根川の流れを変えるという大工事に挑む伊奈忠次(松重豊)は着実に成果を上げていく。長引く工事に幕府の金庫番・大久保長安(高嶋政伸)が猛烈に圧力をかけてくる中、藤五郎は神田上水完成のため、伊奈の協力を求めるが・・・
(出典:NHK公式HP 抜粋)

(出典:NHK公式HP 抜粋)
(下記のバナーへのクリックをお願いします。ご協力、ありがとうございます)
 人気ブログランキング
人気ブログランキング