一身上の変化
終戦後、日本に引き揚げてきてから、晃はサラリーマンとしての人生を踏み始めた。堅実ではあるが、オランダにいたころのように自分でビジネスをしているわけではないので、大きな収入を得ることはできなかった。年もとって来たし、がむしゃらに働くつもりもなかった。
「子供たちも大きくなったことだし、私たちもこの辺で別々の人生を歩みましょうか。」
ある日、妻のロウラが言った。日本的な箱庭のような家に住み、満員電車に揺られて会社に通う夫をみて、つくづく嫌になったのだろう。二人の男の子もすでに成人し、自立していた。オランダ人である妻とは、インドネシアで知り合ってずいぶん若い時に結婚した。この辺で、お互いが自由に生きるのもよいのかもしれない。二人は、円満に離婚することにした。
奇妙なもので、離婚が決まると、新しい連れ合いを紹介してくる人がいる。巡り合わせなのかもしれない。協議離婚をして一年後には、白人の妻はアメリカ人と再婚してハワイに移住し、晃は日系二世のキクと再婚した。
ちょうど、東洋綿花のロッテルダム支店が順調に展開し、ロンドンやハンブルグにも支店を置けるようになっていた。この間に、晃がやったことは、油類検量の国際規格の統一だった。これは、英国ガロンと米国ガロンの定義の違いや精度のあいまいさ、また、異なった尺度やあいまいな測定方法などによって起こっていた深刻な貿易障害でもあった。たとえば、米国で仕入れた大豆油が、欧州に来ると容積が違って目減りしたりした。これは、測定の誤差や、標準とする気温の違いや、容器の膨張率の違いなどによるものだった。輸入する量が多くなると、そのような違いは無視できなくなる。国際的な信用問題までに発展していた。
戦前、日本の一尺は、オランダ法令に基づいて、標準温度接し15℃(華氏59℃)で、1メートルを三尺三寸と規定していた。戦後は、アメリカによる占領政策として、摂氏20℃に変更されていた。
1878年の英国法令によると、青銅で作られたインペリアル標準ヤードは、摂氏16℃(華氏62℃)の時に、正しい長さを示すとされていた。
1リットルは、北緯45度の海抜0m地点で、摂氏0℃では760mmHgに等しい気圧のもとで、摂氏4℃の温度で秤量した1kgの蒸留水と定義していた。
晃は、計算上の間違いは東洋人の誤りだとする西洋人の主張に反論し、ロンドンの国立図書館に通って文献をあたり、計量について綿密に調べて論文にまとめた。こうして計量の間違いや誤差は西洋の法規にあることを指摘して、従来の方式の改正を迫った。これに対して、西洋諸国の業者や管理官からはずいぶん煙たがれたが、最後には主張を認めたもらうことができた。努力は大切であり、いつかは報われることを実感した頃でもあった。
つづく











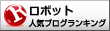

 Michio Kumagai @KumasanHakken
Michio Kumagai @KumasanHakken












