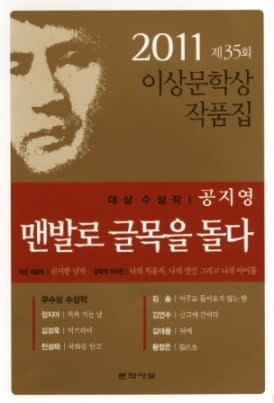暮れの12月22日に安宇植さんが亡くなりました。享年78歳、です。
私ヌルボは直接親交があったというわけではありませんが「金史良」(岩波新書)等の著作や、尹興吉・李文烈・申京淑等々の韓国人作家の翻訳が多数あって、ずっと以前から目になじんできた名前でした。
1990年代末、月刊誌「翻訳の世界」(バベルプレス)で<韓国語翻訳コンテスト>というのをやっていて、その出題者・選考委員が安宇植先生でした。ヌルボも数回応募しましたが、その出題文に提示された李文烈の「若き日の肖像」の冒頭部分などは強く印象に残っています。(「翻訳の世界」は2000年に残念ながら廃刊してしまいましたが・・・。)
昨年、韓国文化院主催:韓国文学読書感想文コンテストの審査委員長ということで、応募して入賞したら直接会って話できるかも、と思ったのですが、コンテストの開催を知ったのがすでに締め切り直前で、課題図書は読んだものの結局時間切れ。表彰式&講演会の日も所用で行かれませんでした。それで次回にはぜひ、と心に期していたのに・・・。
もしかして、一昨年の申京淑の大ベストセラーの名作「オンマをお願い」も安宇植さんの訳で近いうちに出るのかなとも期待していたのですが・・・。(「離れ部屋」のように<オムマ>ですか?)
昨日1月23日付「毎日新聞」の<悼む>欄に、川村湊さんによる追悼文が載っていました。
安宇植さんの訳業がしばしば目にふれるようになってきたのが80年代以降で、それ以前のことはヌルボは知らなかったのですが、1970年代以前は朝鮮大学校の教員だったんですね。主に北朝鮮文学の翻訳に携わり、黄健(ファンゴン)の「ケマ高原」が代表作とのことです。
川村湊さんによると、安宇植さんが80年代以降韓国文学の翻訳に仕事の中心を移したことを彼の「転向」と見る人もいるそうです。つまり<北>から<南>、<社会主義>から<資本主義>への。「安氏は釈明も弁明もしなかったが、在日の文学世界では、やや孤立的だったことは否定できない」と川村さんは記しています。
川村さんが、そのことと、「彼が、金史良文学の中に己を見」たことを重ね合わせて見ている点はなるほどと思いました。金史良の作品は<北>では「粛清」され、<南>でも長らく「北系作家」とされて、「彼の名を出すのさえ忌避されていた」のだそうです。
今も<北>と<南>の間には政治的な壁だけではなく、文学の面でも過去&現代の作家や文学作品の評価や作品の公開等をめぐって高い壁があります。
そうした対立・矛盾が続いているこの時代の中で、日本にいたからこそ成し得た彼の業績はとても大きなものがあったのではないでしょうか。
※川村さんは<北>の文学状況について次のように記しています。
70年代以降、北では父子独裁体制の文芸政策が功を奏し、まともな文学は消滅した。安氏が、それを痛切な思いで見ていたことは疑えない。人間の営みの上に文学があり、それを大切に思えば思うほど、人々の生活の困難と文学の衰退とは、無念でないはずはない。
・・・川村さんも安さんも、文学に携わる人として至極真っ当で、共感を覚えます。
私ヌルボは直接親交があったというわけではありませんが「金史良」(岩波新書)等の著作や、尹興吉・李文烈・申京淑等々の韓国人作家の翻訳が多数あって、ずっと以前から目になじんできた名前でした。
1990年代末、月刊誌「翻訳の世界」(バベルプレス)で<韓国語翻訳コンテスト>というのをやっていて、その出題者・選考委員が安宇植先生でした。ヌルボも数回応募しましたが、その出題文に提示された李文烈の「若き日の肖像」の冒頭部分などは強く印象に残っています。(「翻訳の世界」は2000年に残念ながら廃刊してしまいましたが・・・。)
昨年、韓国文化院主催:韓国文学読書感想文コンテストの審査委員長ということで、応募して入賞したら直接会って話できるかも、と思ったのですが、コンテストの開催を知ったのがすでに締め切り直前で、課題図書は読んだものの結局時間切れ。表彰式&講演会の日も所用で行かれませんでした。それで次回にはぜひ、と心に期していたのに・・・。
もしかして、一昨年の申京淑の大ベストセラーの名作「オンマをお願い」も安宇植さんの訳で近いうちに出るのかなとも期待していたのですが・・・。(「離れ部屋」のように<オムマ>ですか?)
昨日1月23日付「毎日新聞」の<悼む>欄に、川村湊さんによる追悼文が載っていました。
安宇植さんの訳業がしばしば目にふれるようになってきたのが80年代以降で、それ以前のことはヌルボは知らなかったのですが、1970年代以前は朝鮮大学校の教員だったんですね。主に北朝鮮文学の翻訳に携わり、黄健(ファンゴン)の「ケマ高原」が代表作とのことです。
川村湊さんによると、安宇植さんが80年代以降韓国文学の翻訳に仕事の中心を移したことを彼の「転向」と見る人もいるそうです。つまり<北>から<南>、<社会主義>から<資本主義>への。「安氏は釈明も弁明もしなかったが、在日の文学世界では、やや孤立的だったことは否定できない」と川村さんは記しています。
川村さんが、そのことと、「彼が、金史良文学の中に己を見」たことを重ね合わせて見ている点はなるほどと思いました。金史良の作品は<北>では「粛清」され、<南>でも長らく「北系作家」とされて、「彼の名を出すのさえ忌避されていた」のだそうです。
今も<北>と<南>の間には政治的な壁だけではなく、文学の面でも過去&現代の作家や文学作品の評価や作品の公開等をめぐって高い壁があります。
そうした対立・矛盾が続いているこの時代の中で、日本にいたからこそ成し得た彼の業績はとても大きなものがあったのではないでしょうか。
※川村さんは<北>の文学状況について次のように記しています。
70年代以降、北では父子独裁体制の文芸政策が功を奏し、まともな文学は消滅した。安氏が、それを痛切な思いで見ていたことは疑えない。人間の営みの上に文学があり、それを大切に思えば思うほど、人々の生活の困難と文学の衰退とは、無念でないはずはない。
・・・川村さんも安さんも、文学に携わる人として至極真っ当で、共感を覚えます。