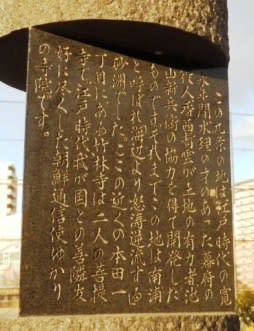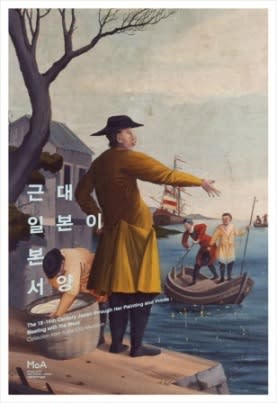<「週刊文春 新年号」を読む(上) サムスン ヒュンダイは没落(?)>の続きです。
韓国・北朝鮮ネタその② 「今週の必読」はファンキー末吉「平壌6月9日高等中学校・軽音楽部」

書評ページの最初がこの本。著者ファンキー末吉は1980~90年代に爆風スランプにドラマーとして活躍・・・って、そうだったのか。彼の名は知りませんでしたが、爆風スランプは憶えてますがな。
で、この本は、2006年7月以来12年2月まで5度にわたって訪朝して、平壌の高等中学校の女生徒たちにロックを教えてきた記録です。昨年11月26日集英社インターナショナルから発売されましたが、出版社の公式サイトを見ると担当編集者の鬼の編集「佐藤」さんが「編集者として担当した本は、どれも愛着があるのですが、正直、今回のこの作品には魂をゆさぶられました」と記しています。
※アマゾンの読者レビューも、数は少ないですが好評で、私ヌルボもこれは読んでみようと強く思った次第です。
あ、書名中の「6月9日」は「平壌6月9日」ではなく学校の名称が「6月9日高等中学校」ということ。金日成が「6月9日に建てろ」と指導したからとか。なぜ6月9日かはちょっと探してみたもののわからず。ファンキー末吉さん(と、ここから「さん」付け)は「6と9ならロックではないか」と燃えたそうです。
関連で、ファンキー末吉さんのブログ<ファンキー末吉BLOG ~ファンキー末吉とその仲間たちのひとりごと~>のことを知ってちょっと見てみたら、これが北朝鮮関係だけでも興味深いネタの宝庫!
2012年2月21日の「5回目の訪朝」と題した記事(→コチラ)だけとってみても「前回の訪朝の後にすぐ金正日が死去したので、奇しくもワシは体制が変わる最後の北朝鮮を見た日本人であり、そして今回の訪朝で恐らく新体制を見た最初の日本人となるであろう」とか、アジアブーム以前から中国に入れ込んでいた自身の過去のこととか、「北朝鮮はご存知の通り貧しい国である。しかし前回の渡航でワシは「平壌は中国マネーのバブルが始まっている」と書いた」以下の今の北朝鮮事情等々が詳しく記されています。
これは今後時間をかけて読む必要あり、です。
ところで、「週刊文春」でこの本を評している中森明夫は「それにしても本書の収録写真の少女らの、なんと美しいことだろう!」と「!」を付けた上「こんな美少女はもう日本にはいない」とまで書いちゃってます。その彼女たちの写真も上記ブログ内を探せば見つかります。
韓国・北朝鮮ネタその③ 「東京「鍋」最前線」で新大久保の<コリア タッカンマリ>を紹介
この巻末カラーページで紹介している5店中の1つが新大久保駅のすぐそばにある<コリア タッカンマリ>。
料理名のタッカンマリは「タク」=鶏、「ハンマリ」は1羽の意味。これが韓国でブームになったのはわりと最近のことなのに、もうとっくにポピュラーなメニューになってる感があります。この店は行ったことありませんが、そのうちに・・・。店の公式サイトは→コチラ。
韓国・北朝鮮ネタその④ 「池上彰のそこからですか!?」は朴槿恵の経歴をてぎわよく紹介
わずか2ページで韓国初の女性大統領となる朴槿恵の今に至る経歴を、彼女の自伝「絶望は私を鍛え、希望は私を動かす」を参考に要領よくまとめています。
彼女の名前の中の「槿(ムクゲ)」が韓国の国花であること、西江(ソガン)大学校電子工学科を首席で卒業後フランスのグルノーブル大に留学したこと、1979年アメリカのカーター大統領が訪韓した際、米軍の韓国駐留の必要性を力説してカーター大統領に撤退計画を撤回させたこと等々が記されています。興味深いエピソードをピックアップしてよみやすく書いているところはさすがです。
※[ヌルボ註:西江大学校は日本の上智大学に比定されるミッション系大学です。
私ヌルボが書く予定でいた朴槿恵の記事は、こんな政治とはぜ~んぜん関係ない方面のネタなんですけどね。朴槿恵のビキニ姿の写真とか・・・って、「見たくない」ですか。そーですか・・・。
韓国・北朝鮮ネタその② 「今週の必読」はファンキー末吉「平壌6月9日高等中学校・軽音楽部」

書評ページの最初がこの本。著者ファンキー末吉は1980~90年代に爆風スランプにドラマーとして活躍・・・って、そうだったのか。彼の名は知りませんでしたが、爆風スランプは憶えてますがな。
で、この本は、2006年7月以来12年2月まで5度にわたって訪朝して、平壌の高等中学校の女生徒たちにロックを教えてきた記録です。昨年11月26日集英社インターナショナルから発売されましたが、出版社の公式サイトを見ると担当編集者の鬼の編集「佐藤」さんが「編集者として担当した本は、どれも愛着があるのですが、正直、今回のこの作品には魂をゆさぶられました」と記しています。
※アマゾンの読者レビューも、数は少ないですが好評で、私ヌルボもこれは読んでみようと強く思った次第です。
あ、書名中の「6月9日」は「平壌6月9日」ではなく学校の名称が「6月9日高等中学校」ということ。金日成が「6月9日に建てろ」と指導したからとか。なぜ6月9日かはちょっと探してみたもののわからず。ファンキー末吉さん(と、ここから「さん」付け)は「6と9ならロックではないか」と燃えたそうです。
関連で、ファンキー末吉さんのブログ<ファンキー末吉BLOG ~ファンキー末吉とその仲間たちのひとりごと~>のことを知ってちょっと見てみたら、これが北朝鮮関係だけでも興味深いネタの宝庫!
2012年2月21日の「5回目の訪朝」と題した記事(→コチラ)だけとってみても「前回の訪朝の後にすぐ金正日が死去したので、奇しくもワシは体制が変わる最後の北朝鮮を見た日本人であり、そして今回の訪朝で恐らく新体制を見た最初の日本人となるであろう」とか、アジアブーム以前から中国に入れ込んでいた自身の過去のこととか、「北朝鮮はご存知の通り貧しい国である。しかし前回の渡航でワシは「平壌は中国マネーのバブルが始まっている」と書いた」以下の今の北朝鮮事情等々が詳しく記されています。
これは今後時間をかけて読む必要あり、です。
ところで、「週刊文春」でこの本を評している中森明夫は「それにしても本書の収録写真の少女らの、なんと美しいことだろう!」と「!」を付けた上「こんな美少女はもう日本にはいない」とまで書いちゃってます。その彼女たちの写真も上記ブログ内を探せば見つかります。
韓国・北朝鮮ネタその③ 「東京「鍋」最前線」で新大久保の<コリア タッカンマリ>を紹介
この巻末カラーページで紹介している5店中の1つが新大久保駅のすぐそばにある<コリア タッカンマリ>。
料理名のタッカンマリは「タク」=鶏、「ハンマリ」は1羽の意味。これが韓国でブームになったのはわりと最近のことなのに、もうとっくにポピュラーなメニューになってる感があります。この店は行ったことありませんが、そのうちに・・・。店の公式サイトは→コチラ。
韓国・北朝鮮ネタその④ 「池上彰のそこからですか!?」は朴槿恵の経歴をてぎわよく紹介
わずか2ページで韓国初の女性大統領となる朴槿恵の今に至る経歴を、彼女の自伝「絶望は私を鍛え、希望は私を動かす」を参考に要領よくまとめています。
彼女の名前の中の「槿(ムクゲ)」が韓国の国花であること、西江(ソガン)大学校電子工学科を首席で卒業後フランスのグルノーブル大に留学したこと、1979年アメリカのカーター大統領が訪韓した際、米軍の韓国駐留の必要性を力説してカーター大統領に撤退計画を撤回させたこと等々が記されています。興味深いエピソードをピックアップしてよみやすく書いているところはさすがです。
※[ヌルボ註:西江大学校は日本の上智大学に比定されるミッション系大学です。
私ヌルボが書く予定でいた朴槿恵の記事は、こんな政治とはぜ~んぜん関係ない方面のネタなんですけどね。朴槿恵のビキニ姿の写真とか・・・って、「見たくない」ですか。そーですか・・・。