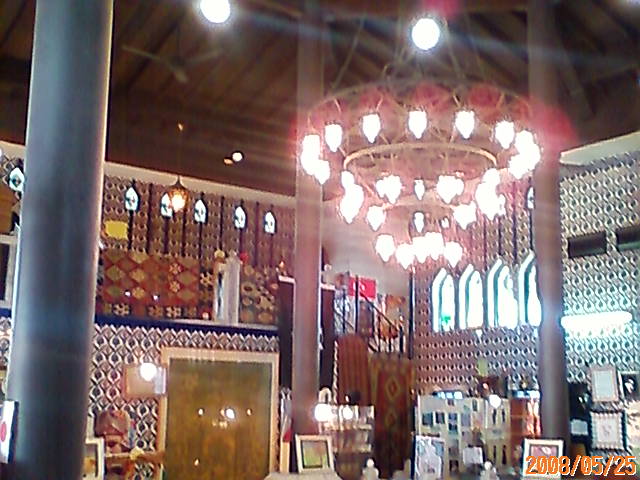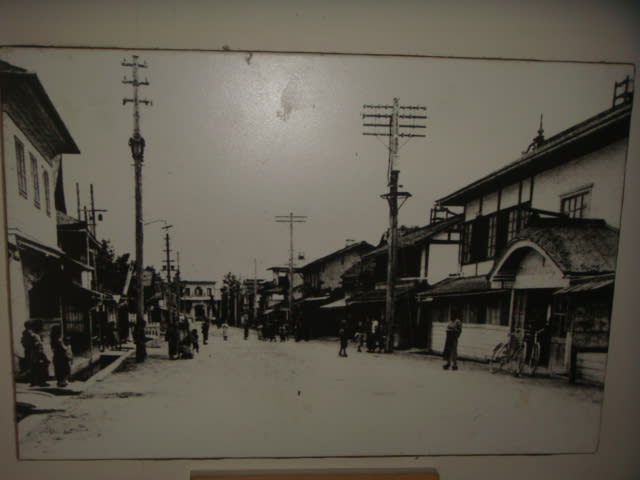アカシアの花が満開の季節。
一昨日山寺に行った時、自転車道沿いのアカシア並木の花が満開だった。
家の裏の線路沿いの土手、寒河江川の川原、などこの辺では至る所に自生している。
4~5年前、アカシアの花を天ぷらにして食べると美味しいと聞いて、早速新鮮な花を摘んできて食べてみた。
天ぷらにしても、思ったより花の形がそのまま残りきれいに揚った。
サクサクとこぼれるような食感、季節にふさわしい甘い香りのする自然が、そのまま口から味わえるようで結構美味しかった。

延々と続くアカシア並木
本来のアカシアはエンジュの樹と言われ、床柱などに使われている高級木材だ。
写真のアカシアはニセアカシアが本当の名前だ。
少し寄り道なってしまうが、エンジュの樹に、あまりよくない思い出がある。
10年以上も前の事、ある方から増築の設計依頼があった。
かなりの旧家の屋敷で、息子さんが戻って来て同居するため、増築したいとの事だった。
一部坪庭を壊し、既存離れの蔵座敷にリビング、水まわりの増築だった。
仕方なく坪庭に生えていたエンジュの樹を伐採する事になった。
このエンジュの樹は自分が生まれる以前からあった樹で、是非増築する玄関ポーチの柱に使用したいというご主人の意向で、丁寧にお払いをし伐採、そして柱に。
エンジュの樹は黒基調の木肌に白の木目が鮮やかな堅木だ。
建物が完成し、ポーチの柱に立派に再生したエンジュの樹に、ご主人様はたいそう喜んでくれた。
しかし、私には何故かしっくりとなじめない違和感があった。
それから1年もしないうちにご主人が病気で亡くなられた。
もともと病床にあって、増築工事以前から週に2度人工透析を受けていたのだが、なんとなく私は完成のとき感じた違和感を思い出してしまった。
あのエンジュの樹さえ切らなければもっと長生きできたのかも知れない・・・と。
建築に関わるさまざまな風習。
例えば「三隣亡」。
十二干支のうち、午(うま)、寅(とら)、猪(いのしし)この三つの日や年が三隣亡で昨年は猪、所謂年間の三隣亡である。
三隣亡は誰もよく気にするが、表に出てくるのは3つのうちのどれかひとつで、その他の干支は出てこない。しかし、年間を通して午、寅、猪にあたる日は隠れ三隣亡としてある。
だいぶ寄り道してしまったが、私はあまり家相とかは信じないほうである。
しかしこのニセアカシアの花が咲く時期このエンジュの樹にまつわる思い出を決まって思い出す。
三隣亡、大将軍、・・・etc 神の戒めとして、「のべつ幕なし」に普請をしてはいけないとした人間の知恵のひとつなのかもしれない。
普請は心と体と(お金・・?)の健康体の時に限る教訓かも・・・。
やっぱり何事もひと休止して、じっくり事を運ぶ事の大切さを教えているのだろう。
花にまつわる話は限りがないほど多い。
こんなきれいな「アカシアの花」にまつわる私の思い出話でした・・・・・。