メタエンジニアの眼シリーズ(131) 「啓蒙と迷妄」
書籍名;『科学思想史』 [2010]
編者;金森 修 発行所;勁草書房
発行日;2010.7.30
引用先;文化の文明化のプロセス Converging、
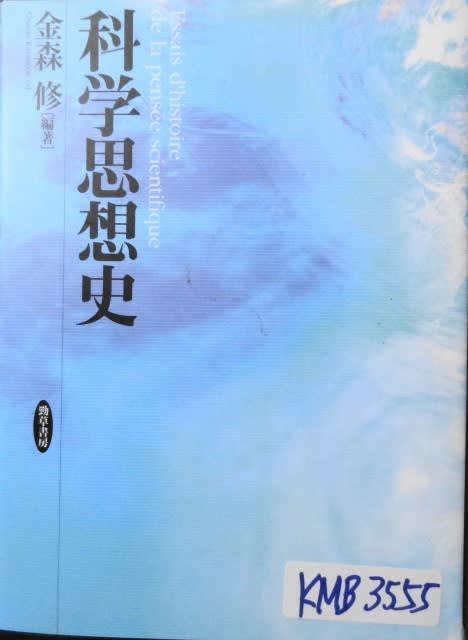
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
この書は、8人の著者によって書かれているが、いずれも編者とおなじ東京大学大学院人文科学研究科の博士課程を修了して、各地の大学に勤めている。それだけでも閉鎖的な印象を受けるのだが、概読して感じたことは、日本で人文科学が理系に比べて地盤沈下したことだった。人文科学は、どのテーマにしても、先ずは人類社会全体のことからスタートするべきと思うのだが、全て微に入り、細に亘るところから出発をしている。全体とし現代社会に与える価値が明確ではなかった。その中で、一つだけ注目したいテーマが取り上げられていた。そこについて述べる。
第4章「啓蒙と迷妄」―「百科全書」の科学項目に見る誤謬理論の歴史、井田 尚
百科全書との日本語が気に入らないのだが、百科事典よりはまともに思える。18世紀に纏められたエンサイクロペディアの話だ。以前、これについて書いた。、西周(にし あまね)の「百学連環」だ。なぜ、この言葉が使われなくなってしまったのか、そこには日本のガラパコス性を感じざるを得ない。西は、英国のEncyclopediaを熟読し、そこから色々な知識を得たようだが、その語源をギリシャ語に求めて、「童子を輪の中に入れて教育なすとの意なり」としている。
『百科事典を意味する英語 encyclopediaは、ギリシャ語のコイネーの"ἐγκυκλοπαιδεία"から派生した言葉で、「輪になって」の意味であるἐγκύκλιος(enkyklios:en + kyklios、英語で言えば「in circle」)と、「教育」や「子供の育成」を意味するπαιδεία(paideia パイデイア)を組み合わせた言葉であり、ギリシャ人達が街で話し手の周りに集まり聴衆となって伝え聞いた教育知識などから一般的な知識の意味で使われていた』
「辞典」よりは、「全書」がまだましだと思って、読み進めた。
「はじめに」では、次のように著者の思いを述べている。
『科学の歴史の中には、発見の成功例という歴史の勝者が織り成すメイインストーリーからこぼれ落ちる無数の失敗から、科学的進歩の障碍となった無知・迷信までもが含まれるため、それらの雑多な試行錯誤が混在する歴史こそが、あり得べき科学の〈全体史〉の姿であるはずだからだ。
誤謬や迷信といった「不純」な要素を排除し、歴史の勝者たる「大発見」の系譜を整合的に語る〈科学史〉にはもうひとつの欠落がある。〈科学史〉を執筆する科学者自身は、自らの学間上の立場を正当化しようとする操作によって、特定の学派や学説に有利な記述に陥るリスクが高いことである。むろん、あらゆる歴史というものは、それを語る者の立場を離れた無色透明の客観的な叙述ではなく、逆に歴史家本人の思想的な立場や歴史観を多かれ少なかれ正当化する党派的な側面を持つ。その意味では、科学史もまた歴史の一分野に他ならない以上、いかなる党派性も持たない科学史などあり得ないのかもしれない。』(pp.188)
このことは、自然科学とは異なる人文科学特有の見かたのように思う。さらに続けて、
『十八世紀のフランスで作家・思想家ディドロと数学者ダランベールによって編纂された「百科全書」(一七五一ー一七七二、本文十七巻、図版十一巻、補遺五巻)は、学芸の諸分野において、世人の目に触れることが少ない専門家の著作や学術団体の浩潮な年報等の形で散在する膨大な人間知識を系統的に分類・整理し、実用に堪えるコンパクトなサイズにまとめた画期的な百科事典として構想された。興味深いことに、編纂者の一人であるダランベールの著書「哲学の基礎」によると、「百科全書」で実現が企図された「学問と技芸の全体的・ 合理的歴史」の主要な記述対象となるのは、「知識」、「臆見」、「論争」、「誤謬」という四つの観念ないし言説のカテゴリーであった 。』(pp.188)
そこで、著者は現代の正統的(例えば、教科書に使われるような)な科学史を正面から批判している。
『「百科全書」の科学項目で記述される知識や誤謬の歴史は、現代の正当的な〈科学史〉にはない。人間知識の表情豊かな多様性と、時と場所が違えば変わる「真理」の相対性を垣間見させてくれる点で、実に味わい深い示唆に満ちている。以下では、そうした「百科全書」の科学項目に見られる典型的な誤謬理論の数々を取り上げるとともに、それらの誤を当時の論争のコンテクストに置き直して捉えなおすことで、「百科全書」の科学項目の歴史的叙述の特色を浮き彫りにしてみたい。』(pp.189)
つまり、「百科全書」の価値を、その広範囲な項目についての正統な叙述だけではなく、一つの項目に対する広範囲な意見を集め、さらに当時の社会状況と照らしながら記述しているところに見い出している。つまり、科学史をメタエンジニアリング的に捉えようとしているように思える。
先ずは、「百科全書」の「序文」に書かれた文章に注目をしている。
『「百科全書」の序論を改めて読んでみると、ダランべールやディドロが、「百科全書」における合理的歴史と現実の違いに意識的であったことが分かる。哲学史家ミシュル・マレルブによれば、人間知識の歴史を記述する「百科全書」には、広義の歴史としての「過去の事実の収集・記録」と、狭義の歴史としての「時間の中における出来事の理解」という、二つの意味がある。マレルブによれば、「百科全書」には、過去に獲得された知識を保存する「記憶」の役割に加え、現時点で知られている限りの人間の知識を、合理的に整理して同時代や未来に伝え、読者を啓蒙する「理性」の役割があり、「百科全書」における人間知識の合理的分類は、この二重の要請から生まれたという。』(pp.200)
確かに、この書が纏められた中世から近世への過渡期には、色々な解釈が林立して、このような表現が必要だったと思う。現代では、すこし不思議な気もするが、もう少し立つとフェイクニュースの真偽判断ができなくなり、再びそのような時代になるのかもしれない。
そこから、本論の「誤謬」についての具体的な紹介が始まっている。最初は、「酵母」という項目についてだった。ここだけで8頁を費やしている。要は、「言語の拡大適用による誤謬」というわけである。当時は、酵母の働きが、人間の生殖作用にまで及ぶとしていた。そして、その問題を列挙した後での結論は、こうなっている。
『以上のように、項目「酵母」では、酵母概念の日常生活における転用はもの喩えとして許容しながらも、人間の生体を扱う医学の理論や技術が問題となる場合に、化学という他の学問領域の用語である酵母概念を拡大適用することを、有害な濫用として批判しているということが分かる。』(pp.202)
そして当時の結論が中途半端になってしまった原因を、「不正確な拡大適用を招く述語の不足」としている。
『 では、なぜ項目「発酵」の執筆者ドーモンは、発酵の誤謬理論たる所以を理解し、人体の生理的機能の説明の大半から発酵の概念を排除しながら、消化の機能の一部に限定する形で発酵の概念の温存を図ったのだろうか。その第一の理由として考えられるのは、消化酵素を含む唾液、胃液、膵液などの消化液の作用による消化の原理の科学的な解明が完全には果たされていなかったという当時の科学的知識の限界であろ。消化液の組成と消化の原理が科学的に解明されていないために、消化のおおよそのメカニズムは理解しながらも、誤謬理論の名残を留める発酵という用語を、相変わらず説明概念として用いるしかなかったのだろう。
』(pp.207)
同じような解説が「炎症」についても述べられているが、詳細は割愛して、結論のみを紹介する。
『項目「炎症」の執筆者は、炎症の理論の歴史的変遷を紹介している。それによると、古代人は、炎症が血液の停滞や充血に起因すると考えた。この古代人の説は、医学がガレノスとヒポクラテスの影響下に置かれた十八世紀間にわたって、装いを新たにしながら受け継がれたという。
十六世紀の初めに栄え始めた化学は、医学を一変させ、塩や硫黄などの化学用語を用いる学派が続出した。医化学派のことである。医化学派の台頭とともに、人体は蒸留器に変えられ、血液は塩や硫黄などの化学物質の貯蔵庫と化した。身体のあらゆる部位には分泌を担う酵母があり、実験室で観察される沸騰や発酵などの化学現象が人間の体内でも起きていると考えられた。パラケルススなどの医化学派は、あらゆる病気を血液の構成要素同士の自然に反した結合に帰した。』(pp.210)
そして、著者の結論は以下のように示されている。
『以上のように、項目「炎症」の執筆者は、炎症の原因をめぐる、古代人、医科学派、発酵論者、医物理学派、アニミストらの代表的な学説を紹介し、中でもシュタールによるアニミスムを最も有力な同時代の学説として紹介した上で、炎症を引き起こす原因は、「刺激感応性」と呼ばれる、霊魂とは無関係な物質的な原理だと思われる、と反論している。』(pp.214)
「種痘」についても、詳しく述べられている。森鴎外が在欧中に、種痘賛成論と反対論の双方の研究所に所属して、判断を下したことは有名だが、当時のヨーロッパでは、全人口問題に波及する大問題だった。従って、結論は容易に出なかった。ここでの「百科全書」の多岐にわたる内容は注目に値する。
『こうした背景から、種痘をめぐる論争が、単に医学界の内部での理論モデルの優劣をめぐる学派間の対立に留まらず、公衆衛生や健康政策の領域にまで社会的影響を及ぼした事情は、「百科全書」の項目「種痘」 に「外科/医学/道徳/政治」という分類記号が付されていることからも、容易く想像できる。「百科全書」の項目「種痘」の執筆者は、奇しくも「百科全書」第七巻の項目「ジュネーヴ」でダランベールが、 フランスに先んじて種痘を受け入れた国として称えている、ジュネーヴ共和国出身の医学者テオドール・トロンシヤンである。項目「種痘」を読むと、種痘の導入の是非をめぐる当時の論争の最大の争点が、自然感染する伝染病の天然痘と、牛痘を植え付け、いわば人為的に天然痘を人体に引き起こす種痘の、いずれが生命にとってより危険なのかという、それなりにもっともな疑問であったことが分かる。』(pp.230)
「外科、医学、道徳、政治」を一気に同じテーブルに取り上げたのは、まさに「百学連環」になっている。
「終わりに」には、次のようにある。
『数々の「大発見」を道標とする科学理論の「進歩」の歴史過程を強調した「科学史」の整然とした歴史叙述への違和感から出発した我々は、十八世紀のフランスで細纂された「百科全書」の科学項目における歴史叙述のあり方に着目した。そこでは、各項目の冒頭に分類項目こそ示されるものの、ある学間や技術に関するレベルの異なる 様々な事実、理論、概念に関するありとあらゆる言説が、基本的には、アルファベット順という無差別的かつ恣意的な配列法のみを秩序として隣り合っている。
「この「百科全書」という広大にして畿蒼たる真贋の言説の森においては、人類が過去に獲得した貴重な真理たる「知識」ばかりでなく、人類の無知蒙味の根源として古来悪評の高い「誤謬」や「迷信」もまた、自然を対象とした人間精神の試行錯誤の成果に相ふさわしい場所を得ている。』(pp.249)
最後に、話は「文学」にまで及んでいる。
『殊に科学における「誤謬」が、広義のフィクションに対する「信」に基づく想像的な疑似理論という点において、一見無縁な文学とも境界を接している事実は、人間の知的な営みに想像力の働きが不可欠であることを暗示しているようで、味わい深い。科学における概念のメタファー的な拡大適用に起因する誤謬に論を起こし、メタファーによるイメージを生命とする文学における科学の表象をもって、科学の誤謬をめぐるこのささやかな施策の円環を閉じることにしたい。』(pp.250)
最後に「円環」の言葉が出てきただけでも、この文章の価値を認めざるを得ない。それにしても、当時の「百科全書」が、真に百学連環であったことが良くわかった。一方で、この形が引き継がれずに、現代の「百科事典」になってしまったことが、科学と技術のどうしようもない細分化と無関係とは思えない。最近のデジタル検索では、もっと細分化が進むことになるのだろう。
書籍名;『科学思想史』 [2010]
編者;金森 修 発行所;勁草書房
発行日;2010.7.30
引用先;文化の文明化のプロセス Converging、
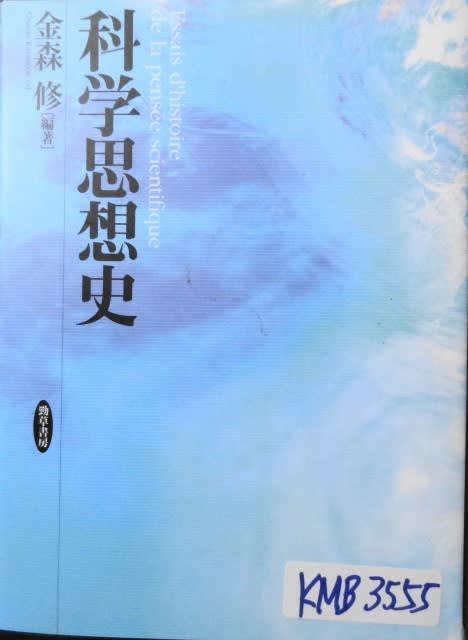
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
この書は、8人の著者によって書かれているが、いずれも編者とおなじ東京大学大学院人文科学研究科の博士課程を修了して、各地の大学に勤めている。それだけでも閉鎖的な印象を受けるのだが、概読して感じたことは、日本で人文科学が理系に比べて地盤沈下したことだった。人文科学は、どのテーマにしても、先ずは人類社会全体のことからスタートするべきと思うのだが、全て微に入り、細に亘るところから出発をしている。全体とし現代社会に与える価値が明確ではなかった。その中で、一つだけ注目したいテーマが取り上げられていた。そこについて述べる。
第4章「啓蒙と迷妄」―「百科全書」の科学項目に見る誤謬理論の歴史、井田 尚
百科全書との日本語が気に入らないのだが、百科事典よりはまともに思える。18世紀に纏められたエンサイクロペディアの話だ。以前、これについて書いた。、西周(にし あまね)の「百学連環」だ。なぜ、この言葉が使われなくなってしまったのか、そこには日本のガラパコス性を感じざるを得ない。西は、英国のEncyclopediaを熟読し、そこから色々な知識を得たようだが、その語源をギリシャ語に求めて、「童子を輪の中に入れて教育なすとの意なり」としている。
『百科事典を意味する英語 encyclopediaは、ギリシャ語のコイネーの"ἐγκυκλοπαιδεία"から派生した言葉で、「輪になって」の意味であるἐγκύκλιος(enkyklios:en + kyklios、英語で言えば「in circle」)と、「教育」や「子供の育成」を意味するπαιδεία(paideia パイデイア)を組み合わせた言葉であり、ギリシャ人達が街で話し手の周りに集まり聴衆となって伝え聞いた教育知識などから一般的な知識の意味で使われていた』
「辞典」よりは、「全書」がまだましだと思って、読み進めた。
「はじめに」では、次のように著者の思いを述べている。
『科学の歴史の中には、発見の成功例という歴史の勝者が織り成すメイインストーリーからこぼれ落ちる無数の失敗から、科学的進歩の障碍となった無知・迷信までもが含まれるため、それらの雑多な試行錯誤が混在する歴史こそが、あり得べき科学の〈全体史〉の姿であるはずだからだ。
誤謬や迷信といった「不純」な要素を排除し、歴史の勝者たる「大発見」の系譜を整合的に語る〈科学史〉にはもうひとつの欠落がある。〈科学史〉を執筆する科学者自身は、自らの学間上の立場を正当化しようとする操作によって、特定の学派や学説に有利な記述に陥るリスクが高いことである。むろん、あらゆる歴史というものは、それを語る者の立場を離れた無色透明の客観的な叙述ではなく、逆に歴史家本人の思想的な立場や歴史観を多かれ少なかれ正当化する党派的な側面を持つ。その意味では、科学史もまた歴史の一分野に他ならない以上、いかなる党派性も持たない科学史などあり得ないのかもしれない。』(pp.188)
このことは、自然科学とは異なる人文科学特有の見かたのように思う。さらに続けて、
『十八世紀のフランスで作家・思想家ディドロと数学者ダランベールによって編纂された「百科全書」(一七五一ー一七七二、本文十七巻、図版十一巻、補遺五巻)は、学芸の諸分野において、世人の目に触れることが少ない専門家の著作や学術団体の浩潮な年報等の形で散在する膨大な人間知識を系統的に分類・整理し、実用に堪えるコンパクトなサイズにまとめた画期的な百科事典として構想された。興味深いことに、編纂者の一人であるダランベールの著書「哲学の基礎」によると、「百科全書」で実現が企図された「学問と技芸の全体的・ 合理的歴史」の主要な記述対象となるのは、「知識」、「臆見」、「論争」、「誤謬」という四つの観念ないし言説のカテゴリーであった 。』(pp.188)
そこで、著者は現代の正統的(例えば、教科書に使われるような)な科学史を正面から批判している。
『「百科全書」の科学項目で記述される知識や誤謬の歴史は、現代の正当的な〈科学史〉にはない。人間知識の表情豊かな多様性と、時と場所が違えば変わる「真理」の相対性を垣間見させてくれる点で、実に味わい深い示唆に満ちている。以下では、そうした「百科全書」の科学項目に見られる典型的な誤謬理論の数々を取り上げるとともに、それらの誤を当時の論争のコンテクストに置き直して捉えなおすことで、「百科全書」の科学項目の歴史的叙述の特色を浮き彫りにしてみたい。』(pp.189)
つまり、「百科全書」の価値を、その広範囲な項目についての正統な叙述だけではなく、一つの項目に対する広範囲な意見を集め、さらに当時の社会状況と照らしながら記述しているところに見い出している。つまり、科学史をメタエンジニアリング的に捉えようとしているように思える。
先ずは、「百科全書」の「序文」に書かれた文章に注目をしている。
『「百科全書」の序論を改めて読んでみると、ダランべールやディドロが、「百科全書」における合理的歴史と現実の違いに意識的であったことが分かる。哲学史家ミシュル・マレルブによれば、人間知識の歴史を記述する「百科全書」には、広義の歴史としての「過去の事実の収集・記録」と、狭義の歴史としての「時間の中における出来事の理解」という、二つの意味がある。マレルブによれば、「百科全書」には、過去に獲得された知識を保存する「記憶」の役割に加え、現時点で知られている限りの人間の知識を、合理的に整理して同時代や未来に伝え、読者を啓蒙する「理性」の役割があり、「百科全書」における人間知識の合理的分類は、この二重の要請から生まれたという。』(pp.200)
確かに、この書が纏められた中世から近世への過渡期には、色々な解釈が林立して、このような表現が必要だったと思う。現代では、すこし不思議な気もするが、もう少し立つとフェイクニュースの真偽判断ができなくなり、再びそのような時代になるのかもしれない。
そこから、本論の「誤謬」についての具体的な紹介が始まっている。最初は、「酵母」という項目についてだった。ここだけで8頁を費やしている。要は、「言語の拡大適用による誤謬」というわけである。当時は、酵母の働きが、人間の生殖作用にまで及ぶとしていた。そして、その問題を列挙した後での結論は、こうなっている。
『以上のように、項目「酵母」では、酵母概念の日常生活における転用はもの喩えとして許容しながらも、人間の生体を扱う医学の理論や技術が問題となる場合に、化学という他の学問領域の用語である酵母概念を拡大適用することを、有害な濫用として批判しているということが分かる。』(pp.202)
そして当時の結論が中途半端になってしまった原因を、「不正確な拡大適用を招く述語の不足」としている。
『 では、なぜ項目「発酵」の執筆者ドーモンは、発酵の誤謬理論たる所以を理解し、人体の生理的機能の説明の大半から発酵の概念を排除しながら、消化の機能の一部に限定する形で発酵の概念の温存を図ったのだろうか。その第一の理由として考えられるのは、消化酵素を含む唾液、胃液、膵液などの消化液の作用による消化の原理の科学的な解明が完全には果たされていなかったという当時の科学的知識の限界であろ。消化液の組成と消化の原理が科学的に解明されていないために、消化のおおよそのメカニズムは理解しながらも、誤謬理論の名残を留める発酵という用語を、相変わらず説明概念として用いるしかなかったのだろう。
』(pp.207)
同じような解説が「炎症」についても述べられているが、詳細は割愛して、結論のみを紹介する。
『項目「炎症」の執筆者は、炎症の理論の歴史的変遷を紹介している。それによると、古代人は、炎症が血液の停滞や充血に起因すると考えた。この古代人の説は、医学がガレノスとヒポクラテスの影響下に置かれた十八世紀間にわたって、装いを新たにしながら受け継がれたという。
十六世紀の初めに栄え始めた化学は、医学を一変させ、塩や硫黄などの化学用語を用いる学派が続出した。医化学派のことである。医化学派の台頭とともに、人体は蒸留器に変えられ、血液は塩や硫黄などの化学物質の貯蔵庫と化した。身体のあらゆる部位には分泌を担う酵母があり、実験室で観察される沸騰や発酵などの化学現象が人間の体内でも起きていると考えられた。パラケルススなどの医化学派は、あらゆる病気を血液の構成要素同士の自然に反した結合に帰した。』(pp.210)
そして、著者の結論は以下のように示されている。
『以上のように、項目「炎症」の執筆者は、炎症の原因をめぐる、古代人、医科学派、発酵論者、医物理学派、アニミストらの代表的な学説を紹介し、中でもシュタールによるアニミスムを最も有力な同時代の学説として紹介した上で、炎症を引き起こす原因は、「刺激感応性」と呼ばれる、霊魂とは無関係な物質的な原理だと思われる、と反論している。』(pp.214)
「種痘」についても、詳しく述べられている。森鴎外が在欧中に、種痘賛成論と反対論の双方の研究所に所属して、判断を下したことは有名だが、当時のヨーロッパでは、全人口問題に波及する大問題だった。従って、結論は容易に出なかった。ここでの「百科全書」の多岐にわたる内容は注目に値する。
『こうした背景から、種痘をめぐる論争が、単に医学界の内部での理論モデルの優劣をめぐる学派間の対立に留まらず、公衆衛生や健康政策の領域にまで社会的影響を及ぼした事情は、「百科全書」の項目「種痘」 に「外科/医学/道徳/政治」という分類記号が付されていることからも、容易く想像できる。「百科全書」の項目「種痘」の執筆者は、奇しくも「百科全書」第七巻の項目「ジュネーヴ」でダランベールが、 フランスに先んじて種痘を受け入れた国として称えている、ジュネーヴ共和国出身の医学者テオドール・トロンシヤンである。項目「種痘」を読むと、種痘の導入の是非をめぐる当時の論争の最大の争点が、自然感染する伝染病の天然痘と、牛痘を植え付け、いわば人為的に天然痘を人体に引き起こす種痘の、いずれが生命にとってより危険なのかという、それなりにもっともな疑問であったことが分かる。』(pp.230)
「外科、医学、道徳、政治」を一気に同じテーブルに取り上げたのは、まさに「百学連環」になっている。
「終わりに」には、次のようにある。
『数々の「大発見」を道標とする科学理論の「進歩」の歴史過程を強調した「科学史」の整然とした歴史叙述への違和感から出発した我々は、十八世紀のフランスで細纂された「百科全書」の科学項目における歴史叙述のあり方に着目した。そこでは、各項目の冒頭に分類項目こそ示されるものの、ある学間や技術に関するレベルの異なる 様々な事実、理論、概念に関するありとあらゆる言説が、基本的には、アルファベット順という無差別的かつ恣意的な配列法のみを秩序として隣り合っている。
「この「百科全書」という広大にして畿蒼たる真贋の言説の森においては、人類が過去に獲得した貴重な真理たる「知識」ばかりでなく、人類の無知蒙味の根源として古来悪評の高い「誤謬」や「迷信」もまた、自然を対象とした人間精神の試行錯誤の成果に相ふさわしい場所を得ている。』(pp.249)
最後に、話は「文学」にまで及んでいる。
『殊に科学における「誤謬」が、広義のフィクションに対する「信」に基づく想像的な疑似理論という点において、一見無縁な文学とも境界を接している事実は、人間の知的な営みに想像力の働きが不可欠であることを暗示しているようで、味わい深い。科学における概念のメタファー的な拡大適用に起因する誤謬に論を起こし、メタファーによるイメージを生命とする文学における科学の表象をもって、科学の誤謬をめぐるこのささやかな施策の円環を閉じることにしたい。』(pp.250)
最後に「円環」の言葉が出てきただけでも、この文章の価値を認めざるを得ない。それにしても、当時の「百科全書」が、真に百学連環であったことが良くわかった。一方で、この形が引き継がれずに、現代の「百科事典」になってしまったことが、科学と技術のどうしようもない細分化と無関係とは思えない。最近のデジタル検索では、もっと細分化が進むことになるのだろう。









