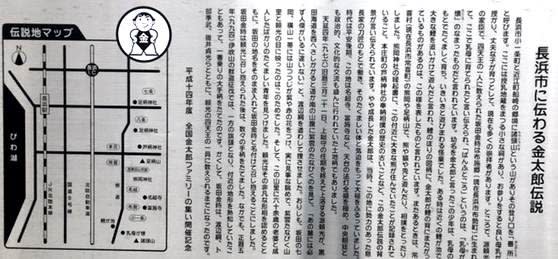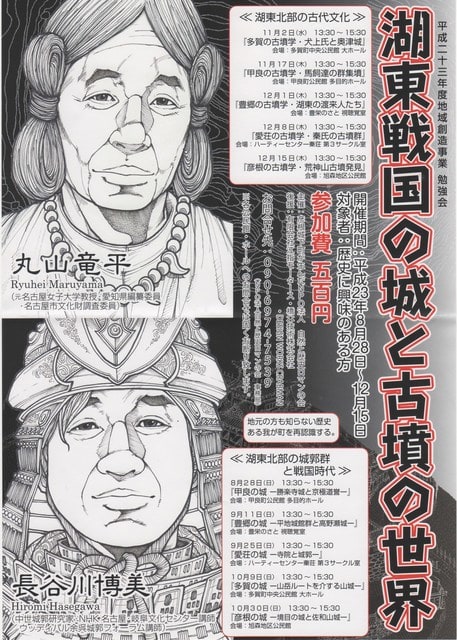高島の万木 高島の安曇川 伊香の勇出 浅井の丁野
◆はじめに
先ず滋賀県高島市で遊牧民族特有のオルドス型銅剣の鋳型が出土した事に驚く。
次に「日本書紀」に天智天皇の都、大津宮に黄金と貴金属にあふれた古代国家
新羅から駱駝「ラクダ」と驢馬「ロバ」が献納された事に驚く。大津には朝鮮
半島特有の床暖房施設、古代オンドルの遺構も発見されている。また万葉など
の古歌で琵琶湖大津の枕言葉は「楽浪」と書いて「さざなみ」と読ませるその
国際性にも驚く。また高島市の鴨稲荷古墳から出土した金銅製の金メッキされ
た王冠や靴儀用礼靴は古代韓半島南部の新羅の王らが着用した王冠などと比し
て全く遜色がない。滋賀高島と言う一地方地域だが古墳の石棺は九州産であり
現代を生きる我々一般庶民からは想像もつかない国際性を示している。なぞの
天皇、継体天皇の別業や基点が近江高島郡であった事も日本の古代史では周知
されている。令和を生きる我々庶民の生活は古代の文化文物や人的交流や人的
移動を考察する余裕は全くないと言える。北陸新幹線が滋賀を外れて若狭方面
を通ると滋賀の人が聞いて落胆していると聞くが、歴史は繰り返す古代北陸道
とは若狭、越前、越中、越後が正規の北陸道である事に気づいてない人が多い。
◆湖西 高島の万木
高島の歴史民俗資料館には何度も行った経験がある。展示物の須恵器の皿には
「万木」と書かれたものが多く私はこの「万木」の文字には胸おどる思いだ。
高島では「万木」と書いて、マンギと読む人は皆無であり。高島では「ゆるぎ」
と読むのだ。万木姓を名乗る万木氏もおられいずれも「ゆるぎ」と読んでいる。
私が思うに「万」は「よろず」と発音し「万木」は「よろき」から「ゆるき」
へと転訛したものでろう。高島の万木は律令の時代の高島の役所、高島郡衙と
推定される。

◆湖北 伊香の勇出山
「ゆるぎ」と聞いて、伊香郡の人々は「勇出山」を想起する人は多いであろう。
勿論この山も「勇出」と書いて「ゆるぎ」と発音するのである。伊香郡の郡衙
の所在地は私は認識していない。伊香の「郡」こほりであるから高月の古保利
村または畝「宇根」遺跡一帯なのであろか?
◆湖北 伊香の勇出山「ゆるぎ」の地名ルーツは湖西 高島の万木「ゆるぎ」か?
高島市には安曇「あど」地名がある奈良時代に作 られた『万葉集』に「足利」
「阿戸」「阿渡」「足速」「吾跡」などと表音表現されている。「足利」と書いて
アドと読む事に驚く。安曇は一般に「あずみ」と発音する場合が多く、本来は何と
海洋の民族、本来は舟を使う操船民族と言う事だ。『日本書紀』の記述に博多の鼠
が越の国に上陸しその海岸に「畝」うねが残ったと記されやがて彼らは更野つまり
信濃に向かったとされる。高月町にも確かに「畝」宇根の地名が残っている是は条
理制に関する地名であろう。長浜市高月町西阿閉(あつじ)の小川北ノ川にかかる
橋の名が安曇橋「あどばし」である事も非常に面白い。高島郡と伊香郡の地名
の類似性には特に注目したい。、和名類聚集には 伊香郡安曇郷があったことが記載
されている。『角川日本地名大辞典』によれば「あどのごう」と読むと解説している。
◆謎の文言
有名な琵琶湖水没都市伝説の揚野郷「阿曽津庄」の総社が伊香郡大森の大森大明神と
言う事は、以前に当該ブログで書いたが一体この「揚野郷」とは何と読むのだろうか?
◆丁野の事
近江国浅井郡には丁野郷が広がっていたとされる。丁野と書いて「ようの」と地元
では呼んでいる。私はこの「丁」が租庸調に関する言葉だと考えている。水田を耕
す人に関わる言葉か?丁野に★「ようろう屋敷」と言う地名がある。中世浅井氏の
城館と推定されるがこの地の豪族中島宗左衛門は関ヶ原合戦の後に石田三成と中島
宗左衛門が伊吹山中で捕縛された件は徳川家康から田中吉政への書状に登場する。
木之本の田部山、丁野の中島宗左衛門城や坂田米原の太尾山城の城主として登場
する人物であるが先祖は治田連「はるたのむらじ」とされ、「新撰姓氏録」では、
彦坐王(ひこいますのみこ)四世の後に近江国の浅井郡に土地を賜り、またその
六世のに治田連の姓を賜ったとされている。田部や丁野や坂田に関わる氏族と思われる。
◆丁と書いて「よほろ」と読む!
『学研全訳古語辞典』によると
よほろ 【丁】
名詞
上代、広く公用の夫役(ぶやく)(=労力を徴用する課役)の対象となった、二十一歳
から六十歳までの男子。律令制での「丁(ちよう)・(てい)」も「よほろ」ということがある。
本来は「膕」の意で、脚力を要したことからいう。後に「よぼろ」とも。
★余談ではあるが江戸時代の商家で使われている人を丁稚「でっち」と呼んでいる。
よほろ 【膕】 名詞
膝(ひざ)の裏側のくぼんだ部分。ひかがみ。◆後に「よぼろ」とも。
◆高島の万木は「ゆるぎ」
◆伊香の勇出やま「ゆるぎ」
◆浅井の丁野「よほろ」
いずれも夫役(ぶやく)(=労力を徴用する課役)の対象となった、二十一歳
から六十歳までの男子。律令制での「丁(ちよう)・(てい)」も「よほろ」を
置いた場所ではないのか?よほろおき=丁置きに関わる地名ではないだろうか?
たしか?丁野木川とも言う名前の川もあったように思うのだが?
◆参考資料
出典 三省堂/大辞林 第三版について
世界大百科事典 第2版の解説
たつかい【田令】
ミヤケ(屯倉)の管理を行う官人。《日本書紀》欽明17年7月己卯条には,蘇我稲目らを
備前児島郡に派遣して屯倉を置かせ,葛城山田瑞子を〈田令〉にしたとあり,分注に
タツカヒとよませている。ついで欽明30年4月条には,白猪(しらい)屯倉の田部の
★丁籍を定めた功によって,王辰爾の甥の胆津(いつ)という人物に〈白猪史〉の姓
を賜い〈田令〉に任じ〈瑞子之副(すけ)〉としている。このように〈田令〉には正
,副の別があったがこれを《日本書紀》編者がタツカヒとよませている点は注意される。
.
日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
田令でんりょう
(1)令の篇目(へんもく)の一つ。「養老(ようろう)令」(30編)にあっては、戸令と
賦役令の間、第九番目に配列されており、全37か条よりなっている。田の面積の単位から
始まり、口分田(くぶんでん)や功田(こうでん)・職田(しきでん)・位田(いでん)など
各種の田、あるいは荒廃田、空閑地に至る土地の規定、用益法などについて定めたもの。
田租(でんそ)に関する規定がこの田令に含まれていることが注目される。母法たる唐令では
、租の賦課規準や徴収法は賦役令において定められているからである。これは、日本古代
律令制の下では、租は課役とは考えられていなかったことを示すものである。この点にかか
わって、唐令においては、受田資格と租調負担とが密接な関連を有しているのに対して、
わが国ではこの両者の関連性が薄いことも彼我の相違点である。(2)訓は「たつかい」。
律令体制確立以前、皇室の直轄地である屯倉(みやけ)の経営にあたるために、中央政府
から派遣された官。初見は『日本書紀』欽明(きんめい)天皇17年(556)七月条に、
備前(びぜん)児嶋(こじま)郡(岡山県児島郡)に設置された屯倉の田令に、葛城山田直瑞子
(かつらぎのやまだのあたいみずこ)が任命されたとあるもの。『続日本紀(しょくにほんぎ)』
大宝(たいほう)元年(701)四月条に「田領をやめて国司の巡検に委す」とあるから、田領が
田令と同じものであるとすれば、大宝令施行まで存続したうえ、その任務が国司に引き継がれた
とみることができよう。なお欽明天皇30年(569)には、吉備(きび)白猪(しらい)屯倉に派遣
された膽津(いつ)が、★田部の戸籍を定めた功によって白猪史(ふひと)の姓を与えられるとと
もに、葛城山田直瑞子の副官として、田令に任命されている。[福岡猛志]
『井上光貞他編『律令』(1976・岩波書店)』