「天は人の上に人をつくらず、人の下に人をつくらず」
福沢諭吉の言葉です。
ティール、自律分散型組織そのものの哲学ですよね。

高校、大学と全く関心がなかった福沢諭吉。
日本のお札の最高紙幣がなぜ福沢諭吉なんだと。
すみません。福沢諭吉先生。
私の浅学が原因でした。
ということで福沢諭吉の哲学を勉強。
福沢諭吉は、儒教的な精神を徹底的に排除しようとかなり過激な主張を「西洋事情」、「学問のすすめ」「文明論の概略」でしていますね。
これはどういうことなのでしょうか?
渋沢栄一の論語と算盤や二宮尊徳の教えなど私自身学んでいるだけに福沢諭吉の哲学はどのような点から儒教批判をしているのか気になります。
儒教自体を福沢諭吉はしっかりと勉強していたからこそのその良い面と悪い面の両方をよく知ったうえで、儒教のこの時代での悪い点を指摘しています。
それは、儒教のもつ封建制です。
そして、当時の日本の外圧に対して明治になってもこの古臭い文化のままではやがて西洋に日本は支配されてしまうぞと福沢諭吉は、やるわけです。
軍艦や大砲、近代的な建造物などその事物にたいしてただやみくもに西洋文明をとりいれ関心をもつのでなくそれらを生み出した文化にこそ福沢諭吉は関心を持てというのです。
文明に導く精神を育むという点で当時の儒教の社会秩序に対する社会のなかに位階があるごとくそれを遵守するとう倫理に対しての批判でした。
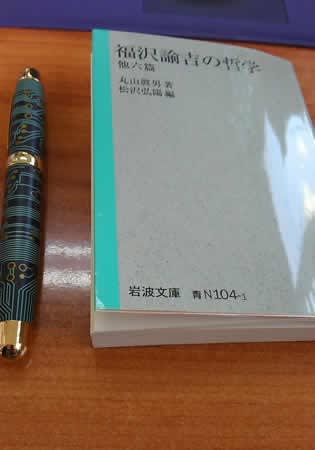
すごい!
これは、まさにイノベーションを目指す企業に置き換えるとおなじことが言えそうですね。
なぜあの企業は、イノベーティブな商品が生まれるんだ、なんとかしろ!
同じものをつくれ!というのでなく、そのような商品が生まれるその企業の文化を学べというわけです。
当時の日本は高い識字率をもってました。しかしそれにもかかわらず、西洋諸国のような軍艦や大砲などをつくるようなその学問を社会にむかって主体的に生きた学問として日本はなっていないというのです。
もっと日常の生活のなかで生きた学問、そして、農民は農民、商人は商人というような固定観念はすでに身分制度は廃止したにも関わらずいまだに、封建制度を色濃く遺したままではいかん!とやるわけですね。
まさに実学の考え。プラグマティズムの思想こそいま、イノベーティブな自律分散型組織を目指す企業はこの明治の福沢諭吉の精神を学ぶべきなのではないかと思うのです。
引き続き学んでいきます。
福沢諭吉の言葉です。
ティール、自律分散型組織そのものの哲学ですよね。

高校、大学と全く関心がなかった福沢諭吉。
日本のお札の最高紙幣がなぜ福沢諭吉なんだと。
すみません。福沢諭吉先生。
私の浅学が原因でした。
ということで福沢諭吉の哲学を勉強。
福沢諭吉は、儒教的な精神を徹底的に排除しようとかなり過激な主張を「西洋事情」、「学問のすすめ」「文明論の概略」でしていますね。
これはどういうことなのでしょうか?
渋沢栄一の論語と算盤や二宮尊徳の教えなど私自身学んでいるだけに福沢諭吉の哲学はどのような点から儒教批判をしているのか気になります。
儒教自体を福沢諭吉はしっかりと勉強していたからこそのその良い面と悪い面の両方をよく知ったうえで、儒教のこの時代での悪い点を指摘しています。
それは、儒教のもつ封建制です。
そして、当時の日本の外圧に対して明治になってもこの古臭い文化のままではやがて西洋に日本は支配されてしまうぞと福沢諭吉は、やるわけです。
軍艦や大砲、近代的な建造物などその事物にたいしてただやみくもに西洋文明をとりいれ関心をもつのでなくそれらを生み出した文化にこそ福沢諭吉は関心を持てというのです。
文明に導く精神を育むという点で当時の儒教の社会秩序に対する社会のなかに位階があるごとくそれを遵守するとう倫理に対しての批判でした。
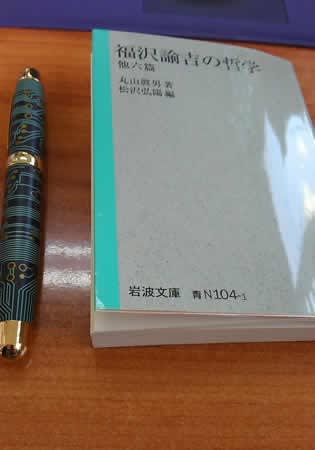
すごい!
これは、まさにイノベーションを目指す企業に置き換えるとおなじことが言えそうですね。
なぜあの企業は、イノベーティブな商品が生まれるんだ、なんとかしろ!
同じものをつくれ!というのでなく、そのような商品が生まれるその企業の文化を学べというわけです。
当時の日本は高い識字率をもってました。しかしそれにもかかわらず、西洋諸国のような軍艦や大砲などをつくるようなその学問を社会にむかって主体的に生きた学問として日本はなっていないというのです。
もっと日常の生活のなかで生きた学問、そして、農民は農民、商人は商人というような固定観念はすでに身分制度は廃止したにも関わらずいまだに、封建制度を色濃く遺したままではいかん!とやるわけですね。
まさに実学の考え。プラグマティズムの思想こそいま、イノベーティブな自律分散型組織を目指す企業はこの明治の福沢諭吉の精神を学ぶべきなのではないかと思うのです。
引き続き学んでいきます。





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます