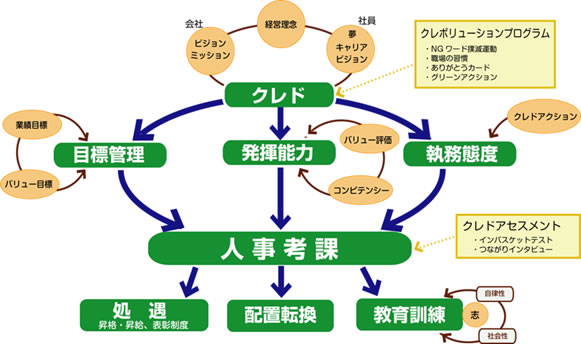今求められているのは、ビジネスのそのものの変革。
社長のそのことへの理解と覚悟そして行動です。
今やっていることを棄てる勇気、自分の思い込みを棄てる覚悟です。
そうしなければ、枯れた井戸で、これでもか!これでもか!と、
シャベルを大きなスコップに変え、シャベルカーへとやり方とツール(戦術)
を変えても、水は出てきません。
いま、必要なのは、掘ることをやめること。新しい、井戸を掘る、または、全く違う
方法で水を得ることなのです。
そのためには、社員にももうこの井戸を掘るのをやめよう!と宣言することです。
そして、徐々に混乱をなくして行ったなあと思うときに人事制度、就業規則は、
自然とつくられてくるものなのです。
人事のシステム化は、システム化する場合に、
大きく2つにわけることが出来ます。
人事制度をマニュアル化することそして、社風づくりです。
大抵の社長は、人事制度の整備マニュアルを考えてしまいます。
それが、人事システムがまわらない理由です。
人事制度をマニュアル化する前に、どうしても、先に、
社風づくりをしていく必要があります。
社風が育っていく前に人事部や総務部に人事制度をつくってくれと
いっても、それはほぼ不可能です。
「どうして、お金と評価を結びつけないの!こんなんじゃ社員が真剣に働くわけないですよ!」
「地域、CSR?社員にかすみを食って仕事をしろというのですか?そんなんで、働くわけないですよ」
「幸福?どっかの宗教団体つくるんじゃあるまいし、そんなの若い人が本当にのぞんでいるんですか?」
「やっぱり、世の中カネが無きゃどうにもならないよ」
とこんな具合で、まともに、社長がCSR、地域貢献をめざし、
「地域に愛され、社員が輝く会社の人事制度」といっても、
形だけつくったところで、その制度が動くと思いますか?
人が育つ前に、その人に人事制度を作らしても
それは、無理。逆に、人が育てば、自然と、その人が、プロジェクト
が、人事制度をつくって運用をし始めるのです。
そこには、タイミングがあります。
弊社では、それをトライブステージとして、
5段階に分けていますが、社員それぞれが、
認め合うと言う段階まで社風が成長しないと、
人事制度はつくってもお金を棄ててしまう
可能性が高いのです。
ですから、今起きている、組織の問題は、
人事制度、規則いったマニュアルだけで
解決するということは、まだ、ピラミッド型の組織で旨くいっている会社。
グローバルな大量生産、大量消費がまだ、通用する会社以外は、
そんな、小手先の人事システムでは、解決しないのです。
社長のそのことへの理解と覚悟そして行動です。
今やっていることを棄てる勇気、自分の思い込みを棄てる覚悟です。
そうしなければ、枯れた井戸で、これでもか!これでもか!と、
シャベルを大きなスコップに変え、シャベルカーへとやり方とツール(戦術)
を変えても、水は出てきません。
いま、必要なのは、掘ることをやめること。新しい、井戸を掘る、または、全く違う
方法で水を得ることなのです。
そのためには、社員にももうこの井戸を掘るのをやめよう!と宣言することです。
そして、徐々に混乱をなくして行ったなあと思うときに人事制度、就業規則は、
自然とつくられてくるものなのです。
人事のシステム化は、システム化する場合に、
大きく2つにわけることが出来ます。
人事制度をマニュアル化することそして、社風づくりです。
大抵の社長は、人事制度の整備マニュアルを考えてしまいます。
それが、人事システムがまわらない理由です。
人事制度をマニュアル化する前に、どうしても、先に、
社風づくりをしていく必要があります。
社風が育っていく前に人事部や総務部に人事制度をつくってくれと
いっても、それはほぼ不可能です。
「どうして、お金と評価を結びつけないの!こんなんじゃ社員が真剣に働くわけないですよ!」
「地域、CSR?社員にかすみを食って仕事をしろというのですか?そんなんで、働くわけないですよ」
「幸福?どっかの宗教団体つくるんじゃあるまいし、そんなの若い人が本当にのぞんでいるんですか?」
「やっぱり、世の中カネが無きゃどうにもならないよ」
とこんな具合で、まともに、社長がCSR、地域貢献をめざし、
「地域に愛され、社員が輝く会社の人事制度」といっても、
形だけつくったところで、その制度が動くと思いますか?
人が育つ前に、その人に人事制度を作らしても
それは、無理。逆に、人が育てば、自然と、その人が、プロジェクト
が、人事制度をつくって運用をし始めるのです。
そこには、タイミングがあります。
弊社では、それをトライブステージとして、
5段階に分けていますが、社員それぞれが、
認め合うと言う段階まで社風が成長しないと、
人事制度はつくってもお金を棄ててしまう
可能性が高いのです。
ですから、今起きている、組織の問題は、
人事制度、規則いったマニュアルだけで
解決するということは、まだ、ピラミッド型の組織で旨くいっている会社。
グローバルな大量生産、大量消費がまだ、通用する会社以外は、
そんな、小手先の人事システムでは、解決しないのです。