
すべての法学は「法とは何か」の問いへの回答である。これが、私の恩師の一人、八木鉄男先生から教えていただいたことのαでありωかもしれない。今、私はそう考えています。而して、本稿は「法とは何か」という問い自体を一瞥するもの。すなわち、「法とは何か」の問いを遂行するためのベースキャンプの設営の試みです。
そもそも「法とは何か」という問いはどんな解答/回答を要求する問いなのでしょうか。次の二つの疑問文でそのことを考えておきましょう。
(01)What is the color?
(02)What is color?
前者は、例えば、「新しい車を買ったんだよ。トヨタのプリウス」と言う相手に対して「その車の色は何色なの」と言うように、具体的なあるものの色を尋ねる質問。他方、後者は、プリズムで太陽光を<虹>に変換して壁に投影しているような場面で、「色っていったい何なんだろうね」と呟く、哲学的と言えば哲学的、物理学的と言えば物理学的な、いずれにせよ、「色そのもの/色の本質」を問う、前者に比べればより抽象度の高い問いです。
而して、「法とは何か」の問いも実は、(01)(02)の両者とパラレルな重層的な問いであると言えると思います。蓋し、
「法とは何か」は、(01L)ある紛争を解決する上でそれに適用される法規や法慣習の内容を具体的に希求する問いであると同時に、(02L)その前提となる、「法とはそもそもいかなるものか/道徳規範や倫理規範等の他の社会規範と法はどう異なるのか/我々は法になぜ従っているのか」を尋ねる重層的な問いである。
そう私は考えています。「法とは何か」の問いは、しかし、それが憲法無効論の如き空理空論に終わらないためには、法が適用され効力を保持している(ある規範が遵守されるべきだと一般に考えられており、同時に、全体的には、また、その法規範を包摂する法体系総体としては現実に遵守されている)当該の社会のあり方を理解しなければならない。かって、パブロフは、「鳥の翼が力学的に完全だとしても、真空の中ではその羽ばたきは空しい物体の移動にすぎないだろう」と述べましたが、「法とは何か」の問いが、よって、法哲学や憲法学が現実の紛争解決と社会統合に関して具体的現実的な貢献をしたいと思うのならば、法哲学や憲法学は法体系がそこに存在している人間社会に対する「構造的-実存的」な理解を深めなければならないのだと思います。
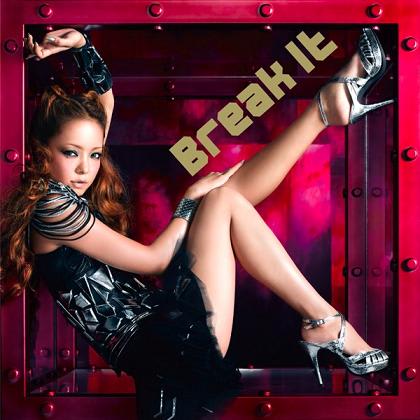
◆制度と実存の二律背反と両面価値
あるいは読者の皆様から顰蹙を買うのを承知で本稿は「性」を一つの切り口に、人間社会の実存的あり方を構造的に、あるいは、人間社会の構造を人間の実存の観点から考えます。蓋し、文化人類学の知見が教えてくれているように、「性」は「言語」「交換」「権力」と並び、あらゆる文化と文明を構成する主要な制度。而して、「法=権力」を「言語」のアナロジーから一瞥しようとする本稿において、人間実存の社会的あり方を検討する予備作業の切り口としては「性」は格好のもの。そう考えるからです。
ポーリーヌ・レアージュ『O嬢の物語』(1954年)、ジョゼフ・ケッセル『昼顔』(1929ン年)やジャン・ド・ベルグ『イマージュ』(1956年)。そして、これらほどの<権威>はフランス文学界では持っていないのですが(というか、映画の成功に比べれば原作は三文性愛小説と看做されているのが正直な所でしょうが)エマニエル・アルサン『エマニエル夫人』(1959年:映画化は1974年)も(その異文化趣味を超えて)、我々が「制度」というものを理解する上での素材を提供しているのではないか。
松田聖子さんが母であり歌手でもあるように、人間存在は、不可避的に、かつ、同時に複数の役割や規定性を帯びている。而して、人生も時間も本質的に有限でかり、かつ、不可逆的。更には、本質的にはある瞬間にはある一つの役割や規定性しか演じることが難しい。このような人間存在の実存を踏まえる時、自分が帯びる複数の規定性や複数の役割をどう調整していくのか。この点の解決が人類の「智恵」であり、その「智恵」のタイプが文明や文化に他ならない。
人間存在の実存をこう踏まえた上で、この「同時に複数の役割や規定性を帯びざるを得ない人間が、それらを遂行するプライオリティをどう調整するか」の解答の一つが「制度」ではないか。例えば、妻の顔と娼婦の顔を持つ『昼顔』のヒロインがその解決を、昼間だけ娼館に通う<スケジュール>で解決したように、また、『O嬢の物語』や『イマージュ』のヒロイン達が、自由と平等を愛するフランス人としての自己のアイデンティテと<奴隷的被虐>に快楽を覚える自己の実存の亀裂を<契約>によって解決したように。
ならば、制度は(偏微分方程式を解く要領とパラレルに)、ある局面では、ある人間存在の実存の過半を捨象して抽象化し、単一の役割や規定性を人間に与えるのだけれども、その裏面としては、その制度によって、その同じ人間は他の時間と空間においてはより効率的に自己の実存を発揮できるのではないでしょうか。エマニエル夫人が若妻という社会的規定性に拘束されながら、同時に自己の心の声に従い快楽を追求する重層的な生活に入ったように。畢竟、制度と実存は二律背反的であると同時に両面価値的でもある。と、そう私は考えるのです。
而して、個人の人間存在の実存と制度を巡るジレンマとアンビバレントな関係は、「権力-権威」の制度についても言えるのかもしれない。生身のある人間を「天皇」として処遇する制度は、彼や彼女達に「国の象徴」という地位を配分することで、社会全体としては効率よく社会統合と社会の秩序維持を保障する(自然からの脅威、他国からの脅威、自国の権力の脅威、社会の他のメンバーからの脅威という4個の脅威から国民を守り、国民に対して最大多数の最大幸福を保障する)<システム>の一斑なのかもしれないということです。
蓋し、例えば、(天災や革命は皇帝の不徳の致す所という)支那を始め様々な文明で観察される「神人交感観」に基づく権力運用のあり方も、物象化した社会秩序を含め人知を超えた自然との共生を不可避とする人間存在が、権力支配の正当化事由に自然の脅威からの国民の保護を織り込んだ結果なの、鴨。尚、「天皇制」に関する私の基本的な考えについては下記拙稿をご一読いただければ嬉しいです。
・「天皇制」という用語は使うべきではないという主張の無根拠性について(正)(補)
http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/b699366d45939d40fa0ff24617efecc4
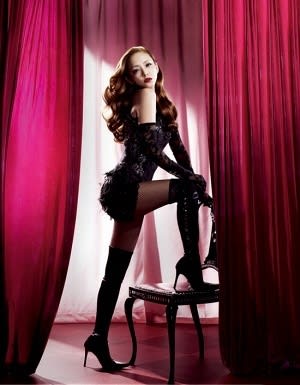
◆機能英文法から見た法の概念
世の中には「裁判員制度は憲法違反だ」とか「日本国憲法は大日本帝国憲法に違反しており無効だ」と述べている方がおられるようです。本稿は具体的に憲法論を展開するものではありませんが、具体的な事例を念頭に置いて以下の説明を読んでいただくべく裁判員制度憲法違反論について簡潔にコメントしておきます。尚、憲法無効論に関しては下記拙稿をご参照いただければ嬉しいです。
・憲法無効論の破綻とその政治的な利用価値(上)(下)
http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11396110559.html
裁判員制度違憲論の根拠は、憲法32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」、同76条1項「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」、そして、最高裁判所と下級裁判所の構成をそれらの裁判官の要件を定めることによってのみ規定している79条及び80条だそうです。蓋し、
「裁判所の裁判を受ける権利は奪われない」→「裁判所を構成するのは裁判官」
→「裁判官でない裁判員が裁判所を構成することを憲法は想定していない」
→「実際、「裁判員」の規定など憲法のどこにも書いていないじゃないか!」、と。
確かに、「徴兵制を採用する諸外国の憲法を見てもその多くは「徴兵制」や「国民の国防の義務」を規定している。よって、それらの規定を欠く(国民の自由の重大な制限である)「徴兵制」は憲法違反だ」という論法と同様、「裁判員」の規定が憲法に欠けていることを根拠とするこの裁判員制度違憲論はそれなりに傾聴に値するの、鴨。
しかし、規定がなければ、憲法の原理原則から、それも見当たらない場合は憲法の本性や概念から妥当な解釈を導き出すのが憲法学というもの。ポイントは、原理原則、憲法の本性や概念を恣意的に捏造するのではなく、「論理的-社会学的」にそれらを間主観性のある形で抽出すること。ならば、現行憲法解釈の原理である民主主義から見て、司法に国民が参加することは(規定が存在しない以上、憲法の要請ではないとしても)現行憲法に違反するとまでは言えない。と、そう私は考えます。ことほど左様に、
憲法の規範意味は憲法条項の字面だけではなく、①憲法に内在する原理原則、②憲法の本性、③憲法の概念から導かれる。そして、繰り返しになりますが、①~③を見出す作業は、「論理的-社会学的」で反証可能性のあるものでなければならない。付け加えれば、(甲)憲法規範の枠組みは憲法の条規と①~③によって確定されるとしても、(乙)多くの場合、憲法規範の具体的内容、特に、憲法訴訟や国会と行政の実務を現実に規定する具体的な内容は、④国民の法意識(何が憲法規範の意味であるかに関する国民の法的確信)と⑤憲法慣習によって肉付けされる。と、そう言えると思います。
而して、例えば、『A Practical English Grammar』(Oxford, 1986年)によれば、
(03)Alice said to me, “I’m leaving.”
(04) “I’m leaving,” Alice said to me.
所謂「学校文法」では(03)(04)も「「私は出で行くところです」と私にアリスは告げた」の意味であり文法的には正しいとされるのでしょうが、耳目を引き付けるのが目的の引用文が後置されることは矛盾であり、実際に、英語のネーティブスピーカーが(03)を使うことはまずなく、よって、機能英文法の観点からは(03)は間違いとされます。同様に、
(05)There is the money in the box.
(06)There is money in the box.
この事例でも、There構文の主語は、聞き手/読み手にとって「新情報」でなければならず(例えば、「昔々、おじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんはやまに柴刈りに、おばあさんは川に洗濯に行きました」の「が」と「は」の使い分けとパラレルに)、(05)の主語に「旧情報」を示す定冠詞が付いているのは機能英文法の観点からは間違いなのです。
これら機能英文法が記述する英文法のルール、否、言語ルールを機能英文法が発見するやり方こそ、憲法解釈において憲法典の条規を超えて憲法規範の内容を間主観的に見出す営みと極めて近い。蓋し、「法とは何か」の問いに答える作業は、それが経験的なものとしても「闇の夜に鳴かぬ烏の声を聞く」 (一休)作業に近いの、鴨。と、そう私は考えています。




















