
2015年から2018年にかけて「小説新潮」に断続的に発表された6つの短編連作に加筆修正を行い、単行本化された作品集である。
「名残の花」はこの連作の第一作の題名であり、それが単行本のタイトルとなっている。そして、第一作「名残の花」の中では、「誘う花とつれて、散るや心なるらん」という謡曲「田村」の一節が主人公の脳裡に甦る背景となりつつ、この短編の末文中の言葉として出てくる。「それをまるで自分が眺め損ねた名残の花であるかのように感じながら、胖庵は豊太郎の腕を支えに、黒焦げた丸太を大股にまたぎ越した」と。
「名残」という言葉を『新明解国語辞典』(第5版、三省堂)で引くと、「(1)その事が終わったあとに、まだそれを思わせる物が残っていること。(2)別れようとして、そのまま別れるに忍びない気持。(3)別れたあとも、その人の残した強い印象が忘れられないこと。(4)連歌の懐紙で、最後の折の称。第四折。」と記されている。
この連作集は、「名残」の持つ(1)~(3)の語義をモチーフにして、様々なテーマ設定の個々の作品において、名残という観点で、そこに漂う哀感を描き出そうとしているように感じた。
江戸幕府が崩壊し、明治という新たな時代が到来。激変していく世の中にスムーズに対応あるいは適応できずに取り残されそうになる人々の側に光を当てる。時代の変わり目に遭遇した名も無い人々の生活の変転を浮かび上がらせるという作品になっている。時代背景はかつての武士が佩刀して未だに街中を歩けた頃の時期に絞られている。
新たな時代を築き上げるという名目のもとに、斬り捨て御免という形で世の中を大きく変えようと新政府が躍動する渦中で、そのあおりを受け放り出される人々の側、いわば個々の小さな私的事象に目を向けることで、この連作は明治初期という時代の一面を浮彫にする役割を果たしている。時代の転換点が生み出す問題事象・功罪を見つめる作品集になっている。
この連作の主な主人公は二人。鳥居胖庵と豊太郎である。
鳥居胖庵とは江戸時代末期に南町奉行として、天保の奢侈禁令や人返し令のもとで、信念を持ち苛烈な取締りを実行したという鳥居甲斐守忠輝である。老中・水野忠邦の造反により家禄没収改易の上に、人吉藩お預け処分となる。さらに秋田藩から丸亀藩へと預け替えられ、幕末・明治維新の動乱期は牢獄暮らし。28年ぶりに江戸(東京)に戻って隠居暮らしに入っている。胖庵と名乗り、齢77歳である。実在の武士がこの連作の主人公のモデルとなっている。
豊太郎とは本八丁堀長沢町に住む滝井豊太郎のことで、金春座の地謡方、中村平蔵の門弟として修行している16歳の若者。明治維新になり、兄は時代の変化に併せ、能の世界を見限り、転職してしまった。豊太郎が家業を継ぎ、西洋文明の導入で激変する世の中で、これからどうなるかわからない能の世界で、一途に修行を積んでいる。
この連作は、主に江戸から明治に変わった世の中に投げ込まれた能の世界の状況を背景にしながら、時代に翻弄される人々の哀感が、短編の連作として描き出されていく。また、時代の急転回の渦中において、歴史の表に出てくることのない庶民の生活感覚が描き出されている。実在人物をモデルにしつつ、歴史の影の部分に光を当てたフィクションである。連作の各短編について、少し内容・読後印象をご紹介しておこう。
<名残の花>
日課である散策の足を東叡山寛永寺、桜の名所・上野の山へと足を向けた鳥居胖庵が、豊太郎と出会うエピソードが中心となる。豊太郎は金春座の太鼓方・川井彦兵衛の子息、五十雄の伴で上野に桜見物にきたが、五十雄を見失い探し回っている途中で、酔っ払いに絡まれる。その場に胖庵が出くわす。これが二人の関係の始まりとなる。そこに、五十雄を連れた大年増の女が現れる。五十雄と会えた豊太郎はホッとするが、その女は曲者だった。
この短編で、胖庵の過去が明らかにされ、胖庵が江戸末期の庶民からどう見られていた存在かが明らかになる。一方で、江戸時代から明治初期への時代の転換期に、能の世界の人々の地位や生活がどのように激変したかの一端も明らかになる。
後日、豊太郎は師匠の中村平蔵を介して、五十雄を連れてきた女と再会することになり、それが金春屋敷のエピソードに展開していく。
ここでは、和田倉門内からの出火で灰燼に帰した金春屋敷の公孫樹の樹上に留まっていた雨だれがぽつりと足元を叩いたことを、胖庵は「眺めそこねた名残の花」に感じたのである。
<鳥は古巣に>
明治維新により演能の機会は激減した。そんな最中、観世流の梅若六郎が、青山下野守屋敷の能舞台を浅倉御蔵前の自邸に引き取った。そして10日間勧進能を開くという。この勧進能に胖庵は孫娘楚乃により無理やり連れてこられる。胖庵は長年の幽閉を解かれて、今は明治政府に出仕する嫡男の屋敷に寄寓の身であるが、嫡男は胖庵に複雑な思いを抱いている。胖庵の居心地は良くない。楚乃は寄寓する祖父の心情を察している。
この勧進能を豊太郎も修行の一環として観能しようと出かけてきたが、席料のことで濡れ衣を着せられ騒動となるエピソードである。だがそこには演能の囃子方の一つ、小皷方の家の内情話が絡んでいた。
能の世界での流派間の関係事情や世襲制の抱える問題などが織り込まれて行く。伝統芸能の世界の内情が垣間見える。さらに、明治維新期の演能状況がうかがえて興味深い。
<しゃが父に似ず>
冒頭に胖庵の曾孫、五歳の伊沢敏之丞は怪我が元で左足が不具合になり病弱である話を描く。そこに長年の蟄居生活で漢方の調薬の腕を医師並みにあげた胖庵の見立てが語られる。一作ごとに、胖庵の背景事情が広がり深まっていくことで、人物をより深く知るという関心が引き起こされる。この冒頭の場面描写は、後の短編への伏線になっている。
この短編では、30年前に江戸三座を浅草はずれの猿若町に強引に移転させて奢侈紊乱を封じようとした時の胖庵の思いと、現在の猿若町の賑わい、喧騒を対比させるという形をとる。時代の対比、江戸庶民のしたたかさをテーマとして、そこに胖庵の名残の心が重なっていく。東京となったこの梅若町の芝居小屋の状況と新政府による狂言綺語の禁止問題が描かれる。胖庵は出かけて行った梅若町で偶然にも南町奉行所時代の元部下であった庄右衛門に再会する。その再会から胖庵はこの問題への対応という核心に一歩踏み込む立場に己の身を置くことになる。
勿論、この禁止は衰微している能の世界にも適用される問題であり、平蔵は大荒れして、豊太郎をいっとき困らせたのだった。題名の「しゃが父に似ず」は謡曲「歌占」の一節「鶯の卵の中の時鳥、己(しゃ)が父に似て、己が父に似ず・・・」に由来する。胖庵は平蔵からこの謡本について知らされる。それが、胖庵にある考えを結実させる。
江戸の名残を、胖庵は今の猿若町に見たのだ。「あの町には自分がとうの昔に失ってしまった江戸が、まだ息づいている」(p140)と。
<清経の妻>
中村平蔵の家で、東京在住の金春座役者が寄り集まり、稽古能が開催されることになる。豊太郎は五番立て中、二番目物「清経」のツレとして、清経の妻役を任せられるという大抜擢を受けた。その稽古に勤しむべき時期に、能を捨てて、富岡八幡宮裏の書肆で働く兄の栄之進と会わざるを得なくなる。兄の話は四谷坂町の亡くなった叔父の家の整理を兄が行ったことに関連していた。その折り、叔母から夫の形見だと言って受け取ったのが大名物「千鳥の香炉」だという。目利きである平蔵にその香炉の箱書きを豊太郎を介して頼みたいという魂胆だった。豊太郎は目利きを胖庵にしてもらおうと考える。
この短編は、この「千鳥の香炉」の真贋に胖庵が関わることから、豊太郎の叔父叔母の思いと行為が明らかになっていく経緯を語るストーリーである。一種の推理仕立てとなっていて、興味深い。
豊太郎が胖庵に会い、目利きをしてもらっている間に、戻って来た鳥好きの敏之丞が目ざとく香炉の鳥を見て感想を語った。そのとき、豊太郎の脳裡に、「清経」の一節、「--形見こそ なかなか憂けれ これなくは 忘るる事もありなんと思ふ」がよぎったのだ。
このエンディングでは、豊太郎と胖庵の推理が異なる。二つの仮説が並立するところが読ませどころとなる。そして、最後は豊太郎が能稽古の開始に遅刻するオチで終わる。
<うつろ舟>
新政府が寺院の寺地について上地令を執行したということは、京都のいくつかの寺院の実例で知っていた。東京では、旗本屋敷返納を命じる上地令が執行されていたということをこの小説を読んではじめて知った。
この短編では、胖庵の孫である伊沢劼之助一家がその上地令の適用を二度受けるというところから始まる。もちろん、そのたびに住まいがどんどん狭くなって行くという次第。ここでは、家移りのために、敏之丞が大好きな鳥たちを手放さざるを得なくなる代償に、楚乃が上野の花鳥茶屋に連れて行くと約束したことの実行に絡むストーリーである。
楚乃の約束に対して、二人で花鳥茶屋に行かせる訳には行かぬと、胖庵が同行する事になる。ところが当日、そこに大蔵省会計係で給仕をしてきた少年が加わることになる。過去形で書いたのはその職を解雇されたからだが、それを否として譲らないので、劼之助が自宅に連れ帰ってきたのだ。当時の新政府の方針がこの背景にうかがえて興味深い。
多崎弥十郎という少年も花鳥茶屋に一緒に行くことになる。花鳥茶屋から見えた能舞台が切っ掛けとなり、多崎弥十郎のことに、フォーカスが当たっていく。それは哀しいストーリーに繋がって行く。後半では、中村平蔵の屋敷での謡曲「鵺(ぬえ)」の稽古場面が描かれる。そして、胖庵は一計を実行するのだが、やるせない哀しい結末となる。
こういう事態に近いことが、たぶん当時発生していたのだろう。時代の転換点で庶民層は苦しむ。時間の経過とともに消されていく小さな事実の累積。歴史書や学校のテキストはそれを形に残さない。捨象してしまう。そういう消されてしまう局面に小説という手法が目を向けさせる手段となっている。
<当世実感>
浅草南元町に暮らす観世座能役者・梅若六郎の隠居祝いに招かれた平蔵が、相当に呑んでいる上に、激怒した状態で屋敷に戻ってきて、豊太郎を困らせる場面からストーリーが始まる。そして、追いかけるようにして五十三代梅若六郎を継いだ源次郎が現れる。源次郎は、かれこれ十日程前に、質屋滝沢屋が将来見込みのある若者を探していて、その支援をしたいという話があり、豊太郎を推挙したいと考えていることを、平蔵に伝えていたと言う。源次郎は有徳者の力を借りるのも悪くはないと勧める。
豊太郎は、師の平蔵の許しを得て、滝沢屋の主人・喜十郎に会いに行く。一旦、世話になろうと心を決めるのだが、思わぬ場面を目撃したことが切っ掛けで、亮輔という人物と出会う事になる。そこから喜十郎の裏の心が見え始めていく。
人間関係の繋がりは不可思議なもの。亮輔の師が胖庵の知人であり、また滝沢屋喜十郎には、廻り廻ってその人物の背景を知る細い糸の繋がりを胖庵が見つけていくという巡りあわせとなる。胖庵がひと働きするという次第。
時代がどのように変わろうと、その渦中に存在する人の生き様、価値観の意味をまず問うという短編である。
胖庵と能の世界に生きる人々を主に扱いながら、時代が激変する過渡期の渦中での庶民側の哀感と時代相を見つめた連作集である。明治維新の捉え方を広げる視点を含んでいる。
ご一読ありがとうございます。
徒然に読んできた著者の作品の中で印象記を以下のものについて書いています。
こちらもお読みいただけると、うれしいかぎりです。
『落花』 中央公論新社
『龍華記』 KADOKAWA
『火定』 PHP
『泣くな道真 -太宰府の詩-』 集英社文庫
『腐れ梅』 集英社
『若冲』 文藝春秋
『弧鷹の天』 徳間書店
『満つる月の如し 仏師・定朝』 徳間書店
「名残の花」はこの連作の第一作の題名であり、それが単行本のタイトルとなっている。そして、第一作「名残の花」の中では、「誘う花とつれて、散るや心なるらん」という謡曲「田村」の一節が主人公の脳裡に甦る背景となりつつ、この短編の末文中の言葉として出てくる。「それをまるで自分が眺め損ねた名残の花であるかのように感じながら、胖庵は豊太郎の腕を支えに、黒焦げた丸太を大股にまたぎ越した」と。
「名残」という言葉を『新明解国語辞典』(第5版、三省堂)で引くと、「(1)その事が終わったあとに、まだそれを思わせる物が残っていること。(2)別れようとして、そのまま別れるに忍びない気持。(3)別れたあとも、その人の残した強い印象が忘れられないこと。(4)連歌の懐紙で、最後の折の称。第四折。」と記されている。
この連作集は、「名残」の持つ(1)~(3)の語義をモチーフにして、様々なテーマ設定の個々の作品において、名残という観点で、そこに漂う哀感を描き出そうとしているように感じた。
江戸幕府が崩壊し、明治という新たな時代が到来。激変していく世の中にスムーズに対応あるいは適応できずに取り残されそうになる人々の側に光を当てる。時代の変わり目に遭遇した名も無い人々の生活の変転を浮かび上がらせるという作品になっている。時代背景はかつての武士が佩刀して未だに街中を歩けた頃の時期に絞られている。
新たな時代を築き上げるという名目のもとに、斬り捨て御免という形で世の中を大きく変えようと新政府が躍動する渦中で、そのあおりを受け放り出される人々の側、いわば個々の小さな私的事象に目を向けることで、この連作は明治初期という時代の一面を浮彫にする役割を果たしている。時代の転換点が生み出す問題事象・功罪を見つめる作品集になっている。
この連作の主な主人公は二人。鳥居胖庵と豊太郎である。
鳥居胖庵とは江戸時代末期に南町奉行として、天保の奢侈禁令や人返し令のもとで、信念を持ち苛烈な取締りを実行したという鳥居甲斐守忠輝である。老中・水野忠邦の造反により家禄没収改易の上に、人吉藩お預け処分となる。さらに秋田藩から丸亀藩へと預け替えられ、幕末・明治維新の動乱期は牢獄暮らし。28年ぶりに江戸(東京)に戻って隠居暮らしに入っている。胖庵と名乗り、齢77歳である。実在の武士がこの連作の主人公のモデルとなっている。
豊太郎とは本八丁堀長沢町に住む滝井豊太郎のことで、金春座の地謡方、中村平蔵の門弟として修行している16歳の若者。明治維新になり、兄は時代の変化に併せ、能の世界を見限り、転職してしまった。豊太郎が家業を継ぎ、西洋文明の導入で激変する世の中で、これからどうなるかわからない能の世界で、一途に修行を積んでいる。
この連作は、主に江戸から明治に変わった世の中に投げ込まれた能の世界の状況を背景にしながら、時代に翻弄される人々の哀感が、短編の連作として描き出されていく。また、時代の急転回の渦中において、歴史の表に出てくることのない庶民の生活感覚が描き出されている。実在人物をモデルにしつつ、歴史の影の部分に光を当てたフィクションである。連作の各短編について、少し内容・読後印象をご紹介しておこう。
<名残の花>
日課である散策の足を東叡山寛永寺、桜の名所・上野の山へと足を向けた鳥居胖庵が、豊太郎と出会うエピソードが中心となる。豊太郎は金春座の太鼓方・川井彦兵衛の子息、五十雄の伴で上野に桜見物にきたが、五十雄を見失い探し回っている途中で、酔っ払いに絡まれる。その場に胖庵が出くわす。これが二人の関係の始まりとなる。そこに、五十雄を連れた大年増の女が現れる。五十雄と会えた豊太郎はホッとするが、その女は曲者だった。
この短編で、胖庵の過去が明らかにされ、胖庵が江戸末期の庶民からどう見られていた存在かが明らかになる。一方で、江戸時代から明治初期への時代の転換期に、能の世界の人々の地位や生活がどのように激変したかの一端も明らかになる。
後日、豊太郎は師匠の中村平蔵を介して、五十雄を連れてきた女と再会することになり、それが金春屋敷のエピソードに展開していく。
ここでは、和田倉門内からの出火で灰燼に帰した金春屋敷の公孫樹の樹上に留まっていた雨だれがぽつりと足元を叩いたことを、胖庵は「眺めそこねた名残の花」に感じたのである。
<鳥は古巣に>
明治維新により演能の機会は激減した。そんな最中、観世流の梅若六郎が、青山下野守屋敷の能舞台を浅倉御蔵前の自邸に引き取った。そして10日間勧進能を開くという。この勧進能に胖庵は孫娘楚乃により無理やり連れてこられる。胖庵は長年の幽閉を解かれて、今は明治政府に出仕する嫡男の屋敷に寄寓の身であるが、嫡男は胖庵に複雑な思いを抱いている。胖庵の居心地は良くない。楚乃は寄寓する祖父の心情を察している。
この勧進能を豊太郎も修行の一環として観能しようと出かけてきたが、席料のことで濡れ衣を着せられ騒動となるエピソードである。だがそこには演能の囃子方の一つ、小皷方の家の内情話が絡んでいた。
能の世界での流派間の関係事情や世襲制の抱える問題などが織り込まれて行く。伝統芸能の世界の内情が垣間見える。さらに、明治維新期の演能状況がうかがえて興味深い。
<しゃが父に似ず>
冒頭に胖庵の曾孫、五歳の伊沢敏之丞は怪我が元で左足が不具合になり病弱である話を描く。そこに長年の蟄居生活で漢方の調薬の腕を医師並みにあげた胖庵の見立てが語られる。一作ごとに、胖庵の背景事情が広がり深まっていくことで、人物をより深く知るという関心が引き起こされる。この冒頭の場面描写は、後の短編への伏線になっている。
この短編では、30年前に江戸三座を浅草はずれの猿若町に強引に移転させて奢侈紊乱を封じようとした時の胖庵の思いと、現在の猿若町の賑わい、喧騒を対比させるという形をとる。時代の対比、江戸庶民のしたたかさをテーマとして、そこに胖庵の名残の心が重なっていく。東京となったこの梅若町の芝居小屋の状況と新政府による狂言綺語の禁止問題が描かれる。胖庵は出かけて行った梅若町で偶然にも南町奉行所時代の元部下であった庄右衛門に再会する。その再会から胖庵はこの問題への対応という核心に一歩踏み込む立場に己の身を置くことになる。
勿論、この禁止は衰微している能の世界にも適用される問題であり、平蔵は大荒れして、豊太郎をいっとき困らせたのだった。題名の「しゃが父に似ず」は謡曲「歌占」の一節「鶯の卵の中の時鳥、己(しゃ)が父に似て、己が父に似ず・・・」に由来する。胖庵は平蔵からこの謡本について知らされる。それが、胖庵にある考えを結実させる。
江戸の名残を、胖庵は今の猿若町に見たのだ。「あの町には自分がとうの昔に失ってしまった江戸が、まだ息づいている」(p140)と。
<清経の妻>
中村平蔵の家で、東京在住の金春座役者が寄り集まり、稽古能が開催されることになる。豊太郎は五番立て中、二番目物「清経」のツレとして、清経の妻役を任せられるという大抜擢を受けた。その稽古に勤しむべき時期に、能を捨てて、富岡八幡宮裏の書肆で働く兄の栄之進と会わざるを得なくなる。兄の話は四谷坂町の亡くなった叔父の家の整理を兄が行ったことに関連していた。その折り、叔母から夫の形見だと言って受け取ったのが大名物「千鳥の香炉」だという。目利きである平蔵にその香炉の箱書きを豊太郎を介して頼みたいという魂胆だった。豊太郎は目利きを胖庵にしてもらおうと考える。
この短編は、この「千鳥の香炉」の真贋に胖庵が関わることから、豊太郎の叔父叔母の思いと行為が明らかになっていく経緯を語るストーリーである。一種の推理仕立てとなっていて、興味深い。
豊太郎が胖庵に会い、目利きをしてもらっている間に、戻って来た鳥好きの敏之丞が目ざとく香炉の鳥を見て感想を語った。そのとき、豊太郎の脳裡に、「清経」の一節、「--形見こそ なかなか憂けれ これなくは 忘るる事もありなんと思ふ」がよぎったのだ。
このエンディングでは、豊太郎と胖庵の推理が異なる。二つの仮説が並立するところが読ませどころとなる。そして、最後は豊太郎が能稽古の開始に遅刻するオチで終わる。
<うつろ舟>
新政府が寺院の寺地について上地令を執行したということは、京都のいくつかの寺院の実例で知っていた。東京では、旗本屋敷返納を命じる上地令が執行されていたということをこの小説を読んではじめて知った。
この短編では、胖庵の孫である伊沢劼之助一家がその上地令の適用を二度受けるというところから始まる。もちろん、そのたびに住まいがどんどん狭くなって行くという次第。ここでは、家移りのために、敏之丞が大好きな鳥たちを手放さざるを得なくなる代償に、楚乃が上野の花鳥茶屋に連れて行くと約束したことの実行に絡むストーリーである。
楚乃の約束に対して、二人で花鳥茶屋に行かせる訳には行かぬと、胖庵が同行する事になる。ところが当日、そこに大蔵省会計係で給仕をしてきた少年が加わることになる。過去形で書いたのはその職を解雇されたからだが、それを否として譲らないので、劼之助が自宅に連れ帰ってきたのだ。当時の新政府の方針がこの背景にうかがえて興味深い。
多崎弥十郎という少年も花鳥茶屋に一緒に行くことになる。花鳥茶屋から見えた能舞台が切っ掛けとなり、多崎弥十郎のことに、フォーカスが当たっていく。それは哀しいストーリーに繋がって行く。後半では、中村平蔵の屋敷での謡曲「鵺(ぬえ)」の稽古場面が描かれる。そして、胖庵は一計を実行するのだが、やるせない哀しい結末となる。
こういう事態に近いことが、たぶん当時発生していたのだろう。時代の転換点で庶民層は苦しむ。時間の経過とともに消されていく小さな事実の累積。歴史書や学校のテキストはそれを形に残さない。捨象してしまう。そういう消されてしまう局面に小説という手法が目を向けさせる手段となっている。
<当世実感>
浅草南元町に暮らす観世座能役者・梅若六郎の隠居祝いに招かれた平蔵が、相当に呑んでいる上に、激怒した状態で屋敷に戻ってきて、豊太郎を困らせる場面からストーリーが始まる。そして、追いかけるようにして五十三代梅若六郎を継いだ源次郎が現れる。源次郎は、かれこれ十日程前に、質屋滝沢屋が将来見込みのある若者を探していて、その支援をしたいという話があり、豊太郎を推挙したいと考えていることを、平蔵に伝えていたと言う。源次郎は有徳者の力を借りるのも悪くはないと勧める。
豊太郎は、師の平蔵の許しを得て、滝沢屋の主人・喜十郎に会いに行く。一旦、世話になろうと心を決めるのだが、思わぬ場面を目撃したことが切っ掛けで、亮輔という人物と出会う事になる。そこから喜十郎の裏の心が見え始めていく。
人間関係の繋がりは不可思議なもの。亮輔の師が胖庵の知人であり、また滝沢屋喜十郎には、廻り廻ってその人物の背景を知る細い糸の繋がりを胖庵が見つけていくという巡りあわせとなる。胖庵がひと働きするという次第。
時代がどのように変わろうと、その渦中に存在する人の生き様、価値観の意味をまず問うという短編である。
胖庵と能の世界に生きる人々を主に扱いながら、時代が激変する過渡期の渦中での庶民側の哀感と時代相を見つめた連作集である。明治維新の捉え方を広げる視点を含んでいる。
ご一読ありがとうございます。
徒然に読んできた著者の作品の中で印象記を以下のものについて書いています。
こちらもお読みいただけると、うれしいかぎりです。
『落花』 中央公論新社
『龍華記』 KADOKAWA
『火定』 PHP
『泣くな道真 -太宰府の詩-』 集英社文庫
『腐れ梅』 集英社
『若冲』 文藝春秋
『弧鷹の天』 徳間書店
『満つる月の如し 仏師・定朝』 徳間書店















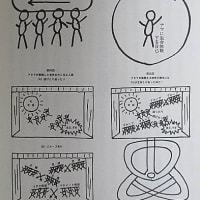




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます