私には人生を掛けて追いかけてるものが二つある。一つは片手袋。もう一つはエルヴィス・プレスリー。今日は片手袋ではなく、エルヴィスのお話。
☆
「凄いものを見た」
青ざめた顔で帰ってきた母は、何度もそう繰り返した。2004年のことだ。私は母のただならぬ雰囲気に、新興宗教か何かにはまってしまったのだと思った。今から考えてみると、その直感はあながち間違いではなかった。魂の救いの話であったのだから。
小さい頃からクラシックしか聞いてこなかった母が、2004年のある日、銀座の東劇を通りかかった。そこにはエルヴィス・プレスリーの大きな顔写真と共に、「原点にして頂点」というコピーが書かれた広告が掲げられていたそうだ。

どういう訳か彼女は、そのコピーを見てふらりと劇場に入ってしまった。そこからの約2時間。彼女はそれまで知ることのなかった世界を体験し、すっかり人が変わって帰ってきたのだ。
私はと言えば、「エルヴィスなんて今頃知ったのかよ」と少し突き放したようにその話を聞いていた。事実その時点でベスト盤か何かを持っていたし、「ロックを始めた人」くらいの知識はあった。だが母親のあまりの剣幕に心の底では(これは何かありそうだな)と感じてもいた。そして次の日、こっそりと行ったのである、東劇に。
劇場に着いて分かったのだが、その時上映されていたのは『エルヴィス・オン・ステージ』というライブ映画だった。映画が始まるとまず字幕が流れる。この映画のオリジナルは71年に制作されたエルヴィスのヴェガス公演の記録であること。30周年記念として再編集とリマスターを施したのが本作であること(日本での公開は04年になった)。
突然、激しいドラムロールが大音量で流れ、エルヴィスが登場した。古き良き50’s、派手な衣装で朗々と歌い上げるバラード、そのどちらでもない虎のように獰猛な男がゴスペルコーラスを従え疾走を始めたのだ。
私の全身に鳥肌が立った。体中を熱い血が駆け巡り、酸素が足りなくなったように意識は朦朧とした。いつの間にか笑いが止まらなくなっていた。そして何故だか猛烈に涙が出てきた。そして、記憶がなくなった…。
50年代にエルヴィスが登場し、誰も見たことのなかった歌い方と踊り方で人々に与えた衝撃。そこから月日は流れ、極東の島国で一組の親子が、スクリーン越しにその姿を見ても、50年前のアメリカの人々とまったく同じ衝撃を受けてしまったのである。
「エルヴィス、凄かったわ…」
母親に告げると、彼女は無言で頷いた。そこから私と母親は競うように、『エルヴィス・オン・ステージ』を体験する為に東劇に通い詰めたのである。
☆
そこから18年。現在の我が家はこんな感じだ。




ジョン・レノンは「エルヴィスは信じない」と歌ったが、私にとって唯一信じられるのはエルヴィスだと言っても過言ではないほどにまでなってしまった。
この間、エルヴィスに対してだけでなく、エルヴィスが置かれている状況にも無知であったことを思い知らされた。母親は知り合いにエルヴィスが好きになったことを話すと、必ず「年をとってもお盛んね」的な反応をされていた。男として、とか恋愛対象として、ではなくソウルを救ってくれる存在として好きになった母親は、そのたびに傷ついていた。飲み屋で隣り合ったロック好きの同年代男性には「ああ、エルヴィスね。あいつの曲、コード進行が全部一緒なんだよ」と知ったかぶりされたこともある。「そんなわけないでしょ!」。なんと母親は怒鳴りつけて帰ってきたそうだ。
私も驚かされることが何度もあった。上映会やイベントに出かけても、とにかく人がいないのだ。さらに若い人となると壊滅的。会場を見渡すと、大体いつも私が一番若いくらいだった。


「50’sは良いとしてその後は太ってくだらない歌ばかり歌ってた」「ミュージシャンなのに曲も作れないのかよ」「ビートルズ聞いちゃうとね」「ドーナツの食べ過ぎで死んだんでしょ?」「黒人の音楽を盗んだ奴」…
今まで聞かされてきたエルヴィスに対する偏見は幾つもある。しかし、それらはまだ良い方かもしれない。誤解どころか、現代の日本ではエルヴィスなんて忘れ去られてしまっているのだ。
だが、そんなことはもうどうでも良い。
エルヴィスを通じて繋がることが出来た人たちがいる。偶然にも近所にエルヴィスの師匠とも言える人が住んでいたのはラッキーだった。そして母親が知り合った関西の方達。元々原宿にあったエルヴィス像が神戸に移転されてからは、日本のエルヴィスシーンは関西の方達が支えてきたと言っても良いと思う。私が2013年、神戸ビエンナーレに片手袋作品を出品した時は、神戸のエルヴィスファンの方々がわざわざ見に来てくださった。“好き”が通じ合えば、年齢も住んでる場所も関係ないのだ。


エルヴィスに影響を受けたクリエイター達がいる。今でもあらゆるカルチャーにエルヴィスの影を確認できたことは、私の支えになってきた。「そうだ、エルヴィスは死んじゃいない」。東スポの見出しはある意味では正しかった。



※すべて何らかの形でエルヴィスが登場します
そして、エルヴィスに救われたソウルがここにある。2007年に亡くなった台湾の鬼才、エドワード・ヤン監督の代表作『牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件』。約4時間に及ぶ作品の最後、台湾の少年が歌う『Are You Lonesome Tonight?』の歌詞の一節『A Brighter Summer Day』が英題となっている。エルヴィスが「今夜はひとりかい?」とささやくその歌声は、行き場のない台湾の少年だけでなく、世界中の孤独な魂のそばにしっかりと寄り添い、「私の孤独なこの心を分かってくれるのはこの人だけなのかもしれない」という救いを与える。少なくともこの私の人生において、どんなに辛い瞬間もエルヴィスは優しく肩を抱きしめてくれていた。これは妄想なんかじゃない。
A Brighter Summer Day - Are You Lonesome Tonight?
☆
『エルヴィス』という映画が日本では7/1に公開される。

その影響があまりに巨大すぎて空気のようになってしまい、逆に誰も意識する事がなくなってしまった現代において、遂に、遂に彼の人生を真正面から描き切ろうとする意欲作が登場した。私の心はこの映画の製作を知った二年ほど前から、期待と不安で引き裂かれそうになっていた。
「見たいのはエルヴィスじゃない。エルヴィスのソウルなんだ…」
公開が近付きいよいよ情緒不安定になってしまっていた6月のある日。応募していた先行試写会ペアチケット当選の通知が私の携帯に届いた。応募しておきながらすさまじく動揺してしまったが、それには他にも理由があった。この十数年間、エルヴィスの支えが必要だった要因の一つが、詳しくは書かないとしても母親との関係性の変化にあった。母は70歳、私も40歳を過ぎてしまった。距離を置くことが正解の時もある。だが、エルヴィスである。さすがに彼女を誘わないというのは、あまりに酷い仕打ちに思えた。最大の楽しみが一気に最大の重荷に姿を変えたが、私は思い切って彼女を誘った。
「エルヴィスの映画の試写会、当たったよ。一緒に行くかい?」
かくして我々は、実に数年振りに二人で出掛けることになったのである。
試写会当日。会場となった丸の内ピカデリーには若い世代を中心にたくさんのお客さん、マスコミ関係者、イベントに出演する芸能人が集まっていた。
「ああ、エルヴィスの為にこんなに人が集まる日が来るんだ!」
我々親子はそろって、上映前に泣いてしまったのである。
ここでは映画の内容は詳しく書かない。しかし、これまで味わってきた偏見や無関心を吹き飛ばし、もう一度エルヴィスをこの世界に蘇らせるような素晴らしい作品だった。我々マニアは当然、細かい部分についてあれこれと盛り上がりたいところだが、エルヴィスについてなんの予備知識がなくてもまったく問題ありません。とにかく少しでも興味がある人は、大きいスクリーン、大音量で見られるうちに劇場に足を運んで欲しいと思います。
三時間近くある映画を見終わった帰り。昔よく親子で行った銀座のラーメン店に母と入り、あれやこれやと映画の感想を語り合った。顔色を変え帰ってきてエルヴィスを語り始めたあの日とまったく同じ熱量で語る彼女を見て、
Well, that's all right, mama
That's all right for you
That's all right mama, just anyway you do…
エルヴィスの歌声が私のソウルに流れてきた。
私とエルヴィス。私のエルヴィス。












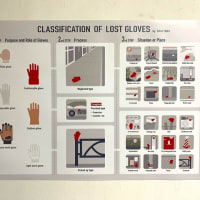







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます